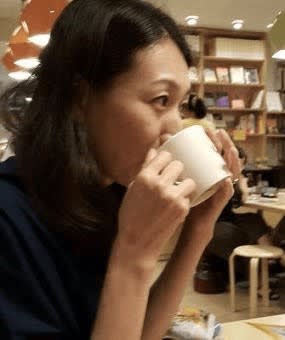過日、校下のサークルの人たちと、岐阜県内の三セク鉄道、樽見鉄道の一日フリーきっぷを使っての日帰り旅に出かけた。
まず大垣駅から北上し、終点の樽見駅まで行って、あとは折返し、ここぞというポイントで下車しながら、附近を散策し、写真を撮ったりして南下した。
この経緯についてはまた追って書いてみたいが、とりあえずはそこで出会った印象的なエピソードについて書きたいと思う。

本巣駅にて
樽見から折返し、三つ目の日当(ひなた)駅で下車した。時刻表によれば次の列車までは一時間余あるので、その間にそれぞれ思い思いにその集落や根尾川の初冬のなかを散策したのだった。
集合予定時刻のやや前に着いた私は、これまで歩いたのとは逆方向も少し見ておこうと歩を進め、山道特有のヘアピンカーブのようなところへさしかかった折だった。

樽見駅近くで
そのカーブの向こうから、ヒョイと一人の老婦人が現れたのだ。私自身がじゅうぶん高齢なのだが、見たとこそれを遥かに上回る彼女は、疲れたらそこに座れる腰掛け型の手押し車をうつむきかげんで押していた。
その歩みは鈍く、10歩も進んだかと思うと立ち止まり、その椅子の部分に腰を下ろすのでもなく、手すりの部分に寄っかかってしばし休み、また歩き始めるのだった。
ちょっと気にかかったのは、スマホのマップによれば、このカーブの先の近くには集落や人家はなく、したがってこの老婦人はかなり先からやってきたことになる。それを確かめるべく、彼女に「こんにちは」と挨拶をしてすれ違い、カーブのところまで行ってみた。やはりマップの通り、かなり先まで集落らしきものはない。

引き返して、ちょうど休憩中だった彼女に尋ねた。
「どこへ行かれるんですか」
彼女は耳が遠いらしく、
「もうすぐ百になるから」
と答えた。
もう一度大きな声で、
「どこへ行くんですか」
と訊いたら、今度は聞こえたらしく、
「在所の日当へ行って、先祖の墓参りをし、畑仕事を」
とのことだった。

日当(ひなた)駅
日当の集落というのは先ほど私が行ってきたところで、近くて数百メートル、はずれなら1キロはある。
こうして話しているうちにも、彼女は俯いて車を押すため、つい道路の中央へはみ出す。いくら田舎道とはいえ、2分に一度ぐらいの割合で車が通る。その都度私は、両手を広げ、車に指示を出しながらやり過ごすのだった。
https:/
道は登り坂にさしかかった。樽見線の渡線部分でしばらく登りが続き、登りきれば今度は下り坂である。登りの部分でも彼女は止まって休憩するのだが、その都度、手押車が下へと動きそうになる。私はそれを支えながら、やってくる車に避けてくれるよう指示を出し続ける。
椅子の部分を指差して、「ここへ座ったら私が押します」というのだが、それに従う気配はない。
この登りもだが下りはさらに危険だ。
私はジレンマにとらわれていた。乗るべき次の列車の時間が迫ってきたのだ。これに乗らなければ、また一時間後を待たねばならない。かといって彼女をこのまま放置するのは危険この上もない。
私は一列車遅らすのを覚悟した。とはいえ、最後まで彼女の面倒はみきれないから、110番に電話をして彼女を保護してもらい、それを見届けてからこの場を離れようと思った。

その時であった。彼女の背後から白いバンが通りかかった。乗用車よりやや車幅が広そうなので、彼女を道路の端へ誘導し、車を反対へ誘導するよう合図をした。
ところがである。その車は私の指示に従わないばかりか、私と彼女の後をぴったり付けるようにノロノロとついて来るのだ。私はさらに大きく手を振って合図をした。
すると、運転していた男性が、窓を開けて言った。
「大丈夫です。それはうちの婆様ですから」
事情を聞くとこうだった。
彼は彼女の息子で、彼女には認知症があって時折、徘徊する。だから家族で気をつけてはいるのだが、しばしばその目を盗んで出かけてしまう。しかし、その徘徊の行く先は毎回決まっていて、私が聞いたように「在所へ行って墓参りと畑仕事」だそうなのだ。
今日も気がついたらいないので、慌てて追っかけてきたところだという。
そこで、もうひとつ意外な展開があった。
「ところで、あなたはどうしてここに?」
と彼に訊かれるままに、「仲間といっしょに、フリーきっぷで樽見鉄道を満喫しているのです」と答えると、とたんに笑顔が弾け、「それはそれは、どうもありがとうございます」と丁重に礼を言われてしまった。

最後に乗った木知原(こちぼら)駅で
え、え、え、あなたは樽見鉄道の社長さん?と驚いたのだが、聞けばこのひと、この間まで、NPO法人「樽見鉄道を守る会」の理事長をしていたという。
私が、彼の母である老婦人と遭遇したのも、樽見鉄道がとりもった縁というべきかもしれない。
というわけで私は、無事ほかのメンバーと同じ列車に乗って旅を続けることができたのであった。
最後に、私が感服したのは、その元理事長、母親の行動を強い言葉や行動で規制することはせず、その安全をガードしながら、彼女の動きに寄り添っていたことである。
力づくで彼女を車に乗せて連れ去ることは可能だったろう。しかし、彼はそれをしなかった。私たちがプラットホームで列車を待つ間にも、彼女の亀の歩みに寄り添いながらノロノロと進む彼の車が目撃できた。
岐阜の山間部、根尾川沿いを走る樽見鉄道、この路線を思い浮かべるとき、上に述べた私の経験は、必ずいっしょに思い浮かべるエピソードとなることだろう。