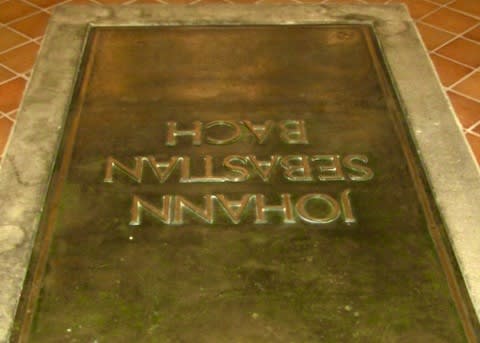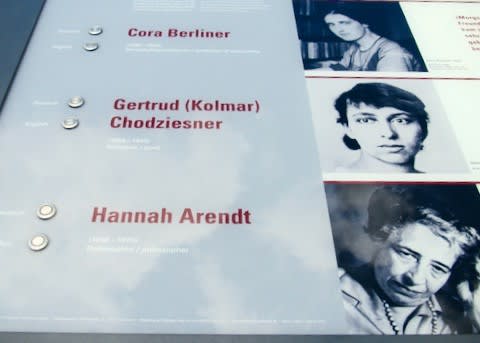20世紀ベルリンのもうひとつの特筆すべき点は、この都市が第二次世界大戦後の冷戦下で、東西に分断されていたということである。
とりわけ、61年に東西を隔てる壁が築かれ、89年にそれが撤去されるまで、この都市はまさに東西冷戦をもっとも具体的な形で表現する箇所であった。

と同時に、89年のその壁の崩壊は、東西冷戦の歴史そのものを終焉させる先鞭をつけるものであった。
こうして今や、ベルリンの、そしてドイツの東西の分断は解消され、その差異もなくなったといわれている。しかしである、現実には今もその差異はあるという。東西においての労働の質的評価が異なるのだ。具体的にいうと、同じ労働についても東のそれは西の85%にしか評価されないというのだ。この差異は大きい。年金にまでついてまわるからだ。むろん、それは問題として意識され、近年改善されつつあるが、それらは東側での不満の蓄積に及ぶという。こうした状況は、近年のドイツにおいての極右の台頭にも関わるというのだが私にはそれを断言するだけの知識はない。

それはさておき、かつての東西の分断の痕跡が明確に残る地点を訪れた。
「チェックポイント・チャーリー」と呼ばれるこの場所は、東西冷戦時代、その境界上に設けられた検問所を復元保存したもので、チャーリーというのは人名ではなく英語の愛称で、「チェックポイント・C」ぐらいの意味だという。
しかし、その名前の響きの軽さからは推し量れない重要な場所であったのは事実である。
東西の双方から観たチェックポイント アメリカ側からみた小屋の近くの看板にはソ連兵の肖像が、またその裏のソ連側には米兵のそれが描かれているが、これはあとからのものである
周知のように敗戦後のドイツは東西に分割され、その首都、ベルリンも東西に分割された。往時のヨーロッパの地図を思い描いてみてほしい。ドイツの東側はすべてソ連、ないしはソ連圏の勢力圏であり、したがってドイツに、そしてベルリンに引かれた境界線は東西冷戦時の、そして「冷戦」とはいえしばしば火花が散る象徴的な場であったわけである。
いってみれば、この境界線上での出来事が、第三次世界大戦の発端たり得る可能性すらあったということである。

事実このチェックポイント・チャーリーでは、ここを突破しようとして銃殺された者もいたし、手違いのトラブルで双方の武装兵士が出動したこともあった。そればかりか、1961年10月には、双方とも20両ほどの戦車部隊がここを挟んで睨み合う事態まで発生し、外交的な折衝でやっとその矛を収めるということすら発生している。

そんな 事実を知ってか知らずか、今は多くの観光客が押し掛け、このチェックポイント・チャーリーをバックに集団で写真を撮るのにプロの写真家が盛んに勧誘を行うまでになっている。
また周りには、お土産屋が目立ち、防毒マスクや軍服などを売っているが、もはや撤退している当時のソ連軍のものが目立つ。ということは、世界中どこでも見えられる米軍服より、今は無きソ連軍のそれに人気があるようだ。とはいえそれらも、お土産用に新しく縫製したものなのだが。

そのすぐ近くの道路上には、61年から89年まで設置されていた「壁」の痕跡がそれと記された鉄板とともに残されている。当時のニュースや残された映像では、大勢の人が壁に登り、ツルハシなどでそれを打毀わしているが、それだけの厚みをもった 箇所は限られていて、全てでは無いことがわかる。私が撮したそれは、この短い足でも楽にまたげる3,40センチの幅のもので しかない。それをまたいで写した写真があるが手前にあるのは私の足である。またその境界をまさに越えようとしている自転車の写真を撮ることができたので掲載しておく。

薄かろうが厚かろうが、国家はその壁を設ける。言語や風俗習慣など、あるいは勝手にでっち上げた歴史的起源になる題材をもとに、他者との差異を強調し自己同一性 を述べたてる。それはこのベルリンのように限られた地域であろうが、あるいはまさに南方からの侵略を防ぐためにメキシコ国境に壁を設けようとするアメリカだろうが、さらにはまた地続きの国境を持たない日本のような国だろうが、その壁は厳然としてある。
ただし日本は海を持ってその壁としているが、その壁に関していうなら、沖縄はその壁の外である。かつての大戦においては、沖縄の滅亡でもって本土を守ろうとし、また戦後においては、日米安保条約によるアメリカとの同盟の実態である米軍基地の70%以上を沖縄に集中し、それどころか 今や辺野古に新しい基地を作り、さらに昨今は台湾有事を口実に沖縄の離島に様々な軍事設備を設置するなど、またもや沖縄を犠牲にする体制を着々と重ねつつある。

ベルリンのチェックペインポイントの話がいささか脱線したが、言いたかったことは壁がなくなったからといってすべての国家の壁がなくなったわけではないということだ。 有形無形のさまざまな壁が国家を取り巻く。そしてそれがある間は人々はそのその壁の内外を巡って争い合うだろう。
チェックポイント・チャーリーがそうした国境をもつ愚かな人類の行為を反省する材料となれば良いとは思ったが、既存の国家そのものへの帰属意識をもったままでは、あれは単に過去の行き過ぎた事例であるというにとどまるだろう
その他、単発でベルリンで見聞したものもあったが、書き残すべきものは以上で終える。これが三日間の私のベルリンの旅であった。いよいよ次はK氏が待っていてくれるライプチヒへと向かう。