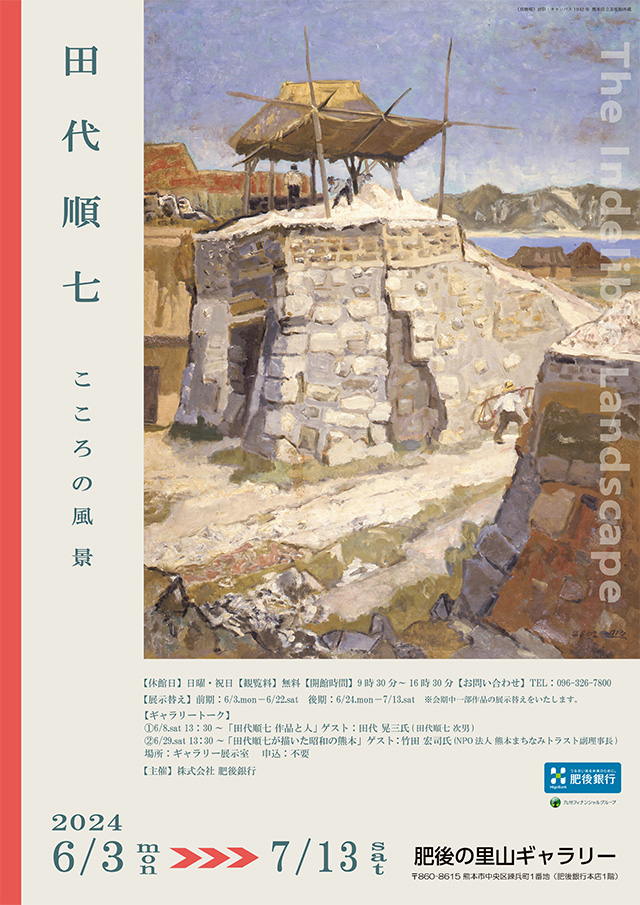11月16日 22:41 · 岡山県立博物館 書付「後藤又兵衛討死之時」発見について報道発表。
後藤又兵衛は、大坂の陣で真田信繁(幸村)らとともに大坂方として活躍した武将で、この戦いで討ち死にしています。
今回発見された資料、書付「後藤又兵衛討死之時」は、又兵衛の首を討った脇差が、又兵衛が豊臣秀頼から拝領したものであったこと、又兵衛最後の様子を秀頼に報告したことなどが記されており、又兵衛のもとで戦った金万(こんま)平右衛門、もしくはその子孫が書き記したものと考えられ、平右衛門の子孫宅に残されていました。大坂方に参加した武将が書き残した記録としても大変貴重なものです。
この資料は、11月25日(金)から来年1月15日(日)まで、岡山県立博物館にて展示されます。

一、後藤又兵衛討死之時従
秀頼公拝領之脇指[行光]、是ニ而
又兵衛首ヲ討、 秀頼公御前ニ而
如此討死仕次第申上候へとて
長四郎と申児姓二脇指相渡
被申候、長四郎脇指請取候へとも
又兵衛印ヲあげ候義ハ不罷成
脇差斗 秀頼公江差上ケ申事、
一、脇ニ居申候小性、是ハ又兵衛指物之
くり半月之片おれヲ又兵衛
討死仕候証拠ニ 秀頼公江差上申候、
一、平右衛門義ハ右両人之者仕廻候後ニ
其場江参着申候事、 (埼玉・柏木様のご協力を得ました)
・脇にいた(別の)小姓に又兵衛の指物である「かえり半月」の片折れしたものを、又兵衛の討ち死にの証拠として秀頼公に差し上げなかったこと。
・平右衛門は長四郎たちに手渡したのが終わった後に(秀頼公の前に)到着したこと。