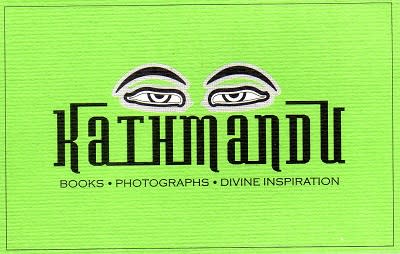ムンバイからバンコクに移動する飛行機で、荒松雄『ヒンドゥー教とイスラム教 ―南アジア史における宗教と社会―』(岩波新書、1977年)を読み始め、バンコクに居る間に読み終えてしまった。
同氏の『インドとまじわる』(中公文庫、原著1982年)は、まだ実際のインドを体験した日本人が少ない1950年代にインド留学した体験をもとに書かれたエッセイであった。滅法面白く、本書の古本をヤフオクで調達しようかと思っていたところ、今年、ちょうどアンコール復刊されていた。あとは、『多重都市デリー』(中公新書、1993年)も読みたいが、これは古本市場にしかなさそうだ。
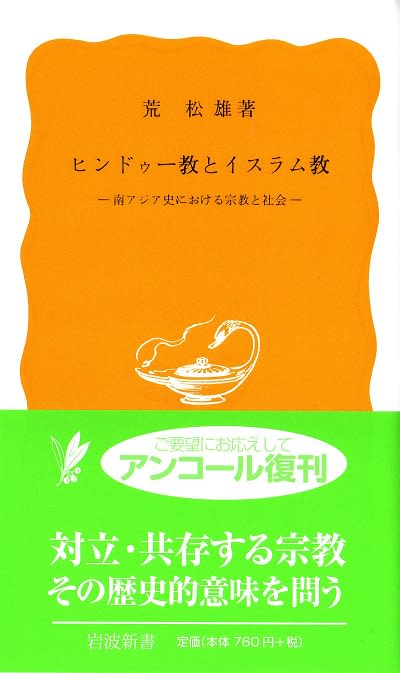
ヒンドゥー教、イスラム教それぞれの特徴や歴史をまとめるのではなく、両者がどのように併存してきたのかという視点で書かれた本である。本書前半はその意味で生煮えのようで、物足りないところがある。後半になってぐんぐん面白くなってくる。
○ヒンドゥー教は東南アジアの島嶼部にまで幅広く広まっており、インドの「民族宗教」と呼ぶには抵抗がある。
○インドへのイスラム教勢による軍事的侵入の第一は、8世紀、ウマイヤ朝の侵入であった。この後、インダス川下流域がインドとムスリムとの接点となった。第二は、10世紀後半以降、西北インドへのトルコ系民族の侵攻であった(ガズナ朝、ゴール朝)。
○しかしそれとは別に、インドへのイスラム教浸透は、非軍事的になされた。それは交易・商業活動であり、スーフィーの活動の影響であった。
○スーフィーは人間の多い場所に拠点を設けた(デリー、ラホールなど)。スーフィー聖者はヒンドゥーのインド人民衆に共感をもって迎えられた。ヨーガ行者を見慣れていたインド人たちは、スーフィー聖者たちにも素直に崇敬の念を抱いていった可能性が高い。
○一般のヒンドゥー民衆が個人的にムスリムに改宗することは困難だった。むしろなんらかの集団ぐるみの改宗のほうが一般的であっただろう。なかでも、カースト=ヴァルナ制のなかで下層民として被差別の立場に立たされていた人たちの集団が、平等観と同胞意識を掲げるイスラム教に改宗したことが考えられる。
○インドのイスラム政権(ガズナ、ゴール、ムガル)は、ヒンドゥーの社会や信仰や統治機構を大きく変えることなく支配するものであった。
○このような両文化の混淆はさまざまな面で観察できる。ムスリム建築であるタージ・マハルは、それ以前のヒンドゥー様式を含んでいる。ラヴィ・シャンカールの使うシタールは、西アジア起源の楽器である。
○寛容であったムガル帝国でも、六代皇帝オーラングゼーブの時代になると、その傾向が弱まっていった。
○社会的には自然に併存していた両文化に楔を打ち込んだのは、英国支配であった(「Divide and rule」)。
○従って、歴史的には、インドとパキスタンの分離独立(1947年)を宗教対立にのみ帰するのは軽率な認識である。
これらの見方は、現在も強くあるパキスタンとの対立や、インドにおけるヒンドゥー・ナショナリズムに向けられる視線にも色付けを施すものだろう。
●参照
○荒松雄『インドとまじわる』
○中島岳志『インドの時代』
○アルンダティ・ロイ『帝国を壊すために』(ヒンドゥー・ナショナリズム)
○ダニー・ボイル『スラムドッグ$ミリオネア』(ヒンドゥー・ナショナリズム)
○ヌスラット・ファテ・アリ・ハーンの映像『The Last Prophet』(スーフィズムのカッワーリー)