ドーハからの帰途、カタール航空の機内で、サタジット・レイ『ナヤック』(Nayak、1966年)を観る。
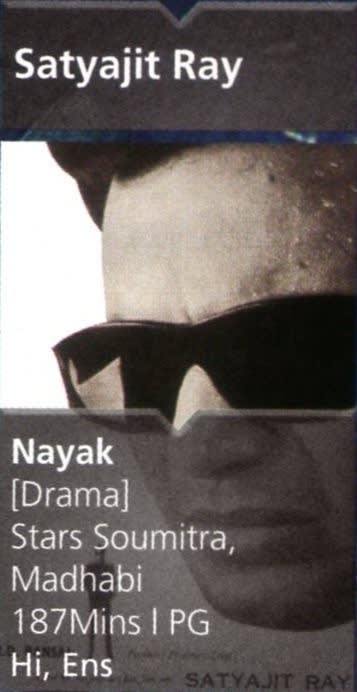
売れっ子映画俳優、アリンダム。傷害事件を起こしてしまい、マスコミから逃げるためもあって、デリーでの表彰式に旅立つ(おそらく西ベンガルから、だろう)。長距離列車のなかではさまざまな人と出逢う。あんたなんて知らんよ、映画なんて『わが谷は緑なりき』以降観ていないよと言う老人。自分のファンだという病気の女の子。俳優という仕事の華やかさに冷や水を浴びせるような、たまたま居合わせた女性記者。
そのうち、アリンダムには、自分の来し方が襲いかかってくる。新米時代、先輩俳優が人前で自分を叱責したが、その後立場が逆転してしまい、仕事のなくなった先輩が訪ねてきたこと。映画に使ってくれと突撃するように懇願してきた若手女優に対し、「自伝に書くから名前を教えてくれ」と言い放ったこと。労働運動に身を投じている長年の友人に、労働者たちの前で発言してくれと頼まれるも、そんなのは絶対にダメだ、リスクがある、と怖れおののき、逃げ出してしまったこと。アリンダムは泥酔し、女性記者に、話を聴いてほしいと頼む。
サタジット・レイ(ショトジット・ライ)は相変わらず映画作りが巧く、複数のプロットも実にすっきりと展開する。映画のテーマは、誰にも心の内奥をさらけ出し、聴いてもらい、時には慰撫してくれる存在が必要なのだということのように思える。極めてシンプルながら、共感しながら観てしまう。
アリンダムにとってのその存在たる女性記者は、しかし、デリー駅で人混みに姿を消す。この潔さもレイならではか。











