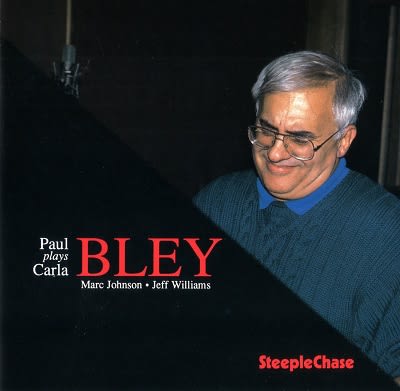青山のイメージフォーラムで、ジョシュア・オッペンハイマー『アクト・オブ・キリング』(2012年)を観る。そろそろ大丈夫かと思ったが、直前に行くと満席だった。立ち見だと言われて入ると、幸運にも、空席があった。

1965年9月30日、インドネシア国軍によるクーデター未遂事件が起きる。これはスカルノ大統領失脚、スハルト大統領誕生のきっかけとなり、また、このときに、やくざや民兵たちにより、共産党シンパや華僑たちをターゲットとした大虐殺があった。犠牲者数は明らかでなく、概数で100万人規模だとされている。
映画は、このときに手を下した者たちにインタビューを行い、さらに、自分の行為を演じてもらうという手法で作られている。彼らはその罪を追求されるどころか、むしろ、社会的地位を得てさえいる。また、北スマトラ知事(メダンでのロケだろう)や、カラ副大統領が、やくざ民兵集団「パンチャシラ青年団」に対し、支持を取り付けようとして、彼らの価値を認めるようなコメントやスピーチを吐いているのである。現在も、もたれ合いの構造が強く残っているのだろうなと思わざるを得ない。
虐殺者たちは、自らの殺人行為を、嬉々として身振り手振りで再現する。誰がみても、最低な下衆連中である。
しかし、かれらの様子が次第に変わってゆく。犠牲者の声を聴き、また犠牲者の役を演じているうちに、心身に異変が生じてくるのだ。口では、「当時はしかたがなかった」、「そのようなものだった」と威勢のいいことを言いながらも。そして、ついに、虐殺場所において、虐殺者は、嘔吐しはじめる。歴史の実態が、隠しようもなく姿をあらわし、「大文字の歴史」にお墨付きを得ていたはずの虐殺者の内臓を喰らい荒らした瞬間だった。
決してドキュメンタリーとして傑作とは言えないし、作り手にも山師的なものが見え隠れする。しかし、これは「私たち」の映画である。すなわち、「大文字の歴史」を内部から噛み進める虫があってしかるべきだということだ。
●参照
朴寿南『アリランのうた』『ぬちがふう』(重なるものが確実にある)