ジェラルド・グローマー『瞽女うた』(岩波新書、2014年)を読む。
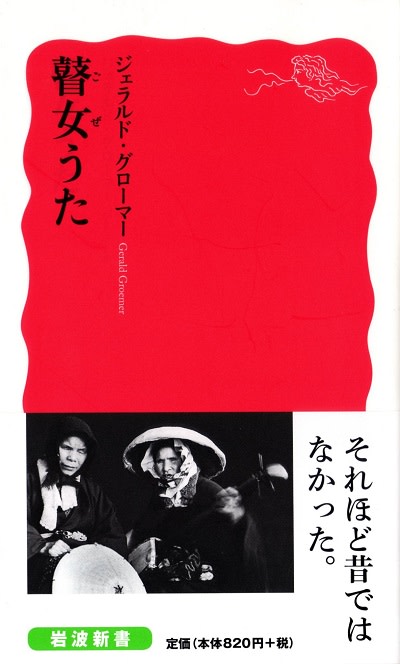
瞽女(ごぜ)とは、盲目の女性旅芸人であり、つい最近まで存在した。新潟に多かったのは事実ではあるが、九州や中国にもいた。その印象は、消えゆく瞽女の記録を残そうとした地域が新潟であり、また、篠田正浩の映画『はなれ瞽女おりん』によるところも大きいという。
本書は、瞽女の活動や、その変遷を詳しく追っている。知らないことばかりでとても興味深い。
江戸初期には、三味線を手にして人びとの家や宴の場で唄を披露し、謝礼を受け取る方法ができあがっていた。不幸にして盲目になってしまった者たちは、瞽女という生業を行うために家族的な集団となり、芸を次々に伝えていった。芸のネタは、地方によって異なる民謡、三味線や琴の芸能、僧の尺八、仏教の説話、ゴシップ的な語りなど多様であった。おそらく、そういった有象無象を吸収して、独自の世界を創りあげていったのだろう。
とは言え、アナーキー、自由に発展させるばかりの芸能ではなかったようだ。ちょっとやそっとでは覚えられない長い唄物語などは、個人の裁量や工夫で変更することが許されないものであった(集団から放逐された「はなれ瞽女」などはその限りではない)。そういった縛りの下で、唄い方は各々の個性を発揮していたという。
芸と引き換えの謝礼だけではなく、村などからの公的な扶持制度によって、経済的に成り立っていた面もあった。しかし、明治に入り、近代という管理システムと経済産業システムが押し寄せてくる。そのようなシステムの中では、定住せず、管理対象になりにくく、また公序良俗を乱すとみなされる瞽女は、次第に行き場を失っていく。盲目の子をイエの外に出すことも、倫理的でないとされた。そして、資本による消費音楽がエンターテインメントの主流となると、もはや、人びとは娯楽として瞽女の芸を求めなくなっていった。
時代の要請とはいえ、文化は、芸能は、それでいいのだろうか、という現代社会への批判が、本書のメッセージでもある。










