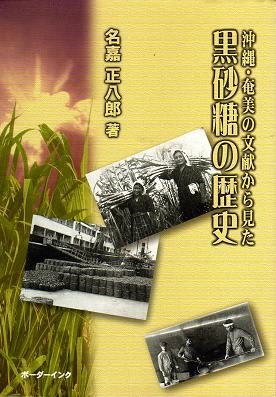今朝の日経・温暖化特集に登場した。白髪が目立っていてどうも・・・。

沖縄県糸満市の大度海岸は、本島の南端に近いところにある。琉球石灰岩の断崖になっている場所が多い(沖縄戦を想起せざるを得ないところだ)。この大度海岸は断崖が海に直接接しているのではなく、イノーの干潟である。珊瑚礁で出来ており、リーフより陸側が干潮時には潮溜りになるわけだ。
イノーということばは沖縄のものであり、「礁湖」、「礁池」などに置き換えられる。良い説明が、吉嶺全二『サンゴの海と「赤土汚染」公害』(沖縄県教育文化資料センター 環境・公害教育研究委員会編『環境読本 消えゆく沖縄の山・川・海』に所収)にあった。ちょっと長いが引用する。
「大潮の干潮時にはヒシ(※干瀬、リーフ)まで歩いていけるので舟はなくとも漁をすることができる。このような地形や景観は日本国内では鹿児島県の奄美大島から沖縄県下の島々が連なった約1000キロメートルにおよぶ琉球列島あるいは、南西諸島と呼ばれている島々だけにみられる。
もっと南の島々やオーストラリアのグレートバリヤリーフなどでは、ヒシは渚から50~100キロメートルも離れたところにあるので大潮の干潮時でも歩いて行くことはできない。
ヒシは、冬の季節風や夏の台風などによる大波を打ち砕いて、ヒシの内側を波静かにする。そこを方言ではイノーという。共通語では礁湖とか礁池とかいうが、南太平洋の環礁になったラグーンを訳した言葉であろうから沖縄のイノーを表すにはしっくりこない。」
イノーは凸凹のある珊瑚礁で揺籃のようで、干満差の大きい干潟だから、多様性のある生き物たちがたくさんいる。干潟とは言え、三番瀬や盤洲干潟のような東京湾のそれとは様相が異なっていることを観察できて嬉しかった。
那覇在住の24wackyさんに案内いただき、「みん宿ヤポネシア」で準備させていただいてから歩いて向かった。宿泊もしていないのに、「ヤポネシア」の人たちはとても親切にしてくれた。素敵なところで、平和運動にも関わっておられて、今度はぜひ泊まりたいと思った。庭にはアセロラの木があった。那覇で買って食べたアセロラも、糸満産だった。

「ヤポネシア」のアセロラ 直後に水没したデジカメで撮影

イノー Leica M4、Biogon 35mmF2、Rollei Retro400、イルフォードMG IV RC、2号フィルタ

イノー Leica M4、Biogon 35mmF2、Rollei Retro400、イルフォードMG IV RC、2号フィルタ
ヘリトリアオリガイ(ジシクン)という二枚貝がびっちり群れを作っていた。タンパク質の糸を出して岩に食いついている。

ヘリトリアオリガイ(ジシクン) Leica M4、Biogon 35mmF2、Rollei Retro400、イルフォードMG IV RC、2号フィルタ
じろじろ観察していると、突然黒い物体が現れて仰天する。ニセクロナマコ(ウマヌタニー)というナマコだった。先っぽのぎざぎざは触手で、ここから砂と共に有機物を取り込んでいる。しかし、同じクロナマコ科のクロナマコもいるようだが、なぜこちらは「贋」なのだろう。

ニセクロナマコ(ウマヌタニー) Leica M4、Biogon 35mmF2、Rollei Retro400、イルフォードMG IV RC、2号フィルタ
ある潮溜りには、血管のような線がたくさんあった。よく見ると、貝が動き回った跡なのだった。

貝の跡 Leica M4、Biogon 35mmF2、Rollei Retro400、イルフォードMG IV RC、2号フィルタ
またある潮溜りには、アマモのような植物があった。ジュゴンが食べるリュウキュウスガモ(ザンクサ)と同じだとすると海藻ではなく海草だ。

海草 FUJI GW680III、Rollei Retro400、イルフォードMG IV RC、2号フィルタ
植物には見慣れない形のものが多くあった。たとえば、コロッケのような、たわしのような形のもの。ガラガラという紅藻だった。また、きくらげのような形の白い海藻は、ウスユキウチワというものだった。下の写真では、ウデフリクモヒトデ(ガラサーダク)の周りで「のほほん」としている。

ウデフリクモヒトデ(ガラサーダク)とウスユキウチワ 直後に水没したデジカメで撮影
腕が長いヒトデは、他にも、ワモンクモヒトデという奴がいた。腕がひとつちぎれているが、再生できるのだろうか。

ワモンクモヒトデ 直後に水没したデジカメで撮影
ウニはあちこちに隠れている。ナガウニ(ウナー)だ。やんばるの東村にいるウニを食べたことがあるが、これが食用になるのかどうかわからない。

ナガウニ(ウナー) 直後に水没したデジカメで撮影
異形で吃驚した生き物は、ケブカガニだ。毛蟹どころではない。文字通り毛深だ。カモフラージュにはいいのかもしれないが、異形なので結構目立つ。

ケブカガニ 直後に水没したデジカメで撮影
ギンポというひょうきんな奴もいて、穴影からこちらを見ている。

ギンポ 直後に水没したデジカメで撮影
ゴカイの糞らしきもの(たぶん)。これは東京湾の「モンブラン」と同じだ。

ゴカイの糞 直後に水没したデジカメで撮影
もちろんこれだけではなく、魚、貝もあちこちでちょろちょろしている。カニは今回あまり目立たなかった。何日も通って観察したいところだ。
なお、イノーの生き物たちについては、『沖縄のサンゴ礁を楽しむ 磯の生き物』(屋比久壮実、アクアコーラル企画、2004年)によって確認した。「ヤポネシア」に置いてあって、便利なので帰る前に那覇で入手した。

●三番瀬
○三番瀬を巡る混沌と不安 『地域環境の再生と円卓会議』
○三番瀬の海苔
○三番瀬は新知事のもとどうなるか、塩浜の護岸はどうなるか
○三番瀬(5) 『海辺再生』
○猫実川河口
○三番瀬(4) 子どもと塩づくり
○三番瀬(3) 何だか不公平なブックレット
○三番瀬(2) 観察会
○三番瀬(1) 観察会
○『青べか物語』は面白い
●東京湾の他の干潟
○盤洲干潟 (千葉県木更津市)
○盤洲干潟の写真集 平野耕作『キサラヅ―共生限界:1998-2002』
○江戸川放水路の泥干潟 (千葉県市川市)
○新浜湖干潟(行徳・野鳥保護区)
●泡瀬干潟(沖縄)
○泡瀬干潟の埋立に関する報道
○泡瀬干潟の埋め立てを止めさせるための署名
○泡瀬干潟における犯罪的な蛮行は続く 小屋敷琢己『<干潟の思想>という可能性』を読む
○またここでも公然の暴力が・・・泡瀬干潟が土で埋められる
○救え沖縄・泡瀬干潟とサンゴ礁の海 小橋川共男写真展
●その他
○加藤真『日本の渚』(良書!)
○『海辺の環境学』 海辺の人為(人の手を加えることについて)
○下村兼史『或日の干潟』(有明海や三番瀬の映像)
○『有明海の干潟漁』(有明海の驚異的な漁法)
○理系的にすっきり 本川達雄『サンゴとサンゴ礁のはなし』(良書!)