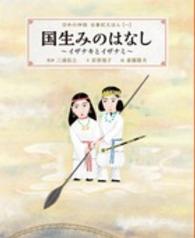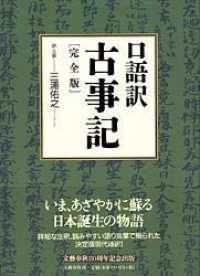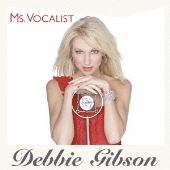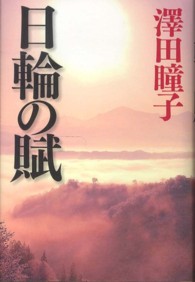「ニッポン社会」入門 英国人記者の抱腹レポート」 コリン・ジョイス
英国記者による「日本事情」。
日本人なら、当たり前すぎて気づかない点を指摘してくれる。
英国人らしいユーモアあふれる文章を楽しめる。
P15
ぼくは一度、一週間にふたつの記事を提出したことがある。ひとつは日本のセックスレスの夫婦について、もうひとつは「できちゃった結婚」についてだ。デスクはすっかり戸惑ってしまったようだ。「日本人はサカリがついたようにヤリまくっているのか、セックスをしなくなっているのか。いったい、どっちなんだ?」
P37
まず、日本語には気の利いた諺がいくつもある。なかでも、「猿も木から落ちる」は日本語学習者なら誰でも早い段階で学ぶ諺だし、おそらく最も優れた言い回しだろう。初学者でもわかる簡単な単語を用いながら、それをつなげた文全体は、人間には誤りがつきものであることを力強く、かつユーモラスに伝えている。
P49
小便をしようとして便器に近づくと自動的に水が流れ、用を足して便器から離れるとまた水が流れる。もう本能的に笑ってしまった。便器にセンサーがついてるなんて!その後、ばくは日本には「超」がつくほど発達した便器と、信じられないくらい原始的な便器の二種類があると知ることになる。
P140
そもそもイギリスはひとつの国ではない。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドという四つの別々の国から成り立つ連合王国である。イギリス以外の人にはわかりにく仕組みであることは認めよう。しかし、スコットランド人を決して”English”(イングランド人)と呼んではいけない。
【ネット上の紹介】
日本社会について手っ取り早く学びたければ、近くのプールに行ってみることだ。規則と清潔さを愛し、我慢強く、大きな集団の悪事に寛容な国民性が理解できるはずだから。過剰なまでに礼儀正しく親切な人々、思ったより簡単で奥深い日本語、ガイドブックには載っていない名所の数々…。14年間日本に暮らす英紙記者が無類のユーモアを交えて綴る、意外な発見に満ちた日本案内。
[目次]
基礎編―プールに日本社会を見た
日本語の難易度―日本語、恐るるに足らず
おもしろい日本語―イライラ、しくしく、ずんぐりむっくり
日本の第一印象―サムライ・サラリーマンなんていなかった
日本の日常―日本以外では「決して」見られない光景
行儀作法―英国紳士とジャパニーズ・ジェントルマン
独創性―日本人はすぐれた発明家だ
ビールとサッカー―日本の「失われなかった」十年
行動様式―日本人になりそうだ
ジョーク―イギリス人をからかおう
東京の魅力―わが町、東京を弁護する
東京案内―トーキョー「裏」観光ガイド
ふたつの「島国」―イギリスと日本は似ている!?
メイド・イン・ジャパン―イギリスに持ち帰るべきお土産
特派員の仕事―イギリス人が読みたがる日本のニュース
ガイジンとして―日本社会の「和」を乱せますか?
日英食文化―鰻の漬物、アリマス
おさらい―ぼくの架空の後任者への手紙