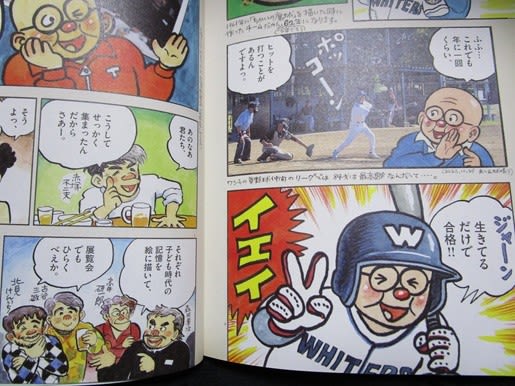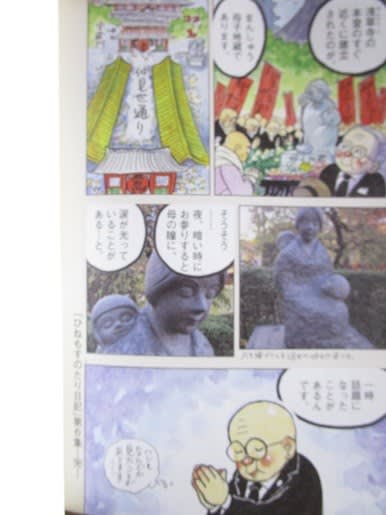P45
肉食動物の目は、動くものに反応するようになっている。(中略)
ところが、ナマケモノはほとんど動かない。
そのため、動くものを探す肉食動物の目には、木立の中で動かないナマケモノは目に入らないのだ。
P27
豚の体脂肪率は15%である。(中略)
この数字は、イヌやネコと比べても低い。(中略)
豚は時速40キロメートルで走ることができると言われている。これは100メートルを9秒台で走る速さである。
P74
カモノハシは、卵を産む卵生だが、卵から生まれた子どもを母乳で育てる。そのため、哺乳類に分類されているのだ。(中略)
2億5000年前からの恐竜が繁栄していた中生代にはすでにカモノハシは存在していたと考えられている。
カモノハシは、大昔から姿を変えていない「生きた化石」なのだ。
P110
百獣の王と言われるライオンの狩りの成功率は、およそ20%程度だそうだ。
それに対して、ブチハイエナの成功率は、70%を超える。
【ネット上の紹介】
ナメクジ、ダンゴムシ、モヤシ、イモムシ、雑草…。いつも脇役の、「つまらない」生き物たち。しかしそのつまらなさの裏に、冴え渡る生存戦略があった!ふしぎでかけがえのない、個性と進化の話。
第1章 「もっともない」生き物
第2章 「にぶい」生き物
第3章 「ぱっとしない」生き物
第4章 「こまった」生き物
第5章 やっぱり、そのままでいいんだよ
第6章 あなたもそのままでいいんだよ