
「椿の海の記」石牟礼道子
4歳頃の水俣が描かれている。
扉絵も著者自身による。
解説には次のように書かれている。
P302
これはあれが始まる前の幸福だった水俣の話であり、いわばあの悲劇の前史だ。この幸福感があったからこそ石牟礼道子は『苦海浄土』を書くことができたのだし、その意味ではこの『椿の海の記』が『苦海浄土』を下支えしているのだ。
【ネット上の紹介】
はだしで盲目で、心もおかしくなって、さまよってゆくおもかさま。四歳のみっちんは、その手をしっかりと握り、甘やかな記憶の海を漂う。失われてしまったふるさと水俣の豊饒な風景、「水銀漬」にされて「生き埋め」にされた壮大な魂の世界が、いま甦る。『苦海浄土』の著者の卓越した叙情性、類い希な表現力が溢れる傑作。
長谷川町子ってサザエさんみたいな人?
読者、視聴者は思うかもしれない。
長谷川町子さんは一度も結婚してないし、当然子どももいない。
3人姉妹+母親で生活。
それでも、一般庶民家庭を描き、その家族は日本中に親しまれた。
P177
母の貞子がマネージャーの役割で、原稿や取材の依頼などに対応する。依頼を受けるかどうかの判断は貞子の仕事だ。姉の毬子は町子の作品を専門に出版する姉妹社を切り盛りしてた。そして、妹の洋子は姉妹社の経理を担当し、さらに雑用を担い、町子の作品を読んで批評もした。
P261
あれだけ堅い結束を誇った三姉妹が最後は絶縁状態になった。そのため、町子が死去した時も、毬子はそれを洋子に知らせるのを拒んだ。
P268
毬子の真意はどこにあったのか。考えられるのは、洋子の存在を危惧したということだ。洋子は結婚して二人の娘がいる。いずれ、町子の財産は洋子やその娘に相続の権利が発生するはずだ。なんとしても、それを阻止したい意思があったのかと推測できる。
(中略)
洋子によると、町子の死は「冠動脈硬化症」だったらしい。
P282
仲良しで温かい家庭を描いた町子は、サザエさんとは対照的な道を歩み亡くなった。家族は崩壊し、まったく赤の他人が町子の残した偉業を管理し、その収益をコントロールするようになった。これは、通常のファミリー企業ではあり得ない話だ。
【感想】
著者の実情と作品が乖離することがある。
例えば、「アン・シリーズ」の著者のモンゴメリは自殺した、とも言われている。あれだけ、少女たちに夢を与えながら、本人は“鬱病で自殺”・・・。
【ネット上の紹介】
作者没後28年なお不動の人気を誇る国民的漫画、アニメの『サザエさん』。だが、15歳で天才少女としてデビューし、72歳で亡くなる5年前まで描き続けた長谷川町子とその家族のことは意外なほど知られていない。戦後の荒廃から日本が怒涛の成長を遂げた時期に『サザエさん』出版を家業として姉妹社を立ち上げた一家は、磯野家の人々とはおよそ真逆の愛憎、かけひき、確執が充満する空間を生きる。度肝を抜く額の収入、家族の不和と崩壊、自伝に書かれた虚―これらをひた隠した長谷川家の三姉妹の、苛烈な人生の光と闇を描いた評伝。
第1章 盗まれた遺骨
第2章 長谷川家の命運
第3章 天才少女漫画家
第4章 戦時下の恋
第5章 「サザエさん」連載開始
第6章 復興期の「サザエさん」第7章 嫉妬と羨望
第8章 巨万の富
第9章 町子の「家出」
第10章 「サザエさん」訴訟事件
第11章 家族崩壊
第12章 長谷川家の光と影

「夢の積み立てしませんか」矢口高雄
矢口高雄さんの銀行員時代の生活と、
漫画家としてデビューする経緯が書かれている。
とても面白く一気読みだった。
P161
「印鑑をお持ちでしょうか・・・・・・?」、などと言う例です。しかし、厳密に言えばこれは間違いです。印鑑とは、ハンコそのものではなく、紙等に押捺した印影のことです。ハンコそのものは印形、もしくは印判です。とはいえ、印鑑でも通じるわけですから、目くじらを立てるほどのことでもないわけですが、ハンコで充分正しいのです。
水木しげる先生のコメント
P241
マンガは略図じゃない――この一言には、目からウロコが落ちる思いでした。
それまでのボクは、マンガは手早く描くものだ、と思い込んでいました。さっきの水木先生のペンさばきは、力強く、気迫に満ちたものでしたが、想像以上にゆっくりとした運びで、細心であり、繊細だったのです。

【ネット上の紹介】
「釣りキチ三平」「ふるさと」「マタギ」等の自然マンガで知られる著者がマンガ家としてデビューしたのは、12年と2カ月にも及ぶ銀行員生活を経たあとであった。デビュー作「長持唄考」(51頁)他、マンガ・カット多数収録。
試雇に任ずる
雇に任ずる
書記補に任ずる
書記に任ずる
願により職を解く
9人の女性作家の評伝。
父との関係に焦点を当てて描かれている。
今年のベストの1冊と思う。
P11・・・渡辺和子
2.26事件関連の本で、父の殺害を目撃した幼い娘が泣きじゃくったという記述を読んだ記憶があった私が改めて確認すると、和子は「いいえ、泣いておりません」と否定した。
「私は、父の死で涙を流したことは一度もございません」
P32・・・齋藤史
ゆくすゑを誰も知らねば渡邊・齋藤の名もつらねたり一つ碑の面に
瀏の娘、齋藤史の歌である。
史は1980年、71歳のときにこの碑を訪れた。二人の名が同じ碑面に刻まれているのを見て複雑な思いを抱いたようで、
人の運命(さだめ)過ぎし思えばいしぶみをめぐるわが身の何か雫す
P62・・・島尾ミホ
「死ニタイ、シンドイ、結婚シタ事ヲクヤム」
「ジュウ(父)ヲ捨テタバチカモ」
ミホが結婚写真を嫌ったのは、それが父を孤独の中で死なせたことを思い起こさせるものだったからかもしれない。
P110・・・石垣りんの詩
家は夢のゆりかご
ゆりかごの中で
相手を食い殺すかまきりもいる
P168・・・田辺聖子
東条英機が自決に失敗したことを知った日の日記には〈とんだ死に恥をさらして気の毒ともあさましいともいいようがない〉(昭和20年9月14日)
P186・・・辺見じゅん
(父の)源義が再婚したのは1949年、辺見が10歳になる年のことである。
2月の末に子どもたちは富山の祖父母のもとから東京に戻り、新しい母・照子と暮らしはじめた。「お母さん」と呼ぶきっかけがなかなかつかめないでいた辺見だが、雛祭りが近づき、一緒に雛人形を飾っていたとき、気持ちがほどけて、自然に「お母さん・・・・・・」と呼びかけていた。
母は虚をつかれた表情でしばらく私の顔を見つめていた。そして次の瞬間、私を強く抱きしめた。(中略)
まだ21歳だった照子を、辺見は母として慕い、生涯にわたって大切にした。弟たちもそれは同じだった。(辺見じゅんは、生涯にわたってお父さん子だった、でも、新しい母をライバル視しなかった。なかなか出来る事じゃない)
P192・・・辺見じゅん(父は、角川書店創業者・角川源義)
弟の角川春樹は、当時、辺見から聞いたあるエピソードが忘れられないと話す。
大和が沈没したのは、春の盛りの4月7日だった。駆逐艦に救助された乗員たちは、翌日、九州の佐世保に帰還した。そのとき一人の兵士が、「桜が咲いている!」と叫びながら、気かふれたように甲板を転げまわったという。陸では桜が満開だった。(中略)「この話に心を動かされた私は、取材を続けてぜひ本にすべきだと辺見に言いました」
大和の乗員は3,332名。うち生存者は276名とされる。辺見はこのうち117名から話を聞き、遺族にも取材している。
P258・・・石牟礼道子
小学校の代用教員として終戦を迎えた道子は、翌年3月、勤め先の学校から帰る汽車の中で、ひとりの戦災孤児と出会う。骨と皮ばかりに痩せ、うつろな目をした裸足の少女。満員車内のでは彼女のまわりだけ空席ができていた。
話を聞くと、少女は15歳でタデ子といった。大阪付近の駅で半年ほど寝泊まりし、姉のいる兵庫県の加古川に行こうと切符を持たずに乗ったという。そのまま遠い九州まで来てしまったのだ。
車掌は、下車を命じたが降りないので困っていると言った。このままでは終点の鹿児島で放り出されることになる。道子はタデ子を連れて帰った。
道子におぶわれた異様な姿の少女を見るなり、晩酌をしていた亀太郎(父)がすぐに立ち上がり、水とお茶を持ってきた。松太郎(祖父)はみずから風呂をたき「このような姿になるまで、よう生きとったのう」と嘆息した。(中略)父と祖父は正反対の性格で、折り合いもよくない。だが家族全員が、他人の窮状を見れば迷わず手を差し伸べる人たちだった。
【参考リンク】1
旧「第七師団転地療養所」について: 旭川平和委員会 (cocolog-nifty.com)
【参考リンク】2


「昭和二十年夏、僕は兵士だった」梯久美子
「昭和二十年夏、子供たちが見た戦争」梯久美子
「昭和二十年夏、女たちの戦争」梯久美子
「百年の手紙 日本人が遺したことば」梯久美子
「狂うひと 「死の棘」の妻・島尾ミホ」梯久美子

「収容所(ラーゲリ)から来た遺書」辺見じゅん
「よみがえる昭和天皇 御製で読み解く87年」辺見じゅん/保阪正康
【ネット上の紹介】
不朽の名作を生んだ9人の女性作家たち。唯一無二の父娘関係が生んだ、彼女たちの強く、しなやかな生涯。
渡辺和子―「私は父の最期のときを見守るために、この世に生を享けたのかもしれない」
齋藤史―「もののふの父の子に生れもののふの父の寂しさを吾が見るものか」
島尾ミホ―「死ニタイ、シンドイ、結婚シタ事ヲ悔ヤム。ジュウ(父)ヲ捨テテ来タバチカモ」
石垣りん―「父と義母があんまり仲が良いので鼻をつまみたくなるのだ」
茨木のり子―「いい男だったわ お父さん 娘が捧げる一輪の花」
田辺聖子―「やさしい言葉の一つもかけることなく、父を死なせてしまった」
辺見じゅん―「父が亡くなり、私もまた死んだと思った」
萩原葉子―「私はまさしく父親の犠牲者としてこの世に生まれた」
石牟礼道子―「憎くて、ぐらしかおとっつあま、地ごく極楽はおとろしか」
魔女がどんな存在なのか、だんだん見えてきた。突き詰めて言えば、「母親」だったんですね。(中略)
魔法は何でもかなえてくれるものじゃないの。自分の願いを「発見」し、その願いを育てる「努力」を続ける。そこには苦しさもあるけど、「喜び」があって、そういうものから魔法は生まれると思った。だから「魔法は誰にでもある」。
2021年5月10日、朝日新聞より
第2章 小林カツ代の家庭料理とは何か?
第3章 大阪大空襲
第4章 カツ代を育てたミナミの味
第5章 料理研究家・小林カツ代誕生
第6章 母として、女としての葛藤
第7章 天命
魔の二二八事件
厳戒令と白色テロ
危険なところが最も安全
あえて虎穴に入る
蒋経国の死と李登輝の決断
台湾人総統の深慮遠謀
対極の道を歩いた男
台湾人に生まれた悲哀
歴史に残る初の直接選挙
心が凍りついた日
息子の遺稿にみる李登輝
第2章 作家デビューから『クララ白書』まで
第3章 マンガ原作の仕事と初連載『雑居時代』
第4章 一九八三年・八四年にみる多様な作品群
第5章 『なんて素敵にジャパネスク』と少女小説ブーム
第6章 男の子の行方―氷室冴子の少年主人公小説
第7章 少女小説から離れて―エッセイと一般小説の仕事
第8章 イメージから生まれた物語―『海がきこえる』
第9章 古代への情熱―『銀の海 金の大地』
第10章 氷室冴子は終わらない―九〇年代後半以降から
附録―「少女マンガの可能性」

「職業は津軽三味線奏者」鈴木利枝
小さいときに母を亡くし、破天荒の父に育てられる。
結果としてプロ奏者として自立したけど、困ったお父さんだ。
青森まで三味線を習うため、引っ越したのに、出会った師匠が最悪。
校長とぐるになって引きこもりに追い込む。
担任は何の役にも立たず。
閉鎖社会の弊害を思い知る。
高校には行かず、父に連れられアジア各地を放浪。
これが立命館アジア太平洋大学を志望する要因となる。
波瀾万丈の人生だ。
難を言うと、文筆家でないので、文章が物足りない。
痒いところに手が届かない。
例えば大學の人間関係がスルーされている。
津軽三味線奏者としての付き合いも同様。
心理的な葛藤の描写がイマイチ。
文章のプロじゃないから、仕方ない。
まぁ、それでも行間を読みとって楽しめる。
【ネット上の紹介】
幼い頃に母と死別、親族間を往復して育った筆者は、小学校高学年で三味線と出会う。独特な奏法の津軽三味線に魅了され、父と修業のため津軽へ。ところが、そこで人間不信となる出来事が……。そして、娘を精神的に成長させようと父が誘ったのは、過酷なアジア放浪だった。一時は、人前に出られなくなり、三味線もほぼ独学という筆者が演奏家となった半生を綴る感動ドキュメンタリー。

「80’s」橘玲
思った以上におもしろかった。
いままで、著者の作品(小説&ノンフィクション)を何冊か読んできたが、一番おもしろかったかも。
80年代から90年代前半を懐かしく思い出しながら読んだ。
P141
マイケル・ジャクソンの「スリラー」が世界を席巻したのは1982年で、「MTV]とそこで流されるPV(当時は「ビデオクリップ」と呼ばれた)がはじめてテレビで紹介された。83年にはシンディ・ローパーが「ガールズ・ジャスト・ワナ・ハヴ・ファン」で、84年にはマドンナが「ライク・ア・ヴァージン」で大ヒットを飛ばした。イギリスの人気デュオ、ワム!がクリスマスソングの定番「ラスト・クリスマス」を出したのもこの年だ(世の中はグリコ・森永事件で大騒ぎしていた)。
P199
89年1月に昭和天皇が崩御し、「不確実性の時代」が始まった。もちろんそれは日本だけのことではない。世界ではベルリンの壁崩壊(89年11月9日)とソビエト連邦の解体(91年12月25日)という現代史を揺るがす大事件が起き、第二次世界大戦後の国際秩序をつくってきた冷戦が終演した。
この混乱に乗じてイラクのサダム・フセインがクェートに侵攻し、91年1月にはアメリカを中心とする多国籍軍の攻撃が始まった。日本では自衛隊の参加の是非が大論争を巻き起こしたが、じつはサウジアラビアが国土防衛のため米軍の駐留を認めたことが歴史を大きく動かすことになる。聖地メッカを異教徒が守ることに反発したウサーマ・ビン・ラーディンが、2001年の同時多発テロを起こすことになるからだ。
もちろんこれは現代から振り返っていえることで、渦中にいるときはいったいなにが起きているのかわからなかった。89年6月には中国で民主化を求める天安門事件が起き、その後、中国共産党は鄧小平のもとで大胆な経済自由化に踏み出すのだが、当時の論調は難民が「盲流」となって日本に押し寄せてくると煽るものばかりで、中国の驚異的な経済成長が始まることを予想したひとはほとんどいなかった。
【おまけ】
橘玲さんて頭はよいけどエキセントリックでとっつきにくい人って思っていたが、本書を読むと、真面目で、友だち思いな面もある。つまりけっこう「いいやつ」じゃないか。見なおした。
【参考リンク】
橘玲『80's ――ある80年代の物語』
【ネット上の紹介】
日本がいちばんきらきらしていたあの時代、ぼくは、ひたすら地に足をつけたいと願った。バブルの足音からその絶頂、そして崩壊まで、1982年から1995年までの長い長い“80年代”の青春。
Prologue No Woman,No Cry
1978‐1981 雨あがりの夜空に
1982 ブルージンズメモリー
1983 見つめていたい
1984 雨音はショパンの調べ
1985‐1995 DEPARTURES
1995‐2008 マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン
Epilogue Redemption Song

「ゲゲゲの女房」武良布枝
NHKドラマにもなった有名な作品。
急に読みたくなったので手に取ってみた。
読んでいて、著者の人柄の良さを感じた。
P250
どんな生き方を選んだとしても、最初から最後まで順風満帆の人生なんてあり得ないのではないでしょうか。人生は入口で決まるのではなく、選んだ道で「どう生きていくか」なんだろうと、私は思います。
【ネット上の紹介】
巨人・水木しげると連れ添って半世紀。赤貧の時代、人気マンガ家の時代、妖怪研究者の時代、そして幸福とは何かを語る現在…常に誰よりも身近に寄り添っていた妻がはじめて明かす、生きる伝説「水木サン」の真実!布枝夫人にとって、夫と歩んだ人生とは、どんなものだったのか…!?水木しげる夫人が、夫婦の半生を綴った初エッセイ。

「高峰秀子の捨てられない荷物」斎藤明美
いったい家族ってなんだろう、と考えさせられる作品。
デコちゃんの愛称で知られる、高峰秀子さん。
日本を代表する女優である。
昔、私が学生だった頃、自伝「わたしの渡世日記」を読んだことがある。
半生を振り返り、生き生きと描写され、昭和史としても価値のある作品。
小学校もほとんど行けず、これだけの文章が書けるとは、どれだけ聡明なのか。
文章が巧いだけでなく、内容に深みがあり、面白い。
さて、本書であるが、裏「わたしの渡世日記」とも言うべき内容。
「わたしの渡世日記」で描かれなかった「負」の側面が描かれている。
著者はデコちゃんの養女・斎藤明美さん。
養女だからこそ書ける数々の真実。
秀子が4歳の時、実母・イソが結核で死ぬ。
そこからが苦労の連続。
養母・志げの元で小さい頃から、子役として働く。
養母と14人の親類縁者たちに食い物にされ続ける。
精神的にも、相当な苦痛だったと推察さる。
これはまさしく虐待である。
このタイトルの「荷物」とは、家族と思っていた。
読むとそれだけでないことが分かる。
養母、親類縁者、後援会、家・別荘・財産、仕事…なにより、“高峰秀子”という重荷。
天国で安らかにされていることを祈る。合掌。
P155
秀子がその聡明さを真っ直ぐに伸ばし長じていく中で、1人取り残され、またその成長にも気づかぬ母は、当初の愛情が妄執に変わり、さらに憎しみとなって、遂には、かつての“愛情”の原型さえも留めぬほどの、歪で醜い、何とも形容しがたい情念だけが志げの上に出現してしまったのだ。
P293
高峰がいつか言ったことがある。
「美空ひばりさんが羨ましかった。お母さんがひばりちゃんのために家庭教師をつけてくれたのよね。いいお母さんだと思う」
P404
人は生涯のうちにどれだけ人と出逢うものか知らないが、その中で、幸せを与えてくれる人が何人いるだろう。
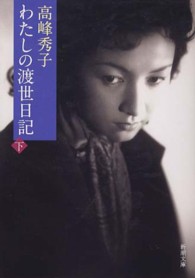
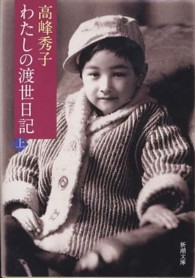
[目次]
一本のクギ
仮面と鎧
荷物
敵
人間嫌い
鶏卵
一日一笑
ふたり
【ネット上の紹介】
五歳で女優デビューし、「二十四の瞳」など数多くの名画に出演。五十五歳で引退後は名随筆家として知られた高峰秀子。養母を巡る親族たちとの葛藤、夫松山善三との生活など、高峰秀子を敬愛して「かあちゃん」と慕い、ついには養女となった著者が、本人への綿密な取材をもとに、その「潔い」生き方を描く、唯一無二の感動的評伝。高峰秀子の「ひとこと」に加え、松山善三によるレビューも収録。

「緒方貞子戦争が終わらないこの世界で」小山靖史
緒方貞子さんの評伝。
写真も多数収録されていて読みやすい。
聖心女子大・初代学長・マザー・ブリットの教え
P75
「『いろいろ勉強しなさい』と、ずいぶん言われました。それも社会科学ではなくて、哲学とかそういうものを学ぶべきだと……。それから、『結婚は、一度してしまえば一生していられるのだから、今はそんなことを考えないで、どんどん学問をしなさい』と言われましたね。(後略)」
P76
「あななたちは、鍋の底や皿を洗うだけの女性になっていはいけません」
「自立しなさい!知的でありなさい!協力的でありなさい!」
芳澤謙吉『外交六十年』より
P107
「私も犬養総理も満州国の独立なり、またはこれを承認することには反対しておった。(後略)」
緒方貞子さんの言葉
P160
『手に入る一次資料を集めなさい。色々探し回ること自体が勉強なのです。それは、必ずしも論文に反映されなくても無駄になりません』
『教育は身に付いた経験や知識を全てはぎ落とした時、最後に残るものです』
リーダーシップと決断力について、判断の基準は何か?
P179
「最後は勘ですね。全部整理していたら決められないですよ、いつまで経ってもね」
P180
「(前略)度胸も大事でしたね。あるいは勇気があることも大事でした。だってグズグズしてものを決められない上役がいると、じれったいでしょう?」
仕事の出来る人…共通の資質とは?
「ある程度、感受性がある、ということは大事でしょうね。それから、思考プロセスがかなり速い、ということもあると思います」
(安全のためにスピードは重要、ということだ…これは様々な分野で言える)
【おまけの感想】
幼い頃から、アメリカに住んだり、中国に住んだり。
聖心女子大一期生で、留学もしている。(当時の女性は、ほとんど尋常小学校程度)
父は外交官、祖父は芳澤謙吉、曾祖父は犬養総理。
血筋という言葉は好きではないが、環境は大きな要素。
恵まれた中で、さらに努力された、と言うことだ。
【ネット上の紹介】
国連難民高等弁務官として、世界中で多くの難民を救い、国際社会で評価された緒方貞子。その半生を追ったNHKスペシャルの待望の出版化!歴史を変えた、リーダーシップの真実とは―。
[目次]
第1章 政治家・外交官の家に生まれて―誕生‐アメリカと中国での生活
第2章 信念の人 父・豊一―日中戦争‐帰国
第3章 少女時代に見た戦争―真珠湾攻撃‐終戦
第4章 リーダーシップの原点―聖心女子大学時代
第5章 戦争への疑問 満州事変研究―アメリカ留学‐論文執筆
第6章 突然の国連デビュー―結婚‐出産‐大学での講義‐国連総会出席
第7章 日本初の女性国連公使―国連日本政府代表部への赴任‐上智大学教授
第8章 紛争と向き合う中で―国連難民高等弁務官時代
第9章 「人間の安全保障」を求めて―二十一世紀JICAでの活躍
エピローグ 日本人へのメッセージ

「セーラー服の歌人鳥居 拾った新聞で字を覚えたホームレス少女の物語」岩岡千景
歌人・鳥居の半生をたどった作品。
なぜ彼女は、成人してもセーラー服を着ているのか?
義務教育も受けていないのに、どのように学んだのか?
児童養護施設、DVシェルターの実態が語られる。
P17
大人になってもセーラー服を着ているのは、「小学校や中学校の勉強をやり直す場を確保したい」という気持ちを表現するためです。
いじめや貧困などさまざまな理由で、自分と同じように学校に行きたくても行けない子どもたちはほかにもいます。「そうした子たちがいることを知ってほしい」という願いも込めています。
P19
「鳥居」というペンネームを使い、本名も年齢も明かさず活動しているのは、性別や年齢の枠を越え、生と死、現実と異次元などの境界さえも越えて歌を届けたいという思いからです。
自分の目の前で友人が鉄道自殺してしまう
P101
警報の音が鳴り止み遮断機が気づいたように首をもたげる
ご遺族に会わないように大雪を選んで向かう友達の墓
【リンク】
岩岡千景『セーラー服の歌人 鳥居』
【ネット上の紹介】ネット上の紹介】
「義務教育も受けられなかった大人たちがいる」との表現から、成人した今もセーラー服を着ている異色の女性歌人「鳥居」。目の前での母の自殺、児童養護施設での虐待、ホームレス生活―過酷な運命に何度もくじけそうになりながらも短歌の中に「孤独な仲間の姿を見た」という彼女の半生を新聞社の文化部記者が物語るノンフィクション。今も複雑性PTSDの病と共に生きる女性歌人の感動的な半生。

「秘密 パレスチナから桜の国へ母と私の28年」重信メイ
重信メイさんと言っても分からないかもしれない。
日本赤軍の元最高幹部・重信房子の娘、である。
海外で生まれ、母は国際指名手配だったので、戸籍がない。
だから、日本に来る時、パスポートがないので苦労している。
幼少期から、成人して日本に来るまでが書かれている。
全編に母への愛情が感じられる。
P20
母が闘った三十年間の活動は、常に正反対のふたつの評価を与えられてきた。その結果、母は、ふたつの顔を持つことになってしまった。
ひとつは、パレスチナ民族解放のために命を賭けて闘った日本赤軍のリーダーとして、アラブ社会から敬愛されていた「英雄・重信房子」の顔である。
もうひとつは二十六名の死者を出した72年のリッダ闘争をはじめ、いくつもの「国際テロ事件」を引き起こした日本赤軍のリーダーとして、イスラエル、日本の政府などから追われていた「テロリスト・重信房子」という顔である。
私は、アラブ社会で生まれて育った。だが、重信房子の娘としてアラブ社会に受け入れられていたわけではない。私は、母の娘であることをひたすら隠し、日本人であることを隠して、住所を転々としながら生きてきた。
P121
母は、いつ殺される、いつ死んでしまうか、いつ逮捕されてしまうかわからない人だった。だから母は、自分がいなくなっても私が1人で生きていけるよう、自立して生きていける人間になるようにと願って、育てたのだと思う。
【ネット上の紹介】
日本赤軍のリーダー、国際的なテロリストとして世界に名を轟かせた重信房子に一人の娘がいた。メイである。数奇な運命にも負けず聡明で、心やさしく、感性豊かなメイが綴った、驚愕の手記!
[目次]
第1章 桜の国へ
第2章 太陽を握って生まれてきた娘
第3章 戦火の下で
第4章 母の記憶
第5章 中学高校時代
第6章 大学生活
第7章 母との再会
第8章 日本で歩き始めて


















