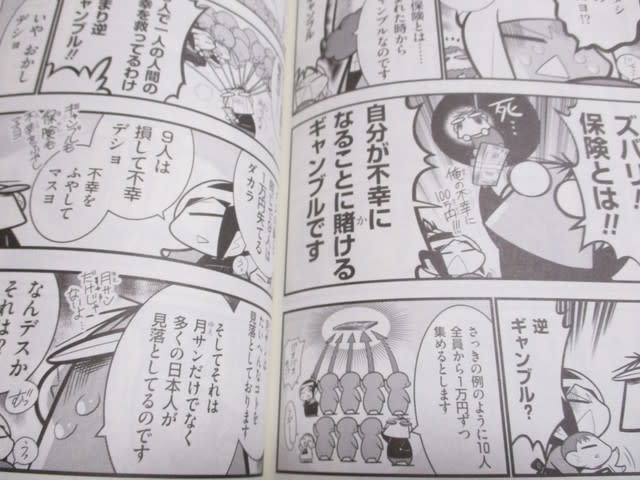P103
(軍艦島は2023年に訪問した。そのうち、三池炭鉱も見学に行こうと思っている)
第2章 なぜ高度成長ができたか?―1960‐1970
第3章 企業一家が石油ショックに勝った―1971‐1979
第4章 金ぴかの80年代―1980‐1989
第5章 バブルも40年体制も崩壊した―1990‐1999
第6章 世界は日本を置き去りにして進んだ―1980‐

「貧乏国ニッポン」加谷珪一
P18・・・シリコンバレー
サンフランシスコ市内から国道101号線を南下し、パロアルトマウンテンビューなどを経て、サンノゼに至るまでの地域のことを指します。
ここにはグーグルやアップル、フェイスブックといったIT企業が拠点を構えており、おびただしい数のIT長者が住んでいます。
P149・・・「プラザ合意」
米国政府は日本に対して強い警戒感を示し、1985年には為替を円高に誘導するよう呼びかけ、各国は米国の要請に応じることになりました。
協議が行われたホテルの名前を取って「プラザ合意」と呼ばれていますが、この国際的な合意によって1ドル=250円だった日本円は一気に上昇を開始、1995年には何と80円まで高騰したのです。(中略)円高対策による低金利で国内には大量のマネーが供給され、逆に日本はバブル景気に突入することになります。
P190・・・日本経済低迷の要因
日本では、いまだに年功序列による内部昇格でトップに就く経営者が多く、十分な適性を持たない人物が企業の舵取りをしているケースが多く見られます。(日本は同族経営が多く、どうしても二世、三世経営者になってしまう)
P67
駐在員が住みたい国ランキング
日本は32位。
賃金が低く、長時間労働、まとまった休みもとれず、幸福感が得られにくいと考えられている。
2位シンガポール、6位オーストラリアになっているが、同意しかねる。
シンガポールは独裁国家だし、オーストラリアは白豪主義で、日本人には住みづらく食事もまずい。但し、コアラ、ウォンバット好きな方は行く価値あるかも。

「金融恐慌とユダヤ・キリスト教」島田裕巳
経済と宗教の結びつきを指摘している。
目から鱗が落ちる佳作。
P49
イエスはユダヤ人であり、彼が説いた教えは、基本的にユダヤ教の教義に基づくもので、それを根本から革新するものではない。(中略)イエスは新しい宗教を開いた開祖ではなく、ユダヤ教の宗教改革家、預言者の1人と見ることもできる。(パウロや他の弟子たちがここまで大きくしたとも)
P53
19世紀の終わりには、ユダヤ人がもっとも多く居住していたロシアや東欧で、「ポグロム」と呼ばれるユダヤ人に対する迫害が激化する。(「屋根の上のバイオリン弾き」で、テヴィエ一家はニューヨークに向かう)
P71
仏教とキリスト教のカトリック、東方教会にしか出家という制度は存在せず、出家者もいないユダヤ教もイスラム教と同様、指導者であるラビは妻帯する。
P96
イスラム教では、その開祖であるムハンマド(マホメット)が、洞窟で瞑想していた際に、彼の前に現れた天使ジブリ―ル(ガブリエル)を通して伝えられた神のことばをつづったものが『コーラン』であるとされている。この『コーラン』に次ぐ地位を与えられている聖典が、ムハンマドの言行録である『ハディース』である。この『コーラン』と『ハディース』に記されたことをもとに、イスラム教の信者であるムスリムが従うべき法として確立されたのが、イスラム法の「シャリーア」である。イスラム原理主義者は、このシャリーアに忠実であろうとするところに特徴がある。
P99
ここで重要なことは、市場原理主義と宗教的な信仰との結びつきである。市場原理主義の根幹には、市場には「神の見えざる手」が働いているという考えがある。(提唱者はアダム・スミスと言われているが、厳密にはinvisible hand と言っているだけで、P105=少なくともスミスは、神の見えざる手という表現を用いてはいない)
P130
(分子生物学の発展により)遺伝子は自らを存続させるために利己的に振る舞い、個々の生物は決して主体的な存在ではないという考えが広まった。マルクスの説く資本には、この利己的な遺伝子に近い性格が与えられ、資本こそが資本家という存在をコントロールしている考え方がとられた。
P176
モスクの内部にも、聖なるものはいっさい存在しない。あるのは、礼拝の目処となるメッカの方角、キブラを示すミフラーブという壁の窪みだけである。イスラム教では、偶像崇拝が厳しく禁止されており、モスクの内部には、ほかに礼拝の対象となるような物は存在していない。
P201
日本人が、本格的に無宗教であることを自覚するようになるのは、むしろ戦後になってからのことである。戦後の社会においては、創価学会をはじめとする新宗教が勢力を拡大し、巨大教団に発展した。とくに創価学会の場合には、他の宗教や宗派の信仰を認めない立場を取り、それを激しく攻撃するとともに「折伏」と呼ばれる強力な布教活動を展開して、社会と衝突した。そうした事態を前にして、自分が社会的に騒ぎを起こす新宗教の信者でないことを明確にするために、無宗教という言い方が広く使われるようになる。
【ネット上の紹介】
グリーンスパンが「100年に1度の危機」と口走ったとき、その脳裏にはユダヤ・キリスト教の終末論があった―。アダム・スミス、マルクス、ケインズなど経済学の巨頭は「神の預言」からいかなる影響を受けていたのか。
第1章 終末論が生んだ100年に1度の金融危機
第2章 ノアの箱船に殺到するアメリカの企業家たち
第3章 資本主義を生んだキリスト教の禁欲主義とその矛盾
第4章 市場原理主義と「神の見えざる手」
第5章 マルクス経済学の終末論と脱宗教としてのケインズ経済学
第6章 なぜ経済学は宗教化するのか
第7章 イスラム金融の宗教的背景
第8章 日本における「神なき資本主義」の形成


第1章 日本が先進国だった時代が終わろうとしている
第2章 どうすれば賃金が上がるのか?
第3章 円安政策こそが日本経済衰退の基本原因
第4章 日本衰退の基本原因は、中国工業化への対処の誤り
第5章 未来に向かって驀進する世界の企業群
第6章 韓国、台湾の成長は今後も続き、日本を抜く
第7章 日本企業はどこに行く?
第8章 日本再生のために政府は何を出すべきか