
「消費される階級」酒井順子
P2
2006年の流行語大賞においては、「格差社会」の他にも「下層社会」「下流社会」「貧困率」といった言葉もノミネートされています。「豊かになるもならないも自己責任」といった考え方の流布によって経済的な上下差が著しくなり、階級が固定化されたのがこの頃である模様。
P41
韓国ドラマにおいては、日本のドラマよりもずっと、一重まぶたの俳優、それも特に女性俳優が重用されていました。
P206
オリンピックや万博といった大規模イベントは、懐メロ歌手のコンサートのように見えます。
P263
表面的な格差や差別は、今後も減少し続けるであろう日本。そうしてできたつるつるした世の中は歩きやすいだろうけれど、滑って転んでしまう人もいるに違いありません。つるっとした世では、段差の多い世よりずっと、立つ時も歩く時も力が必要となるに違いなく、そんな世に向けて、今はせっせと筋力を鍛えるしかないのでしょう。
【ネット上の紹介】
序列、区別、差別。表かえ、姿を変えた「凸凹」は世らは消の中のあちこちに。あの人より、上か、下か。日本人の階級意識をあぶり出す21の視点。
男高女低神話のゆらぎ
五十代からの「楢山」探し
まぶた差別と日韓問題
“親ガチャ”と“子ガチャ”
東大礼賛と低学歴信仰
『ドラえもん』が表す子供社会格差
「有名になる」価値の今昔事情
「ひとり」でいることの権利とリスク
おたくが先達、“好く力”格差
バカ差別が許される理由
ミヤコとアズマ、永遠のすれ違い
「かっこいい」、「ダサい」、「センスいい」
超高齢化時代のおばあさん格差
姫になりたい女の子と、姫として生まれた女の子
デジタル下層民として生きる
男性アイドルは無常の風の中に
世代で異なる、斜陽日本の眺め方
反ルッキズム時代の容姿磨き
モテなくていいけど、出会いたい
稼ぐ女と、使う女
遅ればせながらの金融教育

米原万里の「愛の法則」
読み返し。
P24・・・法的、経済的平等が実現した場合
性格が悪いのにもてる女と、すごく性格がいいのに全然もてない女、こういう理不尽な不平等は残るのではないか?
P65
日本人が言ってる国際化は、国際的な基準に自分たちが合わせていくという意味です。(中略)
アメリカ人が言うグロバリエーションは、自分たちの基準を世界に普遍させるということです。
P85
アラブとユダヤというのは激しく対立しています。パレスチナではもう絶え間なく殺し合いをしています。反目しています。でも、ほんとうはアラブ語とヘブライ語はほとんど同じなんです。同じ言葉の別な方言と言っていいくらいによく似ています。大体東京言葉と関西弁ぐらいの違いしかない、そのぐらい近いのです。
P125
どんな分野にも自分の能力について誤解している人間が、最低20%いると言われています。つまり、自分は実際の能力以上にできると思い込んでいるわけです。
P136
彼は本名を「ジュガシピリ」と言うんですけれど、自分のペンネームを「鋼鉄の意志を持った人」という意味で「スターリン」とつけて、さらにそれを公式の名前にしてしまった人です。
【ネット上の紹介】
稀有の語り手でもあった米原万里、最初で最後の爆笑講演集。世の中に男と女は半々。相手はたくさんいるはずなのに、なぜ「この人」でなくてはダメなのか―“愛の法則”では、生物学、遺伝学をふまえ、「女が本流、男はサンプル」という衝撃の学説!?を縦横無尽に分析・考察する。また“国際化とグローバリゼーション”では、この二つの言葉はけっして同義語ではなく、後者は強国の基準を押しつける、むしろ対義語である実態を鋭く指摘する。四つの講演は、「人はコミュニケーションを求めてやまない生き物である」という信念に貫かれている。
第1章 愛の法則(世界的名作の主人公はけしからん!
もてるタイプは時代や地域で異なる ほか)
第2章 国際化とグローバリゼーションのあいだ(「国際」は国と国とのあいだ
国を成立させる要素 ほか)
第3章 理解と誤解のあいだ―通訳の限界と可能性(同時通訳は神様か悪魔か魔法使い?!
濡れ場の多いベストセラー小説『失楽園』 ほか)
第4章 通訳と翻訳の違い(言葉を相手にする通訳と翻訳
小説を楽しめる語学力があれば通訳になれる ほか)

「お姫様とジェンダー」若桑みどり
ぱらぱらとめくって軽く読んだだけ。
本来ならアップしないのだけど、気になった箇所があったので書き出しておく。
「「白雪姫」とフェティシュ信仰」(石塚正英)を引用しているところ。
P106
「ナチスは自己の思想を宣伝するのにおおいにグリムを利用した。たとえば第二次大戦中に『赤ずきんの狼はユダヤ人であり、赤ずきんはドイツ人、赤ずきんを救い出す猟師は国民を解放するアードルフ・ヒトラーである』」と宣伝した。
P106
『闇の王子ディズニー』によると、ディズニーはイングランド系移民の厳格な父と、優しい母という典型的な家父長制家族に育った。(ディズニーはアイルランド系移民のはず。元ネタが間違っているのか、著者の勘違いなのかは不明)
【参考リンク】
ウォルト・ディズニー - Wikipedia
ウォルト・ディズニーのルーツを探し求めてアイルランドへ(誇張)
【ネット上の紹介】
コレット・ダウリングの『シンデレラ・コンプレックス』が刊行され、話題をよんだのは一九八二年。すでに二十年以上になるが、その間、「白雪姫」「シンデレラ」「眠り姫」などのプリンセス・ストーリーは、ますます大量に生産され、消費されている。大量に消費されるからその影響力も絶大である。本書では、ディズニーのアニメを題材に、昔話にはどんな意味が隠されているかを読み解く。いつの間にか思い込まされている「男らしさ」「女らしさ」の呪縛から、男も女も自由になり、真の男女共同参画社会を目ざす。
第1章 女子大でどうジェンダー学を教えるか
第2章 プリンセス・ストーリーとジェンダー
第3章 「白雪姫」を読む
第4章 「シンデレラ」を読む
第5章 「眠り姫」を読む
第6章 「エバー・アフター」(それからずっと)

「島へ免許を取りに行く」星野博美
何度目かの読み返し。
タイトルの「島」とは長崎・福江島のこと。
ここに五島自動車学校がある。
P18
合宿免許・・・・・・。二十年前ならともかく、もう40も半ばだよ。高校卒業したての子たちと一緒に合宿するなんて、悪い冗談にしか聞こえなかった。
P142
「いいなあ。大村って1回いってみたい。大村純忠の町でしょ」と言ったところ、「誰ですか、それ?」と思いきり怪訝な顔をされた。
「大村純忠。知らない?日本で最初に洗礼を受けたキリシタン大名で、十字架を首からさげて戦場に行ってたらしいよ」
(大村には長崎空港があるので訪問することになる)
P145
「バイキング」というのは、島の北端、三井楽にある道の駅「遣唐使ふるさと館」のレストランでバイキング式ランチを食べる、という意味だ。(中略)
「遣唐使館、三井楽教会、淵ノ元カトリック墓碑群、水ノ浦教会、楠原教会、ってルートはいかがでしょうか」
先生は目を丸くした。
「星野さんはまだ路上にも出とらんのに、島の地理をよう知っとるね」
(私も昨年11月にそれぞれ訪問してきた)
P248-249
質問 いつまでも運転がうまくならず、「下手くそ」と言われ続けています。
回答 運転を形容する言葉は二種類しかありません。それは「安全」と「危険」であって、「上手」「下手」ではない。目指すべきは「安全な運転」であてって、「上手な運転」ではない。運転技術の向上などまったく目指さなくてよか。「上手だけど危険」、これが一番いかん。「下手でも安全」、それでよかとです。
【参考リンク】
・・・五島自動車学校
〒853-0026
長崎県五島市浜町424番3
「島へ免許を取りに行く」星野博美
「島へ免許を取りに行く」星野博美
【ネット上の紹介】
愛する猫をなくしたうえに、人間関係はズタズタ。いやな流れを断ち切りたい。日常に小さな風穴を開けたくて向かったのは、島の小さな自動車学校。そこは、山羊や犬やにわとりがいて、馬にも乗れる牧場のような学校だった!人生の示唆に富む運転教習に悪戦苦闘しながらも過ごした数週間。人や動物や車とのふれ合いから見えてきた風景は?読めば、新しい何かに挑戦したくなる名作エッセイ。
[目次]
第1章(それはにわとりですか?
自動車学校で馬に乗る?? ほか)
第2章(新しい生活
初めて車を運転する ほか)
第3章(世界が逆転する
不思議な教科書 ほか)
第4章(車脳
逃避行 ほか)
第5章(仮免
路上デビュー ほか)
第6章(五島は「出る」
それぞれの旅立ち ほか)
第7章(免許取得
地獄篇 ほか)
P33・・・明石家さんま
「偉くなってしまった人が面白くあるのは、権力者が権力批判するのと同じだけ困難だ」を体現する存在。
P46
「ダメな俺」に居心地の良さを感じる男が必要とするのがスピッツだとしたら、「ダメな俺」をそう簡単に認めたくない男が必要とするのがミスチルだろうか。
P61
「するべきことをしない不良と、しちゃいけないことをする不良がいて、前者は許されがち、後者は愛されがち」
P67
「男性は家庭に不満がないときに浮気しがち、女性は家庭に不満があるときに浮気しがち」(トイアンナ)
【ネット上の紹介】
誰もが知るおじさん著名人たちへのファジーな嫌悪感の正体に迫る!!キャバ嬢、AV女優など実体験を通して夜の世界を体現しつつ、社会学の視点と女の感性を織り交ぜた軽妙な筆致で人気を博している文筆家・鈴木涼美によって、日本社会が生み出した難解なおじさんたちが今、解剖される
愚かなおじさんは愚かじゃない女がお好き?―ビートたけし
言い難き嘆きも手―岡村隆史・藤田孝典
分け入っても分け入っても、あるよ山―乙武洋匡・ダースレイダー
僕らがミスをチル理由―Mr.Children
嫌われ男の一生―麻生太郎
多目的トイレの神様―渡部建
星野源になりたいボーイと小沢健二の全てに意味を持たせたガール―星野源・小沢健二
世界はそれをクロと呼ぶんだぜ―箕輪厚介・鬼滅の刃・愛の不時着
この街に降り積もってく真っ黒な悪の華―松浦勝人・惡の華
ブスの瞳に恋するな―燃え殻〔ほか〕
グリーンスリーヴス
P17
イングランド民謡といわれるこの曲だが、実はヘンリー8世作という根強い説がある。後に妻となって斬首刑に処せられるアン・ブーリンへの求愛を表現した曲だとか。
P88
「処女聖マリアの被昇天の教義」が、ローマ教皇(ピウス12世)によって全世界に向けて交付されたのは、比較的最近のことで、なんと1950年だという。逆に言えば、それまでカトリック教会では、聖母の扱いに決着がついていなかったということだ。
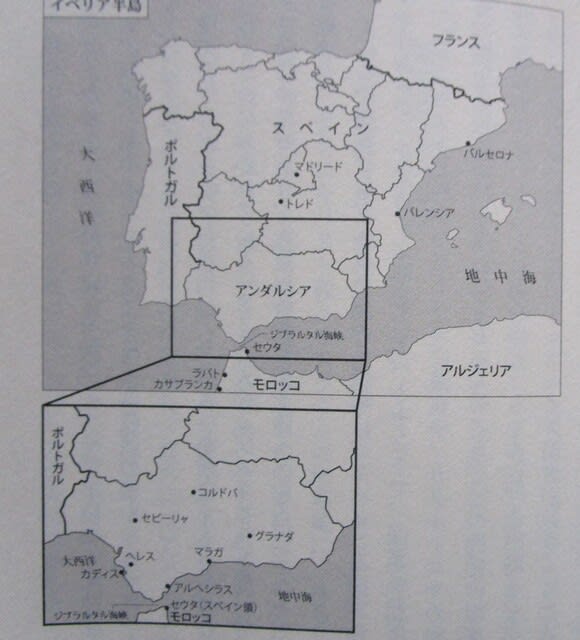
P225
カンティガが隠したい、最も濃い陰は、この歌集に内包された反ユダヤ主義ではないだろうか、という予感がした。
ピーヴァ(ヨアン・アンブロージオ・ダルツァ)
千々の悲しみ(ルイス・デ・ナルバエス)
死に向かって急ごう(『モンセラートの朱い本』)
天にあまねく我らが女王よ(『モンセラートの朱い本』)
死の舞踏(ハンス・ホルバイン)
聖母マリアの七つの喜び(カンティガ一番)
聖母の御業に驚くなかれ(カンティガ二六番)
コンスタンティノープル包囲(カンティガ二八番)
コンスタンティノープルを守った聖母のイコン(カンティガ二六四番)
右手を斬られたダマスコの聖イオアン(カンティガ二六五番)
モーロ王の嘆き(グラナダのロマンセ)
マラケシュを救った聖母の御旗(カンティガ一八一番)
気がふれたホスピタル騎士団の修道士(カンティガ二七五番)
殺されたユダヤ人の子ども(カンティガ四番)
ユダヤ人に汚されたキリストの像(カンティガ一二番)
囚われ人は決して(「獅子心王」リチャード一世)
聖人と福者
サントスの御作業
日本の殉教伝

「今日はヒョウ柄を着る日」星野博美
星野博美さんのエッセイ、再読。
P24-25
女子校出身の私は、女性の言動には非常に神経質なところがある。十代の頃、同級生たちは、あとで引きずり下ろすために相手を持ち上げたり、散々叩きのめしておいて救いの手を差し伸べ、恩を売ったりと、手のこんだ距離の構築を図っていた。女性の発する、真意の見えない曖昧な発言を真に受けると、十中八九、捕食者の餌食となる運命が待ち受けている。
P52
「なぜ盂蘭節に引っ越しすると縁起が悪いの?」
(中略)
「だって盂蘭節は、あの世の門が開いて、あらゆる死者の霊が地上に降りてくる時じゃないか。へんな霊がうちに棲みついたら困るんだよ。門が閉まるまでにきちんと帰ってもらわないとね」
日本のキリスト教徒に質問
P128
「やはりお盆はされないのですね?」
「しません。キリスト教徒の霊は、天国から戻ってきたりしないので。お盆に先祖の霊が帰ってくるという感覚は想像がつきません」
P165
世の中には、猫のいる人間と、猫のいない人間の二種類しかいない。
海苔(のり)が亡くなって、はや一年半になる。私はとうとう、猫のいない人間になってしまった。
【ネット上の紹介】
朝から賑わう戸越銀座商店街。そこでおばあちゃんたちがまとう「ヒョウ柄」の存在に気づいた著者は、人間界と動物界の相似性に敏感になる。そして若い世代‐高齢者、記憶‐真実、現世‐あの世といった境界を行き来しはじめ…。星野博美ワールドの「その先」を指し示す、あやしくてせつない、ユーモアあふれる豊かな異界の淵へ、ようこそ!新境地をひらく最新エッセイ集!

「戸越銀座でつかまえて」星野博美
星野博美さんのエッセイ、再読。
実家=戸越銀座に戻ってからの日々を綴っている。
週刊朝日での連載(2008年7月~2009年9月)が元になっている。
P8
自分はたった一つ、「自由」という小さな選択をしただけのつもりだった。
しかしこの「自由」というやつはすごく強欲で、ストーカーのように執念深い怪物だ。ちょっと楽しそうな出来事が現れるたびに「俺とあいつのどっちが大事なんだ!」とわめき散らし、「おまえは最後には俺のところに戻ってくるよな」と耳元でささやき続ける。それにすっかり洗脳され、楽しみや喜びが罪悪のように感じられる。
自由という名の暴君が、人生を食いつぶし始めたのである。
P72
旅とは何だろう。一言で言えば、片っ端から出会い、片っ端から別れること、だと私は思っている。出会いと別れがひっきりなしに訪れるから、喜怒哀楽の起伏は日常の比ではなく、思春期真っ最中の人のように、泣いたり笑ったり怒ったりを繰り返す。
P198
そしてハンガリーから帰国した日の翌日、しろは死んでしまった。
その翌年は取材のために中国へ行き、帰国した翌日、のりの兄、たまを亡くした。
私が海外へ行かなくなったのはそれからだ。海外へ行くたびに猫を失う。私には海外旅行が、もはや忌まわしいものにしか思えなくなってしまった。
そしてそれから精神状態が落ちこみ、実家へ戻ることに決めたのはすでに述べた通りだ。
P207
獣医のゆき子先生が言った。
「猫ちゃんって、がんばり屋なんですよ。必要以上に元気に振る舞うんです」
もともと捕食動物である猫は、弱みを見せると敵に攻撃されることを知っている。
だから本当は弱っているのに、攻撃されないよう、気丈に振る舞うのだという。
P226
私は丸二日、ゆきの遺体を抱いて眠った。
人が、死を受け入れるのはいつなのだろうか。
P228
このままだと、動物病院へ通ずる道しか歩けない人間になってしまう。ぼやーっと歩いても、動物病院へたどり着けない場所へ自分を隔離する必要がある。そして壊れた頭のプログラムを書き換えるくらいの荒療治が必要なのかもしれない。
そして、長崎県にある五島自動車学校へ、合宿免許を取りに行くことに決めた。
→「島へ免許を取りに行く」
P290
1人暮らしに敗北して実家に戻った。
それを認められるようになったのは、ようやく今年に入ってからだ。その一言を書いたら、鉛筆が進み始めた。そして結局連載時の原稿のおよそ半分は捨て、あらたに書きなおすことにした。
【ネット上の紹介】
40代、非婚。「自由」に生きることに疲れ、一人暮らしをやめて戻ったのは実家のある戸越銀座だった。変わりゆく故郷の風景、老いゆく両親と愛猫2匹、近所のお年寄りとの交流。そのなかで見つけた新たな生き方。“旅する作家”が旅せず綴る珠玉のエッセイ。
第1章 とまどいだらけの地元暮らし(二つの町
妻妾同居 ほか)
第2章 私が子どもだった頃(仔猫と旅人
えこひいき ほか)
第3章 あまのじゃくの道(負け猫と負け犬
時間よ止まれ ほか)
第4章 そこにはいつも、猫がいた(皆既日食
時差 ほか)
第5章 戸越銀座が教えてくれたこと(二〇一一年三月十一日
防災訓練 ほか)

「迷子の自由」星野博美
星野博美さんのエッセイ。
久しぶりの読み返し。
半分くらいを写真が占めているのが特色。
また、インドと重慶についても書かれている。
P47
なぜ香港にこれほどインド系の人々が多いかというと、一言でいえば阿片戦争が原因だ。インドの植民地化に成功した英国は、次に中国を狙って阿片戦争をしかけた。そしてその際植民地として得た香港には、警察や軍隊要員としてインド人を大量に送り込んだ。その末裔たちが、いまでも香港には多く暮らしているのである。
P54
「インドというのは面白いところだよ。インド人はyesという時に首をふるんだよ。何を尋ねても首を振っているから、yesなのかnoなのか、こっちにはさっぱりわからない」
P150-151・・・反日感情について書かれている
1937年の盧溝橋事件の後、蒋介石は重慶に臨時政府をおいた。
そのため、1939-41年まで、日本軍の空爆にさらされた。
あちこちに防空壕が残されている。
著者は、そんな重慶に反日運動が高まっている時に訪問している。
この反日気運は、旧来の単純なナショナリズムだけでは説明しきれない、何か別の不満感情が複雑にからみあって生まれたものではないだろうか。重慶にいたからこそ、私はそう感じた。
[目次]
東京(引っ越しの朝
ブロッコリー ほか)
インド(インドへの道
夢 ほか)
東京(そっぽのアンテナ
サクラチル ほか)
重慶(チュンキン
ルーシーの夢 ほか)
東京(記憶喪失の予定
私は機械になりたい ほか)
[出版社商品紹介]
今日は迷おう。知らない道を歩いてみよう。迷子になることで何が見えてくるのだろう。著者の写真×エッセイ集。

「のりたまと煙突」星野博美
星野博美さんのエッセイ。
久しぶりの読み返し。
P162
私はどうしても猫を室内に閉じこめることができない。自由を好む猫を閉じこめなければならないくらいなら、飼わないほうがいいとさえ思っている。しかし自由にするとは、リスクを負うことだ。自由にしたために、しろは交通事故で左の後ろ足をつぶされ、ゆきは誰かにいたずらされて尻尾を折られた。
そして猫を自由にさせることの最大の皮肉は、飼い主を捨てる自由を与えるということだった。
P172
日本でお盆といえば、先祖が地上に戻ってくるという印象が強いが、香港ではその晩にあの世の門が開き、先祖だけでなく、ありとあらゆる「鬼(=霊魂)」が地上に戻るという、恐れに満ちた節目である。
P182・・・香港の話
「昔は、郵便屋さんがうちの前まで来ても、賄賂を渡さなければ手紙をくれなかったんだよ」
【誤植】P259
逃げ出したそうだった
↓
逃げ出しそうだった
【ネット上の紹介】
すべてを忘れて、私たちは幸せに近づいたのだろうか…。吉祥寺と、戸越銀座。著者はさまざまな猫たちとの出会いと別れを経験し、生と死、そして忘れえぬ過去の記憶へと思いをめぐらせていく。さりげない日常からつむぎ出される短篇小説のようなエッセイのひとつひとつに、現代への警鐘と内省がにじむ。
[目次]
第1章 木春菊
第2章 梅
第3章 桜
第4章 百合
第5章 萩
第6章 芒
第7章 彼岸花
第8章 柳
第9章 柊
第10章 松
第11章 雪柳
第12章 躑躅

「銭湯の女神」星野博美
久しぶりの読み返し。
比較的、初期の作品。
2001年に上梓されている。
順番で言えば、「転がる香港に苔は生えない」の次。
P15
旅に出る機会が比較的多い生活を始めてから13年。たかが旅、と思っていた存在が肥大化し、日常を侵食する瞬間というものがある。大きなものから小さなものまで、何らかの決定を下す時、旅が自己主張し始めるのだ。
p78-79・・・偽装結婚した日本人の話
「結婚の宣誓のあと、キスをしなきゃならないんです。周りの偽装結婚の人たちは、いかにもそれらしく大袈裟に抱き合ってキスしてたけど、私にはどうしてもキスできなかった。その時、ああ、これが偽装結婚ってことなんだな、って初めて実感しました。私はキスすらできない相手と、法律上は夫婦になったんだ、って」
P156
灼熱地獄の南中国を旅していた時のことだ。南中国の沿岸部は鉄路が発達していない。これはこの海岸線が台湾に面しているため、有事の際に鉄道が攻撃目標にされやすいからだといわれているが、それはさておき、移動にはもっぱらバスを利用した。
星野さんは、かつて就職をしたことがある、その初日の話
P177
「星野っていって思い出すのは、入社した日のことだよ。あの日、自分が何いったか覚えてる?」とT氏が尋ねた。もちろん何も覚えていない。私は首を振った。
「これは大事な仕事だから、これから星野さんに引き継ぐよ、っていったんだ。そしたらこいつ、何ていったと思う?『そんなに大切な仕事だったら、引き続きTさんがやってください』っていったんだよ。俺はたまげたね」
(中略)
「よくお局様につっかかって、ひやひやさせられた。星野がお局様に向かって『ちょっと待ってください』っていいながら立ち上がると、フロア全体に緊張が走ったな」
P209
仕事柄、旅に出る機会は一般の人よりは多いが、それが仕事であれ遊びであれ、いまだにどうしても旅が好きになれない。
P216
十代は、個性の見えない自分との闘いだった。
二十代は、自分にしかできないことを模索する自分と、普通の人にできることを期待する周囲との闘いだった。
三十代になり、そんなことはどうでもいい、他人から見て少々異質に見えようが、自分は自分の考える「普通」の生き方をしていけばいい、と腹をくくれるようになった。一番見苦しいのは、「自由業だ」「芸術関係者だ」と開き直って、数々の愚行や不道徳や不義理や非常識を社会から免罪されようとすることだ。
社会と接触して生きていく限り、どんな理由も免罪符にならない。
【注意】
最初、文庫本で読み、2回目、単行本で読んだ。
頁番号が合致しない場合がある。
ご了承ください。
【ネット上の紹介】
切なくも騒々しく、温かい街から戻ってみれば、異和感のなかに生きる私がいた。自分の存在そのものが異物になってしまったようだった―。現在の東京を象徴する両極、銭湯とファミリーレストランを周遊する暮らしから芽生えた思いを、鋭い観察眼と端正な文体で描いた、大宅賞受賞の俊英による39の名エッセイ。
私がテーブルを買う時
燃えるゴミ
パンクは態度である
一〇〇円の重み
大女
The Net
新聞の正しい読み方
偽装結婚
癒しのまやかし
ああ、胃炎〔ほか〕
人間関係が破綻し、友達を失い、愛猫にも死なれ、閉塞状態となる。
それを打開するために、40台半ばにして思い立つ。
「免許を取ろう」と。
ネットで検索したら、長崎の五島列島に希望に添った自動車教習所が見つかる。
無料で馬にも乗れて、目の前が海というロケーションのよさ。
この作品は、そこでの寮生活、日々の奮闘を描いている。
P18
合宿免許・・・・・・。二十年前ならともかく、もう40も半ばだよ。高校卒業したての子たちと一緒に合宿するなんて、悪い冗談にしか聞こえなかった。
私はもともと協調性に著しく欠け、クラブ活動やサークル活動もろくにしたことがない。当然、合宿経験は一切なし。通学する時も、同級生がいない遠くの車両にわざわざ乗るくらい人間関係が煩わしく、会社勤めだって、ロッカールームや女子トイレでたむろする女性たちの井戸端会議がいやで挫折したほどだ。旅行にしても一人旅が鉄則。団体行動がとにかく苦手なのだ。
P61
人間、何かができれば嬉しいし、できなければ悲しい。できないことばかりを考えていたら前には進めない。だからできないことは、「自分には向かない」と言い訳して存在を無視する。そうやってこれまで生きてきた。
P142
「いいなあ。大村って1回いってみたい。大村純忠の町でしょ」と言ったところ、「誰ですか、それ?」と思いきり怪訝な顔をされた。
「大村純忠。知らない?日本で最初に洗礼を受けたキリシタン大名で、十字架を首からさげて戦場に行ってたらしいよ」
P145
「バイキング」というのは、島の北端、三井楽にある道の駅「遣唐使ふるさと館」のレストランでバイキング式ランチを食べる、という意味だ。(中略)
「遣唐使館、三井楽教会、淵ノ元カトリック墓碑群、水ノ浦教会、楠原教会、ってルートはいかがでしょうか」
先生は目を丸くした。
「星野さんはまだ路上にも出とらんのに、島の地理をよう知っとるね」
P155-156
「近くを見るから怖いんだ。遠くを見ろ!そうしたら怖くなくなるぞ」
言われた通りにすると、すーっと恐怖が消えて無くなった。
「メリハリというのはつまり、大胆と慎重、勇気と臆病、自信と謙虚といった、二つの正反対の価値観を使い分ける、ってことですか?」
「すごく難しく言えば、そういうことです」
(中略)
勇気ある前進と、細心の安全確認。大胆な走りと、慎重な危険予測。自分は大丈夫という楽観主義と、どんな悪いことも起こりうるという悲観主義。その際限ない繰り返しが、車を運転するということか。
P204
私が旅の信条としていることだが、世界のどこにもおもしろくない場所など存在しない。自分が行先に選んだ場所をおもしろがれないとしたら、それは楽しむ努力が足りない自分の責任なのだ。想定と違うのなら、その想定をチューニングするべきだ。それでもどうしても楽しめないというなら、立ち去ればいい。通過者にはその自由があるが、選んだ場所を批判する権利はない。
免許を2週間で取得する予定が1ヶ月過ぎようとしていた。
いつしか『寮長』とあだ名されるようになり、若い子たちの面倒もみて、人生相談にものるほどになる。
23歳でバツイチ3歳の子持ち、母を亡くし、生活のために免許を取りにきたガラパちゃん。
P205
「自分、普通の人が一生かけて経験することを、この歳で全部やっちゃったって感じです。この先、いいことなんてあるんですかね?」
自分に発言する資格などないように思えたが、あえて言った。いいことだらけの人生はないし、悪いことだらけの人生もない。いろんなことをゆっくり経験する人もいれば、一気に経験する人もいる。いまは嵐のように思えるかもしれないが、嵐のあとには必ずナギが来る。これからいいことはいくらでもやって来る。それをしっかり掴めばいい。
なんとか運転も出来るようになり、卒業検定も合格、落ちこんでいた精神状態も回復。
平成22年5月25日、東京の鮫洲運転免許試験場で筆記試験を受け、合格する。
P233
誰もが無理だと思っていた車の免許を、本当に取ったぜ!誰かに見せびらかせたい。「どう?」と愛猫、のりに見せてみる。「うるさいなあ、まだ眠いんだよ」という顔で見事に無視される。
あとは実践を積んでさらに上達するだけ。
でも、なかなか上手くならない。
教習所の校長先生に電話をかける。
P248-249
質問 いつまでも運転がうまくならず、「下手くそ」と言われ続けています。
回答 運転を形容する言葉は二種類しかありません。それは「安全」と「危険」であって、「上手」「下手」ではない。目指すべきは「安全な運転」であてって、「上手な運転」ではない。運転技術の向上などまったく目指さなくてよか。「上手だけど危険」、これが一番いかん。「下手でも安全」、それでよかとです。
【参考リンク】
・・・五島自動車学校
〒853-0026
長崎県五島市浜町424番3
「島へ免許を取りに行く」星野博美
「島へ免許を取りに行く」星野博美
【ネット上の紹介】
愛する猫をなくしたうえに、人間関係はズタズタ。いやな流れを断ち切りたい。日常に小さな風穴を開けたくて向かったのは、島の小さな自動車学校。そこは、山羊や犬やにわとりがいて、馬にも乗れる牧場のような学校だった!人生の示唆に富む運転教習に悪戦苦闘しながらも過ごした数週間。人や動物や車とのふれ合いから見えてきた風景は?読めば、新しい何かに挑戦したくなる名作エッセイ。
[目次]
第1章(それはにわとりですか?
自動車学校で馬に乗る?? ほか)
第2章(新しい生活
初めて車を運転する ほか)
第3章(世界が逆転する
不思議な教科書 ほか)
第4章(車脳
逃避行 ほか)
第5章(仮免
路上デビュー ほか)
第6章(五島は「出る」
それぞれの旅立ち ほか)
第7章(免許取得
地獄篇 ほか)

「ペルソナ」中野信子
珍しく自分自身を語っている自伝エッセイのような作品。
P42
生まれか、育ちか、というのは生物分野の研究者たちがしばしば議論の俎上に載せる定番のネタである。英語では Nature or nurture といって、韻を踏むような語句になっている。
P194
勝ち組・負け組という言い方があるが、私はあまり好きではない。なんとも下品な言い方で、軽く使われているが、この言葉には稼いでいなければ生きている価値がないといでもいうかのような野蛮で貧しい響きがある。
同様に、働かざる者食うべからずという言葉も私は大嫌いだ。
P227
通知表に「利己的」と書かれたことがある。誰とも結ばず、一人の時間を楽しむ私に対して教師が抱いた印象がそれだったのだろう。私は「生物はすべて利己的なものだけど?」と思うだけだったが、母がなぜかショックを受けて、私に怒鳴り散らしたのを覚えている。(中略)子どもならではの残酷さで、この人が本当に私を産んだのだろうか、と落胆することもあった。(中略)自分のせいでこんなことを書かれたのかもしれないね、ごめんね、と余裕のある女性なら言ったかなあと思うけれど。ともあれ、7歳の子どもに八つ当たりできるくらいの人格ではあった、と言うことになる。また、小学校の教員といってもあまり頭が回らないのかもしれない、とこの時は腹立たしかった。こんなことを書けば、子が親にどんな目にあわされるか、想像がつかないのだろうか?
【ネット上の紹介】
親との葛藤、少女時代の孤独、男社会の壁…人間の本質を優しく見つめ続ける脳科学者が、激しく綴った思考の遍歴。
はじめに わたしは存在しない
1章 サイコマジック―2020
2章 脳と人間について思うこと―災害と日本 2010~2019
3章 さなぎの日々―塔の住人はみな旅人である 2000~2009
4章 終末思想の誘惑―近代の終わり 1990~1999
5章 砂時計―1975~1989
おわりに わたしモザイク状の多面体である

「すべてを手に入れたってしあわせなわけじゃない」鈴木涼美
15のシチュエーションで、30人の女性への聞き取り調査。
P36
思えば女の一生は、妊娠を心配する10代20代に次いで、不妊を心配する30代40代が始まり、子どもができない身体になって終わる。高校生や大学生は基本的に生理が遅れるたびに、酔って甘かった避妊を後悔し、妊娠検査薬を天にかざして祈り、遅れてきた生理に安堵の涙を流して生きている。
P102
「どうせなら、高校生とか暇なときに子供産む方か゛いい気がする」
P132
いかにも男ウケを狙ったファッションやキャラ作りというのは得てして他の女からの評判を落とすが、男に全くモテない人生というのはそれはそれで他の女からバカにされるものだ。つまり私たちは、男ウケをそんなに狙っていないふりをして男ウケを狙う、というものすごく手の込んだことをしながら生きていかなくてはいけない。そうです、女は面倒臭いんです。
【感想】
人生の節目で様々な選択を迫られる。
結婚するかどうか?
子供を産むかどうか?
仕事を続けるかどうか?
理性で夫を選ぶか、胸キュンで選ぶか?
しかし、どの選択をしても後悔は残る。
選ばなかった選択肢を振り返ってしまう。
ひとつ選ぶとひとつ失う。
本書は30代の女性たちが登場するが、
さらに歳をとるとどうだろう?
認知症のお年寄りは、あるはずのない物を探すことがあります。
(中略)
年をとるということは、多くのものを得て、そして失うということでもあります。あなたはいまも生きているし、あなたのことを大切に思っている人がここにいる。そのいちばん大切なことは何も失われていないということを、探し物を一緒に探すという行為を通して伝えます。(「認知症介護びっくり日記」)
【関連図書】
女性への聞き取り調査というと「沼で溺れてみたけれど」を思い出す。
【ネット上の紹介】
キャリア、結婚、子育て、不倫。女の人生には、果てしない選択肢があり、そのどちらも、意外としんどい。風俗やAVの経験も持ちつつ、東大大学院で社会学を修め、元日経新聞記者でもある、気鋭の書き手、鈴木涼美が、15のシチュエーションで、30人の女性を取材。30代半ばの女のリアルを、エッジの聞いた文章で読ませます。女の人生、15本勝負。軍配はどちらに! 生きるヒントが見つかる、注目のエッセイです。
会社人生―会社は真綿でできた鉄の檻。いてもやめても苦しい
不倫問題―専業主婦を見下す独身、でも妻の方は…
子作り―早く産むか遅く産むかで、女の人生は引き裂かれる
学歴―使えない高学歴は無意味、でもそれがないと…
雇用形態―本当にやりたいことは会社じゃできない、という夢想
出身地―都会のど真ん中で婚期を逃すか、ワンオペ育児か
独身生活と結婚願望―好きでなくなったら別れる、で、なんでいけないの?
ママ―自分が何者でもないのは、会社員も専業主婦も同じ
旦那のスペック―夫に期待したのが間違いだった。主婦が夢から覚める時
モテ―いつまでもモテ続けるわけではないという絶対真理
自分の歴史―過去をひきずり、人生に折り合いがつけられない不幸
東京と地方―キラキラの東京は、捨てるにはあまりにも惜しくて
彼氏―頭の満足と、心や子宮の満足はまったく別もの
地方と都会の不倫事情―ママ友がいたって、寂しさは消えないから不倫する
港区女子―キャバ嬢とソーシャライトの間、それが港区女子

「まだある旅客機・空港の謎と不思議」谷川一巳
プロペラ機のメリット
P30
低騒音であること、短い滑走路で離着陸できること、そして短距離の場合はジェット機に比べて所要時間で遜色はなく、燃費がいいことなどが挙げられる。
P31-32
ジェット機の巡航速度が時速800~900キロに対し、プロペラ便では時速600~700キロ。しかしジェット便での飛行高度がおよそ2万フィート以上なのに対し、プロペラ便は8,000~1万6,000フィートと低い高度を運航するので、距離が短い場合は所要時間差がほとんどない。
P48
現在のプロペラ機は「ターボプロップ」といい、ジェットエンジンでプロペラを回しているが、レシプロ機は自動車などと同じピストンエンジンでプロペラを回しており、いわば主翼にエンジンで回る扇風機が取り付けられているような構造であった。
P169
現在アメリカにはデルタ航空、ユナイテッド航空、アメリカン航空という「ビッグ3」があるが、戦国時代に入る以前は「ビッグ4」といわれ、アメリカン航空、ユナイテッド航空、デルタ航空、イースタン航空という顔ぶれであった。(日本で有名なパンナムは経営破綻した)
P204
空港経営は着陸収入が大半を占めるが、着陸料は機体の重さで決まるので、当然大型機が就航したほうが空港収入は大きくなる。
P208
ハブ空港は大都市にある必要はなく、広大な土地の確保しやすい場所が選ばれた。具体的にはアメリカン航空のダラス、ユナイテッド航空のシカゴ(後にデンバーも)、デルタ航空のアトランタ、コンチネンタル航空のヒューストンなどである。
大手系列のLCC
P263
大韓航空に対してジンエアー、アシアナ航空に対してエアプサン、タイ航空に対してノックエアー、シンガポール航空に対してタイガーエアウェイズ、カンタス航空に対してジェットスター、これらはすべて大手系列のLCCである。エアプサンはアシアナ航空と釜山市の共同設立のための名称だ。
【関連図書】
「旅客機・航空会社の謎と不思議」谷川一巳
【ネット上の紹介】
最新機「ボーイングB787」と「エアバスA380」は何がどうすごいのか。着陸時に「フラップ」「エルロン」「スポイラー」はどんな働きをしている?日本の空港はまるでテーマパーク!?国によって空港はこんなにも設備が違う。機内で、空港で、そう言われてみればなぜ?となる疑問、解決します。
第1章 旅客機の謎
第2章 旅客機発達の謎
第3章 機体の謎
第4章 旅客機運航の謎
第5章 航空会社の謎
第6章 空港の謎
第7章 航空運賃の謎


















