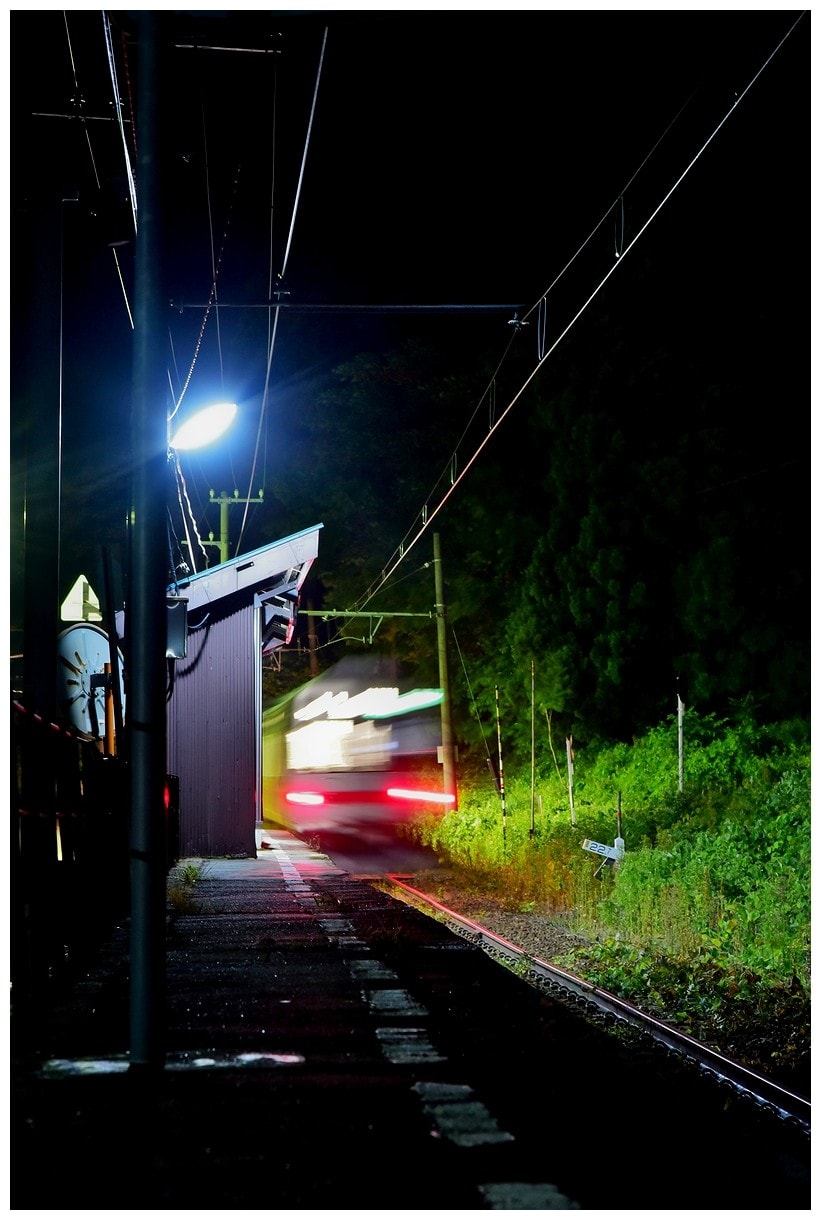(梅雨明けの日差しの中で@馬庭~西山名間)
5月のGWは長電&上田、そして6月は地鉄と松電。コロナ禍の中でも、ちょこちょこと泊まりのない程度のソロ活ショートトリップを繰り返している最近の自分。6月に撮って来た地鉄の写真もあらかた整理し終わったところで、タイミングよく関東地方に梅雨明けの報。梅雨明け一週間は天気の相場的に安定して晴れるだろうと踏んで、群馬の上信電鉄に久々に行って来ました。もうしばらく来てないからホントご無沙汰。お隣の秩父までは良く来るのだけどね。何で上信?というのは特に理由はないけど、強いて言うならば今どき珍しい自社発注車の比率が高い地方私鉄だって事。だったのだけど、いつの間にやら上信のラインナップは最近導入された新前橋電車区のJR107系に席巻されていて、来る電車も来る電車も107系という状態。上信では700形を名乗っているようだけども、あれほどいた独自色の濃い自社発注車はどこへ・・・?という感じ。思えば前来たのってもう7年前くらいだから、時は流れたんだなあと。
梅雨明けと同時に行くにはちょっと灼熱が過ぎたかもしれない上州路。妙義荒船に繋がる山並みを背に、夏の日差しを浴びる向日葵の横を快走する下仁田ジオパーク編成、これは元々西武の701系に施されていたラッピングだと記憶しておるのだけど。701が107という回文的な輪廻転生である。閑話休題、話がそれた。ここから暫く、西上州を走る地方私鉄の夏の日に、お付き合いのほどを。