震災とそれに連動した原発事故は、その破壊しつくされた様子と、その国難の度合いから「第二の戦後」とも言われている。
では実際に終戦直後から占領が開けるまでの間に何が起こり、ボクらの父や祖父の世代の日本人がその国難をどう受け止め、どう切り抜けていったかについては学校教育の中では「全く教えられてこなかった」と言えるだろう。
そんな時代について書かれているのが、ジョン・ダワー著「敗北を抱きしめて」という本だ。この本はアメリカのジャーナリストに贈られる最高の栄誉であり、最も権威ある賞であるピューリッツァー賞を受賞している。とは言っても「アメリカ人が見た日本人観」からは完全に抜け切れているわけではなく、記述に多少違和感を持ったり反論したくなる部分もあるのだが、それでも当時の様子を知るには貴重な一冊であることは間違いない。
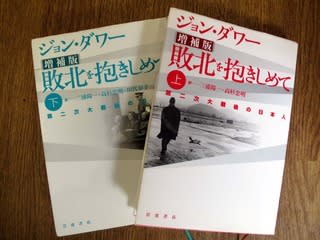
この本には「敗戦という悲惨な状況の中、文字通り『何もかもなくした』日本国民達が秩序を守りつつも、如何に苦難を乗り越え、様々な創造性を発揮して立ち直っていったか」が書かれているが、それと同時に「如何なる問題が解決できずに残ったのか?」ということが書かれてもいる。
今回の震災でも「何もかもなくした」人々が大勢居て、本当にお気の毒に思うが、「敗北を抱きしめて」を読んだ後に比較してみると、被災地と戦後の状況にはかなりの違いがある事に気付く。
戦後の日本は国内主要都市部の多くが爆撃されて灰燼に帰しており、都市部と農村部の差は多少あったにせよ、全国的な食糧難と物資不足に加えて国民は恐ろしいスピードのインフレにさらされていた。当然輸出入も成り立っておらず、事態は深刻であったが、反面、物さえあれば売れる時代であったが故に、荒れ野に生える雑草の如く闇市が各地に生まれ、そこでの取引が盛んになることで「市民の持つパワー」の一面が発揮されていった。だから、「まずは物さえ生産、もしくは供給できれば…」それが復興の足がかりの一つになっていたのだ。
対して今回の震災においては、被害を受けていない中部以西の西日本からの物資が豊富にあるうえ、諸外国からも被災地へ向けて物資が入り込んでくる。それを端的に示しているのが、ペットボトル入りの水や乾電池の供給過程だ。生産施設を失い、資金や体力を失った被災地の企業や商店が復活するには、ただでさえ相当の困難が待ち構えているのに、他から商品が流れ込み、シェアまで奪われてしまった後ではその困難さが更に増すだろう。だから軽々しくも「戦後の危機も乗り切れたんだから…」と言う言葉で括ってしまうべきではないと思う。
しかし、「敗北を抱きしめて」を読んで感じた戦後の一番の問題点は、上述した「如何なる問題が解決できずに残ったのか?」という部分にあると思う。
GHQは「民主主義」を自国(アメリカ)でも達成困難な実験的な部分を含めた内容をもって上から押しつけ、我々日本人もそれを多くの部分で善意に解釈して受け入れてきたが、成果が出る前に朝鮮戦争と冷戦が始まったがためにGHQいや、実質米軍は「既存の力を持った官僚や企業組織」を更に強化して再利用せざるを得なかった。その時に始まった流れによる弊害が今の震災の対応、特に原発事故で顕著に表れているように思うのだ。
「敵を知り己を知らば百戦危うからず」とは「孫子の兵法」の有名な一節だが、これから先の日本は震災の復興を第一に、震災前から続く経済・財政問題や想定していた原発の数から15機も少ない状態での「京都議定書の批准」の履行等、百戦どころかそれ以上の問題が山積みとなっている。いつものパターンで申し訳ないが、近代史を勉強せず、放ったらかして己を知ることを怠り続けたから、「百敗の一部が始まっているのかも知れない。」そんな気がする今日この頃なのだ。
では実際に終戦直後から占領が開けるまでの間に何が起こり、ボクらの父や祖父の世代の日本人がその国難をどう受け止め、どう切り抜けていったかについては学校教育の中では「全く教えられてこなかった」と言えるだろう。
そんな時代について書かれているのが、ジョン・ダワー著「敗北を抱きしめて」という本だ。この本はアメリカのジャーナリストに贈られる最高の栄誉であり、最も権威ある賞であるピューリッツァー賞を受賞している。とは言っても「アメリカ人が見た日本人観」からは完全に抜け切れているわけではなく、記述に多少違和感を持ったり反論したくなる部分もあるのだが、それでも当時の様子を知るには貴重な一冊であることは間違いない。
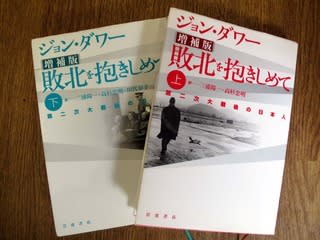
●上・下巻の長編だ●
この本には「敗戦という悲惨な状況の中、文字通り『何もかもなくした』日本国民達が秩序を守りつつも、如何に苦難を乗り越え、様々な創造性を発揮して立ち直っていったか」が書かれているが、それと同時に「如何なる問題が解決できずに残ったのか?」ということが書かれてもいる。
今回の震災でも「何もかもなくした」人々が大勢居て、本当にお気の毒に思うが、「敗北を抱きしめて」を読んだ後に比較してみると、被災地と戦後の状況にはかなりの違いがある事に気付く。
戦後の日本は国内主要都市部の多くが爆撃されて灰燼に帰しており、都市部と農村部の差は多少あったにせよ、全国的な食糧難と物資不足に加えて国民は恐ろしいスピードのインフレにさらされていた。当然輸出入も成り立っておらず、事態は深刻であったが、反面、物さえあれば売れる時代であったが故に、荒れ野に生える雑草の如く闇市が各地に生まれ、そこでの取引が盛んになることで「市民の持つパワー」の一面が発揮されていった。だから、「まずは物さえ生産、もしくは供給できれば…」それが復興の足がかりの一つになっていたのだ。
対して今回の震災においては、被害を受けていない中部以西の西日本からの物資が豊富にあるうえ、諸外国からも被災地へ向けて物資が入り込んでくる。それを端的に示しているのが、ペットボトル入りの水や乾電池の供給過程だ。生産施設を失い、資金や体力を失った被災地の企業や商店が復活するには、ただでさえ相当の困難が待ち構えているのに、他から商品が流れ込み、シェアまで奪われてしまった後ではその困難さが更に増すだろう。だから軽々しくも「戦後の危機も乗り切れたんだから…」と言う言葉で括ってしまうべきではないと思う。
しかし、「敗北を抱きしめて」を読んで感じた戦後の一番の問題点は、上述した「如何なる問題が解決できずに残ったのか?」という部分にあると思う。
GHQは「民主主義」を自国(アメリカ)でも達成困難な実験的な部分を含めた内容をもって上から押しつけ、我々日本人もそれを多くの部分で善意に解釈して受け入れてきたが、成果が出る前に朝鮮戦争と冷戦が始まったがためにGHQいや、実質米軍は「既存の力を持った官僚や企業組織」を更に強化して再利用せざるを得なかった。その時に始まった流れによる弊害が今の震災の対応、特に原発事故で顕著に表れているように思うのだ。
「敵を知り己を知らば百戦危うからず」とは「孫子の兵法」の有名な一節だが、これから先の日本は震災の復興を第一に、震災前から続く経済・財政問題や想定していた原発の数から15機も少ない状態での「京都議定書の批准」の履行等、百戦どころかそれ以上の問題が山積みとなっている。いつものパターンで申し訳ないが、近代史を勉強せず、放ったらかして己を知ることを怠り続けたから、「百敗の一部が始まっているのかも知れない。」そんな気がする今日この頃なのだ。


















