都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
茨木童子再訪と土蜘蛛
安倍晴明(あべのせいめい)の屋敷の庭は整然としている。他の邸宅のように苔むした岩や草が覆い茂った様子がない。まるで人工的につくられた感じなのだ。
晴明は無駄が嫌いであった。星の運行を見て吉凶を占うことは、一種の科学である。陰陽師と科学とは一見そぐわないようであるが、星辰(せいしん:星座)は秩序と法則のもとに運行するものである。
勘や霊感だけではもともと成り立たつものではない。その精神が庭にも現れていた。 石庭に当時としては珍しく北斗七星をかたどった石が置かれていた。
頼光は初めて訪問するのではないが、殺風景な屋敷のたたずまいは、どことなく居心地の悪い感じがした。
それにしても、腕の処理方法を相談しにきたはずの頼光と綱であったが、あまりにも晴明が秘密を知悉(ちしつ:細かい点まで知りつくすこと)していたので驚き、あきれて、しばらく腕のことをすっかり忘れてしまっていた。
秘密裏に進められた花山院の退位を陰陽道で知っていたぐらいの晴明である。大江山討伐などわかっても当たり前なのかもしれない。当面の問題は目の前の奇怪な腕である。腕が悪霊となって綱や頼光に禍をもたらさないよう呪術で封じ込めなくてはならない。
「どうすればよい、晴明!」
源頼光は晴明に対して、ほとんど叫び口のようになっていた。
「はい、七日間謹慎し、鬼の手には封印をして祈祷には仁王経(にんのうぎょう:仏教経典。仁王般若経)を読むことです」
「よし、わかった。そうすることにする。しかし晴明、おぬしは恐ろしい男よ。極秘なことを何でも知っておる。おぬしを敵に回したら枕を高くして寝ることができぬのぅ」
「お褒めに預かり恐縮でございます」
「しかし、このことは内密じゃ、よいのぅ」
「もとより承知」
大江山討伐・・・・・。表向きは攫(さら)われた貴族の娘たちを救出するためとされているが、大江山討伐の背景には、権力へのとてつもない野望が隠されていたのであった。
つまり、藤原道長と当時の清和源氏の棟梁の源頼光とが手を結んで大江山を攻略することが計画されていたのであった。では、はたして大江山の何が、権力者にとって垂涎(すいぜん:ある物を手に入れたいと熱望すること)の的(まと)となっているのだろうか。
まずは、藤原氏と清和源氏との連携の歴史を繙(ひもと)かなければならない。
源頼光の父は源満仲(みなもとのみつなか)という。満仲は清和天皇から数えて五代目にあたり、鎮守府将軍まで昇りつめた。
源満仲を有名にしているのは何と言っても、安和の変(安和二年・969年)であろう。安和(あんな)の変・・・・・。
事の起こりは、源満仲の告発であった。その告発は、冷泉天皇のときに、源高明が皇弟を奉じて謀反を企てているというものである。
右大臣藤原師尹(もろただ)は、満仲のこの告発を取り上げて、源高明は太宰権帥(だざいのごんのそち)に貶(おと)されることとなる。
9世紀中頃から、朝廷内の政権争いで他氏を排斥していった藤原氏は、承和の変で橘氏を、応天門の変で伴氏を、藤原時平によって菅原道真は太宰権帥に左遷した。そして安和の変で源高明が配流させられていく。
つまり、安和の変とは藤原氏による他氏排斥運動の締めくくりだった。
これを機に藤原氏独裁体制は確立し、摂関政治を展開する。
安和の変における密告者の源満仲は着実に藤原氏、とくに北家との結びつきを深めて、清和源氏の地歩を確固たるものにしていった。
満仲は摂津多田の庄に居住し、多田源氏と呼ばれた。摂津多田(せっつただ)の地は金・銀・銅・鉄などの豊富な資源を産出したので、満仲は、その財力をもとに原初的武士団を形成し一族郎等を従えることができた。
満仲は武士であるとともに中級貴族としての顔があった。したがって自然と時の権力者、摂関家に寄り添って、もちつもたれつの関係ができあがった。花山天皇が寵愛した女御が妊娠八カ月で死んで失意に落ちていたのにつけこんで、兼家は謀略をもって花山天皇を出家退位させた。
兼家の娘詮子が先帝円融天皇との間にもうけた懐仁親王が皇太子であったので、早く花山天皇を退位させ天皇の母方の祖父として摂関の地位を確立したかったのである。花山天皇を山科の元慶寺まで人目を隠しながら護送したのは他でもないこの満仲であった。
多田の産する鉱石のなかでも、この時代の実質的に最も重要な金属は鉄である。『多田』の名は鉄をつくりだす設備『:足で踏んで空気を送る大形のふいご)』から来ているともいわれている。
言うならば、満仲は摂津の産鉄王である。頼光はその二代目。鉄は武器・農具・建築材料とその用途は広い。多田で生産された鉄製の農機具は多田の南に広がる平野の潅漑・耕作に使われて、米を初めとした多大な農産物をもたらした。
また、『踏鞴(たたら)』は新たに作るより、弱小の踏鞴(たたら)を吸収し支配する方が簡単である。つまり、建設費用の節約と同時に、そこで働く者たちの技術と労働力を手に入れることができるからである。
大江山討伐も結局そのために計画されたのであった。
タラなど問題ならないくらいの巨大なものであったので、接収(せっしゅう:国などの権力機関が、個人の所有物を強制的に取り上げること)は、廟堂(びょうどう:朝廷)を巻き込んでの国家的計画事業となった。
もっと言えば、大江山には古代にまでさかのぼる歴史的意味がある。
酒呑童子は、越後から近江を経て、比叡山に移りすんだわけであるが、祖先をたどれば越後の海人族である。
越後の海人族と丹後の海人族とは同族で、漁業・農耕・鉱業を営む文化の進んだ古代種族であった。とくに産鉄について高度な技術をもっていて、花崗岩から掘り崩される良質の砂鉄で精錬した鉄は、中国や朝鮮よりも優れていた。
海人族のうち、最大で最古のものが古代において丹後に住み着いていた。
丹後王国と言っていいほどの勢力の海人族の文化があったのである。その支配は広く今の亀岡から紀伊半島まで及んでいたという。あの出雲王国ですら、丹後王国の一部が残ったものだという話もある。もちろん、のちの倭国を形成した大和王権は次々と丹後王国を侵食し、出雲王国さえも国譲りという形で支配下に入れてしまうのである。
大江山の酒呑童子の集団はそんな日本の歴史のなかで、王権に反逆し、丹後王国の命脈を保つ『服(まつろ)わぬ民(服従しない人々)』たちの最後の砦であった。
朝廷は一日でも早くその勢力を取り除き、その鉄資源ならびに陸海交通の至便という利権を奪い取ることに血道(ちみち)を上げていた。いわば頼光たちはその目的を遂げるための特殊部隊であったのだ。
茨木童子が綱から奪おうとしたのは、ずばり廟堂の大江山討伐の計画書であった。この作戦が酒呑童子に分かると、討伐の作戦は実行不可能になり、次の手を打つまでには時間がかかる。
そんな歴史的なうねりの中に頼光たちはいた。
鬼の腕に話をもどそう。
頼光は晴明が言うとおりに、鬼の腕を朱櫃(しゅひつ:ふたが上に開く朱の箱)に入れて、綱の屋敷で七日間仁王経(仏教経典。仁王般若経)を僧侶たちに読経させることにした。
読経し始めて六日目に、養母であった叔母が摂津渡辺から訪れた。
もちろん物忌みをしている綱は七日間、面会謝絶である。誰であろうと会うわけにはいかない。
「七日が明けないことには、人に会うことができないので、もう一日待って欲しいとお伝えしなさい」
綱は従者(ずさ)にそう言った。
老女は、面会を断られると、
「せっかく私がこうして会いに来たのに許されぬとは・・・・。恩を忘れるとはこういうことを言うのですよ」
と、言って泣き始めた。
その涙に従者が油断している隙に、綱の叔母は従者の横をするりと身軽に抜けて読経をしている部屋まで飛ぶようにして侵入していった。とても、老女の動きには思えないほどの機敏さだ。
「お養母上(ははうえ)!」
綱が老女を見てそう言った途端、形相が鬼に一変した。
「ふふふ、愚か者が。我が恨み晴らしてくれようぞ!」
そう言うやいなや、着物を脱ぎおとして片腕の鬼女が踊り出た。
綱の眼前の朱櫃(しゅひつ)を奪い、蓋を荒々しく投げ捨てて中から腕を取り出した。
綱はすぐさま鬼女に斬りつけた。
老女は、見覚えのある鬼女、いや茨木童子であった。
「茨木童子だな!」
「邪魔だてするな」
と鬼女が言うが、すでに顔も言い方も本来の男のものとなっている。綱の剣は、ひらりひらりと体をかわす茨木童子を必死に捉えようとしている。
「性懲(しょうこ)りもなく、また現れおって」
やっとのことで綱の剣が茨木童子の体の上部に触れた。ちょうど首のあたりだ。
「えい!」という気合のもとに渾身の力を振り絞ると、刀は横一文字の軌跡を描いた。ついに茨木童子の首と胴が離れた。
《茨木童子、仕留めたり・・・・・》
ところが、茨木童子が腕を持って屋根の破風(はふ)を突き破り逃げ去って行く。その後ろ姿には首が、ちゃんと付いているではないか。仕留めたと思った首は何とよくみると大きな瓜であった。
「うぬ!謀(たばかり)よって!」
一部始終を見ていた僧侶たちは、恐怖のあまり腰を抜かしてしまっていた。
綱の屋敷から茨木童子が腕を取り返して間もなく、今度は頼光が襲われた。
茨木童子事件のあと、頼光は「瘧病(ぎゃくびょう)」という一種のマラリアのような病気にかかった。平安時代とは、瘧病のような疫病が、よく猖獗(しょうけつ:猛威をふるうこと)を極めた時代であった。四天王が必死で付きっきりの看病をした結果、やっと高熱も下がり落ち着いてきた。
池田中納言の姫失踪事件
源頼光は、内裏に足繁く参内(さんだい)したり、蔵人頭と連絡をとりあったりして精力的に行動し始めた。 司令塔は一条帝というよりも、藤原道長と蔵人頭、藤原行成であった。
折しも、京では貴族の姫君が誘拐される事件や放火が相次いでいた。廟堂の会議において喧々囂々(けんけんごうごう)たる意見がたたかわされた。
「京に不穏の動きあり、大元(おおもと)の酒呑童子を討つべし!」
「いや時期尚早!」
「茨木童子の所業(しょぎょう)、まさに挑発である。これを機に大江山攻略をいたさねば・・・・」
「池田中納言国賢(くにたか)様の姫も酒呑童子に拐(かどわか)かされていると聞いておる。その救出のためにも酒呑童子を討つべきであろう!」
そう言われて、池田中納言は哀願するような目で皆を見回している。自分の娘のことだから、自分から朝議の議題にのぼらせることは憚(はばか)られた。
池田中納言は、国司時代に蓄えた金銀財宝で富貴の聞こえが高かった。その中納言に美貌の一人娘がいた。当然思いを寄せる貴族の子弟は数多く、婿選びが中納言とその奥方の嬉しい仕事であった。
その姫がある日の夕暮れ時に、突然失踪してしまい、池田中納言の屋敷は大騒ぎとなった。中納言の奥方は心配のあまり病床に伏してしまう有り様であった。
「京の隅から隅まで探すのじゃ。見つけたものには恩賞は思うがままぞぉ」
必死の捜索も空しかった。
結局、人探しが最後に頼みとするところは陰陽師のところである。
この時、第一人者の陰陽師安倍晴明はあいにく播磨(はりま)の国守として赴任してしまっていた。贅沢を言ってはおれず、池田中納言は神隠しにあった者を見つけ出すことでは評判の村岡正時(まさとき)と言う名の陰陽師に娘の捜索依頼をした。池田中納言の奥方は、床から跳ね起きて中納言とともに正時のところを訪れた。
正時の前では、池田中納言国賢は、中納言という肩書をかなぐり捨てた、ただの人の子の親になっていた。
「正時よ、私の一人娘を捜し出しておくれ。齢(よわい)は今年十三歳になる。乳母(めのと)や守役(もりやく)、女房たちにも言いきかせて壊れ物にさわるように大切に扱ってきた姫なのだ。縁(ふち)の昇降にも付き添いがつき、強い風には人が屏風がわりになったくらいじゃ。そんな娘を拐かす不届き者がどこにいるのか教えておくれ。いま姫は無事なのか、そうじゃないのか、どうなのだ、正時!」
中納言の目は血走っている。銭の袋をうずたかく積み上げて、正時の前へ差し出した。正時はこれを一瞥して、
「おまかせあれ。お占いします」
と、言って、筮竹(ぜいちく)を扇のように開いては、数本ずつ繰(く)って、またばらすということを、くり返した。傍らにいる中納言と奥方には正時が何をやっているのか、さっぱりわからない。だが、こればかりは正時を信頼して任せるほかなかった。
『えい!』という気合のもとに正時は確信したように言った。
「姫君の行方がわかりました。丹波国大江山の鬼、酒呑童子のところでございます」
「生きているのかそれとも・・・・・」
池田中納言は『それとも』のあとに『死んでいるのか』と続けたかったが、そんな不吉なことは言えず、口ごもった。
「ご安心ください。お命に別状ありません。私の祈祷によってお命の安全は保証いたしましょうに」
少々うさん臭く思いながらも、それを聞いて池田中納言は娘の命を助けたい一心で、銭の袋をさらに積み上げた。
正時は言い出しにくい様子で言った。
「命には別状ないのですが、操の方が・・・・」
「ええい、それ以上申すではない。命さえあれば縁談には不自由せん」
確かにその通りかも知れない。池田中納言ほどの富貴と姫の美貌さえあれば、拐かされたことなど何でもないことかもしれないのだ。正時は、池田中納言が訪問する前に、すでに使役する式神に調べ上げさせて、娘の居場所はつきとめていた。筮竹など本当は必要としなかったが、銭の上乗せのために占うふりをしたのであった。
正時の言うとおり、池田中納言の姫を拐かしたのは酒呑童子であり、実行犯は茨木童子であった。綱に片腕を斬り落とされても娘ひとり拐かすのは他愛もなかった。
朝議が重ねられた。
左大臣道長が、意見が出尽くしたところで皆の意見をまとめるにして言う。
「帝の御威光を損なうような振る舞いは決して許されるものではありません。京から子女(しじょ)をさらっては、そばに侍らせる酒呑童子の所業はまことに言語道断。保昌、頼光、四天王を大江山に討伐に遣わすならば、平定も可能でしょう。ぜひ、この評定でこの議、決裁を仰ぎ、ご宣旨を賜りますよう」
帝は頷いて、
「左府(さふ)の言うとおりである。 頼光は朕も頼りに思う武士(もののふ)じゃ。頼光を呼びなさい。 朕からも話をしようぞぉ」
評定は、この帝の一言で決定した。
「おそれながら、すでに呼び寄せております」
道長は厳かに言った。
頼光が呼ばれた。頼光は御簾(みす)越しに帝に対面した。
「頼光、すでにわかっておろうが丹波国大江山の酒呑童子を討伐して欲しい。朕が治める国には津々浦々まで鬼がおってはならぬ。国の治安を守るためにはお前の力が必要じゃ。退治してはくれまいか」
頼光は畏まって勅命を受けた。
「有り難い仰せでございます。この頼光、身命を賭(と)して大江山討伐に向かわせていただきます」
一条の自分の屋敷に戻った頼光は、自分の屋敷にさっそく藤原保昌や四天王を呼んで、宣旨を伝え第一回目の策略会合をもつことにした。
一同を前にして、頼光は厳粛な面持ちで言う。
「帝から御下命があった。大江山の酒呑童子を討伐せよとのことじゃ。もちろん囚われの池田中納言の姫君ほか多数の子女の救出に向かう。相手は鬼であるというが、人間じゃ。ただ、山に住んでいる者は、妙な武術を心得ておる。必勝を期して神仏の御加護にすがらなければなるまい。私と保昌は岩清水八幡、貞光と季武は熊野権現、綱と公時は住吉明神へ必勝祈願に行く。よいな」
「ははっ」
祈願に行くため、二回目の策略会合は三日後とされた。
(つづく)
大江山討伐
再び頼光邸に集まった五人に向かって頼光は三日間のあいだに練った策略案を披露した。
「この討伐は人数が多過ぎてはならない。大江山に入る道には至るところに酒呑童子の配下のものが見張っておる。むしろ我々は、小人数の修行中の山伏姿で行く。表敬訪問ということで酒呑童子の屋敷に入り、酒好きの酒呑童子に酒をふるまって酔い潰れたところで首級(しゅきゅう:討ち取った首)を取る。どうじゃ」
茨木童子にすでに蔵人頭行成の屋敷で、大江山討伐の話を聞かれているだけに、その報告を受けた酒呑童子は警備を固めているにちがいない。正攻法では討伐はまず無理である。小人数で騙(だま)し討ちにするしかない。
「どうやって武器を運びまするか」
「山伏姿であるから、笈(おい)のなかにでも鎧甲(よろいかぶと)を隠しておけばよいであろう。刀も細工をして持って行くがよい」
「ははっ」
五人は口を揃えて返事をした。
頼光は緋縅(ひおど)しの鎧と、同じ毛の『獅子王』という甲、そして剣を笈の中に入れた。保昌も笈の中に腹巻、甲、短めにした薙刀(なぎなた)を入れ、綱は萌黄(もえぎ)の腹巻に甲、茨木童子を斬った『鬼切』を入れた。貞光、季武、公時も考案して腹巻、甲、剣を笈の中に入れ、他に火打ち石も用意した。雨具としての油紙は笈の上に取り付けた。
山伏姿に変装するのであるから、頭巾(ときん)をつけ、鈴掛(すずかけ)を着て、法螺貝(ほらがい)、金剛杖といったものを準備した。また、丸腰ではいざというときに困るので山伏として不自然でない程度の打刀(うちがたな)を帯びた。
準備万端、丹波国の大江山へと六人は旅立った。一応、外見は修験道を行う一団に見えた。大江山が近くに見えた辺りで、頼光らは柴刈りの男に遭った。
「そこの山人よ。ちょっと尋ねるが、千丈嶽(せんじょうだけ)の鬼の岩屋はどこにあるのか教えてもらいたい」
山人は恐れた表情を顔に浮かばせた。
「あなた方は見たところ山伏のようじゃが、あんな恐ろしいところへ行かない方がよいぞ。向こうへ行って帰ってきたものは村でもおらんからの」
「鬼が住むというその岩屋に届け物があるのじゃ。道筋を教えてほしい」
「そうまでいうのなら道を教えるが、おぬしたち、わしはどうなっても知らんぞ」
心配そうな面持ちで、その山人は地面に小枝で大江山の稜線を描き、鬼の岩屋まで行く道を頼光たちに教えた。
「かたじけない」
千丈嶽に近づくにつれ誰かに見張られているように感じた。薮の中、樹木の背後に見え隠れする人影・・・・・。
頼光は、大江山周辺には廟堂から討伐を助けるための間者(しのび)が、すでに放たれていると聞かされていた。しかし、道を教えてくれた芝刈りの男はどうも間者とは違う。もちろん、こちらの様子を窺っている人影も向こうから姿を現さない以上、それとは違うはずである。 岩屋へ行く道がだんだん険しさをました。峰伝いにしばらく進んでいると、岩穴があった。突然、中から声がした。
「もうし!」
急な声に驚いて、保昌は後ずさりをして、もう少しで崖から落ちそうになった。岩穴の奥に柴葺(ぶ)きの小屋があって、その中から三人の老人が出て来た。その一人が話かける。
「頼光様でございますか」
「いかにも」
「お待ちしておりました」
「間者か」
「いかにも。酒呑童子の見張りがたくさんいたので、姿を現して名乗り出ることができませんでした」
「やはり、あの人影は見張りであったか・・・・」
老人にしては声に張りがある。よく見てみると、若い間者が老人に変装しているのが分かった。他の二人もそのようだ。
六人とも暫時休憩することにして笈を降ろした。
竹筒に入っている水でそれぞれの者は喉を潤(うるお)した。
「鬼の岩屋はもうすぐでございます。酒呑童子は無類の酒好きですので、ここに用意しました丹後の酒を飲ませくださいまし。中には痺(しび)れ薬が含まれておりますゆえ、あなたさま方は解毒の丸薬をあらかじめ飲んでおいてください。痺れ薬が効いたあと、退治するがよろしかろうと思います」
後の世に、この酒は鬼には毒となり人間には薬となる『神便鬼毒酒(じんべんきどくしゅ)』と伝承された。頼光は『神便鬼毒酒』と丸薬を受け取った。さらに、間者は不思議な感じのする鋲のついた星甲(ほしかぶと)を取り出して、説明し始めた。
「酒呑童子は不思議な霊剣をもっております。この星甲は『ひひいろかね』(特殊な鉄)で出来ており、酒呑童子のもつ霊剣と同じ鍛練がなされております。身を護るのであればこの星甲を身につけてくださりませ」
頼光は笈の中の持って来た甲『獅子王』の上に星甲を重ねてしまい込んだ。
頼光たちは間者の一人に案内されながら、千丈嶽(せんじょうだけ)を登った。谷川に出たところで、間者と別れることになった。
間者は別れる際に、
「この川上をお上りください。十七歳くらいの娘が川で着物を洗っているでしょう。その娘はこちらが放った間者(かんじゃ)の『傀儡女(くぐつめ)』でございます。名前は『百舌鳥(もず)』と申します」
と、言って、風のように去った。
『傀儡(くぐつ)』とは、操(あやつ)り人形を歌などに合わせて舞わせることを生業(なりわい)とし、各地を漂白する芸人であるが、もともとは王権に『服(まつろ)わぬ民』であり、時には間者になることもあった。傀儡の女、すなわち『傀儡女(くぐつめ)』たちの中には遊女となったり、女忍者『くのいち』になったりする者もいた。
『服(まつろ)わぬ民』であるのなら、『百舌鳥』は、むしろ酒呑童子側についているはずだが、間者として権力側についたのには理由があった。百舌鳥の父は公家であったのだ。
ある時、薬狩(くすりがり)に来た貴族の子弟の一人が、隠れ里の娘に手をつけた。これが、百舌鳥の父と母である。
隠れ里でそのまま父(てて)なし子として育てられ、百舌鳥は父を知らずに成長した。百舌鳥の母は、病弱であった。事情を知っている廟堂関係者が、酒呑童子攻略のために、百舌鳥を利用することを思いついた。密かに手を回して、その母に有能な薬師(くすし)をつけるという条件で、百舌鳥に間者の任務につくことを承諾させた。隠れ里の『傀儡』集団に属していた傀儡女の百舌鳥が、酒呑童を頼って、身を寄せてきても、大江山では別段、疑う者はいなかった。
頼光にとっても、警戒が厳重な潜入しにくい酒呑童子の本拠を突くのに、百舌鳥という味方は願ってもないものだった。
頼光たちが、川を石や岩を手掛かりに登って行くと、石や岩が赤くなっていた。おそらく、鉄穴流(かんななが)しのせいであろう。
古代の製鉄では砂鉄を埋蔵する山の一角を掘り崩しては川に流し、樋のなかに導いて砂鉄をより分けるという方法が取られていた。その鉄が岩石に付着して酸化し、赤くなっているのであった。
里の者は大江山の鬼を恐れるあまり、岩が赤いのは、大江山の鬼が、さらってきた人間を食べるために切り刻む。そのときに出た血で汚れた着物を川で洗うからだと噂した。
そのまま川を登っていくと、鍬や笊(ざる)で砂鉄を掬(すく)っている何人かの娘たちに出会った。
娘たちは一斉に頼光たちを見て驚いた。他者(よそもの)を見るのがよほど珍しかったようだ。頼光は途中で出会った柴刈りの言った言葉を思い出した。
「村人の中でも、鬼の岩屋へ行った者で帰って来た者はいねえ」
実は、帰る者がいないのは至極当然であった。鬼の岩屋に行ってみようなどというのは仕事にあぶれた者たちだ。そういう者たちが、この鬼の岩屋へ来て見ると皆が忙しそうに、また生き生きと働いているのを見た。人を食う鬼などおらず、何も恐ろしいことはなかった。
働こうと思えばいくらでも仕事はある。身分の上下などもない。一生懸命そこで働きさえすれば、それまでよりもずっとよい暮らしが保障された。だから、帰る者はいるはずがなかった。
娘たちの一人が頼光たちの出現を知らせに走った。他者を見たら、そうするよう言い渡されているのであろう。
《この娘たちはさらわれて、このように働かされているのだな。さて、どの娘が『傀儡女』百舌鳥なのか、どれも皆十七歳ほどの年頃のようであるが・・・・》
すると一人だけ顔つきに驚きの様子を示していない娘がいた。頼光がじっと見つめると目が《お待ちしておりました》と答えているようだ。
《あの娘が百舌鳥だな》
と、頼光は思った。
間もなく十人ほど男たちがやってきた。熱い炉にかかりっきりになっているためか、上半身は裸である。また、強い火にあてられた体は汗と油と煤で赤く腫れあがったようになっていた。下半身には獣皮の猿股(さるまた)をはいている。顔も体と同じように赤く、髪などは伸ばし放題で、やはり火であぶられているせいか一様に縮れている。なるほど人々の思い描く鬼の姿そのものだと頼光は思った。
男たちは頼光一行をぐるりと囲み、咎める(とがめる)ように、口々に言う。
「お前たち、何をしに来た。ここはよそ者が来るところじゃねえ」
「早く帰ったほうが、身のためだ」
頼光は落ち着いた物腰で言う。
「いえ、別に怪しいものではありませぬ。酒呑童子様に挨拶に参っただけのこと。我ら、修験道を修行する者で役行者(えんのぎょうじゃ)様の流れをくむものにございます」
役小角の名前を聞いて男たちは、はっとしたような顔になった。
役行者は、またの名を役小角(えんのおづぬ)という。葛城山の一言主(ひとことぬし)の予言や神託を担(にな)う神官の家系に生まれ、雑密の修法『孔雀明王経法』をおさめて神通力で鬼神を使役したという。役小角はたしかに修験道の祖であるが、一方、やはり葛城山、吉野、熊野の山系に居住していた産鉄族の首領でもあった。そして、全国の『服(まつろ)わぬ山人たち』の神格的存在として崇められていた。役小角は、ときの廟堂の首班、藤原不比等(ふひと)の策略にかかって自分の弟子の韓国連広足(からむこうのむらじひろたり)の讒言(ざんげん)によって捕らえられ、伊豆に流された。
『役小角捕らわる』の報は矢のような早さで全国の山人たちに伝わっていった。そして、小角の救出をせんがため、国内の山人が一斉蜂起する動きがあるとの情報が、廟堂に飛び込んだ。
朝廷は震えあがった。当然のように即刻、役小角は釈放された。そうでなければ未曾有の内乱がこの日本で起こっていたかもしれない。
頼光はそんな役小角の名を口にしたのである。
「そうであったか、役行者様にかかわる者たちか。して、どこから来た者か」
役小角の名前を咄嗟(とっさ)の機転で出したのであるが、思わぬ手応えがあって、頼光は、むしろ内心驚いていた。そして、どこから来たのかを聞かれて、もう一つの嘘を思いついた。
「高野山から参った」
「すると弘法大師様の・・・・・」
高野山といえば金剛峰寺、金剛峰寺といえば弘法大師空海である。
「そのとおりでござる。積もる話もございますゆえ、是非とも酒呑童子、いやお館様にお会いしとうございます。ほれこのように酒を持参いたし、心ばかりの土産も持参いたしました」
酒呑童子無残
頼光たちは唖然とした。
というのは四つに区分けされた庭のそれぞれが、春夏秋冬を表して、春の桜、夏の蛍、秋の紅葉、冬の雪景色が一望のもとに見ることができたのである。
《今は晩秋なのに、あの春の桜や夏の蛍は本物なのだろうか・・・・》
頼光は不思議な気持ちでいっぱいになった。《どんな富裕な貴族でさえ、今を時めく道長でもこうはいくまい。やはり鉄(くろがね)や水銀(みずがね)は大きな財をもたらすものじゃわい》
頼光の隣に座っていた渡辺綱は、素直にそう思った。
それぞれの四季の庭に、やはりそれぞれの季節に合わせた衣装を着た娘たちが、現れ出てきた。楽曲に合わせて、娘たちの踊りが始まった。その艶やかさ、美しさはたとえようもない。
すっかり豪奢(ごうしゃ:非常に贅沢で派手なこと)な雰囲気にのまれた頼光たちは、うっかり討伐のことなど忘れそうになった。すると、百舌鳥の強いまなざしに気づき、頼光は夢心地から目を覚ました。頼光は、喝を入れるために自分の頬を挟むようにしてぴしゃりと叩いた。
《酒呑童子、この宴も今宵限りと知れ!》
頼光は闘志をふつふつと沸き立たせた。しかし、その闘志の多くはむしろ嫉妬からくることに頼光自身、気づいていなかった。何への嫉妬か・・・・・・。
それは富にたいする嫉妬である。富貴な者は、自分以上に富貴な者に対して猛烈な嫉妬を抱く。
宮廷と見まがうほどの、いやそれ以上の栄華をほこる酒呑童子。
ところが、頼光以上に酒呑童子の富を狂うように嫉妬したのは、大江山討伐が行われた長徳元年(995年)に左大臣になりたての道長であった。討伐の日は同じ年の11月1日であった。頼光48歳、道長30歳であった。
この時、廟堂の頂点に立っているのはもちろん一条帝であるが、政治の首班は藤原氏の筆頭、藤原道長である。代々鉄資源を押さえてきた藤原氏は当然、大江山の価値を十分知っていた。権力が酒呑童子の存在を許しておくはずはないのだ。今度の大江山討伐の絵図を描いたのは富と権力を追求する道長と頼光、そして蔵人頭行成であった。
「それにしても茨木童子は帰りが遅いのう。都へまた女子(おなご)でも誘拐(さらい)に行ったのであろうが、先頃は、鬼同丸の仇をとるとかなんとか言って渡辺綱という武者を襲ったのはよいが、不覚をとって腕を斬り取られた。そうしたら、茨木童子は意地になって、腕を取り返してきよった。取れた腕などひっつきようもないのにのう。まあ、勇ましいのもわしの若いころにそっくりじゃわい。はっはっはっ」
酔った酒呑童子が、茨木童子の名を口にした。その名を聞くと、頼光と綱は、かっと頭に血をのぼらせた。討伐決行の心が逸(はや)る。百舌鳥が言うように茨木童子が戻ってくる前に決着をつけねばならない。
するとその時、かなり酔いがまわった飲み癖のわるい『金熊童子』が箸を使って戯れに、
「この刃(やいば)を受けてみよ」
と、言いながら綱を斬るしぐさをした。
綱は金熊童子の悪ふざけに決まっているので、箸など体に触れさせれば良かったのだ。それが、襲撃の機会をねらって心が臨戦態勢になっていた上に、虚を突かれたので作為も思いのままにならず、反射的にひらりと体を一回転してかわしてしまった。
酒呑童子は、『おや?』という顔をした。
「おぬし、身のかわしようが、ただの僧ではないな。何者だ」
綱は、少しも慌(あわ)てず、
「これは不思議な仰せられようでございますなぁ。仏道ばかりでなく私共、修験道を心得てもおりまする。役小角の流れをくみ、高野山での修行を経て、このように獣道を歩き、山野を宿にする者が自然に身を軽くする術を会得するのも道理でございましょう」
「うむ・・・・・」
まだ半信半疑の酒呑童子に、坂田公時が口を開いた。
「わたしは異形(いぎょう)で生まれたゆえ、山に捨てられ老婆に拾われて獣とともに育ちました。自然に猿の身のこなし、鹿の跳躍などは身につき、ほれこのように」
猿の真似をし、ぴょんぴょん跳ねる様は一同を笑いに誘った。
坂田の機転でいっぺんに座が和(なご)んだ。
「お許しくだされ。これが山に住む者の性(さが)でござる。まして、茨木童子の話では源頼光が攻めてくるというので警戒していたのだ。酔うてても頭の片隅では油断できなかった。皆様方の興をそぐようなことを言ってすまなかった。ご持参くださった酒のうまさに度を越した所業(しょぎょう)と思ってご勘弁を。さあ、盃を干されよ」
そう言って酒を酌んだ。
『神便鬼毒酒』を五臓六腑にしこたま染み込ませた『石熊童子』は『虎熊童子』同様、酔いながら田楽踊りを舞い始めた。
渡辺綱もこれを見てすっくと立ち上がって、
「我も、一差し」
と言って、石熊童子の舞に呼応するかのように、
『年を経て鬼に岩屋に春の来て、風や誘いて花を散らさん』
と、謡(うた)ながら舞うのであった。
素面(しらふ)であれば、歌の意味はたちどころにわかりそうなものだが、酔いつぶれんばかりの童子たちにはわからない。
歌の意味は、「ここにいる鬼たちを春の嵐のように花を散らすように斬り散らそう」というものであった。
しばらくして、酒呑童子は覚束無い(おぼつかない)足取りで立ち上がって言う。
「客僧たちよ、そこでしばらくお休みくだされ。今宵はまことに気持ちよう酔うことができた。これも弘法大師さまのお導きであろう。有り難いお話しを承った。ではわしはこれで失礼つかまつる。三人の姫にあなたがたの世話をするように申し付けておいた。ごゆるりと。また明日会うとしましょう」
そう言って酒呑童子は奥の部屋に引っ込んでしまった。
残った童子たちは、酒呑童子が話しているときまでは、さすがにしゃんとしていたが、部屋に引っ込むと同時に、その場に寝てしまった。たぶん『神便鬼毒酒』が効いているのだろう。口までがだらしなく開(あ)いている。
頼光は残された三人の娘に話しかけた。三人は池田中納言国賢の娘、花園の姫、そしてもう一人は吉田中将の娘であった。
頼光は気ぜわしく話した。
「私は頼光と申すものです。拙者どもは姫君たちを救出するため酒呑童子を退治に参りました。酒呑童子のとりことなってさぞかし心細い思いをしたでしょう。もう大丈夫です」
と、言うと、何とも意外な返事が返ってきた。
「お館(やかた)様にはとてもお世話になっております。最初連れて来られたときには、どうなることやらと胸がつぶれる思いをいたしましたが、しだいにそうではないことがわかりました。
今はお館様の側女(そばめ)となって、大江山での暮らしに満足しています。とてもお館様には親切にしていただいております。洗濯や食事の支度も私たち自身でするようになって、自分で何かをするという喜びも知りました。私たちをここから救いだすというお考えでしたら、用なきこと。このままお帰りください」
と、池田中納言の娘が答えた。酒呑童子のことをお館様とさえ呼んでいるではないか。《そう言えば、酒呑童子は自分の生い立ちを話す中で、美貌のゆえに他の僧たちに疎(うと)まれたことを言っていた。多分、大江山での華美な暮らしだけが大江山に引き留めているのでなく、酒呑童子の男性的な魅力も一役かっているのであろう》
正直な話、頼光たちにとっても、大江山討伐の、姫たちの救出はたてまえである。本来の目的は鉄や水銀鉱脈、出雲・越後・朝鮮半島への交通至便という大江山の利権を酒呑童子から収奪することであった。
しかし、救出の表向きの大義名分が当事者から真っ向から、このように否定されては行動が鈍る。次に、吉田中将の姫に違う意見を期待して頼光は尋ねた。
「貴女(あなた)は助け出されたいとお思いでしょう」
「私も池田の姫様と同じです。京の父上、母上もいとしいのですが、私たちはこの地へ輿(こし)入れしたのも同然でございます。生きていることの手応えが感じられる日々をおくっているのです」
吉田中将の姫が、きっぱりとそう言った。
《この娘も同じか・・・・・》
頼光は辟易(へきえき)した。これ以上この姫たちにかかずらわっていても無駄である。頼光たちは、笈から鎧や甲を装着して槍や剣を取り出した。各人がそれぞれの具足をつけている間に、百舌鳥はどこかに行っていた。すると、百舌鳥は大江山の鬼たちの武器庫から刀や甲を持ち出して戻ってきた。百舌鳥が持ってきた刀はどれも、さすが、酒呑童子のところで鍛練した刀であった。頼光は柄を握った瞬間心に張り詰めたものが腕に伝わるのを覚えた。頼光らは持参した刀と取り替えることにした。笈の中に入れるように加工したので刀が短めになってしまっていた。鬼たちの刀の方が役に立つ。渡辺綱だけは、やはり使いなれた『鬼切』を使うことにした。頼光は刀を取り替えたが、大江山へくる途中で渡された「ひひいろかね」の星甲だけは使うことにした。この星甲の上に、さらに『獅子王』の甲をかぶって、二重の防御とした。装備が済むと頼光は大きく武者ぶるいをし、一同を見わたし、『よし』と小声で合図した。頼光は百舌鳥に、
「酒呑童子の寝所に案内(あない)せよ」
と、告げた。
百舌鳥を先頭に、石畳の廊下を抜けて行った。屋内に小川が流れている。架け渡した丸い石橋を、百舌鳥は歩いて渡らず、ひとっ飛びで、飛び越した。百舌鳥が『傀儡女』であったことを頼光たちは再認識した。
さらに、石垣の壁で囲まれた通路をしばらく行くと、直角の曲がりかどに行き着いた。皆は、そこで百舌鳥に足止めをされた。
「お待ちください。しっ、お静かに。この先が酒呑童子の寝所(しんじょ)となっています。門番がいるので姿をまだ現さないでください」
覗くと、窓もなく鉄牢のような建物が見えた。好都合なことに寝所まで続く門扉は開いていた。普段は、これも閉まっているのだろう。
ただ困難なのは、門扉までの間に尖った先が天を向いている鉄柵があり、向こうから太い鉄の閂(かんぬき)がしてある。おまけに、鬼の姿をした門番が槍を持って二人立っていた。
頼光たちが、考えあぐねていると。百舌鳥は束ねていた髪をほぐして、着物の胸のあたりを乳房が見えんばかりに、大きくはだけた。そして、酔ったふりをしながら、門番の方へよたよたと歩いていった。
「お館様、お館様。いつものお館様らしくもない。まだ宵のうちですよ。お休みになるのは、早ようございます」
甘えた声を出しながら、百舌鳥は酔っ払ったふりをして、『ふうっ』と大きく息をついて門扉の前で横たわった。
着物が割れて、太ももが露(あらわ)になった。
二人の門番は生唾を飲んだ。門番はお互いに顔を見合わせて淫靡(いんび)な笑いを浮かべた。そして、目配せをして次の行動を無言で確認し合った。
帰還
帰る道すがら、頼光は姫たちを諭(さと)した。
「京へ帰ったら、酒呑童子のことは話してはなりませぬ。まして酒呑童子を賛美することなどはもっての他ですぞ。酒呑童子はやはり鬼だったのです。酒呑童子を褒めることは貴女たちの父母を悲しませることにしかなりませぬ。あなたたちはこれから花も実もある人生なのですから。およろしいかな」
姫たちが敬愛する酒呑童子は、もうこの世にいない。帰るところは父母のところしかない。しかし姫たちは、酒呑童子のことは一生忘れないで心に秘めていくであろう。ふと、頼光は、池田中納言の娘を見やった。
姫は、酒呑童子のことを想(おも)って泣きはらし、目が腫れぼったくなっていた。それにしても、堀河中納言の姫のことはどう説明しようか頼光は窮した。酒呑童子の子まで身ごもって自刃したわけだが、本当のことを言っても、堀川中納言の姫は生き返ってこない。両親に話しても嘆くばかりであろう。頼光はそう考えて、公時の方を見た。公時が、堀川中納言の姫の髪を、懐紙におさめているのを見ていたからだった。
《公時がうまく説明してくれよう》
公時も、頼光に頼まれるまでもなく、そのつもりであった。それくらいのことは、むしろ自分からやりたいと思っていた。何かわからないが、一種の罪滅ぼしになるような気がしたのである。
大江山の麓の下村(しもむら)までくると、丹波の国司、大宮の大臣(おとど)という者が出迎えた。
大宮の大臣は、頼光たちが京へ帰って廟堂に、今の丹波の国司が酒呑童子のなすがままにさせていたと報告されると困ると思った。国司としての責任を問われないように、点数かせぎに、できるだけの接待を頼光たちにしようとした。
頼光たちは、飲食物を充分補給し、再び出発した。
京に近い『老い坂』まできたところで、廟堂からの使者が来た。
「どうかお待ちください。酒呑童子の首実検 をしたら、首をこの老い坂で葬れとの道長様の仰せでございます」
頼光はいささか憤慨した面持ちで、
「いかなる故(ゆえ)じゃ」
「はい、京に穢れを持ち込むことはならぬとかで・・・・・」
「これは酒呑童子の首なるぞ。敵方とはいえ、首領であった。丁重に葬らなければならないのではないか」
これは嘘である。頼光は酒呑童子の首を丁重に葬る気などさらさらない。
酒呑童子の首を持って行くことで手柄を印象づけたかっただけの話である。
「もう朝議で決定しましたので・・・・・」
「もうよい、わかった」
道長だけの一存ではなく、正式に朝議で決定したのであれば、これ以上、抗(あらが)うことは却って頼光に不利になる。命令に従って埋葬することにした。
酒呑童子の首を埋葬したところは、現在では『老いの坂の首塚』と呼ばれている。
池田中納言の娘は父母に会うとさすがに、泣きながら「母上様」と叫んで母親の胸の中に飛び込んでいった。池田中納言は頼光の手をとって、これ以上ないと思われるほど有り難がった。
京へ戻った翌日、頼光と保昌は、帝に報告をするために謁見することとなった。四天王は身分上、別の部屋に控えた。
一条帝は御簾(みす)越しに頼光に言った。
「ご苦労であった。池田中納言も喜んでおる。よく六人ばかりの者で酒呑童子を退治した。今後、頼光と保昌は昇殿を許す。他にも褒美をとらせよう。何なりと申せ」
頼光が口を開く。
「おそれながら、丹波国をご下賜(かし:高貴な方から物を貰うこと)されんことを」
頼光は抜け目がなかった。酒呑童子を自らが斬って大江山を陥落させたのだから、遠慮をしてみすみす他の者に渡すことはない。
鉄や交通の利権ばかりでなく、酒呑童子の財宝もそっくりそのまま残っている。すでに、部下の何人かは現地に残してきた。まして産鉄のうまみは父、源満仲から教えられて骨の髄まで知りつくしている。
もちろん、ある程度の利益は国庫に入るが、国司となって正直に収益全部を国庫に収める者などまずいない。利益は左大臣道長と頼光に充分流れ込むのであった。
帝は、頼光の望みを受け入れた。
「保昌はどうじゃ」
保昌は、畏(かしこ)まって押しだまっている。実際に酒呑童子退治にもそう目立つ働きはしなかったが、頼光と同格の身分であったので一緒について行っただけでも、四天王より褒美(ほうび)は大きい。
保昌がはっきりしないので、帝の御手ずから賜りの言葉があった。
「では、頼光が丹波なら、お前には丹後の大庄三ヶ所をとらそう」
「ははっ」
頼光は、これを聞いて内心、
《駆け引きの下手な奴だな。そんなことだから南家は北家に勝てないのだ。こんな時だ、もう少し欲を出せばよいのに・・・・》
藤原保昌は藤原南家の系統であった。保昌の祖父の代に、北家との権力闘争に敗れてから日の目をみない一門になってしまった。保昌は北家の道長に近づいて何とか勢力を保持していた。あまり目立つと排斥されるので持ち前の鷹揚(おうよう)さを隠れ蓑にして、世渡りをしていた。
頼光がそんな一種の優越感にひたっていた時、保昌が口ごもりながら帝に奏上(そうじょう:天子に申し上げる子と)した。
「恐れながら、もう一つだけ望みがございます」
保昌がそう言った時、冷水を浴びせられたように、頼光の顔色が変わった。
「何じゃ、何なりと申せ」
と、帝が少し驚いて言うと、
「和泉式部を賜りたく・・・・・」
文才歌才に恵まれ、書や管弦にも秀でた和泉式部・・・・。道長が娘の中宮彰子に箔をつけるために集めた女官の一人であり、すでに三十三歳になってはいたものの、いまだ美貌の才媛である。
その和泉式部を保昌が見初めた。
「左府がとりはからうであろう」
道長は笏(しゃく)を胸にあてて、腰を折って『承知』の礼をした。
頼光は胸をなでおろした。保昌が口を開いた時ひやりとしたが、何のことはない。所望したのは女一人だった。
《武人ともあろうものが、望みがたった一人の女とはあきれた・・・・》
だが、この保昌の無欲が実のところ、頼光との親交を長続きさせているのであった。
もし、保昌が頼光と同じような野心めいたものが、毫(ごう)程でもあったならば、頼光は保昌を遠ざけていたに違いないし、また道長との相談の中で、大江山討伐の人選にも加えていなかっただろう。
こうして、頼光は丹波守に、藤原保昌は丹後守に任じられた。保昌はさっそく和泉式部を娶(めと)り、翌年には丹後に赴任していった。
和泉式部は、最初の夫、橘道貞が和泉守だったところから離婚後でさえ、ずっと、「和泉」式部と名乗っていたが、道貞が死に藤原保昌に嫁いでからはさすがに和泉式部とは言えず、「大江家」の江の字をとって「江式部(ごうのしきぶ)」と名乗るようになった。
式部と最初の夫、橘道貞との間に生まれた子に小式部内侍(こしきぶのないし)がいる。歌詠みの才の誉れ高い和泉式部に劣らず、やはり蛙の子は蛙か、和歌を詠む才能に富んでいた。
和泉式部が丹後にいるころ、この小式部にちょっとした出来事があった。
藤原公任(ふじわらのきんとう)の嫡男、定頼(さだより)が小式部の局を通りすぎる時に、「丹後につかわしける人はまいりたるにや」と、言ってひやかした。丹後にいる和泉式部に代筆を頼んでいるのではないかとからかったのである。
それに対し、
大江山いくのの道の遠ければまだふみも見ず天の橋立
と、応酬したことは有名である。
そんな、小式部内侍も早逝する。和泉式部は世の無常観を、ひしひしと感じた。おのずと和泉式部は丹後の海を思い出すのであった。
《いったい何本の松があるのでしょう》
天の橋立の松並木の生えた砂嘴と背後に広がる大海原を思い出してはその無常観を癒すのであった。
「もう一度、丹後の海を見たい」
それが、晩年の和泉式部の口癖になった。
頼光は丹波守を経て、長保三年(1004年)に五十七歳で美濃守に転じた。同じ年に、頼光は娘を道長の異母弟の道綱大納言に嫁がせ、摂関家とますます密接な関係となり、勢力を確固たるものにしていった。
一世一代の運命の賭として酒呑童子退治をした頼光も治安元年(1021年)7月19日、摂津守を最後に七十四歳で生涯を閉じる。
頼光は、人には明かしてはいないが、酒呑童子の命日には、必ず『老い坂』の首塚まで行って手を合わせていた。道長は頼光が死去した6年後に落命した。それ以後、栄華をきわめた藤原氏は衰退へ向かっていった。
頼光なきあとは、源氏の主導権は弟の頼信に移った。頼信は平忠常の乱を平定することにより、その系統を栄えさせる。その系統から出た頼義・義家が前九年・後三年で活躍し、さらに、義朝・頼朝を輩出して源氏が貴族社会に変わって本格的な武家社会を築いていったのである。
時移り事(こと)去って、酒呑童子退治の話は、時の権勢を恐れて、酒呑童子は世にも恐ろしい鬼として語り継がれていくのであった。
(完)
エピローグ
「酒呑童子」と言えば、恐ろしい鬼で人をさらっては、食べている鬼神として「昔話」として伝えられていました。しかし、考えてみれば、この世に「鬼」などいるはずもなく、天下国家に従わぬ、反逆児であったことが分かります。
「鬼」即ち「悪」として語り継がれてきたものが、実は「正義」だったのではないのか?強いものが「正義」で弱いものが「悪」とされることは、決して許されては成りません。「酒呑童子」の「正義」が「頼光たち」の嘘で固めた謀略の前に敗れていったことは、闇に葬られ、「鬼退治」の物語として後世に伝えられたのです。
用語解説へ(つづく)
第1章
砂嘴(さし):海中に細長く突き出た地形。
与謝(よさ)の海
京都府北部の宮津湾奥、天橋立から西の潟湖(せきこ)。阿蘇海(あそかい)とも。
和泉式部(いずみしきぶ)
平安中期の女流歌人。大江雅致(おおえのまさむね)の娘。和泉守橘道貞と結婚し、小式部内侍を産んだ。為尊(ためたか)親王、次いでその弟の敦道(あつみち)親王と恋をし、上東門院彰子に仕えてのち藤原保昌に嫁するなどした経歴から、恋の歌が多い。生没年未詳。「和泉式部日記」「和泉式部集」がある
藤原保昌(ふじわらのやすまさ)
(958-1036年) 平安中期の廷臣。左馬頭。南家藤原氏。武芸にすぐれ、盗賊袴垂保輔を畏伏させたという。歌人としても著名。和泉式部は妻。平井保昌(ほうしよう)とも。
和泉式部日記
日記。1巻。和泉式部の自作とされるが、他作説もある。寛弘4年(1007年)成立とする説が有力。長保5年(1003年)4月から翌年正月までの、敦道親王との恋愛の経過を、歌を交えて物語ふうに記す。和泉式部物語。
紫式部(むらさき‐しきぶ)
[973年ころ~1014年ころ]平安中期の女流作家。越前守藤原為時の娘。藤原宣孝と結婚し、夫の没後、「源氏物語」を書き始める。一条天皇の中宮彰子(しょうし)に仕え、藤原道長らに厚遇された。初めの女房名は藤式部。他に「紫式部日記」、家集「紫式部集」など。
赤染衛門(あかぞめえもん)
[960年ころ~1040年ころ]平安中期の女流歌人。道長の妻倫子(りんし)と上東門院彰子に仕え、のち大江匡衡(おおえのまさひら)と結婚。家集に「赤染衛門集」。
源頼光(みなもとのらいこう)
[948年~1021年]平安中期の武将。満仲の長男。摂関家藤原氏と結び、左馬権頭となった。弓術にすぐれ、大江山の酒呑童子(しゅてんどうじ)退治の伝説で知られる。
頼光の四天王*
*渡辺綱(わたなべのつな)
[953~1025年]平安中期の武士。源頼光の四天王の一人。京の鬼同丸や大江山の酒呑童子(しゅてんどうじ)、羅生門の鬼を退治した伝説がある。
*坂田公時(さかたのきんとき)
平安後期の武士。相模足柄山に生まれたと伝えられる。幼名、金太郎。源頼光の四天王の一人。後世の御伽草子などで伝説化され、五月人形となって残る。浄瑠璃・歌舞伎では快(怪)童丸の名で登場する。生没年未詳。
*碓井貞光(うすいのさだみつ)
[955年~1021年]平安中期の武将。源頼光の四天王の一人。
*卜部季武(うらべのすえたけ)
[950年~1022年]平安中期の武士。通称、六郎。源頼光の四天王の一人。大江山の酒呑童子(しゅてんどうじ)征伐で有名。
藤原行成(ふじわらのゆきなり)
[972年~1027年]平安中期の公卿・書家。名は「こうぜい」とも。伊尹(これただ)の孫。小野道風(みちかぜ)・藤原佐理(すけまさ)と三蹟の一人で、その筆跡を歴任した権中納言・権大納言から権跡(ごんせき)という。和様書道の完成者で、世尊寺流の祖。日記に「権記」がある。遺墨「白氏詩巻」「本能寺切(ほんのうじぎれ)」など。
浄蔵(じょうぞう)
[891年~964年]平安中期の天台宗の僧。三善清行(みよしきよゆき)の子。宇多法皇の弟子。諸高山を遊歴修行し、平将門(たいらのまさかど)の乱にあたっては大威徳法を修した。
さんばら
ざんばらとも。乱れ髪
被衣(かつぎ)
平安時代ごろから、上流の婦人が外出するとき、顔を隠すために衣をかぶったこと。またその衣や、それをかぶった女性。中世以降は単衣(ひとえ)の小袖(こそで)を頭からかぶり、両手で支えて持った。かずき。
藤原兼家(ふじわらのかねいえ)
[929年~990年]平安中期の公卿。師輔(もろすけ)の三男。兄の兼通(かねみち)と関白職を争い、一条天皇の外祖父として摂政、次いで関白となった。法興院。東三条殿。
安倍晴明(あべのせいめい)
[921年~1005年]平安中期の陰陽家(おんようけ)。土御門(つちみかど)家の祖。彼の占いや予言をたたえた説話は今昔物語・宇治拾遺物語などにみられる。著「占事略決」。陰陽師(おんみょうじ)とも。
式神(しきがみ)
陰陽師の命令のままに動く鬼神(きじん)のことを言う。式神の正体は、実際は扱いされた、世人が相手にしない川の民や山の民であったと考えられる。
茨木童子(いばらぎどうじ)
京都の羅生門で渡辺綱(わたなべのつな)に片腕を切り取られ、のちに綱の伯母に化けてその片腕を奪い返したという、伝説上の鬼。
酒呑童子(しゅてんどうじ)
丹波の大江山に住んでいたという伝説上の鬼の頭目。都に出ては婦女・財宝を奪ったので、勅命により、源頼光が四天王を率いて退治したという。御伽草子・絵巻・謡曲・古浄瑠璃・歌舞伎などの題材となっている。
廟堂(びょうどう)
天下の政治をつかさどるところ。朝廷。
第2章
源頼信(みなもとのよりのぶ)
[968年~1048年]平安中期の武将。満仲の三男。鎮守府将軍。藤原道長に仕え、平忠常の乱を戦わずして鎮めて武名をあげた。
「雨夜(あまよ)の品定め(しなさだめ)」
源氏物語の帚木(ははきぎ)の巻で、五月雨の一夜、光源氏や頭中将(とうのちゅうじょう)たちが女性の品評をする場面。雨夜の物語。
産女(うぶめ)
難産のために死んだ女性の幽霊
袴垂(はかまだれ)
平安時代の伝説上の盗賊。今昔物語・宇治拾遺物語にみえ、和泉式部の夫藤原保昌の弟保輔(やすすけ)ともいわれるが未詳。
検非違使(けびいし)
平安初期に設置された令外(りょうげ)の官の一。初め京都の犯罪・風俗の取り締まりなど警察業務を担当。のち訴訟・裁判をも扱い、強大な権力を持った。平安後期には諸国にも置かれたが、武士が勢力を持つようになって衰退した。
破風(はふ)
切妻(きりづま)造りや入母屋(いりもや)造りの妻側(端:つま)にある三角形の部分。
一条天皇(いちじょうてんのう)
[980年~1011年]第66代天皇。在位986~1011年。円融天皇の第1皇子。名は懐仁(やすひと)
源頼光(みなもとのよりみつ)(948年―1021年)

 平安中期の武将,貴族。清和源氏満仲の長子としてうまれた。摂津源氏の祖である。摂津,伊予,美濃等の諸国の受領を歴任し、内蔵頭,左馬権頭,東宮権亮等をつとめた。
平安中期の武将,貴族。清和源氏満仲の長子としてうまれた。摂津源氏の祖である。摂津,伊予,美濃等の諸国の受領を歴任し、内蔵頭,左馬権頭,東宮権亮等をつとめた。
藤原摂関家に接近し,その家司(けいし)的存在となって勢力を伸長した。摂関家とは摂政・関白に任ぜられる家柄のことである。
例えば988年(永延2)摂政兼家の二条京極第新築に際し馬30頭を献じた。また1016年(長和5)の大火で焼亡した道長の土御門第(つちみかどてい)の再建に際して、1018年(寛仁2)道長の土御門第新造のときにその調度品のいっさいを負担したこと,道長の異母兄道綱を娘婿に迎え彼を自邸に同居させたことなどはその現れである。
こうした摂関家との関係は,969年(安和2)藤原氏が起こした他氏排斥の疑獄事件。右大臣藤原師尹(もろただ)が、左大臣源高明(たかあきら)(醍醐(だいご)天皇の皇子。賜姓源氏)を左遷し、その結果、自ら左大臣となる安和の変以降の父祖の伝統を受け継ぎ清和源氏発展の基礎を築くものであった。
また頼光は早くからその武勇で知られており,彼や彼の郎党と伝えられる渡辺綱、坂田金時、碓井(うすい)貞光、卜部季武(うらべすえたけ)のいわゆる頼光四天王の名は「今昔物語集」をはじめ多くの説話集や軍記の中に見いだすことができる。
一条戻橋をはさんで、安倍清明と向かい合う場所に邸を構えていたのが、源頼光である。清明が怨霊退散の知能派ならば、頼光は魔物退治の武闘派ということになる。
彼らが同時期に同じ区域に住んでいたことは、このあたりが御所(今の御所ではない)の鬼門の方角に当たり、魔界・異界との接点であったからかもしれない。
ある時期の都の平安は、この知能派・武闘派二人によって、辛うじて保たれていたのである。
頼光自身も強者であったが、彼の手勢にはすぐれた武将が多かった。特に四天王といわれたのが、渡辺綱、碓井貞光、卜部季武、坂田公時(金時とも)いずれも腕自慢・力自慢の面々で、数々の鬼、土蜘蛛、魔物を退治している。
特に有名なのが、大江山の鬼・酒呑童子の話である。丹後の国大江山の奥に、朝廷から見れば非合法軍事政権を作り、都に出没しては人をさらい財宝を略奪していた酒呑童子軍との戦いは、頼光たちにとっても一世一代の激戦であったらしく、長く世に語り継がれるところとなった。
ちなみに、「唐津くんち」の曳山(ひきやま)では「酒呑童子と頼光の兜」が、ひとつの出し物として今も伝えられている。これは酒呑童子が戦いの最中に頼光の兜に噛み付いたことに由来するとも、斬り落された酒呑童子の首が頼光の兜に飛びついたからともいう。

 「鬼」とともに、頼光の武勇伝を彩るもうひとつの存在が「土蜘蛛」である。
「鬼」とともに、頼光の武勇伝を彩るもうひとつの存在が「土蜘蛛」である。
土蜘蛛というのは、大和朝廷側から見た、先住未開民族の蔑称であったという見方もあり、そうすると、蝦夷(えぞ)なのか熊襲(くまそ)なのかが、平安京周辺にもまだ住んでいたことになる。また、背丈が低く背中が曲がっていた先住未開穴居民という説もあるが、真偽のほどは分からない。
そんな土蜘蛛伝説を伝える代表的な場所が2つある。いずれも頼光によって退治された土蜘蛛の伝説を伝えるものであるが、冷遇されたままに置かれていたせいか、はっきりした伝承が残っていない。
ひとつは、上品蓮台寺に残るもので、「頼光塚」とされている。そのままなら、彼の墓所を示すものであるが、これが頼光の退治した土蜘蛛が潜伏していた塚であるともいい、今となってはいずれかはっきりしない。
椋の巨木の根元に、極めて小さな石碑を立てただけのものであり、これとても後世のものであろうから、名のある人と言えでさえ、立派な墓所を構えることのなかった当時の風習や、実は随所で寸断された平安京の歴史が、偲ばれるのである。
 いまひとつは、北野天満宮のすぐ西隣の、東向観音寺に残されているものである。
いまひとつは、北野天満宮のすぐ西隣の、東向観音寺に残されているものである。
これは元々畑の中にあった蜘蛛塚と伝えられるものを、この地に移設し弔ったものであるが、いわば石灯籠の頭の部分だけが伝わっている。以前は露にさらされていたが、損傷が激しいせいであろう、いまは祠に囲い込まれた状態になっている。
蜘蛛塚などという存在も、徐々に忘れ去られて行くのにちがいない。
このように見てくると、外敵である「鬼」従わぬ京都盆地先住民「土蜘蛛」そして朝廷内に渦巻く人間たちの欲望の結果生じる怨霊と、都は自然のもたらす災害以外の、様々な災厄の種を抱えながら、辛うじて歴史を保ってきた跡がうかがえる。
「鬼」「土蜘蛛」や妖怪たちは、いわば「服(まつろ)わぬ民」として、朝廷から迫害され、陰陽師によって、物の怪の類として葬られていった。
当時の人々は、雲の上の存在である朝廷内のいざこざなど知るはずもなく、飢饉と飢えに因って生じた盗賊や人殺しの集団を鬼とよび、魑魅魍魎を恐れ、空腹の中で細々と暮らしていたに違いない。
今も「伏魔殿」といわれる省庁の官僚という名の鬼たちが蔓延る中、今の政治に従わぬ、いわば、「服(まつろ)わぬ民」は政権交代という妖術で政治を変えようとした。
新しく政権を担う人たちは「鬼」を退治するのか、味方にするのか、屈服して元の木阿弥となるのか、国民は固唾を呑んで見守っている。
したっけ。
一般に役小角(えんのおづの、おづぬ、しょうかく)と呼ばれ、他に役優婆塞(えんのうばそく)と呼ばれる。
霊峰葛木山の神官加茂家に生誕する。幼少よりその天才的な才能を発揮し、若くして山岳修行に入る。神の導きで飛鳥元興寺の高僧より「孔雀明王経」の教えを受け、その後密教の奥義を修めること30年、不思議の術を顕す超人として人々の前に姿を見せる。
小角は「鬼神を使役し、様々な奇跡をなした」とされ、前鬼後鬼二体の鬼神(護法)を従えた姿で表される。様々な厄を一切除き、天候すら操る小角は畏敬され、彼のまわりに宗教団体が形成されていく。それが修験道の母体組織となる。
『源平盛衰記』などによれば本名は賀茂役君小角(かものえのきみおづの)で、一応神道の名家賀茂一族の分家にあたる。(ただし父親の名字は高賀茂とも伝わる)
奈良時代に葛城山の麓に生まれ、古代から続く山岳信仰の一部を引き継ぎつつ、仏教とその一流派である大乗仏教を加えて、修験道と密教の基を興した。
一説には634年に生まれたとされているが、伝説の色が濃く、やや信頼性が薄い。
前鬼と後鬼という夫婦の鬼を使役したと言われることから、邪法を使う者として名をおとしめられることもある。
 ただしこの前鬼と後鬼だが、能の『鞍馬天狗』などでは大峰山の天狗だとされている。そこから考えると、もともと彼らは役行者と同じ山岳修験者で、行者に付き従った者たちだろう。他でも、鬼のような姿をしていたがれっきとした人間だったといわれている。
ただしこの前鬼と後鬼だが、能の『鞍馬天狗』などでは大峰山の天狗だとされている。そこから考えると、もともと彼らは役行者と同じ山岳修験者で、行者に付き従った者たちだろう。他でも、鬼のような姿をしていたがれっきとした人間だったといわれている。
行者は『今昔物語』などでは葛城山にまつられる国津神である一言主(ひとことぬし)を使役するなど、多くの不可思議な逸話を残すため、宗教家ではなく呪術者や妖術使いのようにもいわれる。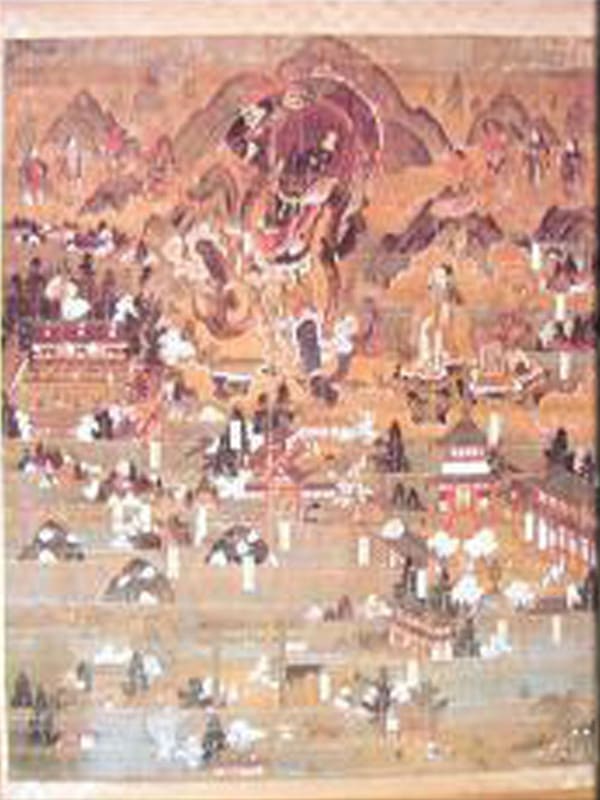
山伏はどうやら鉱山を神聖な山としてみていたようだ。修験道の護摩などの火を用いていた業は、この踏鞴(たたら) を使用している。踏鞴は本来製鉄に使用する鞴(ふいご)である。当時、鉄は、金や銀より重要なものであり、朝廷は彼らを恐れていた。
 山岳信仰はクニトコタチ(国之常立神:くにのとこたちのかみ)やオオナムチ(大国主命:おおくにぬしのみこと)などを霊山にまつることがあり、実際葛城山では『古事記』の雄略記にも書かれる一言主が古くから信仰されており、一応国津神系の神道だが、彼はその信仰に大乗仏教を加えた。
山岳信仰はクニトコタチ(国之常立神:くにのとこたちのかみ)やオオナムチ(大国主命:おおくにぬしのみこと)などを霊山にまつることがあり、実際葛城山では『古事記』の雄略記にも書かれる一言主が古くから信仰されており、一応国津神系の神道だが、彼はその信仰に大乗仏教を加えた。
そのことから、神道派や純粋な仏教派には、異端視されたのではないかと思われる。
『続日本紀』などには文武3年(西暦699年)、他の呪術師の訴えによって、伊豆に流刑に処されたと記述されている。
また『日本霊異記』では、小角の所行に怒った一言主が、人に憑いて現れ、「行者は国を傾けようと謀っている」と託宣したことが流刑の原因とされている。
数年後、罪を許され刑を解かれたようだが、そのあたりはかなり曖昧で、正確には良くわからない。
したっけ。
「おんようじ」ともいう。大宝令(たいほうりょう)の制で陰陽寮(おんようりょう)や大宰府(だ ざいふ)に置かれた方術専門の官人。占筮(せんぜい)や地相をして、吉凶を知ることをつかさどったが、平安時代、陰陽寮のつかさどった天文、暦数、風雲の気色をうかがう方術を陰陽五行の思想に基づいた陰陽道とよぶようになると、陰陽師もそれらの方術を使う者すべての名称となった。
ざいふ)に置かれた方術専門の官人。占筮(せんぜい)や地相をして、吉凶を知ることをつかさどったが、平安時代、陰陽寮のつかさどった天文、暦数、風雲の気色をうかがう方術を陰陽五行の思想に基づいた陰陽道とよぶようになると、陰陽師もそれらの方術を使う者すべての名称となった。
平安中期に賀茂忠行(かものただゆき)が出てこれを世業化して賀茂家というが、子の保憲(やすのり)系統は暦道(陰陽寮の学科の一。暦法と漏刻の学を教授した。)を中心とし室町中期から勘解由小路(かげゆこうじ)家、ついで幸徳井(こうとくい)家とも称した。
賀茂 保憲(かものやすのり)は、延喜17年(917年)-貞元2年2月22日(977年3月14日)、平安時代中期の陰陽師、陰陽家。賀茂忠行の長男。
 忠行・保憲の高弟の安倍晴明(あべのせいめい)の流れは天文道(天文・気象を観察し
忠行・保憲の高弟の安倍晴明(あべのせいめい)の流れは天文道(天文・気象を観察し
 、その変異により吉凶を察知する術。律令制では、陰陽は当時の寮に天文博士が置かれ、天文の観察や異変の際の密奏を司った)を主とし、室町中期以後は土御門(つちみかど)家という。
、その変異により吉凶を察知する術。律令制では、陰陽は当時の寮に天文博士が置かれ、天文の観察や異変の際の密奏を司った)を主とし、室町中期以後は土御門(つちみかど)家という。
安倍晴明は廟堂や武士の間で絶大な信頼があり、ある意味政治を動かしていたともいえる存在である。しかし、その正体は多数の式神(しきがみ)を使い、情報を集めていたに過ぎない。式神とは、陰陽道(おんようどう)で、陰陽師が使役するという鬼神。都のいたるところにばら撒かれ、変幻自在な姿で、人の善悪を監視するという。式神の正体とは、実際は扱いされた、世人が相手にしない川の民や山の民そして奇形、異形のものたちであったと考えられる。

 式神の諜報活動により多量の情報を手に入れ、原因・事前に分析・対策を考えていたのである。依頼者は総てを知っている陰陽師を恐れ信頼したのである。この情報網を多く持っていた安倍晴明が第一人者であったことは、式神によるところである。
式神の諜報活動により多量の情報を手に入れ、原因・事前に分析・対策を考えていたのである。依頼者は総てを知っている陰陽師を恐れ信頼したのである。この情報網を多く持っていた安倍晴明が第一人者であったことは、式神によるところである。
これを求めたものは古代の貴族層のみならず、中世以後は武家、近世になると庶民にまで広がった。
*平安時代:8世紀末784年(延暦3)の長岡京遷都から、12世紀末の鎌倉幕府創始、1185年の平氏滅亡、源頼朝(よりとも)の守護・地頭(じとう)設置とするまでの約400年間のあいだ
*陰陽五行思想(いんようごぎょうしそう、おんみょうごぎょうしそう):、中国の春秋戦国時代ごろに発生した陰陽思想と五行思想が結び付いて生まれた思想のこと。陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)、陰陽五行論(いんようごぎょうろん)ともいう。陰陽思想と五行思想との組み合わせによって、より複雑な事象の説明がなされるようになった。
*安倍晴明:[921~1005年]平安中期の陰陽家(おんようけ)。土御門(つちみかど)家の祖。彼の占いや予言をたたえた説話は今昔物語・宇治拾遺物語などにみられる。
したっけ。
土蜘蛛とは、古代日本における、天皇への恭順を表明しない土着の豪傑(律令制に従わない、いわば『服(まつろ)わぬ民』)などに対する蔑称。

『古事記』『日本書紀』に「土蜘蛛」または「都知久母(つちぐも)」の名が見られる。
例えば、『肥前国風土記(えちぜんのくにふどき):713 年の詔により作られた風土記の一。主に地名の由来を記す。』には、景行天皇(けいこうてんのう)が志式島(しきしま。平戸)に行幸(72年)した際、海の中に島があり、そこから煙が昇っているのを見て探らせてみると、小近島の方には大耳、大近島の方には垂耳という土蜘蛛が棲んでいるのがわかった。そこで両者を捕らえて殺そうとしたとき、大耳達は地面に額を下げて平伏し、「これからは天皇へ御贄を造り奉ります」と海産物を差し出して許しを請うたという記事がある。
また、『豊後国風土記(ぶんごのくにふどき)713 年の詔により作られた風土記の一。』にも、五馬山の五馬姫(いつまひめ)、禰宜野(ねぎの)の打猴(うちさる)・頸猴(うなさる)・八田(やた)・國摩侶、網磯野(あみしの)の小竹鹿奥(しのかおさ)・小竹鹿臣(しのかおみ)、鼠の磐窟(いわや)の青・白などの多数の土蜘蛛が登場する。 また一説では、神話の時代から朝廷へ戦いを仕掛けたものを朝廷は鬼や土蜘蛛と呼び、朝廷から軽蔑されると共に、朝廷から恐れられていた。(「鬼」については2009.08.29を御参照下さい)
土蜘蛛の中でも、奈良県の大和葛城山(やまとかつらぎさん:、奈良県御所市と大阪府南河内郡千早赤阪村との境に位置する山。)にいたというものは特に知られている。大和葛城山の葛城一言主神社(かつらぎひとことぬしじん じゃ)には土蜘蛛塚という小さな塚があるが、これは神武天皇(古事記、日本書紀において日本の初代天皇とされている)が土蜘蛛を捕え、彼らの怨念が復活しないように頭、胴、足と別々に埋めた跡といわれる。
じゃ)には土蜘蛛塚という小さな塚があるが、これは神武天皇(古事記、日本書紀において日本の初代天皇とされている)が土蜘蛛を捕え、彼らの怨念が復活しないように頭、胴、足と別々に埋めた跡といわれる。
一般に土蜘蛛は、背が低く、手足が長く、洞穴で生活していたといわれる。これは縄文人の体形と、農耕ではなく狩猟や採集を主とする穴居生活から連想されたものらしく、このような生活習慣の違いなどが人々からさげすまれた原因とも考えられている。
 14世紀頃に書かれた『土蜘蛛草紙』では、京の都で大蜘蛛の怪物として登
14世紀頃に書かれた『土蜘蛛草紙』では、京の都で大蜘蛛の怪物として登 場する。酒呑童子討伐で知られる平安時代中期の武将・源頼光が家来の渡辺綱を連れて京都の洛外北山の蓮台野に赴くと、空を飛ぶ髑髏に遭遇した。不審に思った頼光たちがそれを追うと、古びた屋敷に辿り着き、様々な異形の妖怪たちが現れて頼光らを苦しめた、夜明け頃には美女が現れて「目くらま
場する。酒呑童子討伐で知られる平安時代中期の武将・源頼光が家来の渡辺綱を連れて京都の洛外北山の蓮台野に赴くと、空を飛ぶ髑髏に遭遇した。不審に思った頼光たちがそれを追うと、古びた屋敷に辿り着き、様々な異形の妖怪たちが現れて頼光らを苦しめた、夜明け頃には美女が現れて「目くらま し」を仕掛けてきたが、頼光はそれに負けずに刀で斬りかかると、女の姿は消え、白い血痕が残っていた。それを辿って行くと、やがて山奥の洞窟に至り、そこには巨大なクモがおり、このクモがすべての怪異の正体だった。激しい戦いの末に頼光がクモの首を刎(は)ねると、その腹からは1990個もの死人の首が出てきた。さらに脇腹からは無数の子グモが飛び出したので、そこを探ると、さらに約20個の小さな髑髏があったという。
し」を仕掛けてきたが、頼光はそれに負けずに刀で斬りかかると、女の姿は消え、白い血痕が残っていた。それを辿って行くと、やがて山奥の洞窟に至り、そこには巨大なクモがおり、このクモがすべての怪異の正体だった。激しい戦いの末に頼光がクモの首を刎(は)ねると、その腹からは1990個もの死人の首が出てきた。さらに脇腹からは無数の子グモが飛び出したので、そこを探ると、さらに約20個の小さな髑髏があったという。
このように、天皇への恭順を表明しないものたち『服(まつろ)わぬ民』は、妖怪、怪物として後世に伝えられていくのである。
したっけ。


























