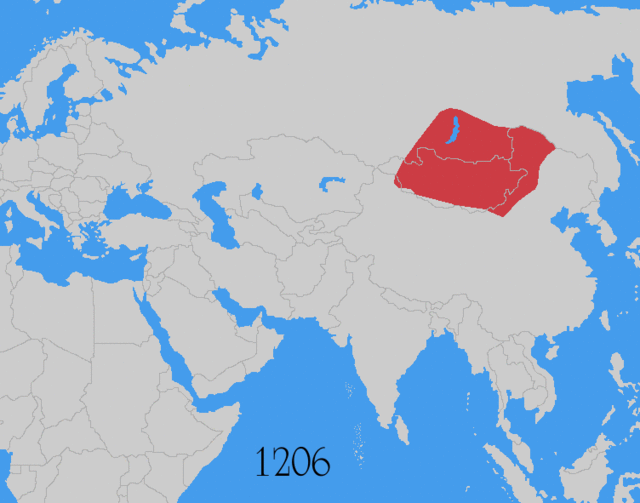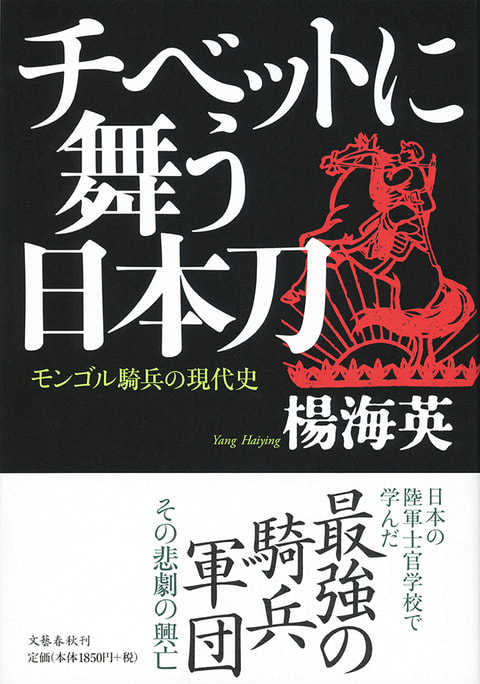数多くのモンゴル部族を統一したのがテムジンです。やがて、彼はほかの部族も統一して分裂していたモンゴル高原の諸勢力をまとめ上げたのです。1206年、クリルタイで大ハーンの地位につきチンギス=ハーンと名乗り、ここにモンゴル帝国が成立したのです。
クリルタイというのは遊牧部族の族長会議です。ハーンというのは王の称号。チンギスという言葉の意味はわかっていません。
モンゴル帝国の創始者チンギス・カンと、その他の後継者たちはモンゴルから領土を大きく拡大し、西は東ヨーロッパ、アナトリア(現在のトルコ)、シリア、南はアフガニスタン、チベット、ミャンマー、東は中国、朝鮮半島まで、ユーラシア大陸を横断する帝国を作り上げました。最盛期の領土面積は約3300万km²で、地球上の陸地の約25%を統治し、当時の人口は1億人を超えていたのです。
モンゴル帝国は、モンゴル高原に君臨するモンゴル皇帝(カアン、大ハーン)を中心に、各地に分封されたチンギス・カンの子孫の王族たちが支配する国(ウルス)が集まって形成された連合国家の構造をなしていたのです。
中国とモンゴル高原を中心とする、現在の区分でいう東アジア部分を統治した第5代皇帝のクビライは1271年に、緩やかな連邦と化した帝国の、モンゴル皇帝直轄の中核国家の国号を大元大モンゴル国と改称します。そしてその後も皇帝を頂点とする帝国はある程度の繋がりを有していたのです。
この大連合は14世紀にゆるやかに解体に向かうが、モンゴル帝国の皇帝位は1634年の北元滅亡まで存続しました。また、チンギス・カンの末裔を称する王家たちは実に20世紀に至るまで、中央ユーラシアの各地に君臨し続けたのです。
下の図面は動く図面は、いろいろな年代におけるモンゴル帝国の領土の範囲を示しています。
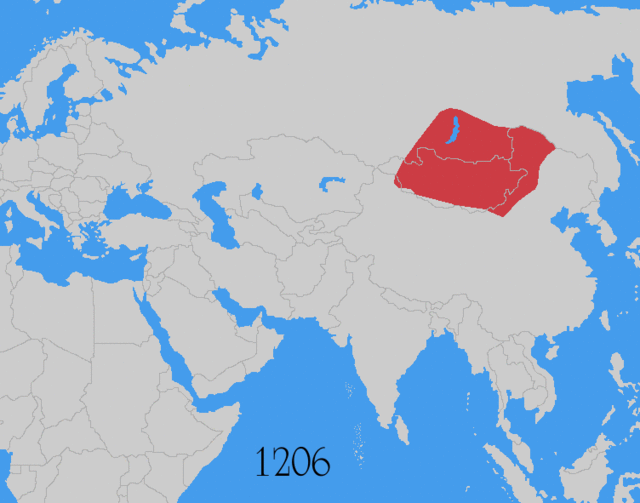
(この図面の出典は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%AB%E5%B8%9D%E5%9B%BD です)
このモンゴル帝国の拡大は中国本土も占領し、元という国家が作られたのです。この元朝は、1271年から1368年まで中国とモンゴル高原を中心とした領域を支配しました。
下に元朝の領土を示します。

図面の出典は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83_(%E7%8E%8B%E6%9C%9D)#.E5.AE.97.E6.95.99 です。
中国王朝としての元は、北宋崩壊(1127年)以来の中国統一政権であり、元の北走後は明(1368年 - 1644年)が中国統治を引き継いだのです。
この元は、チンギス・カンの孫でモンゴル帝国の第5代皇帝に1260年に即位したクビライ(フビライ)が、1271年にモンゴル帝国の国号を大元と改めたことにより成立したのです。
鎌倉時代に日本へ攻め込んだのがこの元朝と高麗の連合軍でした。
日本の鎌倉時代中期に2度にわたり行われた日本侵攻のは1度目を文永の役(1274年)、2度目を弘安の役(1281年)と呼ばれています。
さて中国の元朝で特筆すべきはキリスト教とイスラム教の隆盛と思います。
中国の宗教で、はじめにモンゴルの保護を勝ち取ったのは金の治下で生まれた全真教を始めとする道教教団でした。その教主、丘長春自らがサマルカンド滞在中のチンギスの宮廷に赴き、モンゴルによる保護、免税と引き換えにモンゴル皇帝のために祈ることを命ぜられのです。これにより全真教団はチンギスの勅許によって華北一帯をはじめとするモンゴル帝国の漢地領土において宗教諸勢力を統括する特権を得たため、その勢力は急速に拡大する事になりました。
しかしモンゴル人はその他の多くの宗教を寛大に許したのでイスラム教やキリスト教も盛んになったのです。
国際交易の隆盛にともなって海と陸の両方からイスラム教が流入し、泉州などの沿岸部や雲南省などの内陸に大規模なムスリム共同体が出来上がったのです。現在の北京にある中国でも最古級のモスクである牛街清真寺はこの当時、中都城内にあり、モンゴル帝国、大元時代に大きく敷地を拡大したモスクのひとつだったのです。
もうひとつの大宗教はキリスト教で、ケレイト王国や陰山山脈方面のオングト王国などモンゴル高原のいくつかの部族で信仰されていたネストリウス派のキリスト教は元朝のもとでも依然として信者が多かったのです。
また一方、ローマ教皇の派遣した宣教師が大都に常設の教会を開いて布教を行っていたのです。ローマ法王は1307年に初の大都管区大司教を任命していたのです。
これは驚くべき歴史で、日本にローマ・カトリックがザビエルによって導入された1549年より実に約240年も前のことだったのです。
この様な元朝やモンゴル帝国は次第に衰退し、近代には清朝の支配下になり、ロシアの台頭によりモンゴル帝国はロシアと清朝によって分断されるのです。
ロシア支配下の部分は共産革命後は共産党支配のモンゴル人民共和国になり、ソ連崩壊後はモンゴル国になります。一方、清朝支配の領域は内モンゴル自治区になり中国の領土になっています。そして文化革命期には軍政がしかれ大量粛清の嵐が吹いたのです。受難の民族の歴史です。
そして満州国の存在した期間は内モンゴル自治区は日本の支配下にあったのです。
関東軍はそこのモンゴル将校を日本の士官学校へ入学させます。そして最強の騎兵部隊として育てたのです。その騎兵隊は終戦後、今度は中国共産党の配下に入ったのです。そして中国のチベット攻略戦争の時、このモンゴル人騎兵隊を急先鋒にしてチベットへ攻め込んだのです。モンゴル人の信じるラマ教の本山のあるラサを攻撃するモンゴル騎兵隊の心境は悲しみに満ちていました。このモンゴル騎兵隊の悲劇は、楊 海英 著、「チベットに舞う日本刀ーモンゴル騎兵の現代史ー」に書いてあります。この本の写真を下に示します。出典は、http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163901657 です。
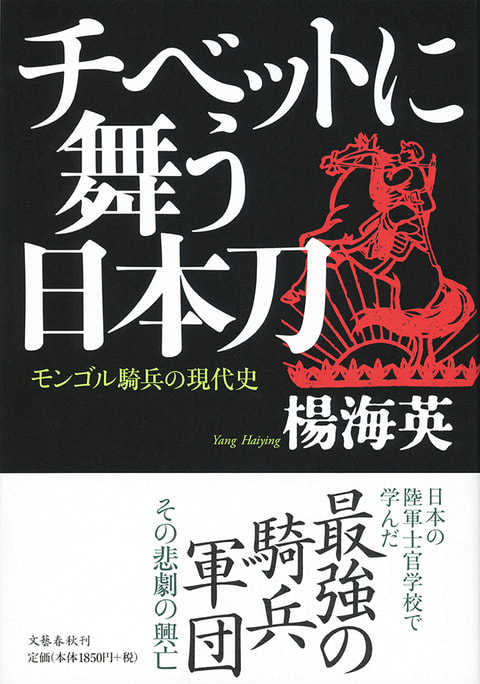
モンゴル民族について思いつくままに連載記事を書いてまいりましたが、今回でこの連載記事の終わりと致します。(完)