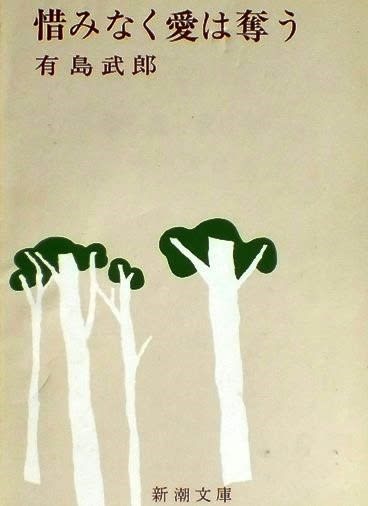リニューアル再掲:菅江真澄の道(浅虫温泉森林公園浅虫湾眺望・2007.09.27撮影)
筆者が24年から自信の掛かりつけ湯に認定した県都青森市の
奥座敷浅虫温泉はだか湯の浅虫湾眺望の映像・記事を更新した。
映像:菅江真澄が見聞したであろう外ヶ浜浅虫温泉の現代の様子 ( 鳥瞰図風に撮影 )
※藩政時代は、陸奥湾に面した津軽藩領は「外ヶ浜」と地域名がついていた。
記述:菅江真澄遊覧記 二 ~ 外ヶ浜づたひ{天明八年(1788)7月6日}~
『 かくて浅虫の浦につくと煤川の岸に・・・少し高い岩のたっているのを肌赤島
・・・鳥の形をしたのを鷗島・・・鳥居の見えるのが湯の島・・・出湯の村に宿をと
った。・・・ 滝の湯、目の湯(椿館)、柳の湯、おお湯、はだか湯などが、た
いそうきよらかに湧き、また軒を連ねた家々のうしろにも湯があってよい』
・・・「とりわけこの津軽というところは温泉の数がたいそう多い」と答えた。
どこと何処にと尋ねると、「ご存知のとおり、関の湯の沢、碇ヶ関の湯、大
鰐、蔵館、嶽、湯谷 ( 湯段)、切明、酸か湯、下湯、温湯、板留、要目、沖
浦、二升内、大川原、田代、根子、猿、笹内、・・・・そしてこの浅虫です 」 』
(過去の記録:2,019.08.06)
紀行家:菅江真澄は青森県・秋田県の各地を巡行して詳細に日記に書き残している。
その中には温泉地に関するものも数多く、江戸時代の温泉地の様子を調べる重要な
手がかりとなり、温泉史を紐解く資料でもある。青森県の代表的な浅虫温泉も記述。
参照#① 青森市 (外ヶ浜地域含む) 温泉紀行 ② 菅江真澄 (紀行家・歌人) 探訪紀行
リニューアル再掲:寺山修司記念館内の展示品(勉強机に投射された「時には
母のない子のように」の歌詞「誰にも愛を話せない‥‥」
(2015.03.07)
天井桟敷女優のカルメンマキが歌って大ヒットした曲。
深夜のラジオからこの曲が流れると思わず涙した青春。
寺山修司作詞、のちのパートナーとなる田中美知作曲。
nstagram:‥‥‥‥➡‥‥‥‥‥ ➡ ‥‥‥‥‥➡‥‥‥
歌詞:時には母の無い子のように
『 時には母の ない子のように
黙って海を みつめて居たい
時には母の ない子のように
ひとりで旅に でてみたい
だけど心は すぐかわる
母のない こになったなら
だれにも愛を はなせない…』
解説:この、どうしようもないやるせない詩と曲と歌、多くの人々の青春に、
影を投げ掛けたヒット曲この年になって漸く気がついた。寺山修司のマザコン
というか母と子の悲しくも切ない関係。寺山は東京に母を招いてから地獄の様
な日が続く。結婚は許してもらえず、新婚の夜に外から石を投げられたり壮絶
な親子愛だった。それでも母を傷つけまいとした寺山の哀しみ。寺山を取り巻
く女性…母、妻、愛人。そして夭折。それらは寺山修司の才能を阻害するもの
でない。人を愛し、いたわり、そして別離。人を信じ、駆け抜けて逝った天才。
この様に、いつの世も芸術家には悲劇がある。
参照#寺山修司(前衛芸術家・歌人)探訪紀行
Memoir:岩木山トレッキングで、岩木山に関わる文学作品を見直して、追加した。
本稿の画像は東北温泉探査で秋田県南縦走した時に撮影したものである。
春の奥羽路を南下して横手に至る。横手と言えば冬の風物詩かまくらを思い起すが
季節がら街中は何処にでもある景観だ。そこで、横手公園(横手城址)を目指した。
お城は復元(他のお城を手本に)されたもので弘前城程の広さもないが、弘前出身
の文学者(当時売れっ子作家)石坂洋次郎の文学碑が一隅にあった。暫し碑文を見る。
碑文:石坂洋次郎作品「若い人」より
『小さな完成よりもあなたの孕んでいる未完成の方がはる
かに大きなものがあることを忘れてはならないと思う・・』
所感:石坂洋次郎は筆者同様弘前市の出身で弘前高校の卒業である。その点に親
しみをもつのだが、どうも作風については明るくて、かろやかで、深く沈
んでいた筆者には馴染めないものだったが、「温泉と文学」という研究テー
マを得てからは見方が変わった。そして、吉永小百合が「 草を刈る乙女 」
ロケで来た時に父が案内した記憶もあり、徐々に作品を辿るようになった。
(注:草を刈る乙女は石坂洋次郎の青春小説を映画化、嶽温泉が出てくる)
参照#① 弘前市(古都・城下町)温泉紀行 ② 石坂洋次郎 (青春小説家) 探訪紀行
Memoir:伊香保温泉階段歌碑・与謝野晶子歌碑(群馬県 2008.09.05撮影)
与謝野晶子と温泉地は深いかかわりがあり、全国の温泉地に足跡が残され
ている。娯楽の少ない明治では上流社会の娯楽場・温泉地での歌会・句会
が当時の流行であったと推察。伊香保での歌会で披露した歌文と思われる。
「伊香保の街」
榛名山(はるなさん)の一角に 段また段を成して
羅(ロー)馬(マ)時代の野外劇場の如く
斜めに刻み附けられた 桟敷形(さじきがた)の伊香保の街
屋根の上に屋根 部屋の上に部屋
すべてが温泉宿である そして榛(はり)の若葉の光が
柔かい緑で 街全體(たい)を濡らしてゐる
街を縦に貫く本道は 雑多の店に縁どられて
長い長い石の階段を作り 伊香保神社の前にまで
Hの字を無数に積み上げて (晶子)
解説:歌というよりは写実的に伊香保温泉の特徴を述べていると言っていい
だろう。伊香保温泉は天辺の伊香保神社の境内から階段状の温泉街に
源泉が導かれた日本で最初の集中配湯の温泉地といってもいいだろう。
与謝野晶子の短歌を階段に刻んだ伊香保温泉の旦那衆も又風流の極み。
説明:歌文最後の「Hの字」は石段の石組がHの様に見える事から表現された
もので温泉街の色っぽい話ではない、誤解のない様に歌を鑑賞のこと。
この階段状の光景がアニメ千と千尋のイメージの一つともされている。
光景は温泉地でないが台湾の観光地「九份(チュウフェン)」 に似てる。
参照#① 群馬県 温泉地 データ・ベース
② 与謝野晶子( 官能・情熱歌人)探訪紀行
③ 台湾観光地「九份( チュウフエン)」の景観
リニューアル:再掲 乙女の像 (十和田八幡平国立公園:2011.02.22 撮影)
異常なほどの酷暑では厳冬湖の厳しい景観を思い浮かべ涼を摂る
(過去の記録:2015.03.05)
十和田湖畔には人の造った構造物はそぐわない。素朴な景観ゆえに美しくもあり
倍増するものだが。しかし、乙女の像は美の緊張を打ち破り大自然に溶け込んだ。
詩歌:この像を造った詩人・彫刻家、高村光太郎がこの像に次の詩を添えている。
原文はこの像の土台の石板に彼の直筆で刻まれているが、読む人は少ない。
『天然四元の平手打ちをまともにうける
銅とスズの合金で出来た
女の裸像が二人
影と形のように立っている
いさぎよい金属が青くさびて
地上に割れてくづれるまで
この原始林の圧力に堪えて
立つなら幾千年でも黙ってたってろ』(高村光太朗)
解説:背景の湖面にカルデラ山が同じく、形と影に映っている。この像はそれを
意識して、影と形を、鏡に手を合わせる裸像にしたのだろう。老体にムチ
を打ち、最愛の智恵子の面影を刻み込んだ高村光太郎渾身の遺作であった。
乙女の像は対岸の子ノ口に設置予定だったが当時の関係者らの強い意向で
今の休屋に建てられた。月日を経る内に乙女の像は十和田湖の景観に同化。
そして十和田湖を訪れる観光客の殆どは湖畔の銅像に足を延ばすのである
参照#① 高村光太郎 ( 無垢の愛 ) 探査紀行
② 厳冬期の十和田湖絶景 2023.3.12
Memoir:石川啄木記念館に隣接啄木の宿柱に掲げられた短歌の木簡
石川啄木記念館には歌人啄木の人生が凝縮されているといっても過言
ではない。そして、保存の渋民尋常小学校隣接、啄木の寄宿家の柱に
掲げらた木簡。記された石川啄木の短歌にこころを奪われたのだった。
碑歌:「 かにかくに 渋民村は恋しかり
おもひでの山
おもひでの川 」 (啄木 :一握の砂)
参照 # ① おもひでの川、おもひでの山の景観
② 石川啄木(哀しみの歌人)探訪紀行
感想:もうこの短歌に解説はいらないだろう。啄木の良さは分かりや
すい歌文の中に、一瞬の心の情感が、深く刻まれていると思う。
久し振り北海道:登別温泉から帰って、自宅の部屋から眺めた
八甲田山に、何故かこの短歌が浮かんだ。ふるさとはありがい。
いよいよ夏山シーズン、今年も八甲田山の大自然に抱かれたい。
※かにかくに:副詞であれこれと、いろいろと、の意味である。
映像:谷地温泉、自然湧出のいで湯の宿。自家発電の宿、電波が届かない宿
追悼:瀬戸内寂聴 99歳の大往生 2021.11.09
闘う作家、悟りと法話の尼僧&作家が亡くなった。巨星落ちる、男と女、家族、
何よりも人間としてどうあるべきかを探った女流作家瀬戸内晴美。その彼女が
大作「源氏物語」第九巻「早蕨・宿・東屋」を執筆する為 1996年 夏から秋に
谷地温泉投宿。筆者も、少しゆとりが出来たら、筆者も谷地温泉に長逗留して
瀬戸内晴美著源氏物語をジックリと読み解きたいと思うのだが・・・・・・・。
(過去の記録:2009,8.30)
自然の宝庫。源泉池には銀ヤンマが飛び交い谷地の森にはテンが棲む。耳を澄
ませば野鳥の囀りが聞こえる。温泉で体を癒し自然で心を癒す。一級の温泉地
の条件が備わっている。瀬戸内寂聴 (晴美)が長期滞在し執筆活動をしたのも頷
ける。文学碑こそないが此処もまた文学の湯の郷。
波乱に満ちた人生。夫の同僚と駆け落ち、人生を捨てる覚悟、悟り、常人に出
来ない経験をした彼女の顔は観音様の様に眩しいのは何故だろう?瀬戸内寂聴
が詠んだ俳句2首の色紙が新館休憩処の額縁に収められていた。
『 雪の壁 抜ければ谷地に 湯の煙 』(寂聴)
『 がたろうの ひるねの夢や ねむの花 』(寂聴)
※「がたろう」とは河童の異称
瀬戸内寂聴:1922年5月生、小説家、天台宗尼僧。文化功労者、文化勲章。徳
島県立高等女学校、東京女子大学卒。徳島県徳島市名誉市民。元天台寺
住職。代表作に 『夏の終り』 『場所』『現代語訳 源氏物語』など多数。
参照#① 八甲田山(登山口)温泉紀行
② 谷地温泉周辺に出没する可愛らしい珍獣「てん」
③ 瀬戸内寂静も癒された谷地温泉の交互浴の浴室浴槽
【静岡県温泉探査・沼津編 2019.5.24】
沼津駅前に降り立ち先ず目に飛び込んできたのが文豪井上靖の詞碑である。日本赤十字
奉仕団が沼津で青年期を過ごした井上靖の遅咲きの文学者の業績を称え、井上靖文学碑
第一号として建立した。反戦・平和の井上文学を意図とし次の様な詞が刻印されている。
碑文:『若し原子力より 大きな力を持つものがあると
すれば、それは愛だ。愛の力以外にはない 』 (井上 靖)
KEY:京都大学(旧帝大)卒、毎日新聞社入社、芥川賞受賞、平和アピール七人委員会
著作:風林火山、天平の甍、敦煌、青き狼、しろばんば、おろしや国粋夢譚、孔子 他
【静岡県温泉探査・熱海編 2019.5.24】
映像:熱海温泉老舗温泉旅館竜宮閣の玄関に掲げられた堀辰雄の色紙・写真類
熱海温泉と堀辰雄・・・・意外な組み合わせ。堀辰雄といえば透明感のある繊細な小説家
というイメージ。太宰治、山頭火や中原中也のような無性に寂しい孤立的な文人では
ない。それが熱い源泉、夏のイメージ熱海温泉の竜宮閣に立ち寄る・・・この宿の縁戚。
色紙:竜宮閣現在のご主人の母上が堀辰雄と再従姉弟という関係がこの宿のゆかり。
『 向日葵は 西洋人より 背が高い
軽井沢にて 辰雄 』
解説:堀辰雄と言えば、サナトリウムで繰り広げられる物語「風立ちぬ」を思い起す
学生時代にはちょっと苦手な作風(か弱い、そんなイメージ)であった。堀辰雄
自身も肺結核を患っておりサナトリウム生活を送っている。その時の揮毫かな。
参照#熱海温泉 竜宮閣 福々の湯
≪ 緊急速報:新年号「令和」制定 日本政府首相官邸発表 2019.4.1 ≫
恐らく日本国の全国民がこの瞬間に何らかの形で関わった事と思う。自分が生きる時代を
誰かに委ねなければならないもどかしさで傍観した人もいただろう。その結果万葉集から
出典の「令和」が新元号と告知された。本ブログで万葉集に触れたのは本蘭記述のみだった。
「大化 (645年)」以来、248番目の元号改定は掲題の吉野川の流れの様に悠々な歴史を辿
ってきた事を改めて思う。そして、日本最古の万葉集「梅花の歌32首序文」に記述された
「初春の令月にして気淑く風和ぎ梅は鏡前の粉を披き蘭は珮後の香を薫らす」はやがて咲
く吉野桜に引き継がれる。きっと、吉野山の様な全山春爛漫の時代になって欲しいと願う。
参照#新元号『令和』ゆかりの地 大宰府天満宮(大伴旅人ら梅花の宴の地)
(過去の記録:2017.7.29)
奈良県、紀伊山地の経ヶ峰付近を水源とする川。吉野山山系を流れ
和歌山県に入り紀ノ川となって紀淡海峡にそそぐ。長さ 81kmの川。
吉野山を訪れてこの川を詠った歌人柿本人麻呂の歌が万葉集に残る。
長歌:柿本人麻呂(持統天皇吉野山行幸随行時の作・万葉集巻1-36)
やすみしし わが大君の 聞し食す 天の下に 国はしも 多に
あれども 山川の 清き河内と 御心を 吉野の国の 花散らふ
秋津の野辺に 宮柱 太敷きませば 百磯城の 大宮人は 船並
めて 朝川渡り 船競ひ 夕川渡る この川の 絶ゆることなく
この山の いや高知らす 激つ瀧の都は みれど飽かぬかみ
反歌:柿本人麻呂(万葉集巻1-37)
見れど飽かぬ 吉野の河の 常滑の絶ゆることなく また還り見む
考察:平安の吉野山は貴族にはレジャー(リゾート)ランドであった。
吉野川に船を浮かべ宮人が涼みわたる姿は宮廷の威光を放って
華やかさは勿論宮廷遊びの最高の姿でもあった事が推察される
追記:万葉集にはこんな歌もある(万葉集 巻7-1131詠み人知らず)
原文・・・皆人之 戀三芳野 今日見者 諾母戀来 山川清見
皆人の 恋ふるみ芳野 今日見れば うべも恋ひけり 山川清み
(皆が行きたいという吉野山に今日来てみて納得しました。山も
川もすべてまことに風雅で、なんと魅力的なことなのでしょう)
参照#①奈良県吉野町「吉野山」 ②吉野山麓の名湯吉野温泉元湯
映像:前田家別邸の夏目漱石が浸かった湯殿。ここで前田卓(ツナ)女史と鉢合わせする。
夏目漱石ゆかりの温泉地:小天(おあま)温泉にやって来た。夏目漱石はよほど温泉
が好きなのか?それとも明治の社交場は温泉地という事情かここでも「坊ちゃん(道後
温泉)」同様名作を残している。実際にこの湯殿で起きたことを描いたのが小説「草枕」。
草枕:抜粋 { 宿の娘:那美(前田案山子(かがし)次女卓(ツナ))との遭遇シーン }
『・・・女の影は遺憾なく、余が前に、早くもあらわれた。・・・真白な姿が雲の底
から次第に浮き上がって来る・・頸筋を軽く内輪に、双方から責めて、苦もな
く肩の方へなだれ落ちた線が、豊かに、丸く折れて、流るる末は五本の指と
分れるのであろう。ふっくらと浮く二つの乳の下には、しばし引く波が、ま
た滑らかに盛り返して下腹の張りを安らかに見せる。張る勢を後ろへ抜いて、
勢の尽くるあたりから、分れた肉が平衡を保つために少しく前に傾く。逆に
受くる膝頭のこのたびは、立て直して、長きうねりの踵につく頃、平たき足
が、すべての葛藤を、二枚の蹠に安々と始末する。世の中に・・これほど自然
で、これほど柔らかで、これほど抵抗の少い、これほど苦にならぬ輪廓は決
して見出せぬ。・・・輪廓は次第に白く浮きあがる。今一歩を踏み出せば・・・・
あわれ、俗界に堕落するよと思う刹那に、緑の髪は、・・・風を起して・・・・・・・
渦捲く煙りを劈いて、白い姿は階段を飛び上がる。ホホホホと鋭どく笑う女
の声が、廊下に響いて、静かなる風呂場を次第に向(むこ)うへ遠退(の)く・・・』
鑑定:さあ、この文章を観てどう思うだろうか?漱石は画像右上の階段から降りてく
る前田家の娘ツナ(出戻り)の裸体を文章で現した。東大出のエリート教授
が表現するとこの様に面倒臭いものとなる。イヤラシサなど微塵もないのだ。
しかし、一般人ならこれは覗き表現にすぎない。藝術とはこの様に昇華する。
参照#夏目漱石 (則天去私) 探訪紀行
長門湯本温泉に来たもう一つの目的は童謡詩人の金子みすゞに触れること。
金子みすゞは長門湯本温泉のもう少し先の仙崎が生誕の地で記念館もある。
しかし温泉街には石碑やそれらしきものが無く漸くモザイク画詩文に接す。
詩歌:「こだまでしょうか」
遊ぼうっていうと、遊ぼうっていう
馬鹿っていうと、馬鹿っていう
もう遊ばないっていうと、もう遊ばないっていう
そして、あとでさみしくなって
ごめんねっていうと、ごめんねっていう
こだまでしょうか、いいえ、誰でも。 (金子みすゞ)
鑑賞:なんて素直で、正直で、透明で、優しくて、純心で無垢なことばを
繰り出す人なんだろう。金子みすゞの詩は一貫してこの清らで涼や
かで、ほのぼのした言葉で溢れている。心がポワ~ンと解放される。
追想:帰りの列車の関係で、金子みすゞ記念館まで行けず、長門湯本温泉
でなんとか金子みすゞの影に接したく探した結果、映像のモザイク
画の民家を音信川沿いに発見。電車を乗り継いで来たかいがあった。
記録:この民家のモザイク画は、「みすゞ燦参sun実行委員会」が新名所
づくりを目指す「プロジェクトⅯ」の一環として制作されたものだ。
縦3メートル、横9メートルの壁画で、1枚1枚に観光客や市民が
メッセージなどを書き込んだ仙崎名物の蒲鉾板 8,000枚填め込んだ。
参照:金子みすゞ生誕の地仙崎にある金子みすゞ記念館(金子みすゞ記念館HP)
( 2018年 山口県 温泉観光紀行 完 )
≪速報:温泉地景観 矢立峠界隈 (秋田県 日影温泉)2018.6.29≫
羽州街道北辺の要衝。この先北北東は津軽藩領である。その要衝を
思わせる矢立路に繋がる側道。この道をイザベラバード、吉田松陰、
伊能忠敬などが縦走した。秋田杉に囲まれた日影温泉屋波が甦った。
・
記述:イザベラ・バード 「日本奥地旅行記」(平凡社:高橋健吉訳)
『・・・すばらしい森の奥に入っていく。ゆるやかな勾配の長いジ
グザグ道を登って矢立峠に出る。この頂上には方尖塔がある。
・・・秋田県と青森県の県境を示す。これは日本にしてはすばら
しい道路である。・・・私は日本で今まで見たどの峠よりもこの
峠を賞め讃えたい。・・・ブルーッヒ峠・・・ロッキー山脈の・・・・・
しかしいずれにもまさって樹木が素晴らしい。その巨大な杉』
価値:19世紀の旅行家・探検家のイザベラは世界中を巡っている。そ
の中で、矢立峠をロッキー山脈の峠よりも絶賛していることに
驚愕するとともに、三大美林の秋田杉の価値に改めて感心した。
記録:秋田杉の見分け方。尖塔の尖ったものが植林で成長したものだ。
一方、尖塔が丸みを帯びたものは長い年月を経た天然の秋田杉。
参照#矢立峠途中にある日影温泉
湯田温泉駅から中原中也の生誕地を目指して数分。左手に公園が見えて来た。
井上公園は明治の政治家井上馨の屋敷跡を整備したもので、明治の歴史的な
建築物(七郷落時代の寓居)を保存展示。その一角に中原中也の詩碑がある。
碑文:「帰郷」 より
『・・・これが私の古里だ さやかに風も吹いてゐる
心置きなく泣かれよと 年増の低い声もする
あゝおまへはなにをしてきたのだと・・・
吹き来る風が私に云ふ』(中原中也)
解説:中也は貧困の歌人石川啄木とは対照的であった。破産追われし寺小僧
と、裕福で名士の坊ちゃんとでは背景が違い過ぎる。しかし、何故か
望郷の思いは重複する。ともに古里に気楽に帰れない事情は似ている。
参照#①中原中也記念館 ②石川啄木歌碑「石川啄木(ふるさとの・・・宝徳寺)」
③中原中也(ダダイズム)探訪紀行
映像:純愛と博愛の作家有島武郎の評論が収められた新潮社文庫本(現在青空文庫参照可)
「惜しみなく愛は奪う」この衝撃的なフレーズが大正時代に綴られたことに驚きを覚える。
人を愛するということは、相手のすべてを奪って自己のものにすること・・・という評論は
国家主義時代の背景下にあって、個人主義を論じ、なによりも強い愛情表現は先進だろう。
原文:評論の一文を下記に抜粋
『・・・人は愛人を見出すことに誤謬(ごびょう)なきことが出来る。そして個性の全的要
求は容易に愛を異性に対して動かさせないだろう。その代り一度見出した愛人に
対しては、愛はその根柢から揺ゆらぎ動くだろう。かくてこそその愛は強い。そ
して尊い。愛に対する本能の覚醒(かくせい)なしには、縦令男女交際にいかなる制限
を加うるとも、いかなる修正を施すとも、その努力は徒労に終るばかりであろう』