「こんにちわッ、テディちゃでス!
むむゥ! たいふゥだしィ!」
「がるる!ぐるるがる!」(←訳:虎です!G20だし!)
こんにちは、ネーさです。
そうね、台風は突然発生するし、
G20のために鉄道の駅は警備がスゴイことになってるし、
落ち着かない週末になりそうですが、
そんな中でも、はい、読書タイムですよ。
本日は、こちらの御本を、さあ、どうぞ~♪
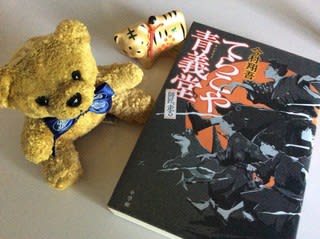
―― てらこや青義堂 師匠走る ――
著者は今村翔吾(いまむら・しょうご)さん、2019年3月に発行されました。
『青義堂』は『せいぎどう』とお読みくださいね。
「てらこやさんッていうとォ~…?」
「ぐるがるるる?」(←訳:学校だよねえ?)
もとは、お寺での学問指南所であったのが、
江戸時代になると
上方では《寺子屋》、
江戸では《筆学所》などとも呼ばれるようになり、
やがて全国的にも広まっていった教育施設――
寺子屋。
前回記事の展覧会情報では
師匠・メスキータさんと弟子・エッシャーさんたちの絆、
その絆が守ったメスキータさんの作品について
お喋りいたしましたけれど、
この御本にも、登場します。
お師匠さんとお弟子さんたちが、
明和七年(1770年)の江戸に。
「めいわァ??」
「っるがるる?」(←訳:っていうと?)
明和は、大雑把に言っちゃいますと、
江戸中期、でしょうか。
徳川家の第8代将軍・吉宗さんの孫にあたる
家治(いえはる)さんが第10代将軍に就いていた頃、ですね。
戦国の世は、すでに遠い昔話。
争いごとのない平穏な明和の江戸の、
日本橋南松川町に
『青義堂』なる屋号の
寺子屋さんがありました。
「ふァ~にぎやかァでスゥ!」
「ぐるるがるるる?」(←訳:賑やか過ぎない?)
戸を開ければ、
今日も降ってくる黒板消し……ならぬ手桶。
叱る師匠と、
エヘヘと舌を出す生徒たち。
あ、寺子屋さんでは
生徒ではなく、筆子(ふでこ)、というのだそうですが。
ここ『青義堂』の筆子たちときたら!
「わんぱくゥだしィ!」
「がるるぐる!」(←訳:困り者だし!)
『青義堂』の筆子さんたちは、
皆それぞれに“ワケあり”な子どもたちばかり。
剣術の才はあるのに
学問への熱意は空っきしだったり。
評判のいいお店の子なのに
お金の大切さが全然わかってない子だったり。
可愛い女の子なのに
兵法大好き~!だったり。
「たいへんでスねッ、せんせいィ!」
「ぐるがるるるるる!」(←訳:気が休まらないよ!)
筆子たちにキリキリ舞いさせられつつも、
彼らを慈しみ、
労をいとわず教え、諭し、走り回るのは
坂入十蔵(さかいり・じゅうぞう)さん。
手桶の熱湯を浴びせられても
ひるまず臆せず、
わんぱくな筆子たちに相対します。
でも、実は。
十蔵さん自身も“ワケあり”だったんです。
「えェッ? そうはァみえないィでス!」
「がるるぐるるる?」(←訳:普通に見えるよ?)
十蔵さんの生まれた坂入家は、
伊賀組(いがぐみ)の与力でした。
時代小説マニアさんには、もうお分かりですね。
そう、伊賀といったら、あの伊賀です。
「もッもしかしてッ!」
「ぐる~!」(←訳:忍者~!)
しかも、伊賀組きっての秀才と目されていた十蔵さんは
優秀な公儀隠密でもありました。
そんな変わり種のお師匠さんと、
変わり種の筆子たち。
トラブルに巻き込まれないはずがないわよね?
「やぱりィ!」
「がるるっるぅる?」(←訳:そうなっちゃう?)
ネタばれになってしまうので
これ以上は書けないのが、ああ、残念でなりません。
けれど、『青義堂』に集う面々の
賑々しくも純真爛漫な冒険は、
時代小説好きな方々だけでなく、
ミステリ好きさん&エンタ好きな方々にも
おすすめですよ。
「おししょうさんはァ、ふでこさんのォためにィ!」
「ぐるるるるがるるるるるぐるる!」(←訳:筆子さんはお師匠さんのために!)
教える者と教わる者、
ふたつを結ぶ物語を
ぜひ、一読してみてくださいね~♪
むむゥ! たいふゥだしィ!」
「がるる!ぐるるがる!」(←訳:虎です!G20だし!)
こんにちは、ネーさです。
そうね、台風は突然発生するし、
G20のために鉄道の駅は警備がスゴイことになってるし、
落ち着かない週末になりそうですが、
そんな中でも、はい、読書タイムですよ。
本日は、こちらの御本を、さあ、どうぞ~♪
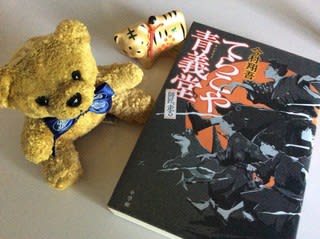
―― てらこや青義堂 師匠走る ――
著者は今村翔吾(いまむら・しょうご)さん、2019年3月に発行されました。
『青義堂』は『せいぎどう』とお読みくださいね。
「てらこやさんッていうとォ~…?」
「ぐるがるるる?」(←訳:学校だよねえ?)
もとは、お寺での学問指南所であったのが、
江戸時代になると
上方では《寺子屋》、
江戸では《筆学所》などとも呼ばれるようになり、
やがて全国的にも広まっていった教育施設――
寺子屋。
前回記事の展覧会情報では
師匠・メスキータさんと弟子・エッシャーさんたちの絆、
その絆が守ったメスキータさんの作品について
お喋りいたしましたけれど、
この御本にも、登場します。
お師匠さんとお弟子さんたちが、
明和七年(1770年)の江戸に。
「めいわァ??」
「っるがるる?」(←訳:っていうと?)
明和は、大雑把に言っちゃいますと、
江戸中期、でしょうか。
徳川家の第8代将軍・吉宗さんの孫にあたる
家治(いえはる)さんが第10代将軍に就いていた頃、ですね。
戦国の世は、すでに遠い昔話。
争いごとのない平穏な明和の江戸の、
日本橋南松川町に
『青義堂』なる屋号の
寺子屋さんがありました。
「ふァ~にぎやかァでスゥ!」
「ぐるるがるるる?」(←訳:賑やか過ぎない?)
戸を開ければ、
今日も降ってくる黒板消し……ならぬ手桶。
叱る師匠と、
エヘヘと舌を出す生徒たち。
あ、寺子屋さんでは
生徒ではなく、筆子(ふでこ)、というのだそうですが。
ここ『青義堂』の筆子たちときたら!
「わんぱくゥだしィ!」
「がるるぐる!」(←訳:困り者だし!)
『青義堂』の筆子さんたちは、
皆それぞれに“ワケあり”な子どもたちばかり。
剣術の才はあるのに
学問への熱意は空っきしだったり。
評判のいいお店の子なのに
お金の大切さが全然わかってない子だったり。
可愛い女の子なのに
兵法大好き~!だったり。
「たいへんでスねッ、せんせいィ!」
「ぐるがるるるるる!」(←訳:気が休まらないよ!)
筆子たちにキリキリ舞いさせられつつも、
彼らを慈しみ、
労をいとわず教え、諭し、走り回るのは
坂入十蔵(さかいり・じゅうぞう)さん。
手桶の熱湯を浴びせられても
ひるまず臆せず、
わんぱくな筆子たちに相対します。
でも、実は。
十蔵さん自身も“ワケあり”だったんです。
「えェッ? そうはァみえないィでス!」
「がるるぐるるる?」(←訳:普通に見えるよ?)
十蔵さんの生まれた坂入家は、
伊賀組(いがぐみ)の与力でした。
時代小説マニアさんには、もうお分かりですね。
そう、伊賀といったら、あの伊賀です。
「もッもしかしてッ!」
「ぐる~!」(←訳:忍者~!)
しかも、伊賀組きっての秀才と目されていた十蔵さんは
優秀な公儀隠密でもありました。
そんな変わり種のお師匠さんと、
変わり種の筆子たち。
トラブルに巻き込まれないはずがないわよね?
「やぱりィ!」
「がるるっるぅる?」(←訳:そうなっちゃう?)
ネタばれになってしまうので
これ以上は書けないのが、ああ、残念でなりません。
けれど、『青義堂』に集う面々の
賑々しくも純真爛漫な冒険は、
時代小説好きな方々だけでなく、
ミステリ好きさん&エンタ好きな方々にも
おすすめですよ。
「おししょうさんはァ、ふでこさんのォためにィ!」
「ぐるるるるがるるるるるぐるる!」(←訳:筆子さんはお師匠さんのために!)
教える者と教わる者、
ふたつを結ぶ物語を
ぜひ、一読してみてくださいね~♪















