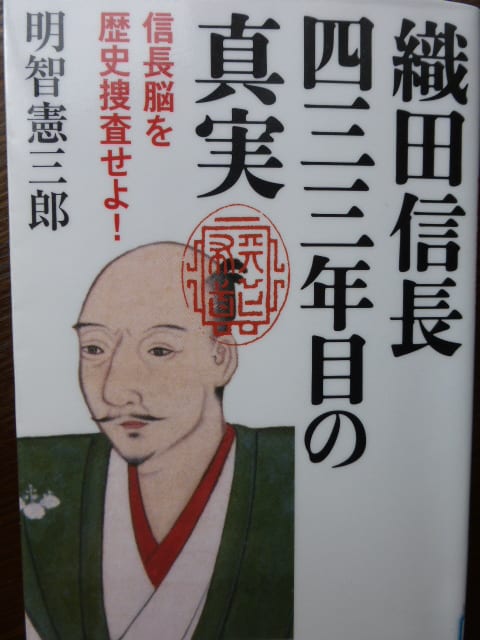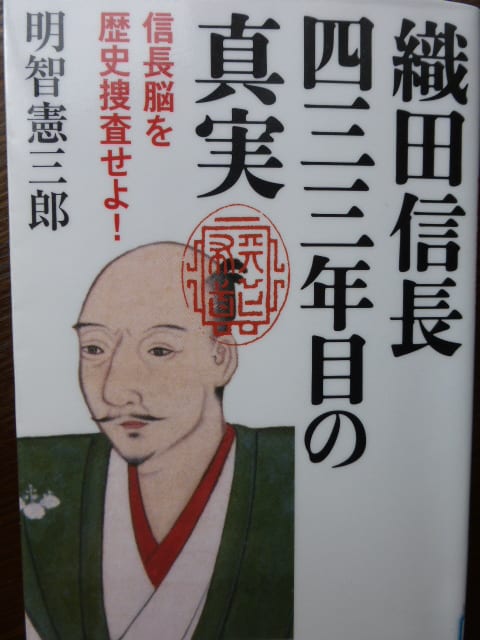明智憲三郎氏の『織田信長四三三年目の真実』を読んだ。ベストセラー『本能寺の変 431年目の真実』、さらには、2009年の『本能寺の変 四二七年目の真実』から興味深く読んでいる。真実を獲得するために史料を徹底的に調べ、事件の成り立ちを論理的に追及、矛盾を解き明かしていく歴史捜査の手順や流れが実に素直で好感を持つ。今回は、より読者に分かりやすくするために、出来事の証言、謎、疑問を解くといったステップアップスタイルで、他にない論理分析性の高いものである。これらは、長年のシステムエンジニアで鍛えた、システムズ・アプローチの技を思い出す。現在のWebシステムのようなトライ&エラー的な開発ではなく、レガシーである大型汎用コンピュータ時代のシステム開発である。一日1回のまとまったバッチ処理のテスティングをするために、机上デバッグ(業務処理確認や問題個所探索 などをプログラムリストと頭の中で行う)に集中したのを思い起こす。本能寺の変の歴史解説書において、古い時代の通説が増幅され、定説となり、権威学者・著名人の説を否定することがタブー視されてきた中で、本当のことを知りたいものにとって、明智氏の出版物は読みながら、自分自身が考え、分析できる楽しみを提供してくれるものである。読後感として、まだまだ、理解できないところもあり、特に、穴山梅雪の件については、解釈が異なるままである。