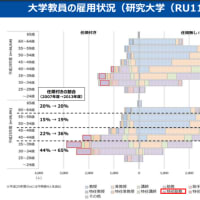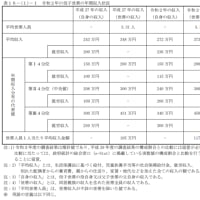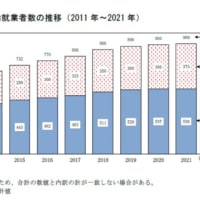時折「ほとんど0円大学」という、サイトをチェックしている。
公式:ほとんど0円大学 おとなも大学を使っちゃおう
このサイトをチェックする理由は、単なる(知的?)好奇心からなのだが、大学が行う公開講座の充実度から考えると京大を中心とした関西の大学がとても積極的である、ということを感じる。
もちろん、東京の大学もあるのだが、講座数やその内容のバラエティさという点では、関西の大学が圧倒的に多い。
そして、講座内容を見るたびに思うことは、「なぜ名古屋をはじめ、他の地域の大学ではこのような市民に開放された講座が少ないのだろう?」ということだ。
名古屋で言うなら名古屋大学が中心となって、毎年10月~11月にかけ「街なかサイエンス」という市民向け公開講座を開くことはあるのだが、その内容はタイトル通り「サイエンス」が中心だ。
元々名古屋大学の始まりが、医学部と理工学部であったということを考えると、サイエンス=科学が中心になるのは仕方ないのかもしれないのだが、多くの市民が興味・関心が持てる内容とは限らない。
だからこそ、幅広い分野での公開講座であってほしい、と思うのだ。
国立大学が「独立行政法人」という名がつくようになり、大学であっても研究成果などが求められるようになった。
と同時に、研究費用なども大学独自で、ある程度調達する必要も出てきた。
そこで注目されるようになったのが「産学連携」だった。
大学は基礎研究などを主に行い、その研究を応用、実用化する為に企業のサポートを得る、という連携体制だ。
ただこの「連携体制」は、ある特定の企業との連携を深めるばかりではないか?という、気がする時がある。
それは、大学などが行う公開講座でのサポートとして、特定の企業名が登場することが多いからだ。
名大について言えば、トヨタ自動車とその関連企業が多い、ということになる。
それで良いのだろうか?
むしろ、京都大学をはじめとするより多くの市民に大学の研究を知ってもらうことで、地域全体の文化的なメリットが高いだろうし、そのような中から、特定の企業以外からの研究のアイディアをもらうことになるのではないだろうか?
その結果として、思わぬ地元の企業から「産学連携」の話も出てくると思うのだ。
それだけではなく、大学が積極的に町に出ることで、それまで「大学」そのものに興味関心が無かった人達や小中高校生たちの「知的好奇心」を刺激し、地元の大学への進学を希望する生徒も増えてくると思うのだ。
東京の大学や関西の大学には「名物教授」と呼ばれる教授も多く、その先生の授業を受けたいがために、進学を希望するという生徒もいるだろう。
逆にそのような「(ローカル)名物教授」を育て、魅力ある大学にする為にも、このような幅広いジャンルの市民向けの公開講座は、有効だと思う。
タイトルの「書を捨て、町に出よう」と言ったのは、劇作家で演出家であった唐十郎だった。
唐十郎のような型破りな発想が、大学にも求められているような気がするのだ。