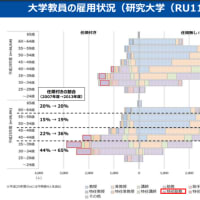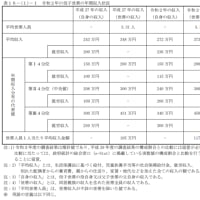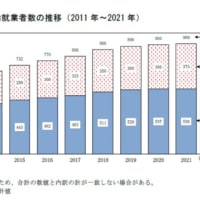朝日新聞のWebサイトを見ていたら、「これからの旅は、個性を体験するようになるのかも?」という記事があった。
朝日新聞:自然と一体 貸し切り風呂が森に点々 宮城 遠刈田「温泉山荘だいこんの花」
この記事の写真を見たとき、「これからの旅は、その土地の個性を楽しむ」ということになるのでは?という気がしたのだ。
約3年に及ぶ「コロナ禍」で、人の行動に変化が生まれているような気がしている。
一つは「旅行や美術館巡り、ライブやスポーツ観戦」などが、規制されていたことに対する反動。
もう一つは「出かけないことへの耐性」だ。
「出かけないことへの耐性」というと、大げさな表現のようだが、「用事がなければ、出かけたくない」という気持ちで休日を過ごされる方も多いのではないだろうか?
「出かけたくない」のではなく、「人目を気にしている」という部分もあるとは思うのだが、「巣ごもり生活」の長期化で、「日常的に出かける目的」を見失ってしまっているようなところがあると思う。
特に「買い物」などに関しては、「ネットショップでポチする」というある種の「楽な買いもの体験」をしてしまったため、わざわざ繁華街の百貨店に出向いて、売り場を歩くということに「便利さ」のようなものが感じられなくなってしまっているのでは?という、ことなのだ。
あくまでも個人的なことではあるが、「コロナ禍」になってから、あれほど好きだった書店巡りに行かなくなり、ネットで購入することが多くなった。
「書店に行くのが、面倒くさい」というよりも、フラッと出かける気持ちが以前より無くなってきている、という感覚なのだ。
その反面「旅行や美術館など、非日常的な体験」に関しては、「出かけたい」という気持ちが強くなっているような気がしている。
その中でも「旅行」は、「いつでも行ける」と思っていたら「行けない時があるのだ」という経験をした、「コロナ禍」期間だったように思う。
「行けない時がある」という状況になってくると、セントラルキッチンで料理をサービスするようなチェーン化した宿泊施設ではなく、「その土地に行かないと食べられないお料理を提供してくれる場所に行きたい。個性的な体験ができるところへ行ってみたい」という気持ちのほうが、強くなってくるように思う。
何故なら、チェーン化された宿泊施設は、どこへ行っても同じサービス、同じような部屋だからだ。
もちろん、旅行先ごとに宿泊施設を変えればよいだけなのだが、評判の良いチェーン化された宿泊施設というのは、一つのステイタスがあり、そのステイタスに憧れていた、という時期がここ20年くらい続いていたように感じていた。
ただそのようなステイタスではなく「自分好みの個性ある宿泊施設」のほうが、今の社会的な雰囲気が求めているような感覚を持っている、というのも事実なのだ。
おそらく、「自分だけの隠れ家的宿泊施設(温泉なども含む)」へと、人の気持ちが移っていくような予感をしている。
「自分のもう一つの家」という、「巣ごもりができる旅先」という感覚だ。
ここ3年ほど前から話題になっている、「ソロキャンプブーム(というべきか?)」の背景には、著名タレントさんのYouTube配信などの影響だけではなく、「自然の中で簡単に巣ごもりたい」という、潜在的欲求があったので?と、考えている。
「キャンプは無理でも、自分の隠れ家という場所は、自分の個性にあった場所でありたい」、そんな生活者を掘り起こすことが、地方の活性化にもつながるのでは?と、考えている。