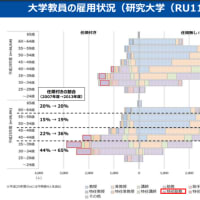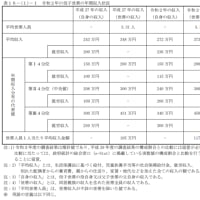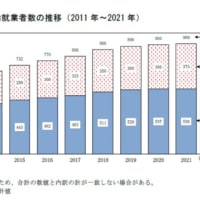10月下旬の日経新聞の地方ニュースの記事一覧を見て、驚いたことがある。
それは、日本各地で「星空」をテーマとしたツーリズムに取り組む動きがあったからだ。
そのような動きに敏感だったのは、日経だけではなかったようで、朝日新聞のGlobalにも「星空」に関する記事が掲載されている。
朝日新聞:星空保護に取り組む篠原ともえさん「地球に住むマナー」を指摘 光害対策を応援
「星空」を地域資源として活用しようとしている地域の多くは、過疎に近い状況にあるようだ。
むしろ、10年ほど前から問題になっている「光害」と呼ばれるような、深夜でも様々な光があふれる都市部では、「星空を見る」ということ自体出来なくなっている。
昨今では深夜時間帯だけは、ライトダウンするようになっている所もあるようだが、都市規模が大きくなればなるほど、人工的な光があふれる様になっていることには違いないはずだ。
東京都庁にプロジェクションマッピングなどの話題もあり、プロジェクションマッピングで観光客を誘致するような動きもあるような話も聞かないわけではない。
それほど、都市部の生活者は「光に溢れた生活」をしている。
それを逆手にとって「自然の中で感じ取る明り=星空」を、積極的に情報発信しようとする動きも出ている地域がある、ということなのだ。
このような動きは、決して今に始まったことではないのでは?と、感じる部分がある。
というのも「コロナ禍」以降、「自分の生活の場」をなんでも揃う都会からやや不便ではあるが、「生きている実感」が感じられるという理由で、地方に移住する若い人達が少しづつ現れてきたからだ。
この背景にあるのは、自分たちの暮らし方(=ライフスタイル)をYoutubeのような動画サイトで紹介しつつ、都会では感じられない自然の豊かさを感じる生活を実践しているからだ。
もちろん、実質的にはYoutube広告から得られる収益が主な収入源となっている可能性の方が高いが、このような日本の地方での暮らしが、Youtubeのようなネットサービスによって世界中に発信されることで生まれる、意外な観光地もある。
例えば、東北のネット環境が全くない鄙びた温泉宿に、海外からの観光客が殺到している。
さほど大きな旅館ではなく、ネット環境が全くないような場所にあるにもかかわらず、宿泊客の7割近くが海外からだという。
これまでのインバウンドの発想の中心は、「アクセスが良い。買い物ができる。世界的に有名な観光地がある」ということを必須条件だったように感じる。
しかし、そのような発想は周回遅れなのかもしれない。
確かに、京都で観られるオーバーツーリズムは、その地域で生活をしている人達の生活そのものを、脅かす状況になりつつある。
その一方で、上述したようなあえて鄙びた場所にある温泉旅館を選ぶ海外からの旅行者も増えている、ということなのだ。
著名な観光地をあえて外す海外からの旅行者は、既に日本に何度か来日した経験があり「ガイドブックで紹介されているような場所には興味が無い」のだ。
とすれば、これまでインバウンドの必須条件が無くても、地域創生の為の海外からの旅行者誘致は可能になる。
それは日本の伝統的なお祭りであったり、豊かな自然、歴史的遺構などだ。
と同時に、点で観光地を考えるのではなく、面で考える自然豊かな地域資産の掘り起こし、という発想が求められている気がする。
最新の画像[もっと見る]