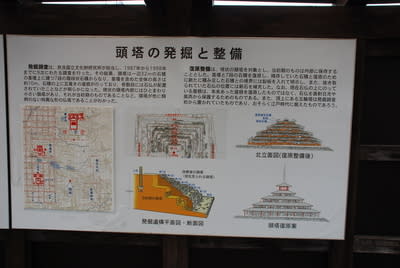これは、多宝塔。江戸時代のものだ。明治時代に修復されている。

やっと本堂に来た。
実は、当日は、12年に一度の、本尊の毘沙門天ご開帳の初日だった。千円でちょっと高いが、聖徳太子が造った伝えられる毘沙門天様。拝む価値十分。12年間御利益があるというあり難い御札もいただける。
じっくり見れるが、ほとんど御前立ちと同じように見える。
その翌日が大祭であったが、さぞ盛り上がったことだろう。
平日にもかかわらず、御祈祷を受ける人が多く、その間は、堂内に入れない。
御祈祷は、遠くからも聞こえたように、相当勇ましいもので、お経をアコーディオンのように、右から左へ、行ったり来たりさせる。密教ど真中という感じだ。

こちらが本堂。前が舞台になっていて、大和平野を見下ろすすばらしい景色を堪能することができる。

本堂への登り口には、霊宝館がある。信貴山縁起の精巧な模写を見ることができる。
すばらしいものだ。
題材は、本寺の中興の祖である命蓮上人が、修業していたころの物語である。
飛倉巻では、毘沙門天を信奉し、長者になったが、信心を失った元貧者が、お返しする托鉢を倉に投げ入れたところ、倉が動き出し、転がり出した鉢が倉を乗せ、飛んで行ったという話である。
延喜加持巻は、醍醐天皇が重病になり、命蓮上人に祈祷を頼んだところ、上人は、剣の護法童子が朝廷に出現すると答え、その通りとなり、病が治ったという話である。
千の剣を身につけ、黄金の車輪を回し雲を呼びながら、枕元に向かう童子は、この絵巻のクライマックス。切手少年だった私には、お馴染の絵でもある。
尼公巻は、命蓮上人の姉である尼公という姉が、信濃の国から、弟である命蓮上人を探しに来て、東大寺の大仏殿の力で再会を果たすという話。ここに描かれている大仏の姿が、まだ焼失する前の姿ということで、貴重な記録にもなっている。
今回、信貴山縁起を見る機会を得て、有名な絵巻は制覇。話の面白さといい、絵のユニークさといい、繊細さといい、日本の文化のすばらしさを改めて思う。
霊宝館の横に見えるのが、経蔵堂。大きなお経が詰まった厨子があり、マニ車のように回せるようになっているのだが、一人では、重くて回らなかった。

本堂から、境内を見下ろしたところ。お堂や、塔が沢山見える。

聖徳太子像。聖徳太子は、ここで、毘沙門天から嚆矢を授かり、物部氏に勝利したのだ。普通の聖徳太子像とは、イメージが大きく異なる。

劔鎧護法堂。醍醐天皇を重病から救った劔鎧護法を本尊としている。様々なお堂は、信貴山縁起に描かれた言い伝えに基づくものが、多い。

本堂を見上げたところ。読経の声が聞こえてくる。

お寺の下は、ダムになっており、赤い橋がある。開運橋を呼ばれているが、昭和6年に造られたもので、上路カンチレバー橋という貴重なものだそうだ。

信貴山大橋のバス停に着いたら、白虎の像があった。平城遷都1300年因んで、奈良平野の西の入口に、その守り神である白虎の像が造られたようだ。
行きにくい場所なのに、巨大な、寺院だった。タイガーズファンの信者も多いのだろうか。
虎年の今年は、参拝のチャンス!