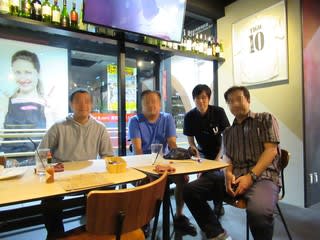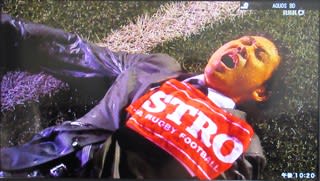リスペクトコラムです。
Jリーグシャレン絡みの記事を書いていたのですが、そこで出てくるのがSDGsというキーワード。読者の皆さん知っていますか? 世界的に最近広まってる言葉で、社会の様々な分野で出てくる言葉です。最近報道でもよく見かけるようになりました。それがスポーツ界でも波及しており、どうしても一度スポーツ界でのSDGsを紹介しないわけにはいかなくなりました。


【スポーツと持続可能な開発(SDGs)】
国際社会は国連を先頭に、社会のあらゆる領域との徹底的な協議プロセスを進め、今後15年間に追求すべきものとして、下記の17項目からなる持続可能な開発目標(SDGs)に合意しました。スポーツは、平和と開発の目標達成に向けて前進するための費用効果的で柔軟なツールとなることが判明しています。国連は、SDGsの17項目それぞれの達成に向けた課題に取り組む潜在的能力を備えた重要かつ強力なツールとして、スポーツがその役割を果たすことを期待しています。
①「貧困をなくそう」:あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ
スポーツは、幸せや、経済への参加、生産性、レジリエンスへとつながりうる、移転可能な社会面、雇用面、生活面でのスキルを教えたり、実践したりする手段として用いることができます。
②「飢餓をゼロに」:飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する。
栄養と農業に関連するスポーツ・プログラムは、飢餓に取り組む食料プログラムや、この問題に関する教育を補完するうえで、適切な要素となりえます。対象者には、持続可能な食料生産やバランスの取れた食生活に取り組むよう、指導を行うことができます。
③「すべての人に健康と福祉を」:あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する。
運動とスポーツは、アクティブなライフスタイルや精神的な安寧の重要な要素です。非伝染性疾病などのリスク予防に貢献したり、性と生殖その他の健康問題に関する教育ツールとしての役割を果たしたりすることもできます。
④「質の高い教育をみんなに」:すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する。
体育とスポーツ活動は、就学年齢児童の正規教育システムにおける就学率や出席率、さらには成績を高めることができます。スポーツを中心とするプログラムは、初等・中等教育以後の学習機会や、職場や社会生活でも応用できるスキルの取得に向けた基盤にもなりえます。
⑤「ジェンダー平等を実現しよう」:ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る。
スポーツを中心とする取り組みやプログラムが、女性と女児に社会進出を可能にする知識やスキルを身に着けさせる潜在的可能性を備えている場合、ジェンダーの平等と、その実現に向けた規範や意識の変革は、スポーツとの関連で進めることもできます。
⑥「安全な水とトイレを世界中に」:スポーツは、水衛生の要件や管理に関するメッセージを発信するための効果的な教育基盤となりえます。
スポーツを中心とするプログラムの活動と意図される成果を、水の利用可能性と関連づけることによって、この問題の改善を図ることもできます。
⑦「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」:すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する。
スポーツのプログラムと活動を、省エネの話し合いと推進の場として利用すれば、エネルギー供給システムと、これに対するアクセスの改善をねらいとする取り組みを支援できます。
⑧「働きがいも経済成長も」:すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する。
スポーツ産業・事業の生産、労働市場、職業訓練は、女性や障害者などの社会的弱者集団を含め、雇用可能性の向上と雇用増大の機会を提供します。この枠組みにおいて、スポーツはより幅広いコミュニティを動員し、スポーツ関連の経済活動を成長させる動機にもなります。
⑨「産業と技術革新の基盤をつくろう」:レジリエントなインフラを整備し、包摂的持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る。
レジリエンスと工業化のニーズは、災害後のスポーツ・娯楽用施設の再建など、関連の開発目標の達成をねらいとするスポーツ中心の取り組みによって、一部充足できます。スポーツはこれまで、開発に向けたその他従来型のツールを補完し、開発と平和を推進するための革新的な手段として認識されており、実際にもそのような形で利用されてきました。
⑩「人や国の不平等をなくそう」:国内および国家間の不平等を是正する。
開発途上国におけるスポーツの振興と、スポーツを通じた開発は、途上国間および先進国との格差を縮めることに貢献します。スポーツは、その人気と好意度の高さにより、手を差し伸べることが難しい地域や人々の不平等に取り組むのに適したツールといえます。
⑪「住み続けられるまちづくりを」:都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする。
スポーツにおける包摂と、スポーツを通じた包摂は、「開発と平和のためのスポーツ」の主なターゲットのひとつとなっています。気軽に利用できるスポーツ施設やサービスは、この目標の達成に資するだけでなく、他の方面での施策で包摂的かつレジリエントな手法を採用する際のグッドプラクティスの模範例にもなりえます。
⑫「つくる責任、つかう責任」:持続可能な消費と生産のパターンを確保する。
スポーツ用品の生産と提供に持続可能な基準を取り入れれば、その他の産業の消費と生産のパターンで、さらに幅広く持続可能なアプローチを採用することに役立ちます。この目的を有するメッセージやキャンペーンは、スポーツ用品やサービス、イベントを通じて広めることができます。
⑬「気候変動に具体的な対策を」 :気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る。
観光を伴う大型スポーツ・イベントをはじめとするスポーツ活動やプログラム、イベントでは、環境の持続可能性についての認識と知識を高めることをねらいとした要素を組み入れるとともに、気候課題への積極的な対応を進めることができます。また、被災者の間に絆と一体感を生み出すことで、災害後の復興プロセスを促進することも可能です。
⑭「海の豊かさを守ろう」:海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する。
水上競技など、スポーツ活動と海洋とのつながりを活用すれば、スポーツだけでなく、その他の分野でも、海洋資源の保全と持続可能な利用を提唱できます。
⑮「陸の豊かさも守ろう:陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る。
スポーツは、陸上生態系の保全について教育し、これを提唱する基盤となりえます。屋外スポーツには、陸上生態系の持続可能で環境にやさしい利用を推進するセーフガードや活動、メッセージを取り入れることもできます。
⑯「平和と公正をすべての人に」:持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する。
スポーツは復興後の社会再建や分裂したコミュニティの統合、戦争関連のトラウマからの立ち直りにも役立つことがあります。このようなプロセスでは、スポーツ関連のプログラムやイベントが、社会的に隔絶された集団に手を差し伸べ、交流のためのシナリオを提供することで、相互理解や和解、一体性、平和の文化を推進するためのコミュニケーション基盤の役割を果たすことができます。
⑰「パートナーシップで目標を達成しよう」:持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。
スポーツは、ターゲットを絞った開発目標に現実味を与え、その実現に向けた具体的前進を達成するための効果的手段としての役割を果たします。スポーツ界は、このような活動の遂行その他を通じ、草の根からプロのレベル、また、民間から公共セクターに至るまで、スポーツを持続可能な開発に活用するという共通の目的を持つ多種多様なパートナーやステークホルダーの強力なネットワークを提供できます。
引用:国際連合広報センター公式HP
という内容でした。ようは社会・地域貢献での世界基準なのかな。堅苦しい内容ですが、スポーツに限らず今後いろいろなシーンで出てくると思います。ここでは各課題がスポーツでどう解決できるかが書かれています。いろいろ専門用語が出ていますが、順番に解説していきます。 17のゴールの説明ですが、元が英語なので、どうしてもこういう事になるのでしょう。
「ジェンダー」:生物学的な性別に対して、社会的・文化的につくられる性別のことだそうですが、何度読んでも100%把握できません(笑)。ようは「女性だから」の「だから」という部分らしいです。
「包摂的」:正式には「社会的包摂的」になり、英訳では「ソーシャル・インクルージョン」であり、社会的に弱い立場にある人々をも含め市民ひとりひとり、排除や摩擦、孤独や孤立から援護し、社会の一員として取り込み、支え合う考え方のことだそうです。「包摂的社会」とは、どんな弱者もみんなで取り込んで支え合うという意味なのかな。
「ディーセント・ワーク」:働きがいのある人間らしい生活を継続的に営める人間らしい仕事(労働条件)のこと。
「レジリエント」:弾力。復元力。回復力。強靱さ。


【スポーツSDGs(スポーツ庁)】
「このSDGsの達成にスポーツで貢献していきます。スポーツの持つ、人々を集める力や人々を巻き込む力を使って、SDGsの認知度向上、ひいては、社会におけるスポーツの価値のさらなる向上に取り組みます。『スポーツSDGs』の趣旨に御賛同いただける企業やスポーツ団体等とも連携し、より大きなムーブメントにしていきたいと思っております。」
〔Our Global Goals〕
「スポーツ庁とビル&メリンダ・ゲイツ財団は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への気運の高まりに合わせて、SDGsへの関心を高めるため、スポーツSDGsの一環として、パートナーシップを締結いたしました。ビル&メリンダ・ゲイツ財団が行う「Our Global Goals」について、スポーツSDGsの一つとして広報を行い、スポーツSDGsムーブメントの高まりに繋げてまいります。」
引用:スポーツ庁公式HP
このスポーツ庁の取り組みですが、東京五輪もあって盛り上がっていますね。その財団はマイクロソフト社のビル・ゲイツ会長夫妻が'00年に創設された世界最大の事前基金団体で、世界における病気・貧困への挑戦を主な目的としており、特にアメリカ国内においては教育やIT技術に接する機会を提供する活動を行っているそうです。いいところと組みましたね。
大変堅苦しいものですが、どのみち今後このSDGsがいろいろ出てくる事でしょう。Jクラブでもそのうち、SDGsができていないとダメ出しされる時代が来るでしょう。柏や浦和さんが、国際援助機関と連携していますが、やはりそういう活動がスタンダードになってきているのかもしれません。当ブログの「Jクラブの付加価値」にも取り入れていく事になるのかな。「SDGs」の「G」がGOALというのは、サッカーにも絡んだネーミングで面白いですね。