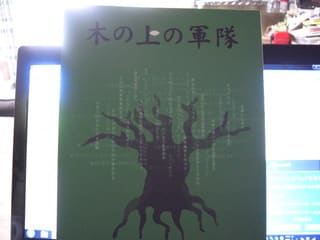4月10日、渋谷のシアターコクーンにて「木の上の軍隊」を観てきました。〈最後の部分は加筆しました。〉
近頃、プチ予知的な事が結構あって、このお芝居の上演もまさにそんな感じの出来事だったのでした。この事は「『木の上の軍隊』は来年上演決定」という記事の中にも書いたことですが、「日の浦姫物語」を観た後、この「木の上の軍隊」という作品が幻で終ってしまったことが残念でならず、誰か残っているプロットなどを引き継いで書いてくれないかしらと思った翌日辺りに上演決定のニュースを知ったのです。
プチ予知などと書きましたが、きっと誰もがこの作品が幻になってしまったことを残念に思っていたのだと思います。
でもいざ上演が決まったとなると、どんなお話になるんだろうかとワクワクするのと同時に微かな心配のようなものも感じたりもしたのです。この部分は余計なお世話の無用な心配ってものですが、アレコレ思うということは、お芝居を愛する者のそこも楽しみな部分なのかと思います。
私が感じた微かな心配というのは、当初のキャストさんと違っていた点から来たのだと思います。
毎度おなじみの舞台の人から、どちらかと言うとテレビのドラマの中で見知っている人。
私にとっては、片平なぎささん=「赤い霊柩車」の人。サスペンスの女王がいかなるお芝居を見せてくれるというのだろうか・・・
が、彼女の高い澄んだ声はこのお芝居にぴったりでした。そしてその声は既に若くない。彼女は若さを失ったのではなく歳を重ねてあの落ち着いた澄んだ太い声を手に入れたのだと思いました。
「暇か?」と言わない山西さん、期待していました。期待通り。
藤原竜也君、やっぱり彼は演技が上手い。
私は泣きました。
新兵の「純」なるものに。
上官の悲しいほどの醜さに。
物語に。
そしてまたパンフレットを読んでまた泣きました。
井上先生が残していたものは、膨大な沖縄の資料と一枚のメモでした。プロットはなかったみたいです。だけど蓬莱竜太さんがみんなの気持を受けてこの作品を完成させたのですね。
今回のパンフレットは出来たらお買い求めになることをおすすめします。読むべきことがたくさん在るように感じました。
井上先生のこともそうですが、私の場合は、今の自分に響く言葉がありました。
蓬莱さんの原稿に、チャップリンの映画の中のセリフの引用がありました。
「人が逃れられないのは死だけじゃない。生きることからも逃れられない。人生から逃れられない。ライフ!ライフ!ライフ!」
お芝居がとっても良かったので、劇場で「すばる」を買い求めてきました。
全て満足。
唯一難を言うと、・・・
―ぶっちゃけ、こまつ座ってアンコール回数少ないよね。おじさまとかおばさまとか〈私より上の〉直ぐに席を立つんだもの。
後1回ぐらいはやって欲しいなあ―・・・って、思った^^
以下はちょっぴりのネタバレ感想です。と言ってもあらすじなどを書いてはいません。全国を回るお芝居ですが、見る機会が当分は無理だなと思われる方は下の「すばる」のシナリオはいかがですか。
 |
すばる 2013年 05月号 [雑誌] |
| 集英社 | |
| 集英社 |
このお芝居の骨格をなしていたのは、やはり新兵の沖縄方言でいうセリフとラストに繰り返されて言うセリフだと思うのです。
沖縄方言ってイイですよね。時々真似したくなるんだけれど、うまくいきません。
「なんでそういうことをするのかねぇっと。・・・・・・・」
「・・・・」の部分にはその後の台詞が続くわけですが、純粋な青年の心が伝わってくるのです。
どうして命をかけて戦えるのか。愛する人のためなのか。
純粋な青年には、命令されたから動くという人がいるという事がわからないのだと思います。
正義や愛や、守るべき者たちを守るためという大義のない人間。
お芝居では描かれていない日本兵に拠る沖縄の人の大量虐殺は、生きる残るために何度も沸き起こってきた上官の新兵の殺意として描かれていたのかもしれません。
「守られているものに怯え、怯えながらすがり、すがりながら憎み、憎みながら信じる」
このセリフを聞いて、今の自分達に当てはめない人はかえって少ないと思いました。
信じるしかないのですよね。
だけど信じるに値する「国」で有って欲しいと切に切に願います。
私がそれ以外で「おおお」と思い泣けたシーン。
青年が自分の気持を吐露するシーンで、彼は叫びます。その叫びは時折木から聞こえてきた奇妙な音と一緒だった・・・というのは、私が感じただけみたいです。シナリオを読んでもそういうシーンにはなっていませんでした。でも彼が最後に高笑いというか叫んだのは木の出す音の高さと一緒だったような気がしました。偶然なのか、役者の感なのか演出なのか、凄い効果がありました。
木はただ見続けているだけ。
感情もなく淡々としています。
でも人間どもが吐き出す矛盾の叫びを、木は知っていたかのようでした。
感想を書くのならば、やはり作家様がココゾと思った部分をスルーしては行けないような気がします。
二人が木から降りた後の女のセリフ
「しかし、二人はいまだにこの木の上にいる。そこから占領されてゆく世界を眺めているだけでどこにも行けない。」
この後も心に残る台詞が続くのですが、戦闘機や爆音の音やプロペラ機の風の演出が、「今」という時代を不安にもさせ、そして切なく余韻を残します。
まるで新兵が上官が自分たちであるかのように・・・
下の本も買って来ました。後日感想を載せると思います。
 |
水の手紙: 群読のために |
| 井上 ひさし,萩尾 望都 | |
| 平凡社 |