 「ねえ、ママ。あのねえ。」と涼太が言った。
「ねえ、ママ。あのねえ。」と涼太が言った。
「なあに。」と、優しげに微笑んで私は答える。
だけど、声は冷たい氷のようだと感じていた。微笑みも作られたようなこわばった顔だと思った。
しとしとと雨が降っていた。狭いアパートの一室で三歳の子供とずっと二人でいるのが憂鬱だった。夫の文繁はいつも帰りが遅い。
―仕事だよ。付き合いだよ。男には必要だろ。―
結局彼は、なんだかんだといって、独身の頃と大して変わらない生活を送っている。
―変わったさ。お前達を食わせているじゃないか。―
食わせてもらっているんだ、私たちは・・・
確かに彼は自分が稼いできたお金の一部を私に渡す。ほんの一部。彼は豊かで、私は同じ家の中にいながら結婚するまでは感じたことのなかった貧しさと言う事を経験させられている。何だか、彼といると自分が能無しのブタのように思えてくる。どうして、あんな男を愛したの。今も愛しているの。
文繁は私を鎖で繋いだと思っているのだ。子供と言う鎖。
でも、女は産んだ子供を無条件で愛する生き物なのだと、男たちは勘違いをしている。その勘違いが、様々な悲劇を生んでいることもある。
その男を愛していなかったら、その男の子供も憎い。そんな気持ちを文繁は、たぶん理解できないに違いない。文繁ばかりではない。他の多くの男達や幸せな母達、または何事も理性が優先する利口な女達だって同じ事だ。
しとしと降る雨に閉じ込められた何かの塊みたいだ。黒く醜い塊だ。
「涼太。」と、私は呼びかける。
「パパねえ、今日も遅くなってお泊りだって。だから、夜ご飯はコンビニのお弁当にしよう。」
「うん、いいよ。僕、お弁当好きだし。」
そして、二人で雨の中を歩いてコンビニへ買い物に出かけた。文繁は、今日はマージャンの約束があると言っていた。帰りは遅くなるのでカプセルホテルに泊まるのだ。
―そんなものを買ったりしているから、やった金がなくなるんだ。俺は知らないよ。―傍にいない冷たい男の声が聞こえてくる。
やっぱり私は、何かに縛られているんだろうか。
少し行くと、いつものコンビニへの道の途中、ガードマンの初老の男が立っていた。
「今日はこの道、歩行者も通れないんです。すみませんが、回ってください。」
そう男は言って、涼太に小さく手を振った。
コンビニは目と鼻の先だったのに、めんどくさいなと思いながら、通ったことのない道を回った。この道は空き地だった所を切り開いて作ったところだ。たぶん調整地だったのだろう。そこの空き地は道以外は空き地のままだったり駐車場になっていたり、家庭菜園になっていたりしていた。
雨の中で他に人もいなかった。レインコートを涼太は着ていたので、私は手を離した。手から放たれた風船のように、涼太は小走りに意味もなく走った。小雨が涼太のレインコートを濡らしていく。畑のナスや空き地のハルジオンの花の上、ひっそりと一台だけ止まっている白い車の上に、雨は降り注いでいた。
私はそんな風景を見ながら、ぼんやり思っている。
―子供なんて殺すの簡単だなあ。道路をさっさと先に渡って、さあ、早くおいでって言えばいいんだから。
雨は降り注いでいく。私の心の中を冷やして、凍らせていく。
「ねえ、ママ。あのねえ。」と涼太が言った。
「なあに。」私は答える、凍りついた心とこわばった顔で。
「あのさ、あのね。」
「だから何。」
「僕の秘密、教えてあげようか。」
なんだ、くだらない。
「うん、教えて。ママ、知りたいな。」
私は優しい声で、だけどイライラしながら言った。
「あのね、ママ。僕ねえ・・・」
私は涼太が言いやすいようにしゃがんであげた。
すると涼太は嬉しそうに笑って、だけど決意したように私の肩を掴んでいった。
「ママ、僕は世界で一番ママが好きなんだ。ママのこと考えると僕、嬉しくなっちゃうの。」
その時重い雨雲が流されてきたのだろうか。急に雨粒が大きくなり、バラバラバラと音を立てて落ちてきた。
「濡れちゃうよ。」と言って、私はレインコートを着ている涼太に傘を差し出し、その肩を抱き寄せた。レインコートの水滴が私を濡らす。だけれども、冷たいコートの内側から伝わってくる、子供の熱い体温が、調べとなって、ゆっくりと私の中に流れ込んでくるのを、私は感じていた。






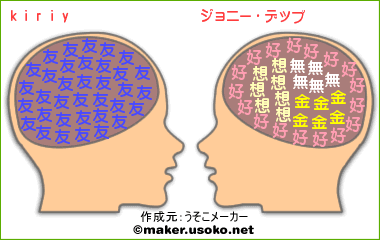


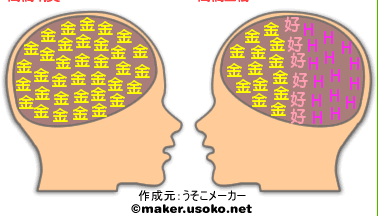















 「ねえ、ママ。あのねえ。」と涼太が言った。
「ねえ、ママ。あのねえ。」と涼太が言った。











