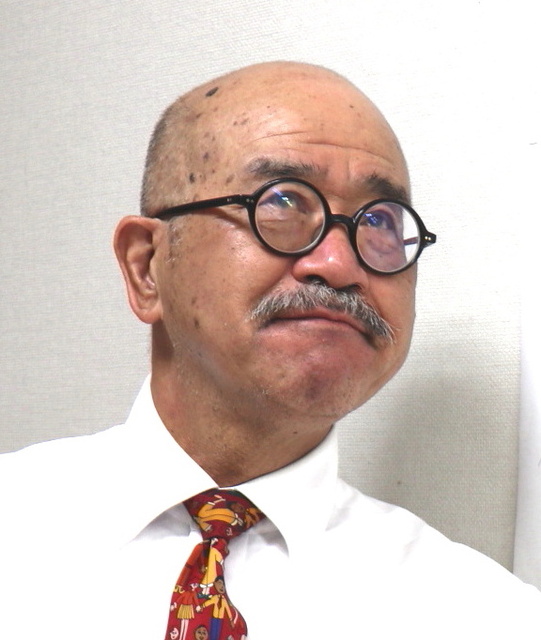憲法記念日。この日だけ盛り上がる議論。
戦後の世界で憲法改正の回数を調べてみると、
アメリカ6回、ドイツ58回、フランス27回、カナダ18回、イタリア15回。アジアでは中国9回、韓国9回。
憲法が「校歌のようなもの」だとすると、これは古い方がいいですね。甲子園でもチャラチャラした新しい校歌はカッコよくない。伝統校の風格ある校歌が響くと、歴史を感じてカッコイイ♪
これが「校則のようなもの」だとすると、ちょっと無理が出てきます。70年も前の校則で生活するのはなんぼなんでも難儀だろう。
日本人は「憲法は変えないが、適当に違反するけど、それはまあ仕方ないし」という「日本的な現場ナアナア対応」で、世界の変化をしのいできた。工学的に見ると劣化が進んでいて「賞味期限は切れている」という状態だと思いますよ。
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し」と高らかに宣言した時期には、中国も無かったし、北朝鮮も無かった。民族紛争や環境問題なども見えない時代で、世界はお花畑みたいに感じられていました。で、夢見る少女が詩を書いたような憲法が出てきたのです。現実は変わってしまって、世界はそんなお花畑じゃないことがわかっても「そんな現実、私は見たくない。絶対に認めません!」ということになってますよね。意地っ張りな少女。
70年前の自動車、家電製品、服などで、今も使えるものがありますかねえ。ま、伝統工芸館とか歴史資料館に陳列して「わーっ。これ、うちにもあったよなあ。懐かしいー」というのなら。
私、憲法記念日を記念して日本国憲法を読みましたが、昔の日記を読んでいるような甘い感傷や「うわっ。こんなこと書いてる。若かったなぁ」という気恥ずかしさを感じました。
宗教論争にしないで世界各国の憲法と比較しながら工学的、科学的に判断していくべきものだと思います。
具体的に
1、国会などの日数の規定が「30日以内」などと長い。当時は新幹線や飛行機がなかったからですね。
2、新聞、手紙とハガキ、無線電信などを予定しているから、電話(まだ家庭に普及してなかった)、テレビなどは想定外で、インターネットや携帯電話はもっと想定外。
3、公害や環境の問題は登場していなかったから規定が無い。プライバシーという考えも無かった。
4、日本国内に外国人が住むという発想が無かった。日本人が外国で暮らすというケースも想定外。
5、戦争に懲りたせいか、大規模災害など緊急事態の対応方法が何も決められてない。
被災地に食料を運んで提供しようとしたら食品衛生法違反でウンヌン、道路上で壊れた車両を除去したいが道路運送車両法の関係で車の持ち主を探して同意をえなければ、などという、何かの冗談かいなというケースが紹介されました。
今も熊本では地震が続いていて、こういう緊急事態の対処方法は決めておくべきだと思います。
憲法を作るときに、あの時はまあ大急ぎだったから「日本は災害の多い国だから」ということは考えなかったのでしょうけど、それなら今から追加しておかないといけません。
写真は彦根市役所。NHK大河ドラマ「真田丸」に乗って石田三成をPRしています。
その次は野洲川の河川敷を自転車で走ったときの風景。この鳥、何だかわかりますか。
近江鉄道でトコトコと行った多賀大社。名物の「多賀屋の糸斬り餅」を買いました。
そして、おうみ進学プラザの鯉のぼり。五月の琵琶湖の空を元気に泳ぎます。