細川綱利に対する家臣の諫言が幾たびかある。その中に「松井壱岐の諫言」があると人づてに聞いたことはあったが、その内容を知り得ないでいた。
ところが、「木下韡村日記」の天保十五年三月廿九日の項に「續兵家茶話日夏繁高撰」の引用として次のように記載されていた。
細川の長臣松井新助、其始光源院に奉仕し、其後細川幽齋ニ随身し、幽齋より長岡氏を授け、長岡佐渡主康之と改称セリ、
其男長岡佐渡興長ハ三斎カ妹聟となり、後年寛永九年申肥後封国の時、興長八代城代と爲て禄五万石を領地し、其男佐渡
寄之、其男佐渡直之、其男佐渡某、元禄十五年丁丑壱岐と名改、其男昨今之佐渡某也、世々細川家第一之長臣也、図書興顕と云、
何か不知 然るに右の壱岐之代ニ當て主人越中守綱利、行跡不宜沙汰有り、依之一封之諫書呈セリ
ここにある「右の壱岐之代ニ當て」が間違いであり、以下の諫言は松井興長によるものであり、間違えられて伝えられている。
韡村先生も間違いに気づかれぬまま記録に留められたのかもしれない。
尚、以下の文章は後に宝暦の改革を実行した大奉行・堀勝名が「秘書」として書き記し、残したものである。
年代の特定が出来ないが、綱利十六・七歳のころのものと思われる。彼の生活ぶりが良くわかるし、興長の主家の存亡を愁いた決死の諫言であることが理解できる。綱利の初入国を待つて、興長はなくなる。
一御當家者御先祖幽齋公、三斎公、忠利公、於所々戦功被励、尤武道専一御心懸有之候故、近代迄御家風相残、諸士武藝心
懸候處、當御代至諸家中武藝止、遊興長日送候、是皆 殿様武藝御嫌有而御遊興与宗被遊候故、諸家中学之風俗悪敷罷也
候事
一御代々忠勤励候侍者被捨置、當時任御出頭、御小姓之美麗成者共江ハ過分之高禄被下候事不可然候事
一忠勤之励候も無御加増、又新参ニ無功者江ハ高知被下候故、御代々之侍共不快存候事
一不相應之金銀被出、跳子被召抱、毎度之跳御見物不可然、別御慰も可有之事
一近年御出頭用人致出来候而、諸事渠等申上候事御承引被成候故、両人中悪敷者ハ讒、又懇意成者ハ不奉公仕候而も能樣ニ
取成申上候事
一此度御参勤之節、御側廻に美麗殊更御小姓道中之過美、御代々無之儀、不宜奉存候事
一近年之御物入、御代々無之儀御座候故、御勝手及困窮候事
一御遊興被長、公儀之御勤愚罷成候儀不可然事
一御奥之女中任御寵愛我侭申候、是皆 殿様女中之申次第被成候故、御威勢借我侭申候事
一公儀訴訟之儀、御出頭用人江贈賄送候得□□人非公事も利有之樣ニ申上、又不叶筋之訴訟も相叶候様ニ申上候事
一ヶ樣之品々 公儀へ相知候者、忠利公以来之御領国危ク奉存候事
右之條々御承引無御座候ハゝ、八代之城地并私知行指上、長御暇拝領可仕候、恐惶謹言
月日 長岡佐渡
右願之通相達、綱利江も至極過分之旨ニて、則出頭用人知行取上、両人共ニ遠流也 但名不知、其後又岩間主税、片山典膳甚
出頭、女人形仕隠居時、家老と成壱万石つゝ授之、而又料理人山本武左衛門悪人形仕甚出頭セしと也
以上、續兵家茶話日夏繁高撰










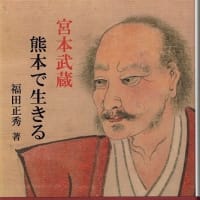














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます