「JAZZTOKYO」に、「ニューヨーク、冬の終わりのライヴ日記」を寄稿させていただきました。
トマ・フジワラ『Variable Bets』(Relative Pitch Records、2014年)を聴く。

Tomas Fujiwara (ds)
Ralph Alessi (tp)
Brandon Seabrook (g)
3人が3人とも相互に扇動したらどうなるかというプロセス。演奏空間は無重力となり、3つの遊星がお互いの周りをぐるぐると回り続ける。
扇動に向いているのはブランドン・シーブルックのギターか。この揺さぶりに対し、ラルフ・アレッシのトランペットは高音で絶えざる遊星群の駆動力として働く。フジワラのドラムスには、揺さぶりをかけるシンバルと、駆動力となる微分的で多彩なパルスがある。
●参照
アンドリュー・ドルーリー+ラブロック+クラウス+シーブルック@Arts for Art
アンドリュー・ドルーリー『Content Provider』(シーブルック参加)
クリス・ピッツィオコス@Shapeshifter Lab、Don Pedro(対バンでシーブルックのNeedle Driver)
『けーし風』第86号(2015.3、新沖縄フォーラム刊行会議)の読者会に参加した(2015/4/25、和泉橋区民館)。参加者は12人。
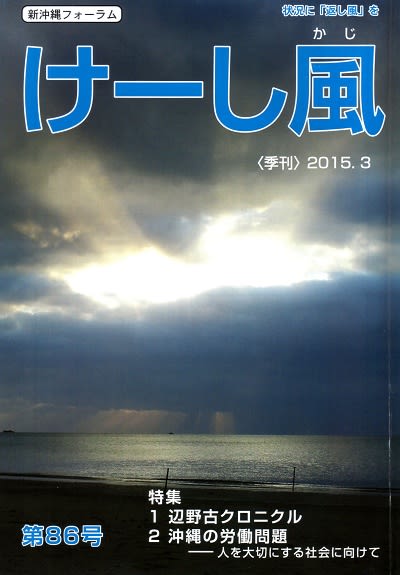
以下のような話題。
○名護市は稲嶺市政のもと基地の再編交付金を得ていない。それによる破綻は結果的に起きず、財政運営できている。(川瀬光義氏による指摘)
○同じように補助金で財政がまかなわれている自治体は多いが(基地、原子力)、その使途が限定されていること、ハコモノの運営コストが逆に財政を圧迫してしまうことなどから、総じて、自治体は豊かになっていない。
○「基地か経済か」という問題設定に大きな間違いがあるとの指摘(宮本憲一氏)は非常に重要である。
○辺野古の埋め立てに用いられる土砂の採掘が、小豆島、徳之島、佐多岬、天草・御所浦島、五島・椛島、防府、黒髪島、門司において行われている。このことがまだ大きな問題として認識されておらず、また、環境アセス法の対象となっていない。
○「本土」での沖縄基地問題に関する報道がなぜ不十分なのか。
○①ヤマトゥとの連帯(新崎盛暉氏がヤマトゥでの言説空間を重視)、②アメリカに訴えかけること、③アジアとの民衆的な連携を、それぞれどのように運動につなげていくのか。①は従来の方法であり、新たな策が求められているが、②への過度の依存には抵抗が大きい。③は抽象的・思想的なフェーズにある。
○辺野古に投じられる予算(3,000億円)がほとんど知られていない。
○辺野古基地に反対する辺野古基金に、2週間で約9,000億円が集まった。
○辺野古と往復する「島ぐるみバス」は、沖縄県庁前から毎日(!)出ている。初めて辺野古に行く人にとってはとても便利。
○沖縄の観光ブーム。ライカム(観光客もターゲット)がオープンし、USJ(ネオパーク沖縄と本部町)には名護市も賛成している。水や電気の負担はどうなるのか。そして、観光ブームはいずれ去っていく。
終わったあと、秋葉原唯一の沖縄料理店「今帰仁」で飲み食い。(飲みすぎた)

●話題に挙がった本・記事
宮本憲一+川瀬光義『沖縄論』(岩波書店)
『越境広場』創刊0号
『N27』(「時の眼ー沖縄」批評誌)
石川文洋『フォト・ストーリー 沖縄の70年』(岩波新書)
仲里効『眼は巡歴する』(未來社)
『沖縄文学選 日本のエッジからの問い』(勉誠出版)
後藤乾一『近代日本の<南進>と沖縄』(岩波現代選書)
平岡昭利『アホウドリを追った日本人 一攫千金の夢と南洋進出』(岩波新書)
木村草太『憲法の創造力』(NHK新書)
『ふぇみん』2015/4/15(特集 辺野古・高江は今)
西脇尚人「沖縄の新聞を読む/代表制の矛盾を突く」(沖縄タイムス 2015/4/8)
佐藤学「普天間基地問題 「事実」と沖縄の主張」(北海道新聞 2015/4/10)
高嶺剛『パラダイスビュー』(1985年)を観る。沖縄にも映画にも詳しいOさんが貸してくださった。
「復帰」前の沖縄。チルー(戸川純)は、想いを寄せるレイシュー(小林薫)のマブイ(魂)が落ち、犬に喰われる夢を見る。それはすなわち、神隠しのしらせであり、ろくなことにならない。一方、沖縄人以上に沖縄を愛するヤマトンチュー(細野晴臣)は、ナビーと結婚しようとしていた。周囲は、ヤマトンチューは異民族でもないし結婚を許してもよいだろうとする。しかし、そのナビーは「毛遊び」でレイシューと関係し、妊娠してしまう。やがてレイシューは、チルーの複雑な感情ゆえ警察に逮捕されるが、護送車が独立派に襲撃され、その間に逃走する。レイシューは破滅へと向かっていく。
高嶺剛の映画は、いまも昔も変わらず生暖かく、けだるい。観ているとドラッグが脳内に浸透してきて、覚醒して観ているのかどうかわからなくなってくる。やはり戸川純と小林薫を起用した『ウンタマギルー』(1989年)が傑作として名高いが、『パラダイスビュー』も魔力は同等以上だ。
すべて沖縄語を使い(日本語の字幕付き)、照屋林助、嘉手苅林昌、宮里榮弘といった沖縄芸能の達者たちを登場させているという点でも画期的な映画だと言うことができる。しかし、商業的に成功するのは、この手法を使い、より観る者に迎合した『ナビーの恋』などの二次利用作品なのだった、ということにふと気が付いてしまう。
●参照
高嶺剛『夢幻琉球・つるヘンリー』 けだるいクロスボーダー
沖縄・プリズム1872-2008(高嶺剛『オキナワン・ドリーム・ショー』)










