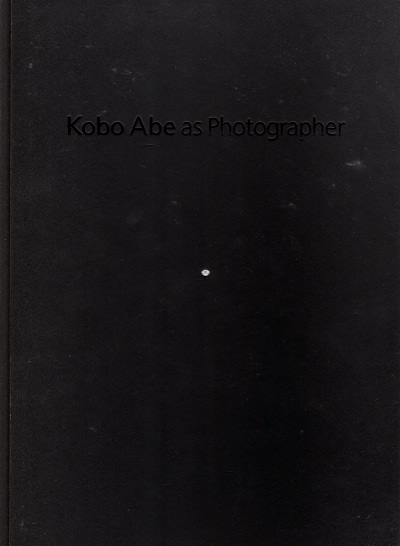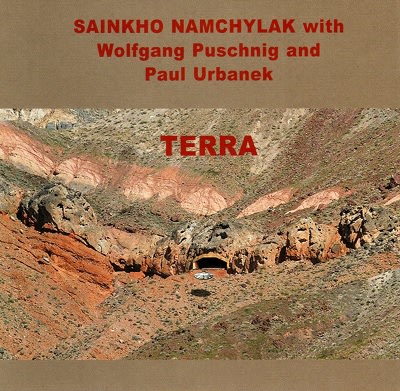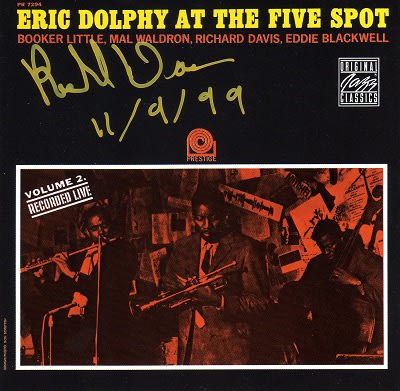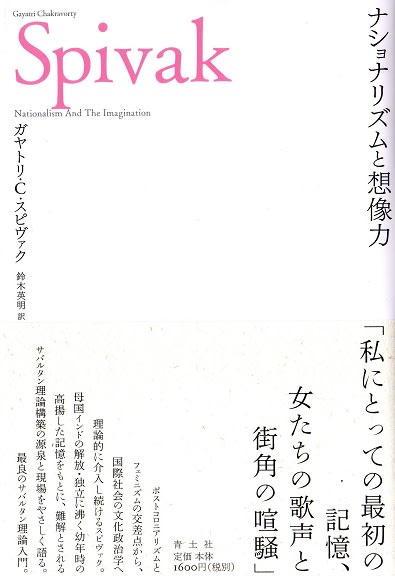澁澤龍彦『高丘親王航海記』(文春文庫、原著1987年)を読む。何をかなしんでか休日まで金融の勉強をしなければならないのだが、移動時間には好きなものを読んでよいことにする。そうすると妙に熱中して読みふけってしまう。現実逃避に他ならず、昔からの悪い癖である。

高丘親王は9世紀の人、桓武天皇の孫、平城天皇の子。入唐し、天竺行きを志すも東南アジアで消息不明になったという記録がある。この、碩学・澁澤龍彦唯一の長編小説は、高丘親王の不思議な旅をフィクションとして夢想している。夢想は本当に夢想であり、夢と現を行き来しながら、下半身が鳥の裸女、顔が犬にして局部に鈴をつけた男、とがった口からぺろぺろと長い舌を出す大蟻食い(結構なインテリ)、海から入道のように現れては話をするジュゴンなど、想像を絶する世界を見せつける。いや面白い面白い。
ジュゴンを「儒艮」と書く。全身薄桃色、肛門から虹色のシャボン玉のような糞が飛びだしてはふわふわと空中を漂い、ぱちんと割れて消える。海南島から東南アジアに向かう途中の海で現れたとき、船長が「このあたりの海にはよく見かけます。」と喋っている。かつては東南アジアでも、そして沖縄でも、ジュゴンを食べる習慣があったそうで、かなり良い味であったという(そのあたりは、辺見庸『もの食う人びと』に書かれている >> リンク)。本作ではジュゴン食に踏み込んではいないが、人間との距離が近かったことをイメージさせる描きようだ。
この小説が面白いのは、現代書かれたことをメタ小説として活かしていることだ(渋澤の博学ぶりを発揮させるにはそれがよかったのか)。例えば、大蟻食いが登場すると、高丘親王のお付きの男が食ってかかる。
「それなら、私もあえてアナクロニズムの非を犯す覚悟で申しあげますが、そもそも大蟻食いという生きものは、いまから約六百年後、コロンブスの船が行きついた新大陸とやらで初めて発見されるべき生きものです。そんな生きものが、どうして現在ここにいるのですか。いまここに存在していること自体が時間的にも空間的にも背理ではありませぬか。考えてもごらんなさい、みこ。」
大蟻食いは、それは人類本位の考え方だと反論する。何でも、地球の裏側、新大陸の大蟻食いと「足の裏にぴったり対応」して、さかさまに存在するのだ、と。滅茶苦茶だ。
ひょっとしたら、同じ日本SFとして、筒井康隆『万延元年のラグビー』(1971年)を意識していたのではないか、などと想像する。その中では、井伊大老の首を奪い合う場面で、水球についての登場人物の発言に対し、別の男に、「ウォーターポロは、まだ、ない」と反論させている。また、筒井康隆は何の作品でだったか、「イースター島の地球の反対側にはウエスター島という島があり、そこからはモアイ像の足が倒立している」というギャグを書いていた記憶がある。
高丘親王一行は、東南アジアを抜けて、いよいよ師子国(スリランカ)へと向かう。もちろんスリランカの7割を占めるシンハラ人の先祖が獅子であったということを意味している(国旗にもライオンが描かれている)。投錨する予定の港は東海岸のトリンコマリー。しかし、風のために東南アジアに押し戻され、スリランカに上陸することができない。高丘親王よ、私もトリンコマリーには辿りつけなかったぞ、などと呟きながら読み続ける。私がスリランカを旅したときは内戦が激しく、LTTE(タミル・イーラム解放のトラ)が占領しているために足を運ぶことができなかった街なのである。
●参照
○ヴィクトル・I・ストイキツァ『幻視絵画の詩学』、澁澤龍彦+巖谷國士『裸婦の中の裸婦』