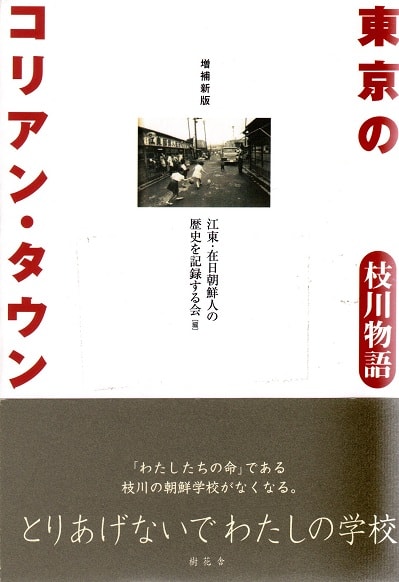『大江健三郎 大石又七 核をめぐる対話』(NHK・ETV特集、2011/7/3 >> リンク)を観る。
大石又七氏は漁船・第五福竜丸の乗組員であった1954年3月1日、マーシャル諸島のビキニ環礁近くで米国により秘密裡に行われた水爆「ブラボー」の実験に遭遇する。乗組員たちが浴びた放射線量は2000~3000ミリシーベルトと致死量の半分に達しており、既に乗組員23人中14人が亡くなっている(その多くが癌)。大江健三郎は大石氏より1歳年下、大学入学時に駒場の立て看で同世代の若者が被曝したことを知ったという。
1953年8月12日、ソ連の水爆実験が米国にショックを与える。
1953年12月8日、アイゼンハワー米大統領が国連で演説。核兵器のIEAによる平和的管理を謳う。
1954年3月1日、米国による秘密裡での水爆ブラボー実験、マーシャル諸島の住民と第五福竜丸が被曝。
1954年9月24日、乗組員最初の犠牲者(久保山氏)。同じ日、「読売新聞」は、原子力平和利用の記事を掲載。
米国の矛盾する行動は非難を浴び、日本では、1955年に「第一回原水爆禁止世界大会」(原水禁)が開かれている。冷戦下にあって、米国は日本の共産主義化を恐れた。国家安全保障委員会(NSC)の当時の報告書には、「核兵器に対する日本人の過剰な反応によって核実験の続行が困難になり、原子力平和利用計画にも支障をきたす」とあり、「日本に対する心理戦略計画」を検討すべきであると書かれていた。
そのとき、世論工作のパイプとして登場したのが正力松太郎(当時、読売新聞社主)であった。正力は財界に働きかけ、原子力平和利用のキャンペーンを打ち続けた(>> リンク)。当時の「読売新聞」には、「原子炉に危険なし―安くつく発電のコスト」、「野獣も飼ならせば家畜」という文字が躍っている。
1955年1月4日、日米合意文書に調印し、事件を政治決着、米国を免責。「問題ない」ゆえに乗組員を全員退院させる。
1955年4月28日、原子力平和利用懇談会発足。
1955年11月~、全国で「原子力平和利用博覧会」開催。正力や中曽根康弘の顔が見える。
1957年8月20日、東海村・原研の実験炉が臨界に達する。燃料は米国の濃縮ウランだった。
1965年、第9回原水禁世界大会。すべて反対すべきとする社会党(当時)と、社会主義国の核を擁護する日本共産党とが対立し、分裂に至る。
1967年、夢の島に放置されていた第五福竜丸が発見される。
1975年、米国のマーシャル諸島住民に対する影響調査の報告書。白血病は「放射能と関係があるかもしれないし、ないかもしれない」と記述。実際には、流産や異常出産、甲状腺障害が相次いでいた。
1986年、マーシャル諸島が米国より独立。平和ミュージアム設立。
大江健三郎は、ヒロシマナガサキからビキニを経てフクシマに至る歴史、それと並行するこのような欺瞞の歴史を述べ、「それは今も続いている」と目を見開いた。そして、責任を取るべき側が安全な場所に居り、逆にそれを追い詰めないという構造を「日本人のあいまいさ」であると表現する。しかしそれは早晩行き詰ってしまうものであり、なぜフクシマが起きたのか、みんながわかるようにつきつめて調査し、報道すべきだと言う。
大江は言う。「deter」という英語には、相手を暴力により脅かすという意味が込められている。しかし、「抑止力」という言葉には、まるで弱い者のための力であるかのような平和的なイメージが糊塗されているのだ、と。
続けて、録画しておいた、新藤兼人『第五福竜丸』(1959年)を観る。
映画は、1954年1月、第五福竜丸が焼津の漁港を出港する場面からはじまる。林光の明るい音楽、皆が笑顔で見送る。漁場に向かうまでの船上では、気の良い乗組員たちが口笛を吹き、軽口を叩き、時には喧嘩しながら、共同作業を行う。今見るとそらぞらしく、まるで社会主義のプロパガンダ映画である。デビュー間もない井川比佐志のベタな演技にも、場にそぐわない宇野重吉(最初に亡くなる久保山氏の役)の顔にも違和感を覚える。
水爆実験の場面は迫真性がある。白い光を全員が呆然と見つめ、西から太陽が昇った、いやピカドンじゃねえか、と騒ぐ乗組員たち。ほどなくして轟音が届き、真っ白い粉が降り注ぐ。彼らにはそれが何であるか判らないが、砕かれた珊瑚礁の「死の灰」であった。焼津に戻ったときには顔が真っ黒になっていた。そして被曝と判明するや東大附属病院と東京第一病院に入院する。
映画の出来は贔屓目に見ても良くない。最後には、久保山氏(宇野重吉)の死に際して、大臣や米大使代理のスピーチを入れ、追悼文、合掌、鳩と続く。もちろん歴史的な価値は大きい。
●参照
○『科学』と『現代思想』の原発特集 >> リンク
○黒木和雄『原子力戦争』 >> リンク
○『これでいいのか福島原発事故報道』 >> リンク
○有馬哲夫『原発・正力・CIA』 >> リンク
○原科幸彦『環境アセスメントとは何か』 >> リンク
○山口県の原発 >> リンク
○使用済み核燃料 >> リンク
○『核分裂過程』、六ヶ所村関連の講演(菊川慶子、鎌田慧、鎌仲ひとみ) >> リンク
○『原発ゴミは「負の遺産」―最終処分場のゆくえ3』 >> リンク
○東北・関東大地震 福島原子力の情報源 >> リンク
○東北・関東大地震 福島原子力の情報源(2) >> リンク
○石橋克彦『原発震災―破滅を避けるために』 >> リンク
○長島と祝島 >> リンク
○既視感のある暴力 山口県、上関町 >> リンク
○眼を向けると待ち構えている写真集 『中電さん、さようなら―山口県祝島 原発とたたかう島人の記録』 >> リンク