中辺路(なかへち)
大辺路(おおへち)
子辺路(こへち)
伊勢路(いせじ)
「ちゃんと歩ける熊野古道」では中辺路と伊勢路の2つしか取り上げられていなかった。
私が気になるのは子辺路。
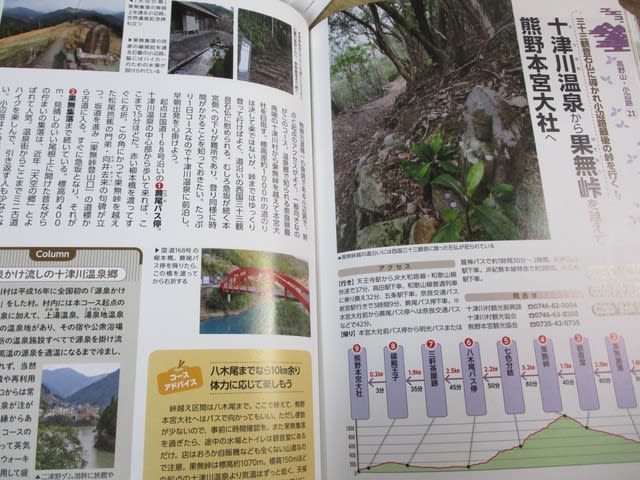
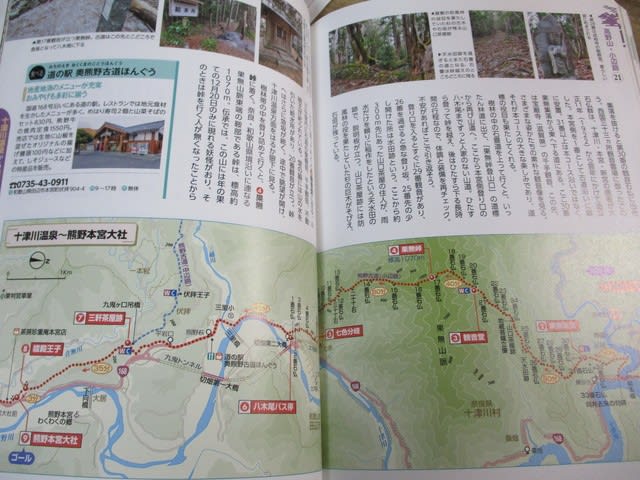

熊野本宮大社
熊野速玉神社
熊野那智大社
那智山青岸渡寺
補陀絡山寺)
大辺路(大辺路ルート全図)
紀伊路(紀伊路ルート全図)
高野山と小辺路(高野山・小辺路ルート全図
高野山・金剛峯寺)
伊勢路(伊勢路ルート全図
伊勢神宮)
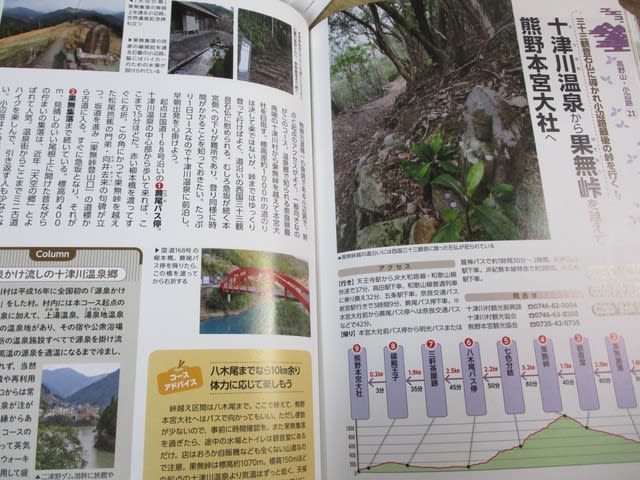
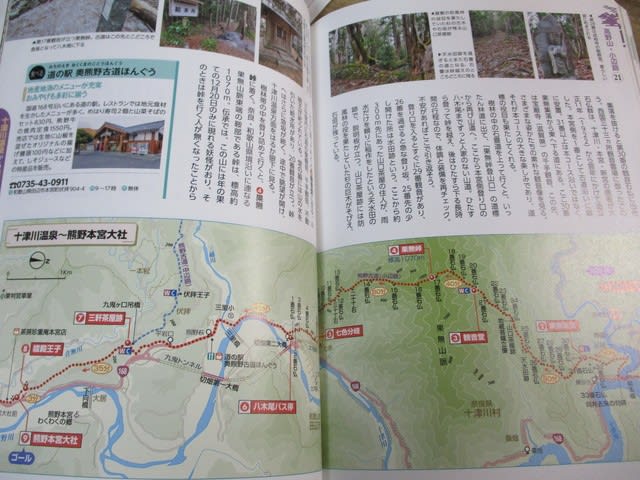





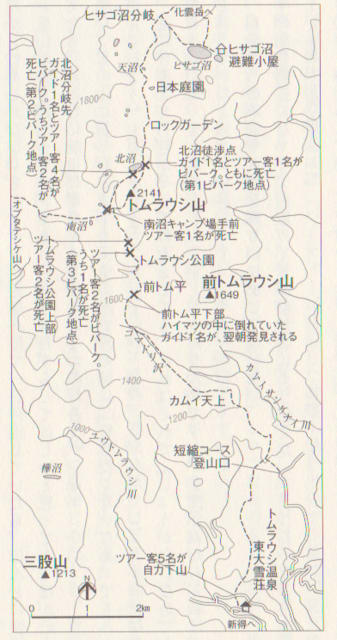
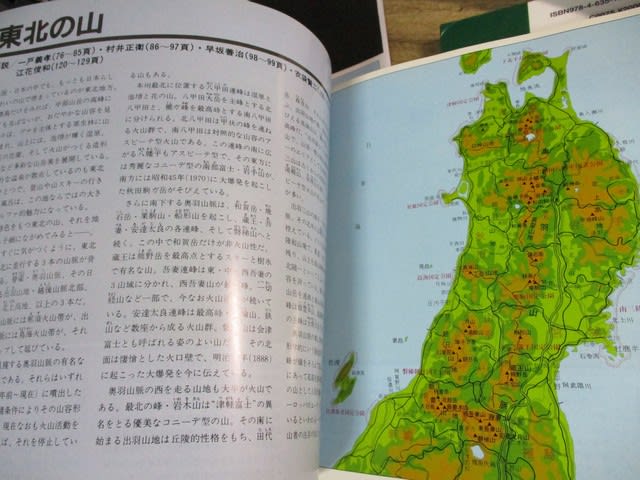


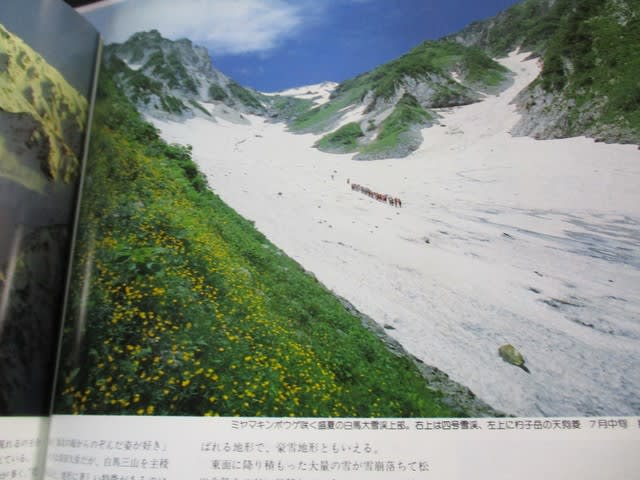

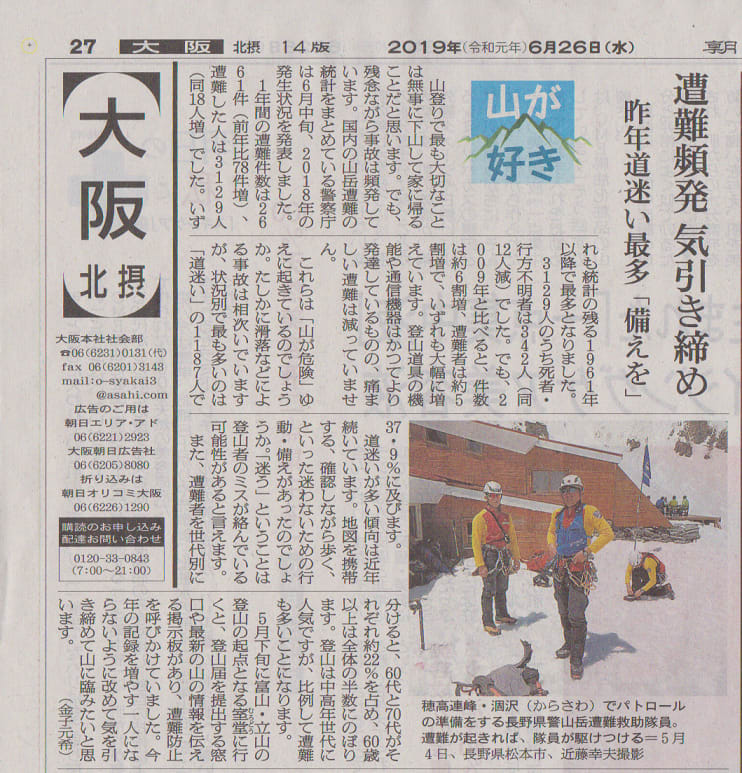

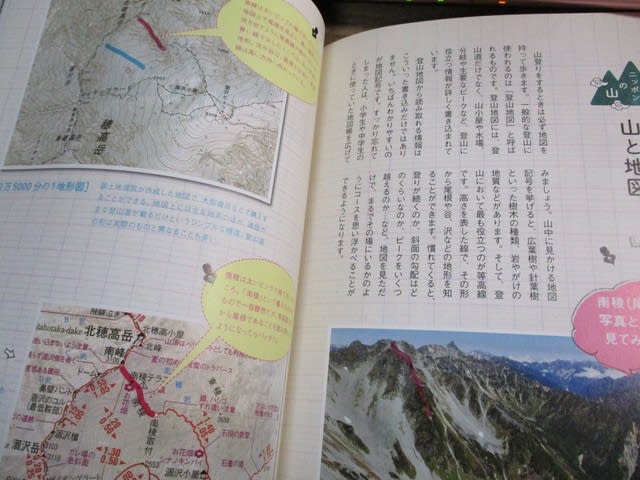

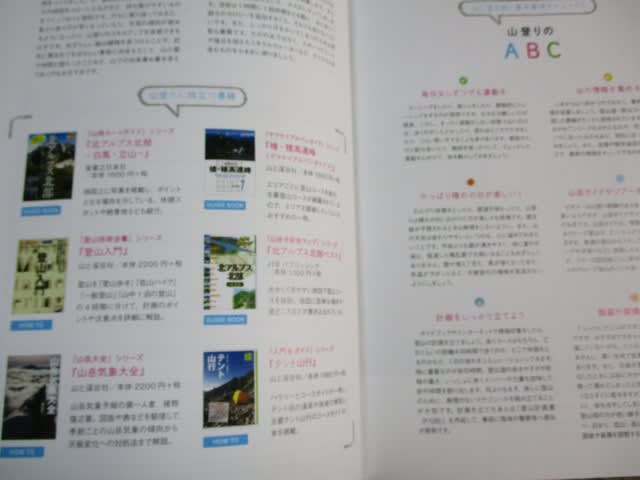




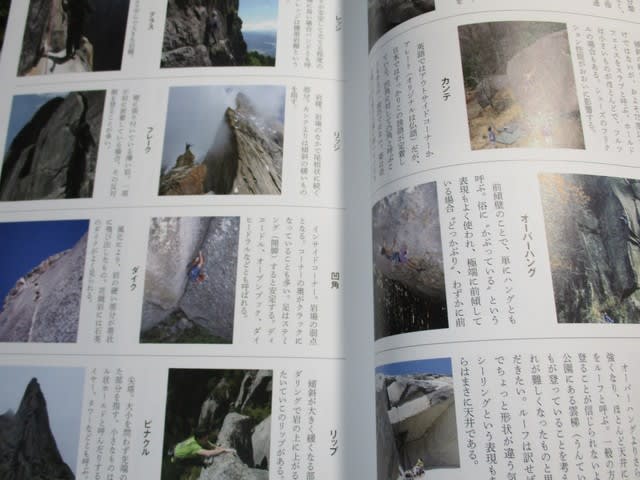
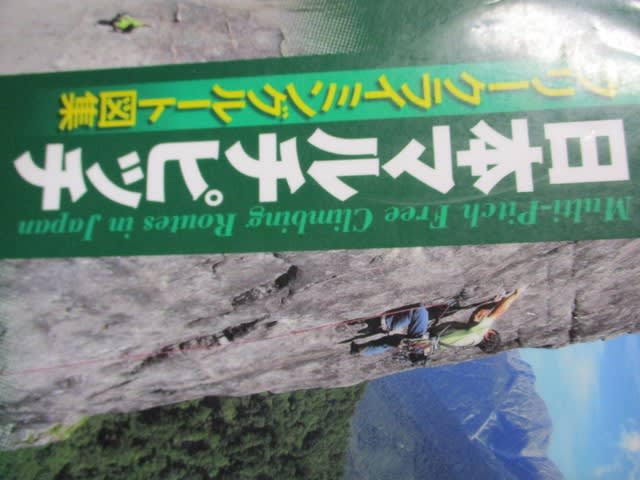
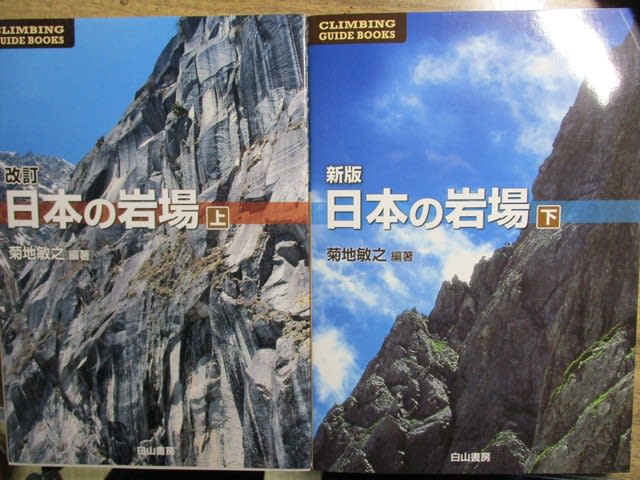
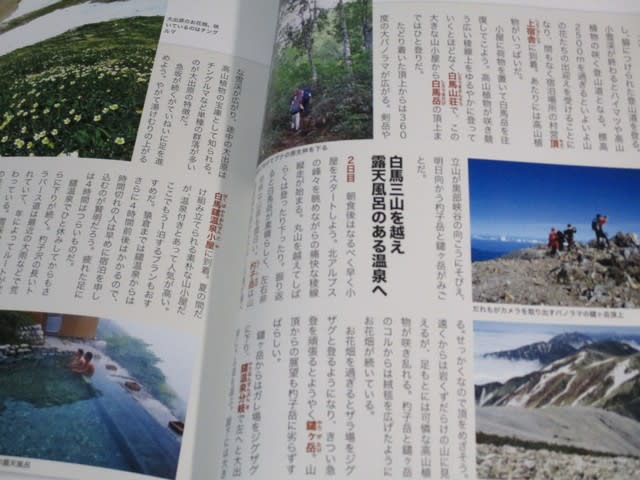


「最新アルパインクライミング」菊地敏之
右上するラインを登るとき、ゲートを左にする。
左上するラインを登るとき、ゲートを右にする。
どうしてか?
なんとなく感覚でセットしていたヌンチャク。
ウィップフラッシュ現象とは何か?
きちんと図解で説明してくれる。
読んでみて。
P53
メーカーによれば、固定されたナイロンロープの上を別のロープが数メートル流れただけで、固定された方のロープは一気に溶融点に達し切断するとのことだ。
P68
そのような所(前傾やハング)ではロープを急激に止めるとクライマーがロープに惹かれて壁に叩き付けられる可能性がある。
(中略)
「ロープを流す」という言葉が復活したものと思われる。
(中略)
しかしながらこの場合の「制動」は、昔のものとはそのやり方が決定的に違っている点に注意したい。それは要するに、ロープは「流す」のではなく「しっかり止め」、しかしビレイヤーが体を浮き上がらせる、あるいは軽く持っていかれることで衝撃を緩和する、というものだ。(言葉ではっきり説明されて納得。私はATCが普及する前=93年頃には意識的に行っていたと記憶する。周りもそうしていた、と思う。)
どんな時に破断が発生するか?
下図はゲートの向きにより、カラビナが横を向く場合がある、と。ハンガーに引っ掛かる場合もある、と。
下の図はウィップフラッシュ現象による破断。
ゲートの向きが重要…読んでみて。
下の図は、ワイヤーゲートの問題点について。
軽いカラビナはボルトハンガーに乗りやすい。
下の図は、各種ビレイディバイスの使い勝手について。
マルチをする場合、重要な問題。
【誤植】
P25
ハンス・フリーリン
↓
ハンス・フローリン
著者は校正の資格をお持ちと聞いている。
菊地敏之さんの作品で誤植があるのは珍しい。
【おまけ】
イラストを描かれているのが著者の奥さん。
昔、岩場に二人で来られているのを、お見かけしたことがある。
イラストレーターとは知らなかった。
【本書とまったく関係のない、おまけのおまけ】
関西の夫婦は、どうして岩場でケンカするのだろう?
関東のカップルが、大声で夫婦喧嘩をしているのを、見たことがない。
(その代わり、いきなり別れるらしい、と聞いたけど…一長一短か?)
本書とまったく関係ない話を書いて申し訳ない。
【ネット上の紹介】
大好評『最新クライミング技術』の続編&最新技術の決定版。クラック&ナチュラルプロテクション、ビッグウォール、アイスクライミングを軸に、新しいアルパインクライミングの技術と本質に迫る。
1 アルパインクライミング概説
2 ロープアクセス
3 クラッククライミング
4 ビッグウォールクライミング
5 冬期登攀
6 レスキュー技術
 立ち読みする
立ち読みする
「山岳装備大全」ホーボージュン/村石太郎/永易量行
装備を33カテゴリーに分けて詳細に解説している。
装備の種類や機能だけでなく歴史も書かれている。
気になるところだけ読んでもOKだし、ざっと目を通すだけでも参考になる。

紫外線…海抜ゼロ地点から1000m上がるごとに約10%も増えていくのだ。(白内障、ヒフ癌の原因となる)
【ネット上の紹介】
トレッキングブーツ、バックパック、オールウェザーシェルなど主要装備33カテゴリーを詳説。テント・冬季登山関連用具も対応。バッテリーなど小物18カテゴリーもコラム掲載。トップレベルの知識をもち定評ある最高の筆者による執筆。用具の特長と機能美を際だてるハイクオリティな写真。
トレッキングブーツ
フットベッド
トレイルランニングシューズ
小型パック
大型パック
ベースレイヤー
オールウェザーシェル
レインウェア
フリースウェア
ダウンウェア〔ほか〕
山と渓谷 2019年1月号
今ごろ1月号を買ってどーするの?って言われそう。
別添小冊子の「山の便利帳 2019」が欲しかったから。
交通機関、山小屋情報が詰まっている。
独りで行動するので、車より電車が多くなる。
今は行けないけど、遠出をしたら、特にそうなる。
その場合に備えての情報収集が必要。
【関連事項】
今日、宝剣の滑落事故について会話をしたが、次の4点が重要と感じた。
①体力(全ての基本)
②技術(体力の上に築く建築物のようなもの)
③装備(つねに更新する必要あり)
④自然条件(自然には逆らえない)
以上4点にプラス⑤を追加するなら『情報収集』でしょう。
こちらも、つねに更新する必要あり。
クライミングのショート・ルートは、2-3分のルートが多い。
それでも、緩急をつけて登るので、力が抜ける時がある。
慣れた人ほど、核心に備えて、身体が力を抜こうとする。
山の場合、数時間の間、ずっと緊張しっぱなし、ってのはないし、無理と思う。
気の抜ける時がある。
いかに危険箇所を見抜き、集中力を持続するかが重要。
体力・技術・装備を総動員して対処する必要がある。
…結果論になってしまうけど。
亡くなられた方のご冥福をお祈りします。
【リンク】
中アで滑落、3人死亡1人重傷 登山道に凍結箇所多く
【ネット上の紹介】
[特集]
●登山の現在形
平成から未来の山を語ろう
◇第1部 登山者たちの現在形
・丹沢塔ノ岳で聞いた登山者たちの“今”
・本誌アンケートから見る読者の現在形
・これからの山を語ろう 花谷泰広×望月将悟
・豊かな「山時間」の過ごし方
◇第2部 テーマで見る平成日本登山史
・インターネットの普及
・女性の活躍
・自然の脅威
・多様化する登山
・集団から個人へ
◇第3部 現在の山、これからの山
・平成登山用具史とこれから
・山岳遭難を減らすために
・山小屋の役割を考える
・環境問題の行方
・増える外国人登山者
・山のビジネス最前線
◆お正月に登りたい山
・[ルポ]東京都/日の出山~御岳山/大阪府・金剛山
・[コースガイド] 47都道府県「お正月に登りたい山」ガイド
・[コラム]2019年は亥年!登ってみたい干支の山