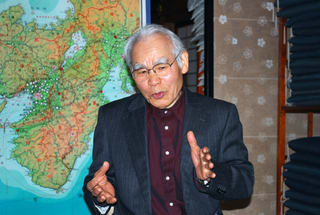5/16(土)、上北山村に向かう途中、川上村(奈良県吉野郡)のあたりでお昼になる予定だった。村内に良い食べ物屋さんがないか、川上村に詳しい藤丸正明さん(ふじまる・ただあき 株式会社地域活性局代表)にお聞きすると「大滝の山里というそば屋さんが美味しいです」と教えていただいたので、訪ねてみた。
大滝地区は、吉野町方面から入ると、村の入り口(北端)にある。「そば処 山里(そばどころ・やまざと)」は169号線の沿道にあるので、とても分かりやすい。柿の葉寿司で有名な「大滝茶屋」も近い(南方向に行く)。

店先に「おすすめ 天ざるそば 1300円」とあったので、これを注文した。店内には「当店のそば粉は信州産の石臼挽で手打ちの二八(にはち)そばです。冷たいそばがお勧めです」とある。そばは十割より二八(そば粉8割)くらいがちょうど良いと最近思い始めていたので、これは具合がいい。
トップ写真が天ざるそばだ。エビのほか野菜の天ぷらがついていた。大きな葉っぱはオカノリ(陸海苔)で、「健康レシピの食材辞典」によると《アオイ科で「冬葵(ふゆあおい)」の変種といわれます。葉を乾燥させて火であぶると、海苔に煮た食べ物になることから名付けられたとか。ゆでると少しだけぬめりが出ます。おひたしとか胡麻あえにぴったり。意外にくせもアクもないので、いきなり炒めても大丈夫です。葉は、カルシウムやビタミン類が豊富に含まれています》。
http://syokuzai.ochamehaha.com/2006/09/post_63.html

小さな芽は、アシタバ(明日葉)の若芽だ。Wikipediaによると《セリ科シシウド属の植物。日本原産で、房総半島から紀伊半島と伊豆諸島の太平洋岸に自生する》《和名の由来は「夕べに葉を摘んでも明日には芽が出る」という、強靭で発育が速いことから来ているというが、さすがにそこまでの生命力があるわけでもない》《伊豆大島では、アシタバを椿油で揚げた天ぷらが名物料理になっている》《便秘防止や利尿・強壮作用があるとされ、緑黄色野菜としてミネラルやビタミンも豊富なことから、近年健康食品として人気が高まっている》。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%82%BF%E3%83%90

二八そばは、そばの香りものどごしも良い。店内は民芸調にこざっぱりとまとめられている。いただいた名刺には《100%手打ちにて、提供しています。たまに売り切れあります。お電話いただければ残しておきます》とあった。

他のメニューは、冷たいそばでは、ざるそば(700円)、山かけそば(900円)、上三味そば(天ぷら、とろろ、合鴨 1800円)。温かいそばは、梅若そば(梅、大葉、ワカメ 800円)、カレーそば(900円)、天ぷらそば(1100円)。ミニ丼は、親子丼(350円)、他人丼(400円)。他にうどんメニューもある。
メニューは豊富だし、ミニ丼が選べるのも有り難い。川上村探訪の際は、ぜひお立ち寄りいただきたい。
※吉野郡川上村大滝872 ℡0746-53-2248[中西靖雄・釉子(つやこ)さん]
月・火休 営業時間 11:00~14:00
大滝地区は、吉野町方面から入ると、村の入り口(北端)にある。「そば処 山里(そばどころ・やまざと)」は169号線の沿道にあるので、とても分かりやすい。柿の葉寿司で有名な「大滝茶屋」も近い(南方向に行く)。

店先に「おすすめ 天ざるそば 1300円」とあったので、これを注文した。店内には「当店のそば粉は信州産の石臼挽で手打ちの二八(にはち)そばです。冷たいそばがお勧めです」とある。そばは十割より二八(そば粉8割)くらいがちょうど良いと最近思い始めていたので、これは具合がいい。
トップ写真が天ざるそばだ。エビのほか野菜の天ぷらがついていた。大きな葉っぱはオカノリ(陸海苔)で、「健康レシピの食材辞典」によると《アオイ科で「冬葵(ふゆあおい)」の変種といわれます。葉を乾燥させて火であぶると、海苔に煮た食べ物になることから名付けられたとか。ゆでると少しだけぬめりが出ます。おひたしとか胡麻あえにぴったり。意外にくせもアクもないので、いきなり炒めても大丈夫です。葉は、カルシウムやビタミン類が豊富に含まれています》。
http://syokuzai.ochamehaha.com/2006/09/post_63.html

小さな芽は、アシタバ(明日葉)の若芽だ。Wikipediaによると《セリ科シシウド属の植物。日本原産で、房総半島から紀伊半島と伊豆諸島の太平洋岸に自生する》《和名の由来は「夕べに葉を摘んでも明日には芽が出る」という、強靭で発育が速いことから来ているというが、さすがにそこまでの生命力があるわけでもない》《伊豆大島では、アシタバを椿油で揚げた天ぷらが名物料理になっている》《便秘防止や利尿・強壮作用があるとされ、緑黄色野菜としてミネラルやビタミンも豊富なことから、近年健康食品として人気が高まっている》。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%82%BF%E3%83%90

二八そばは、そばの香りものどごしも良い。店内は民芸調にこざっぱりとまとめられている。いただいた名刺には《100%手打ちにて、提供しています。たまに売り切れあります。お電話いただければ残しておきます》とあった。

他のメニューは、冷たいそばでは、ざるそば(700円)、山かけそば(900円)、上三味そば(天ぷら、とろろ、合鴨 1800円)。温かいそばは、梅若そば(梅、大葉、ワカメ 800円)、カレーそば(900円)、天ぷらそば(1100円)。ミニ丼は、親子丼(350円)、他人丼(400円)。他にうどんメニューもある。
メニューは豊富だし、ミニ丼が選べるのも有り難い。川上村探訪の際は、ぜひお立ち寄りいただきたい。
※吉野郡川上村大滝872 ℡0746-53-2248[中西靖雄・釉子(つやこ)さん]
月・火休 営業時間 11:00~14:00