
▲ 梯子型の火の見櫓 日本大正村(岐阜県恵那市明智町)にて
▲ 櫓型の火の見櫓 松本市内にて
▲ 飛騨高山 山桜神社の火の見櫓
「火の見櫓」は2本柱の梯子型(1本柱のものも含める)と3本、4本柱の櫓型とに大別される。
火の見櫓と聞いて思い浮かべるのは後者、櫓型のものが多いのではないかと思う。櫓型の火の見櫓は屋根と見張り台、そして櫓という構成要素から成る。これらの構成要素にはいくつかの造形要素があるから、組み合わせはかなりの数になる。実際、櫓型の火の見櫓は千差万別の造形を生んでいる。
火の見櫓の起源は江戸時代の前期にあるということだが、現在では消火ホースを乾燥させたり、防災用無線(サイレンやスピーカー)設置のための塔としてかろうじて生きながらえているものが多い。その一方、役目を終え、取り壊されてしまったものも少なくない。
単一機能であるのにもかかわらず、多様なデザインが見られる火の見櫓は景観構成上の要素であり、地域のコミュニティーの象徴でもある。建築が景観上好ましくないデザインであったり、地域のシンボルとは成り得ない存在であったりするのとは対照的だ。両者の違いは一体何に起因するのだろう・・・。
たかが火の見櫓、されど火の見櫓。この頃、火の見櫓に学ぶことは多いと感じている。
最新の画像[もっと見る]
-
 「老人と海」を読む
2時間前
「老人と海」を読む
2時間前
-
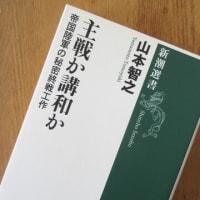 「主戦か講和か」を読む
1日前
「主戦か講和か」を読む
1日前
-
 ダイヤリーとブログを補完的に使ってきた
1日前
ダイヤリーとブログを補完的に使ってきた
1日前
-
 ダイヤリーとブログを補完的に使ってきた
1日前
ダイヤリーとブログを補完的に使ってきた
1日前
-
 ダイヤリーとブログを補完的に使ってきた
1日前
ダイヤリーとブログを補完的に使ってきた
1日前
-
 8月末を期限に、機をみて別のブログに引っ越します。
2日前
8月末を期限に、機をみて別のブログに引っ越します。
2日前
-
 Y字路の▽敷地
2日前
Y字路の▽敷地
2日前
-
 Y字路の▽敷地
2日前
Y字路の▽敷地
2日前
-
 誰そ彼
3日前
誰そ彼
3日前
-
 ウォーキング再開
5日前
ウォーキング再開
5日前










隣の集落とは少しデザインを変えて欲しい
というような要望をしていたのかもしれません。
火の見櫓は健全な集落の象徴のような気がしています。
拙ブログを紹介していただきありがとうございました。
安曇野の山々は雪衣を着始めました。
地域のコミュニティーの象徴でもあるのですね。
まさに たかが火の見櫓、されど火の見櫓。
先日は、勝手ながら
透明タペストリーを紹介させていただき
ありがとうございました m(_ _)m
U1さんに喜んでいただけたようで光栄です☆