■ 信濃毎日新聞6月25日付朝刊の総合面(2面)に「読書1ヵ月で「0冊」33% 全国世論調査 必要性は9割が認識」という見出しの記事が載っていた。日本世論調査会が実施した面接調査で分かったそうだ。全国250地点から18歳以上の男女3000人を選び、6月10・11両日、旅行などで会えなかった人を除き、1727人に調査対象者が直接面接して得た結果だという。
記事には1ヵ月間に読む本の冊数が0~2冊の人が約83%、1ヵ月間の本の購入金額は0円が33%、千円未満が31% という調査結果が示されている。
記事には**本を読めば論理的思考やコミュニケーション能力が鍛えられるし、それなりの見識を持てるようになる**(後略)と、作家・石田衣良さんのコメントが載っている。私はこのような効用を期待して読んでいるわけではない。本を読むことが好きというか、楽しいという単純な理由から。だが、以前と比べて読書量はかなり減った。別に読書は義務でも何でもないから、読みたい本を読みたいときに読むまでだ。
6月の読了本3冊
『敗者の想像力』加藤典洋/集英社新書
日本人は敗戦ときちんと向き合ってこなかった、敗戦を正面から受け止めて思想化してこなかったという認識に立った新たな戦後論。
論考の中で余談的に書かれている「なぜゴジラはいつも日本にやってくるのか」は、なるほど! だった。ゴジラは第二次世界大戦で死んだ兵士たちの体現物として受け止められている。戦争の死者たちは国のために戦った。戦争に負けた後、方向転換した日本に彼らが帰る場所がない。**東京に上陸し、復興なった夜の都市を蹂躙するゴジラの咆哮は、「自分がそのために死んだ国は、どこにいったのだ」、「祖国はどこにいった?」と、嘆いているようにも聞こえる。**(91頁)
『スマイル! 笑顔と出会った自転車地球一周 157ヵ国、155,502km』小口良平/河出書房新社
小口さんが旅の間、大事にしていた魔法の3つの言葉、「こんにちは」「ありがとう」「おいしい」。
食はその国の文化そのもの。「おいしい」はその国の文化を受け入れること。世界中の人びととの交流を通じて得たこの認識には説得力がある。すごい体験を「ドーダ!」とならずに淡々と綴っているところがすごい。ドーダの過去ログ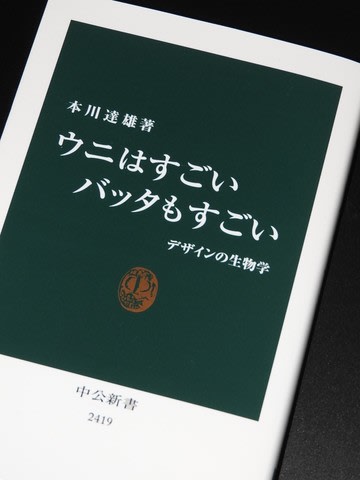
『ウニはすごい バッタもすごい』本川達雄/中公新書
意味のある体のデザイン
生き延びるための戦略
生き物たちの驚きの世界
本川氏の著書『生物学的文明論』新潮新書、『生物多様性』中公新書 を読みたい。明日注文しよう。


















