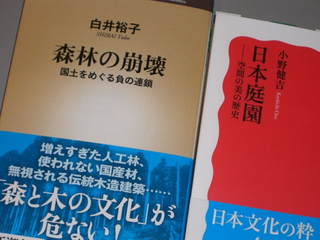■ 前稿に引き続き「繰り返しの美学 昔の記録」撮影1991年8月。
長野市立博物館。長野の宮本忠長さんの設計、日本建築学会賞を受賞している。コールテン鋼で葺いたおおらかな屋根、コンクリート打ち放しの外壁、列柱。
確か内井昭蔵さんもやった出目地付きのコンクリート打ち放しの円柱が並んでいる。これだけきれいにコンクリートを打設するのは難しい。柱と壁との取り合い部分は型枠を組むのも大変だっただろう。
繰り返しの美学の対象を平面的なものにまで広げたが、やはり基本は直線的な繰り返し、それも建築構成要素の繰り返しだ。等間隔に全く同じ要素を並べるというシンプルなルールに拠っている。誰にでも分かり易い可視化された秩序。
やはり時々基本に戻らないと。