
864 小川村小根山 撮影日170815
■ 火の見櫓の手前に消火ホース乾燥塔が立っている。切妻屋根の小屋は消防器具置場。火の見櫓は少し傾いている。
構面の1面が梯子になった簡易な3角形の櫓。

864 小川村小根山 撮影日170815
■ 火の見櫓の手前に消火ホース乾燥塔が立っている。切妻屋根の小屋は消防器具置場。火の見櫓は少し傾いている。
構面の1面が梯子になった簡易な3角形の櫓。

(再)小川村高府の火の見櫓 手前は高府公民館 撮影日170815
■ 12日の信濃毎日新聞朝刊に長野県内各地に残る「戦争遺跡」を紹介する記事が掲載された。松代大本営地下壕や信濃町にある称名寺(しょうみょうじ)の石の鐘(鐘を供出させられ、代わりに石を吊り下げた)など10ヶ所の遺跡が紹介されていたが、その中に小川村の「弾痕が残る鉄塔」があった。
記事はこの鉄塔について次のような紹介をしている。長野市にあった長野飛行場で管制塔として使われていて、1945(昭和20年)8月に空襲に遭い、階段の手すり子(記事では手すりの柵と表現している)などに銃弾が貫通した跡が2ヶ所ある。戦後、小川村に移築され、今は火の見櫓として使用されている。
戦後72年、戦争当時のことを記憶している人は減少する一方だ。この火の見櫓のような戦争の痕跡・記録を継承していく責務があると思う。現在この火の見櫓の階段の登り口に扉が設置されていて関係者以外登ることができない旨、表示してあるが、年に一度、例えば長野空襲の日・8月13日に登ることができるようにしたらどうだろうか。
この火の見櫓を2015年7月に見ているが(過去ログ)、終戦記念日の今日、8月15日にまた見てきた。 ①
① ②
②
記事で紹介されていた弾痕が確認できた。この痕跡は戦争の身近な「証言者」だ。
*****
改めてこの火の見櫓を観察する。 ③
③
①の写真とは逆の方向から見た全形 太目の3角櫓、広い床面の上に6角形の屋根が載る。
櫓のブレースと階段の内側の側桁を兼用した合理的な構成。
管制塔の広い床をそのまま火の見櫓の見張り台の床として使っているのであろう。床面から上部は移築した際、追加設置したのではないか。
床外周の下地材に付けたガセットプレートに屋根を支える柱の下端をリベット接合で取り付けている。
銘板には昭和二十七年竣工とある。終戦の年から7年後にこの場所に移築したことが分かる。
昭和20年8月13日の空襲で47人が犠牲になったとされている。

■ 『八月六日上々天氣』長野まゆみ/河出文庫を読み終えた。物語は昭和16年暮れの東京に始まり、昭和20年8月6日の広島で終わる。
東京の女学校に通う15歳の珠紀と彼女を慕う4歳年下の従弟・史郎。物語では互いの心模様の変化の軌跡が記される。史郎は珠紀に淡い恋ごころを抱き、珠紀も史郎が気になる存在に。淡々と流れる日常は次第に戦争の色彩を帯びてくる。
やがて珠紀は史郎の担任だった教師・市岡と結婚。市岡は軍に志願し、珠紀は市岡の郷里の広島へ移り住む。そして史郎も海軍兵学校を受験するために広島へ。そして物語はあの日に向かって進む、そして運命のその時・・・。
**八時過ぎごろ、台所のガラス戸がやけに振動するので、珠紀は庭へ飛びだした。
「小母さん、今、地震があったのじゃないかしら、」
「東京とちがうけん、ここいらじゃ、やたらと地震なんてありゃせんよ。」
「そうよねえ、」**(139頁)
長野さんはこのようにその時を間接的にさらっと描くにとどめている。この日の朝、汽車で広島駅へ友人に会いに出かけた史郎は・・・。
突然断ち切られた静かな日常が逆に効果的で、広島に投下された原爆で多くの人たちが命を奪われたことが鮮明に浮かび上がる。
印象に残る作品だった。
偶々8月6日に長野まゆみさんの講演を聴き、その時に買い求めた『八月六日上々天氣』。作品とのこのような出合いに何か縁を感じる。
*****
昔読んだ井伏鱒二の『黒い雨』には原爆が投下された広島の惨状が紙幅を割いて具体的に描写されてはいなかったか。

■ 塩尻市市民交流センター・えんぱーくで行われた長野まゆみさんの講演を聴いてきた。「作家生活30年を振り返って」と題した講演だったが、後半は聴講者の質問に応えるというかたちで進められた。
どうやら長野さんは女性に人気の作家のようで、聴講者の大半が女性だった。質問したのも全員が女性で、質問の前のコメントから察するに、デビュー作の「少年アリス」を読んで以来のファンという人が多かったようだ。
講演終了後は例によってサイン会。会場の入り口に平積みされた本の中から『八月六日上々天氣』河出文庫を買い求め、サインをお願いした。
本のカバーの裏面の作品紹介文に**少女たちの目から原爆を描き話題となった名作。**とある。今まで読んだことのない作家だからどんな作品なのか見当もつかないが、なんでも読んでやれ精神で、とにかく読んでみることにする。
**屋号の蝶を染め抜いた万蝶ののれんは、柳橋の火の見やぐらを過ぎてすぐのところにひるがえる。**(16頁) 読み始めたら火の見やぐらが出てきた。
「Sさん」
「あ、こんにちは」
「またここで会ったね。ここにはよく来るの」
「時々」
「そう。スタバでコーヒーでも飲もう」
*****
「Sさん、突然だけど満月って聞いて何を連想する?」
「え、満月っていうと、うさぎ、かな」
「やっぱりそうだよね、うさぎだよね。Kさんに訊いたらだんごって言ってたけどね。でもさ、何でうさぎかな」
「ちいさい頃、聞いてました、月でうさぎがお餅ついてるんだって」
「もしそのことを聞いていなかったら、満月見たってうさぎだって連想できないと思うけどね。ワニやカニに見えるとか、本を読む女の人とか、あと何だっけ、編物をする女の人とかさ、国によって違うんだよね」
「ええ、先入観なしで見たら、何に見えるのかな、うさぎには見えないかもしれませんね」
「よく、心霊写真とかいってテレビでやるけど、あれだってここが目でここが口でとかって説明されなかったら、わからないのが大半だでしょ。そういう説明をされて初めて見えてくるんだよね」
「そうですね・・・」
「だから小さい子どもにうさぎの話をしないで、満月の時何に見えるか訊いてみると、いろんな答えが出ると思うけどね。よくこのこの頃、個性を尊重した教育の実践とか聞くけどさ、月のうさぎみたいに初めに答えを教えちゃったら子どもたちの自由な発想が育たないと思うんだよね」
「なんです、今日は教育問題ですか」
「でもないけど。Sさん、覚えている?昔教室に日本地図って張ってあったでしょ」
「ええ」
「日本地図って北海道が上になるように張ってあるでしょ」
「そうですけど、それって決まってるんじゃないんですか? 北を上にするって」
「かも知れないけど・・・、でも上下逆に見ると、日本列島ってまるっきり印象が違うんだよね」
「でも九州が上になった地図なんて見たことないですけど・・・」
「そうだよね、でも先生がときどきそうしてくれたら、子どもたちの日本に対するイメージが変わるって思わない?」
「変わるかもしれませんね。でもそれが何か・・・」
「そうすれば子どもたちっていろんな発想すると思うけどな」
「官僚だか政治家だか知らないけど、九州を上にして日本地図を見てさ、日本のグランドデザインというか、例えば高速道路の計画をしたら、今と同じなったと思う?」
「そうか、ならなかったかもしれませんね」
「でしょ。だから大事だと思うよ、地図の張り方。それから、絵本に出てくるような地球の断面のイラストね。スイカの皮より厚く地殻を描いてあるイラストだけど、あれがいけないんだよね。すごく丈夫なイメージだから地震がいつ起こってもおかしくないなんて思わない。そんなんじゃ、防災意識なんて育たないよ。卵の殻みたいに薄くって、しかもゆで卵みたいにひびだらけってイメージできたら、もっとみんな地震に備えると思うけど。ちょっと飛躍してるか」
「そうか、初めの印象って大事なんですね・・・」
「こんなの極端な例かもしれないけど、案外こんなことって世の中に多いかもね」
「そうですね」
「それに世界地図も問題だよ」
「世界地図ですか・・・」
何とか図法、メルカトル図法? 名前忘れたけど、シベリアがやたら大きい世界地図」
「でも最初にあの地図を見たわけですから、実際の形とは大分違うなんてことは分からなかったです」
「あの地図を子どもたちが最初に目にするってどうなのかね、僕は地図より先に地球儀を見せるべきだと思うけど」
「ええ、確かにそうかもしれませんね」
「そうしないと正しい地球観っていうか、それが育たない。映画の「ET」ね、あの映画で子ども部屋に地球儀が置いてあったのを覚えている。宇宙を扱った映画だから演出かもしれないけど、印象に残っている」
以下省略
070719の記事 改稿
■「趣味はなんですか」と訊かれると困ってしまう。
特にこれといって趣味をもたない私は仕方なく「読書です」と答えることになるのだが、読書は趣味といえるのかどうか。それは食事をするのと同様に、人の基本的な営みではないのか。
小学生の頃どんな本を読んだのか、ほとんど思い出すことが出来ない。学校から帰るとカバンを放り出して外で友だちとビー玉などをして遊ぶ毎日だったから、本はあまり読まなかったのだろう。
それでもコナン・ドイルの「シャーロックホームズの冒険」やヴェルヌの「十五少年漂流記」や「地底旅行」「海底二万海里」などは今でも覚えている。
松本清張の「砂の器」を読んだのは確か中学2年生のときだった。こんなに面白い小説があるんだ、とその後清張作品に熱中するきっかけになった。「ゼロの焦点」「球形の荒野」などが印象に残っている。
学校の図書館で借りて読んだ「波」は山本有三の作品、暗い内容だったと思う。「罪と罰」は中学生の時読んだほとんど唯一の海外作品。この本は今でも自室の書棚にある。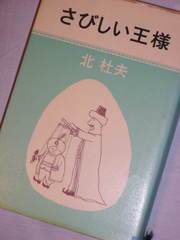
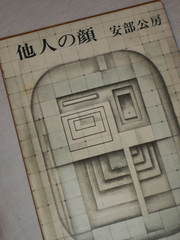
高校生の頃。大江健三郎、安部公房、三島由紀夫らは当時人気があったと記憶している。同級生は中学生の時、漱石や鴎外などを当然の如く読んでいた。日本の近代文学を読んでいなかった私は劣等感を抱いた。
「さびしい王様」を英語のK先生から借りて読んだことを覚えている。厳しい指導で有名だったK先生も、北杜夫のファンだったのかもしれない。読了後、同書を買い求めた。「他人の顔」の解説を大江健三郎が書いていることに気がついた。
もし安部公房が早世していなければノーベル賞を受賞したかもしれない。そうすれば大江健三郎の同賞受賞はなかったかも・・・。

学生の頃の思い出の本は倉田百三の「出家とその弟子」、福永武彦の「忘却の河」。
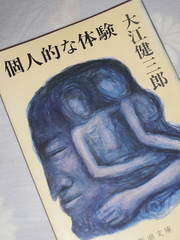
「木精 或る青年期と追憶の物語」北杜夫のこの小説に出会ったのは二十代の時。いままで繰り返し何回も読んだ。
ノーベル賞受賞を機に大江健三郎の初期の作品を読み返したのは三十代。当時子どもがまだ小さかったこともあって、「個人的な体験」には感銘を受けた。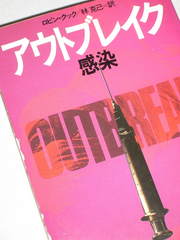
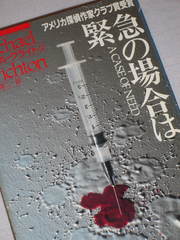
ロビン・クックの医療サスペンスや「ジュラシックパーク」のマイクル・クライトンの作品は四十代にほとんど読んだ。
村上龍、司馬遼太郎・・・。
立花隆は「超」勉強好き人間。氏の文章は論理的で読みやすい。「臨死体験」や「脳死再論」などを興味深く読んだ。
柳田邦男、・・・。
藤村の「夜明け前」を読んだのはそれ程前のことではない。加賀乙彦は日本の近代小説の白眉だとベタぼめだが、週刊誌に「お言葉ですが」を連載した高島敏男は、へたくそな小説であんなものを名作だと言う人の気がしれない、と手厳しい。小説の評価は人によって様々だ。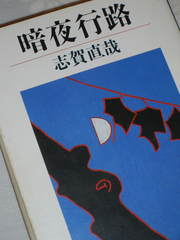

「痴人の愛」や「暗夜行路」、「黒い雨」などを読んだのも実は四十代。これらの作品はやはり高校生の頃読んでおくべきだった。いや「暗夜行路」はもっと若い頃一度読んでいるような気がする。

北杜夫が敬愛していたトーマス・マンの「魔の山」は、なんとも冗長で分厚い岩波文庫の上下巻を読了するのは大変だった。ちなみにこの長編小説を翻訳した望月市恵は北杜夫も尊敬していた松高の名物教師(私の記憶が確かなら)。
服部真澄の「龍の契り」「鷲の驕り」はサスペンス。この頃読んでいない。
藤沢周平「橋ものがたり」、吉村昭・・・。
最近は川上弘美。彼女の描くふわふわ、ゆるゆるな世界に魅了されている。もっとも「真鶴」で彼女の描く世界の雰囲気は変わったが。
小川洋子、南木佳士・・・。
そして今(07年)は村上春樹。暗喩を多用するこの作家は読み手に解釈を委ねる部分が多いような気がする。海外に多くの読者を得ているのもこの辺に理由があるのかもしれない・・・。この結論は早計かな。
これからは・・・
書棚に並ぶ本たちは私の来し方の想い出を留めている。
**人はなぜ追憶を語るのだろうか。どの民族にも神話があるように、どの個人にも心の神話があるものだ。
その神話は次第にうすれ、やがて時間の深みのなかに姿を失うように見える。
だが、あのおぼろげな昔に人の心にしのびこみ、そっと爪跡を残していった事柄を、人は知らず知らず、くる年もくる年も反芻しつづけるものらしい。**
「幽霊」北杜夫
070624 再掲
■ 7月に読んだ本は以下の4冊。
『シルクロードがむしゃら紀行 女ひとり一万キロ』大高美貴/新潮社
ビザ取得できず、宿確保できずのトラブル・トラベル。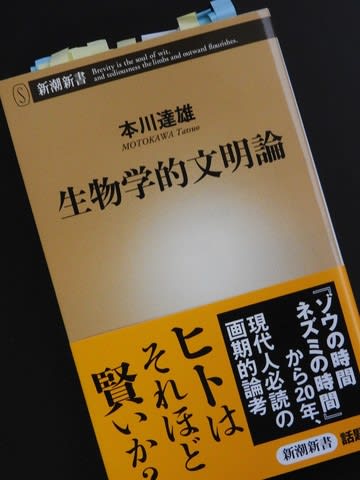
『生物学的文明論』本川達雄/新潮新書
生物学的発想で世の中眺めれば、違った生き方が見えてくる・・・。
『地図と鉄道』今尾恵介編著/洋泉社
地図と鉄道、まさに趣味中の趣味。
『「建築」で日本を変える』伊東豊雄/集英社新書
見えてきた近代主義的な建築の限界。伊東さんが見出した建築の新たな方向性。
**近代主義建築はどのような場所であれ地域であれ、建物の内と外をはっきり分けることによって人工的で均質な内部環境を目指してきたのに対し、これからの建築はその場所特有の空気や熱環境と繊細な関係を保つことによって、多様な内部環境をつくることが求められているのだと思うのです。**(64頁)
その具体的な事例として示された4つのプロジェクト。その1つが「信濃毎日新聞松本本社」。櫓の姿からイメージしたという(このことは知らなかった)社屋の外観スケッチなどが紹介されている。竣工予定は来年の4月と意外に早い。今から空間体験が楽しみ。