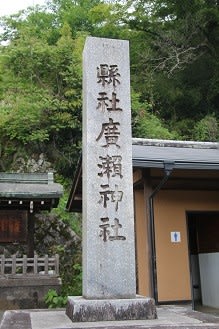(鴻巣台墓地)

海軍中佐贈正四位勲四等功三級廣瀬武夫墓
広瀬武夫の墓のある墓地も西南戦争でも激戦地となった。薩軍は墓石を倒してバリケードとして使用したといわれる。官軍は山林や民家に火を放ち、薩軍の抜刀攻撃に備えた。
広瀬武夫は、明治三十七年(1904)の日露戦争で、二回に渡り旅順港入口を封鎖するため、船を沈める作戦の陣頭指揮をとった。二回目のとき、閉塞作業を終えて帰ろうとすると、杉野兵曹長の姿が見えないので、沈みゆく船内を探しに引き返した。しかし、発見することができず、ボートに乗り移ろうとしたその瞬間、砲弾が体に命中し、武夫の姿は一片の肉を残して海中に消えた。三十五歳であった。
その直後から広瀬は軍神として崇められ、神格化されることになった。
同じ墓地に広瀬武夫夫人や父重武の墓や、広瀬一族の墓もある。

廣瀬重武墓
広瀬武夫の父重武の墓である。広瀬家の始祖は、肥後の菊地一族といわれる。父広瀬重武は、天保七年(1836)の生まれ。岡藩の下級武士であったが、廉直で義気に富んだといわれる。幕末には勤王の志士として活躍し、岡藩の小河一敏や中川栖山らと意気投合、藩の大義を伸ばそうとして常に機務に参画した。文久二年(1862)、島津久光の入京の際、藩論をまとめて上京し、そこで寺田屋事件に遭った。帰藩後、幽閉されたが、解禁後再び上京した。しかし、慶応元年(1865)、僧胤康事件により再度拘禁された。維新後は裁判官となり、飛騨高山や天草などに赴任した。晩年は竹田に戻って隠棲した。明治三十四年(1901)、年六十六で没した。硬骨の人で、同時に情義に厚いことでも有名だったといわれる。
(広瀬武夫生誕の地)
墓地と同じ茶屋の辻に広瀬武夫生誕の地がある。
広瀬武夫がこの地に生まれたのは、慶応四年(1868)五月二十七日。広瀬重武の二男である。広瀬家も明治十年(1877)の西南戦争で戦火に遭ったことから、父重武の赴任地である飛騨高山に移った。武夫は、小学校教師、攻玉社を経て、海軍兵学校に入学。卒業後、少尉候補生として遠洋航海を経験し、水雷術の訓練を受け、日清戦争では水雷艇に乗り込み、大連湾、旅順港口を掃海した。明治三十年(1897)にはロシア留学を命じられ、後に交戦国となるこの地で、四年八ヶ月を過ごし、厳冬のシベリア経由で帰国した。

陸軍中佐廣瀬武夫誕生之地
(番所跡)

番所跡
広瀬武夫誕生地から百メートル余り東へ行くと、水源池の横に番所跡を示す説明板が建てられている。この場所は、明治十年(1877)五月二十八日、薩摩軍は亀甲台の陳地から退却してこの番所より左手方向(胡麻生峠方面)、右手方面(上角口)に分かれた。政府軍はそれを追って、右手方向に突進して追撃したが、そこに左手方向に逃げた薩摩軍が戻り応戦した。夜間の斬りこみ戦のため、両軍の死者数夥しく、遺棄された薩軍の戦死者は、番所横に埋葬され小高い丘になった。これが千人塚で、地元では耳塚と呼んで、昭和初期まで供養が続けられていたという。
「日本の戦死塚」(室井康成著 角川ソフィア文庫)の巻末に掲載されている戦死塚リストにも千人塚が掲載されている。しかし、千人塚と思しき場所は、樹木が生い茂っており、特定するのは困難である。
(そうぞうの丘)
そうぞうの丘というのは、無料キャンプ場を備えた野外活動施設だそうである。その駐車場入り口付近に、中川栖山の屋敷跡や移築された小河家門などがある。

中川栖山屋敷跡
中川栖山(せいざん)は、文政八年(1825)の生まれ。諱は久煕。通称土佐。栖山は雅号である。豊後岡藩中川氏の支流で、世々家老職を務める家に生まれた。勤王家で、同藩士小河一敏、広瀬重武、田近長陽らと奔走。嘉永六年(1853)、米艦浦賀来航の折、日向木曽の慈眼寺胤康を招いて国事を議し、老職中川式部と謀り、内政を改革し、雄藩と協力して事を成そうとした。文久以来、九州の勤王浪士が集まり、文久二年(1862)には小河らを上京させ、島津久光を擁して事を挙げようとしたが失敗。文久三年(1863)四月、隠居禁固に処された。明治元年(1868)、九州鎮撫総督澤宜嘉に召されて長崎に赴き、天草五箇庄知事に任じられた。辞職後、長崎に岡物産会社を興し、煙草の輸出など殖産興業に努めた。明治四年(1871)、年四十七で没。

小河家入口
そうぞうの丘に入る坂道の途中に小河家を表す説明板が建てられている。
小河家は、第三代藩主中川久清(入山)のとき、広島より来藩し、以降代々中川候に仕え、家禄五百石を給されていた。小河一敏は、文化十年(1813)のこの地で生まれ、七歳で藩儒学者角田九華の門に入り、奇才を発揮し師を驚かせたといわれる。二十四歳の若さで藩の元占役(もとじめやく)に抜擢された俊才で、文武両道に優れていた。岡藩尊攘派を代表する一人となり、尊王攘夷論が沸き立つと上方に出て西郷吉之助や桂小五郎らの勤王の志士と交わった。維新後は、政府の重職や大阪堺県知事となり、土木事業を行い、農村の疲弊を救済した。一時、宮内省の長官に補されたが、堺での大工事の咎で罷免された。のち疑いが晴れて太政官に任じられた。七十八才で没。葬儀に際し、明治天皇から金三百円の功労金と正四位を賜った。
小河家屋敷入口の門は、藩主一族の第一家老中川栖山の屋敷(現そうぞうの丘)の門である。野殿屋敷に移されていたが、道路改修工事により取り壊されることを惜しみ、平成八年(1996)、子孫の小河一博氏がこの地に移して再建したものである。

小河家屋敷門

小河一敏生家
(洗竹窓跡)

洗竹窓跡

洗竹窓跡
洗竹窓(せんちくそう)は、竹田を中川藩が治めていた時代、約三百有余年前に作られた茶園で、江戸時代の豪商加島冨上の別荘の跡である。京都嵐山から持ち帰り移植したと伝えらえる樹齢およそ三百年の紅葉の老樹が亭々として枝を拡げ、秋景の紅一際艶やかな彩を添えた。田能村竹田が「東楓林山」と名付けたことでも知られる。
もとは風流人である淵野宗渕の臨川亭の跡で、寛政から天保年間に岡藩御用達、加島吉郎兵衛(冨上)によってさらに拓かれて別荘洗竹窓として生まれ変わった。台上の北壁の断崖には江戸千家茶道開祖の筆になる「雪積千山孤峰不白」の文字が刻まれ、その下に受け台が刻まれ、台上には置物式に彫刻された一匹の狛犬の座像があり、岸壁には三日月状に刻まれた灯明台があった。
文政元年(1818)には、田能村竹田や角田九華らが洗竹窓に集い国論を語り合い、鎖国制度を改める建議の方策を練ったとも伝えられる。この地で作詩された頼山陽、田能村竹田の作品も多く残されている。
洗竹窓は、西南戦争の際に焼失し、現在、吉郎兵衛が起居した別荘茶室は存在していない。辛うじて田楽焼きで宴が開かれたといわれる田楽石が残されているのみである。一面茫々たる雑草が茂り、見る影もない。
(胡麻生台)

胡麻生台
この周辺では、江戸時代付近の畑で胡麻を栽培していたことが知名の由来となっている。峠は竹田と入田、高千穂を結ぶ往還の途中にあり、人々が竹田を旅立つ際に竹田との別れを惜しむ「さよなら峠」ともいわれた。
やはり明治十年(1877)の西南戦争で激戦地となり、茶屋の辻を舞台とした戦闘では、休戦となったときにこの地に薩軍が集結したとされる。戦闘は尾根の戦いから稲葉川を渡り、古城で最後を迎えた。

胡麻生地蔵尊
茶屋の辻の胡麻生(ごもう)台、亀甲台、鴻巣台は、尾根と谷底が交互にあり、身を隠すには絶好の場所で、竹田にとっては防戦のための屏風の役割を果たしていた。

胡麻生地蔵尊
(田能村竹田の墓)

竹田先生墓(田能村竹田の墓)
胡麻生台から西側の谷に向かって古い墓地があり、その一番奥に田能村家の墓がある。
田能村竹田は、安永六年(1777)、藩医の家に生まれた。幼少の頃、英雄寺十世道寿和尚について漢学を、渡辺蓬山に画の手ほどきを受けた。その一生の大半を「墨絵と詩文」に費やし、豊後南画の祖と称される秀逸な画家で、多くの作品を残した。
五十五歳のとき、名画といわれる「暗香疎影図」を描いたが、どんな作品でも粗末に描くことはなかったとされる。画道を究める間に藩校の校長を務め、豊後国誌の編纂にも携わった。また藩主に政治の立て直しの建白書を出した。さらに九州各地から京都まで旅をして多くの文人と交友があり、中でも頼山陽とは無二の親友であった。
天保六年(1835)、大阪中之島の岡藩蔵屋敷で五十九歳の生涯を閉じた。大阪天王寺の浄春寺に葬られたが、弘化元年(1844)、長男の如仙が遺髪と歯牙を竹田に持ち帰り、胡麻生峠の墓地に埋葬した。墓石は浄春寺にあるものを模したものとなっている。