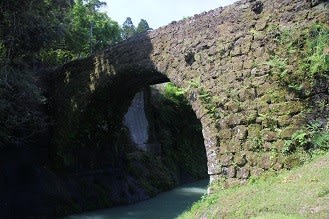(多磨霊園つづき)

光照院殿無量真實日文大居士(河鰭實文の墓)
河鰭實文は弘化二年(1845)の生まれ。父は内大臣三条実万。養父は世々神楽をもって奉仕する河鰭公述。万延元年(1860)二月、河鰭公述の養子となり、従五位下に叙され、文久三年(1863)、従五位上に進んだ。慶應四年(1868)二月九日、有栖川宮熾仁親王が東征大総督に任命されると、錦旗奉行を拝命し、同十五日親王に従って京都を発し、四月江戸城に入り、ついで大総督府参謀加勢に任じられ、七月帰京。八月、錦旗奉行を免じられ、明治二年(1869)正月、侍従に任じられ、六月戊辰の戦功により賞典禄百石を永世下賜された。明治三年(1870)三月、東京府出仕を命じられ、十月東京府権少参事となった。その後、内務省御用掛、内務権少書記官、元老院議官等を歴任し、貴族院議員に互選され、明治四十三年(1910)、死去の日特旨をもって従二位に昇叙された。年六十六。【21区1種10側】

藤田家之墓(藤田高之の墓)
藤田高之は弘化四年(1847)の生まれ。通称は次郎。藩校に学んで、文久三年(1863)、句読師になった。慶應三年(1867)、神機隊の参謀となり、慶応四年(1868)戊辰戦争では、初め備中地方の鎮撫に従い、のち江戸に出て、五月、大総督府から軍監として武蔵国埼玉郡忍に派遣され、さらに奥州各地を転戦した。明治七年(1874)、司法省に出仕して少丞に進んだ。のち立憲改進党の創立に関係した。大正十年(1921)、年七十五で没。【10区1種12側】

清渓山井先生之墓
山井清渓は弘化三年(1846)の生まれ。父は淀藩士内田成允。山井璞輔(介堂)の養子となった。安井息軒に入門し、伊予西条藩の藩校択善堂の学頭をつとめた。維新後は東京の養正塾などで教え、明治二十九年(1896)には一高の教授となった。明治四十年(1907)、年六十二にて没。【3区1種9側】

介堂山井先生墓
山井介堂(璞輔)は、文政五年(1822)の生まれ。松崎慊堂に朱子学を学び、足利学校にて古典籍を比較考証した。慊堂の推薦によって、長く断絶していた山井崑崙の家名を再興。伊予西条藩の藩校拓善堂の教授となった。文久二年(1862)、四十一歳にて没。【3区1種9側】

守田家累代之墓(守田勘弥の墓)
歴代守田勘弥の墓である。十二代守田勘弥は、弘化三年(1846)の生まれ。本名は寿作、俳名は是好と称した。文久三年(1863)、守田家の養子となり、勘次郎といった。元治元年(1864)、十二代を相続し、江戸三座の一つ守田座の座元になった。明治五年(1872)、劇場を従来の猿若町から率先して新富町に移し、ガス燈、椅子席の新設、「留場」「かっぱ」の廃止など、劇場制度の一新を断行した。明治八年(1875)十一月には劇場名を新富座と改め、団菊左をはじめ当代の人気俳優と河竹黙阿弥を作者に擁して、以後の五、六年間新富座時代と称される黄金時代を現出した。一方、政府の高官、学者、文人と交わり、俳優と演劇の地位向上に努めた。晩年は新富座の経営困難と多大な負債のため、明治三十年(1897)、不遇のうちに没した。年五十二。【1区1種6側】

専光院殿妙感久利大居士(仙石久利の墓)
ありがた山を調査した後、吉盛氏の要望に応えて多磨霊園に移動して、仙石久利・政固の墓を訪ねた。以下、吉盛氏の「但馬の殿様」より抜粋。
仙石久利は、文政三年(1820)の生まれ。父は五代出石藩主久道。文政七年(1824)、襲封。先代政美の急死で家督を継ぎ、先々代の久道が後見した。天保六年(1835)、いわゆる仙石騒動により仙石家は二万八千石を召し上げられ三万石に減封となり、久利は藩政を離れて学問に精進するように命じられた。減知後の出石藩では、依然として内紛が続き、久利は酒匂清兵衛を執政に任じ、藩士の削減を命じ、反対派は追放する強権を発動した。天保十四年(1843)、再び幕府の処分が検討されたが酒匂の切腹により回避した。以後、帰参した追放組の堀新九郎や桜井一太郎が藩政を主導し、海防負担の裏付けもあって嘉永三年(1853)、二千五百石余ではあるが旧領の一部復活に成功した。文久二年(1862)、藩政を私物化したとして堀新九郎に切腹を命じ、同年十二月、藩主直裁を宣言した。明治二年(1869)、藩知事。翌明治三年(1870)、致仕。出石鍛冶屋町の清水屋敷に居住したが、明治九年(1876)、上京。明治三十年(1897)、年七十八で没。
同じ墓域に仙石政固も葬られている。政固は天保十四年(1843)の生まれ。慶應元年(1865)、久利の養嗣子となり、明治二年(1869)には新政府に出仕して学校権判事となり、明治三年(1870)、承継して出石藩知事、明治四年(1871)、廃藩により免官。大正六年(1917)、七十五歳にて没。
仙石家の墓は、手入れがされていない様子で、雑草が腰の高さくらいまで伸びている。