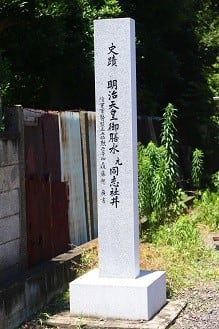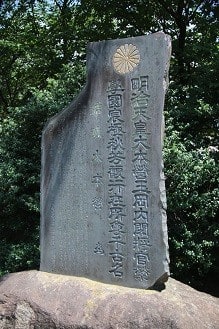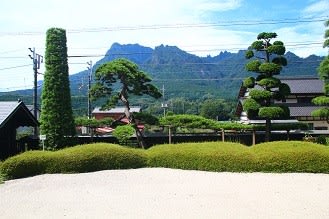著者片山杜秀氏というと、個人的には音楽評論家という印象が強いが、本人にしてみれば音楽評論は余技であって、本業は政治思想史を専攻する大学の教授ということなのかもしれない。本書は四百年という長い時間をかけて醸成されてきた水戸学を深く掘り下げたものであるが、話題は水戸黄門のテレビドラマや映画から、近松門左衛門の「国性爺合戦」、さらにはロルツィングの歌劇「ロシア皇帝と船大工」に至るまで、古今東西の歴史・文化・芸能・芸術まで幅広く言及しながら、水戸学を多面的・複層的に追究する。歴史の専門書とは一味違う面白い読み物となっている。
水戸学、あるいは尊王攘夷思想は、明治維新の原動力となっただけではなく、我が国の近代化に貢献したともいえるし、戦前の日本を支配した、亡国の思想といえるかもしれない。水戸学と聞いただけで、嫌悪感や拒絶反応を示す方も多いだろう。その思考がたどった経緯も特殊である。人によっては「馬鹿馬鹿しい」「あり得ない」「異常だ」と感じた瞬間、そこで思考を止めてしまいかねない。しかし、筆者片山氏は、決して距離を置かず、かといって過度に同調するわけでもなく、常に適度な距離を保ちながらこの異形の思想の真相を明らかにしていく。その一貫した姿勢には好感を持つことができた。
四百年にわたる水戸学の流れを最上流まで遡ると、テレビドラマや講談、映画でもお馴染みの「水戸黄門」こと徳川光圀まで行き着くことになる。それにしても徳川御三家の一つであり、副将軍として徳川幕府を支える水戸藩でどうして佐幕より尊王なのか。
その謎を解くには、まず光圀の出自を知らなくてはならない。光圀は水戸徳川家の家祖頼房の三男に生まれた。長男頼重をさしおいて、水戸家を継いだ。因みに頼重は讃岐高松の松平家当主として大名となった。兄を差し置いて弟が主となったという不義が生涯光圀を悩ませたというのである。
のちに光圀は義公と称されることになる。「義」とは「物事に道理が通っているか」ということである。その尺度で歴史をみれば、南朝こそ正義であり、正統であると断じることになる。楠木正成は忠を尽くした義士として崇拝の対象となる。
光圀は「大日本史」の編纂を藩の事業として起こそうとした(なお、「大日本史」という書名が決まったのは、光圀の次の藩主綱篠(つなえだ)のときであり、当時は「本朝通鑑」という呼称であった)。「大日本史」は単に我が国の歴史を叙述するではなく、「正」か「閏」かで洗い直した。この手の議論はどうしても空疎で観念論的になりがちである。戦前にも南北朝正閏問題では激しい議論が交わされたし、本書によれば、同じように光圀と林鵞峯(林羅山の子)との間でも「どちらが正でどちらが閏であるか」という議論が交わされたこともあったという。
今では南北朝の正閏など真剣に考えている人などいない。正閏問題など過去の論争だと思う人が圧倒的に多いだろう。しかし、現代でも薩長は悪で幕府こそが正義だと主張する人もいるし、会津史観と呼ばれる見方もある。イデオロギーで歴史を見ると、時に史実を歪めることになる。
尾張は六十二万石、紀伊は五十五万石。これに対し水戸藩は三十五万石。つまり他の二家と比べると半分程度に過ぎない。水戸藩領は肥沃ではない畑作地帯であり、漁業も良港に恵まれない過酷な条件であった。その上、「天下の副将軍」として江戸定府が原則とされ、石高以上の儀礼的・政治的出費を強いられた。江戸初期から一貫して水戸藩の財政は破綻寸前であった。何故、水戸だけがこのような目に遭わなくてはいけないのか。この不条理を忍んで受け入れるために尊王というイデオロギーが必要であった。佐幕を正義とする「絶対的根拠」として天皇が発見されたのである。
この水戸のイデオロギーに攘夷という思想が確立するのは、外国勢力が日本に押し寄せてくる十九世紀のことである。
文政七年(1824)、常陸国大津村沖にイギリスの大船が出現した。やがて乗組員が下船し、大津浜に上陸した。これを聞きつけ、藩から派遣されたのが、会沢正志斎と彰考館の飛田子健(逸民)であった。二人は英語を解さず、ほとんど筆談とジェスチャーでコミュニケーションをとろうとした。その結果、正志斎は彼らが捕鯨と偽って日本を植民地化する意図をもって近づいてきたと断定する。大津浜事件と呼ばれる。
この一報を聞いて藤田幽谷は直ちに息子東湖を大津浜に行かせ、異国人どもを全員斬るように命じた。父子がまさに別れの盃を交わしていたときに「薪水を乞う以外に他意はなし」として、異国人全員が解放されたとの報が届く。済んでのところで最初の攘夷は実行されないままとなった。
その頃、水戸沖には外国の捕鯨船が頻繁に出没するようになっていた。水戸の漁民は、捕鯨船に近づき、やがて異国船に乗せてもらい、飲食のもてなしまで受けた。異国船との交流を通じて漁民の中には片言の英語を使えるようになる者までいたという。攘夷思想などという厄介なものがなければ、これが人間の素直な姿なのかもしれない。私も大津浜事件のことは知っていたが、それ以前水戸の海で行われていた捕鯨船と漁民との交流の話は、本書で初めて知った。
文政十二年(1829)、斉昭が水戸の藩主の座につき、水戸学は新たな局面を迎える。斉昭は「三雑穀切返し法」を廃止し、倹約を徹底し、助川城や砲台を築いて海防を強化した。実学としての水戸学が実践されたのである。
水戸藩における天保の改革の評判を聞いて、全国から水戸詣でが始まった。長州の吉田松陰も水戸を目指した。水戸の尊王攘夷思想は、藩境を越えて全国に拡散したのである。
水戸学には将軍をとばして天皇と直接結びつくという理屈はない。天皇と将軍と副将軍の三者にねじれがないことが前提である。その前提が最初に崩れたのが井伊直弼の大老就任時であった。
この時、過激な尊王攘夷派は、天皇―将軍―副将軍のラインに捻じれを生じさせているのは、将軍と副将軍の間にあって、将軍権力を簒奪して居座っている井伊大老だとする。その結果、起こったのが桜田門外の変というわけである。
水戸学の矛盾が極まったのが、元治元年(1864)の天狗党の乱であった。本書では一章を割いて天狗党の乱を分析している。天狗党の争乱は、複数の党派が絡み合い、その経緯は複雑怪奇としか言いようがないが、筆者は水戸学を切り口に見事に腑分けして見せた。
孝明天皇は一貫して攘夷の実現を求めている。天意は明白である。ならば水戸藩は、幕府が一刻も早く攘夷を完遂できるように背中を押さねばならない。天皇と将軍の思想・行動が食い違ったら、迷いなく天皇を優先する、というのが水戸藩尊攘派左派の論理であり、蹶起した天狗党が依拠する正義である。
実は天狗党には藩外からも参加者が数多く参加していた。尊王攘夷を奉じるという点では天狗党と同じであったが、決定的に異なるのは水戸藩士のような「副将軍の家臣」という意識は全く持っていない。むしろ攘夷の実行のためには討幕も辞さないという危険思想を持った連中であった。そういう過激な討幕攘夷派が加っていたことが、天狗党の悲劇を生んだといえなくもない。
これに対し、水戸学右派の人たちは、尊王の志は保ちつつ、同時に幕府権力(将軍と副将軍)を守ろうとした。将軍の意向に関係なく天皇の意思に忠実にふるまうという水戸学左派とは相容れないが、尊王攘夷という思想面ではお互いに共感できるとところがある。藩主慶篤の命を受けて、天狗党と諸生党との仲裁に動いた宍戸藩主松平頼徳も右派に属していた。
水戸学を信奉する連中と対局にあるのが、諸生党と呼ばれる人たちである。彼らは、水戸藩が分不相応に軍事費を使いまくり、その結果藩財政を崩壊させた斉昭、そして斉昭を無条件に崇敬する天狗党には批判的である。彼らはせっかく握った政権を放さないという固い結束を誇っていた。諸生党は幕府と結ぶことで自らの正当性を担保し、説得に向かった頼徳に対して砲弾をもって応えた。一瞬にして頼徳軍は反幕府軍になってしまった。
エピローグでは三島由紀夫の切腹を取り上げる。三島由紀夫の先祖に幕臣永井尚志がいたことは広く知られている。三島由紀夫の曾祖父永井岩之丞(尚志の養嗣子)は宍戸藩主松平頼徳の妹の高姫を娶った。その娘永井なつが、三島の祖母である。三島は祖母に溺愛された。三島の切腹へのこだわりは、祖母の仕込みではないかというのが筆者の推論である。
確かに三島由紀夫の作品を読んでいると、切腹への執着、憧憬は異常なものがある。「奔馬」(「豊饒の海」第2部)では、「正に刀を腹に突き立てた瞬間、日輪は瞼の裏に赫奕と昇った。」と切腹を描く。あまりに切腹をかっこよく美化していないか。
確かに頼徳の最後は切腹であった。私の知る限り、幕末の大名で切腹した人は頼徳しかいないように思う。禁門を侵し朝敵とされた長州でさえ、三人の家老の切腹で済まされているのである。その一事をもっても頼徳の最期は異常である。
頼徳の切腹は、決して格好の良いものではなかった。江戸で慶篤に事態を説明する場を設けるという甘言にのった頼徳は、水戸に連行され、釈明の場も取り調べもなく沙汰を申し付けられた。周囲を諸生党の連中に取り囲まれ、介錯もなく長い間、頭を垂れて苦しんだというから、見世物のような扱いだったのであろう。全く屈辱的なものであった。
もし三島が祖母から曾祖叔父の最期を正確に聞かされていたなら、三島の切腹へのこだわりは違う形になったのではないかと思うのである。