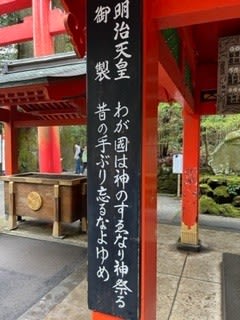ようやくコロナ感染も減少傾向となり、街も日常を取り戻しつつある。個人的には先日三年振りに海外出張に行けたし、二年振りに帰省して両親と会食することもできた。新橋駅前でも、数年振りに古本市が開催された。連日、古本市に通いつめ、三冊の古本を入手した。そのうちの一冊である。
本書は、今から十七年前の平成十七年(2005)に刊行された新書である。今では本屋の店頭で購入することは困難であるが、今なお価値のある一冊だと思う。
黒船を率いたペリーが日本を開国に導いたことは良く知られている。ペリー以前にも外国から使節が何度も日本を訪れたが、固く閉ざされた扉を開くことはできなかった。何故、ペリーがそれを成し遂げることができたのか。
日本の開国は、ペリーの綿密な準備と、その上に構築された戦術の成果といえる。彼は三万ドルもの大金を費やして、シーボルトの「ニッポンに関する記録集」(1832)を初めとして、日本について書かれた文書や書籍を収集した。
その結果、日本の歴史と鎖国政策の由来、天皇制と政府、行政組織、宗教、国際関係の歴史、産業、技術、科学、民族、産物、資源、文学、芸術といった、あるとあらゆる分野に精通するに至った。
彼の対日戦略は、決して場当たり的ではなく、極めて周到、冷静な分析の上に、練りに練られたものであった。
- できるだけ多くの隻数の艦隊を率いて日本人に恐怖心を起こさせる。
- さかんに測量作業を行い、砲門を開いて威嚇し、日本に混乱を生じさせる。
- ペリー自身は、幕府の閣僚級の者としか会わない。大統領の親書は、小役人などには渡さない。
- 米国の最高水準の文物や、科学技術の結晶である工業製品を持参。記録掛から料理人に至るまで人物を重視し、精神的な交流を持ち掛ける。
日本の開国という誰も成しえなかった成果を持ち帰ったペリーに対し、米国内で「砲艦外交」とする批判があったのも事実である。日本国内でもペリーの高圧的な姿勢に大きな反発があった。しかし、それまでの使節は友好的に日本にアプローチした結果、悉く日本から「追い払われた」。それを考えれば、ペリーのとった手法は唯一無二の方法だったのかもしれない。
海洋ジャーナリストという肩書を持つ筆者は、単にペリーの経歴を追うだけではなく、彼のゆかりの土地を自ら訪問し、しかも一般人ではなかなか進入できないような場所まで足を運んでいる。「あとがき」によれば、自ら操船する外洋帆走クルーザーで、ペリー艦隊が立ち寄った日本の七つの港と米国の四つの港をはじめ、艦隊と同じ錨地に停泊する体験を試みたという。筆者が訪れた港は、米国ではニューポート、ボストン、ニューベッドフォード、ニューロンドン、ニューヨーク、ワシントン、ボルチモア、ノーフォーク、アナポリス。日本では、那覇、泊(沖縄)、二見(小笠原)、下田、久里浜、浦賀、田浦(横須賀)、横浜、箱館。ほかにコロンボ、シンガポール、香港、マカオ、上海に及んでいる。私も那覇、小笠原、久里浜のペリー上陸の地碑を踏破した。なかなかこの三ヶ所を全て訪問した人はいないだろうし、このことは密かな自慢であるが、筆者のペリー愛はそれを遥かに上回っている。その偏執的ともいえる情熱には脱帽するしかない。
本書のルポルタージュでもっとも注目すべきは、ペリーの生誕地であるニューポートである。ニューポートでは、ペリーの生家、ペリーの兄、オリバーの像、ペリーの像のほか、ペリーが洗礼を受けたトリニティ教会、そしてペリーが改葬されたアイランド墓地などを見ることができる。いつかニューポートを旅してみたいという夢が膨らんだ。