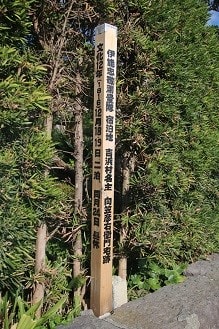著者は、外務省出身で駐ウズベキスタン大使や駐イラン大使、国際情報局長などを歴任した方で、外務省や外交に関する著作も多い。本書はアーネスト・サトウや英国の視点から幕末史を見直したものである。決して素人の描く歴史本ではなく、一つひとつ正確に歴史をとらえていることに感心する。
あまり知られていないが、桜田門外の変がたったの三分で決着したこととか、若き日の伊藤博文はテロリストであったこととか、薩英戦争や長州藩の四か国連合艦隊との戦闘を通じて薩長両藩が早々に攘夷を放棄したこととか、有名な西郷隆盛と勝海舟の会談により官軍による江戸総攻撃が中止されたのではなく、その前にイギリス公使パークスの圧力により中止が決定されていたこと等、やや意表を突いた指摘であるが、いずれも正確である。
――― 「論で負ければ刀で処理する」、幕末期の一つの特徴です。それは明治期、そしてそれ以降の長州出身の政治家にみられる一つの特徴です。
と、言い切っているが、これはどうだろう。元治元年(1864)、井上馨(維新前は聞多)が同藩士に襲撃された事件のほか、長州藩士が関与した暗殺事件といえば、文久二年(1862)の伊藤博文、山尾庸三による塙次郎暗殺、文久三年(1863)の朝陽丸事件、元治元年(1964)中山忠光の暗殺、明治二年(1869)大村益次郎の暗殺くらいしか思いつかない(もちろん精査すれば、ほかにもあるだろうが)。この時代、暗殺はどの藩でも横行していたし、時に幕府や新選組がその主体となったこともあった。長州だけが特別に暗殺が多いという事実はない。むしろ、件数でいえば、土佐藩が関与した事件の方が多いだろう。
また、自民党幹事長であった小沢一郎氏が海部首相を擁立した際に「神輿は軽くてパーが良い」と述べたという例をひき、
――― 日本社会には依然として、知的に優れた人物がトップになることを担保する制度はありません。
と断言しているが、政治や官僚の世界はいざ知らず、一般民間企業では「知的に優れた人物」がトップに立たないと悲劇である。私の知っている限り、民間企業のトップは知的に優れた人ばかりである。
一方、孝明天皇毒殺説とか坂本龍馬暗殺にも言及しているが、個人的にはこの部分は賛同しかねるところである。
――― アーネスト・サトウはこの微妙な時期に、幕府に武力行使を主張する薩摩藩の西郷隆盛、長州藩の伊藤博文、そして公武合体を模索する土佐藩の後藤象二郎、更には江戸で薩摩藩が不穏な動きを見せている中で薩摩藩の留守居・篠崎彦十郎と会ったり連絡をとったりしているのです。勿論幕府側とも接触しています。この時期、日本人でもこの広さで接触している人はいないのではないでしょうか。
と、アーネスト・サトウの交流範囲の広さ、幕末史に与えた影響力の大きさを指摘する。この点については、まったく異論がない。間違いなく、幕末史におけるキーマンの一人である。
あまり知られていないが、桜田門外の変がたったの三分で決着したこととか、若き日の伊藤博文はテロリストであったこととか、薩英戦争や長州藩の四か国連合艦隊との戦闘を通じて薩長両藩が早々に攘夷を放棄したこととか、有名な西郷隆盛と勝海舟の会談により官軍による江戸総攻撃が中止されたのではなく、その前にイギリス公使パークスの圧力により中止が決定されていたこと等、やや意表を突いた指摘であるが、いずれも正確である。
――― 「論で負ければ刀で処理する」、幕末期の一つの特徴です。それは明治期、そしてそれ以降の長州出身の政治家にみられる一つの特徴です。
と、言い切っているが、これはどうだろう。元治元年(1864)、井上馨(維新前は聞多)が同藩士に襲撃された事件のほか、長州藩士が関与した暗殺事件といえば、文久二年(1862)の伊藤博文、山尾庸三による塙次郎暗殺、文久三年(1863)の朝陽丸事件、元治元年(1964)中山忠光の暗殺、明治二年(1869)大村益次郎の暗殺くらいしか思いつかない(もちろん精査すれば、ほかにもあるだろうが)。この時代、暗殺はどの藩でも横行していたし、時に幕府や新選組がその主体となったこともあった。長州だけが特別に暗殺が多いという事実はない。むしろ、件数でいえば、土佐藩が関与した事件の方が多いだろう。
また、自民党幹事長であった小沢一郎氏が海部首相を擁立した際に「神輿は軽くてパーが良い」と述べたという例をひき、
――― 日本社会には依然として、知的に優れた人物がトップになることを担保する制度はありません。
と断言しているが、政治や官僚の世界はいざ知らず、一般民間企業では「知的に優れた人物」がトップに立たないと悲劇である。私の知っている限り、民間企業のトップは知的に優れた人ばかりである。
一方、孝明天皇毒殺説とか坂本龍馬暗殺にも言及しているが、個人的にはこの部分は賛同しかねるところである。
――― アーネスト・サトウはこの微妙な時期に、幕府に武力行使を主張する薩摩藩の西郷隆盛、長州藩の伊藤博文、そして公武合体を模索する土佐藩の後藤象二郎、更には江戸で薩摩藩が不穏な動きを見せている中で薩摩藩の留守居・篠崎彦十郎と会ったり連絡をとったりしているのです。勿論幕府側とも接触しています。この時期、日本人でもこの広さで接触している人はいないのではないでしょうか。
と、アーネスト・サトウの交流範囲の広さ、幕末史に与えた影響力の大きさを指摘する。この点については、まったく異論がない。間違いなく、幕末史におけるキーマンの一人である。