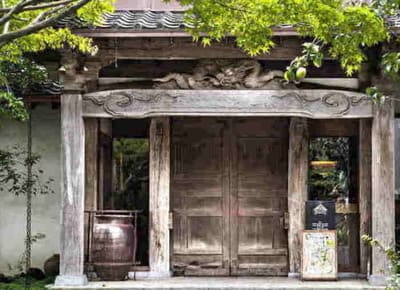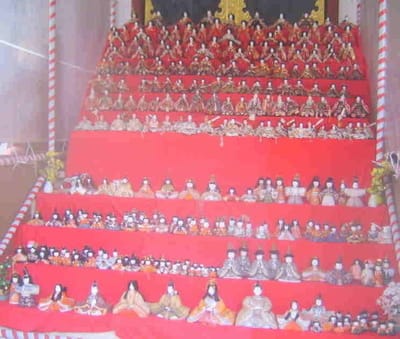旧士幌線は道央の士幌から大雪山国立公園の深い森林のに十勝三俣の結ばれ、石炭運送や森林開発を担っていた鉄道輸送路であったがトラック輸送に置き換わり役割を終え廃線になる。
その旧士幌線は基本的に国道273と平行して走っているが、途中の糖平(ぬかひろ)湖は北海道の鉄道の中でも最も海抜の高い位置にあり、その山岳、渓谷地帯を走る山岳路線であった。
この山岳路に25/1000の急勾配と急カーブの厳しい路線立地に沢山の橋を作る背景にあった。
同線を走っていた鉄道路線も次々と消えていく中でタウシュベツ川橋梁の遺構は特異な存在であり、一目見ておきたいと掻き立てらる北の大地、北海道の一つである。
◇四季の自然変化が幻想の世界を生み出す
北海道中央部糖平湖にかけられたコンクリートアーチ橋は旧国鉄土幌線にかけられた橋であり、かっては煙を吐き出し逞しく走った機関車の姿があった。糖平ダム建設のため湖底に消えた。

それが冬、山に降る雨が雪になり湖に流れ込む水量が減ると湖面の水位が下がり、橋が姿を現す。
秋には再び湖底に沈むので,こうして消えた鉄橋が再び姿を現す、世にも不思議な変幻自在の存在である。
橋長は130m、直径10mのアーチが11連続き、その姿はローマ宮殿の遺構にイメージにつながる。
このアーチ橋は鉄道廃線と共に解体の危機であったが、NPO法人の活動で残された。1月に入ると糖平湖が凍ると水位が一気に下がり橋桁が次々と姿を現す。
橋桁のコンクリートの表面は氷結した湖面が水位が下がる度にガリガリと削り落として行くために痛めが生まれてゆく。
厳しい冬を何度も乗り越えた重みが、橋梁に刻まれ、人工的に構築されたコンクリート表面が岩肌のように風化し、歯止めがかからないまま、何れはその姿が消えてゆく運命にあると言われている。
◇某年9月タウシュベツ川橋梁へ
前日は美瑛と富良野、更に幾寅駅の「鉄道員(ポッポ屋)」のロケ地など、何時来るともなく列車の姿もなく淋しい駅舎風情に浸り鉄っちゃんになりきってしまった。設置された粗末な木造駅舎が既にシミを帯び、永い間風化した姿がそっくりタイムカプセルして、往時の世界に浸ることが出来る。赤い郵便ポストも時代を象徴している。

駅舎に隣接するだるま食堂。閉じられた入口のガラス戸にはここを潜った暖が見える。鉄道利用客が駅前で一献を交わし、気炎を上げ、しばしの時を過ごす、絵になる世界をオープンセットが演出している。

秋の日は短く、国道38、274をひたすら走り、当日の宿泊先である、然別湖に投宿する。
翌日、ホテルを出発し、糠平湖方面に向かう。
道幅も狭く、連続カーブが続く九十九折りに久しぶりに山岳ドライブを味わう。
糠平湖はてっちゃん、てつこさんを喜ばす士幌線の廃線跡に残されたコンクリート製のアーチ橋がある。士幌線は国道273に併設されているが深い渓谷にあり、事前準備もなかったので、その姿を見つけ出すのに骨が折れた。
それでも3箇所の著名な橋と鉄道資料館を執念で探し出し、当日の大きな目標の一つは達成した。
◇上士幌町鉄道資料館
旧国鉄士幌線の廃線後残されたのが鉄道資料館である。

廃線跡に残された大小60余りのコンクリート橋梁群は「北海道遺産」に選ばれ、同線の残された備品類や当時の写真など資料が掲示され、当時の生生しい姿と再会することが出来る。士幌線を守ったネクタイに制服で身を固め制帽姿の駅員さんが、生き生きとした姿で出迎えらる。

一方資料館の外には廃線レール・枕木は機材を流用し国鉄で線路保守管理を担当したOBの指導で敷設した再現線路が敷かれていた。
大人も子供も本格的な枕木は専用軌道で自ら踏む人力でトロッコが風を切って、かって走った1930年代に立ち返り、士幌線の乗車体験ができる。

□いよいよ、タウシュベツ川橋梁へ
上然別町から273号線を糠平湖方面に目指す。樹林帯の中、果てしなく続く真っすぐの道の右側がタウシュベツ川橋梁である。何処まで続くのか、森に囲まれた花道、往復車線に全く車が見えず、この静寂の中、遭遇するのは動物位であろうか
 。
。
◇悪路も何のその
此処タウシュベツ川橋梁には国道273を右折し、林道に入って行く。
完備された舗装の国道から、一転して未舗装の物凄い荒れ地に車は上下に激しく揺すられながら糖平湖湖畔近くまで入ってゆく。

途中1車両が漸く渡れる狭い場所に隅っこに赤い標識があり、一歩間違えれば落車の危険もある。幸いに対向車もなかったが、お見合いがあれば、狭い道を後退して退避場所に移動することも必要である。
激しい揺れに緊張しまくりながら走り、林道の奥の駐車場になっている広場に漸く辿り着く
◇水没した悪路歩き
駐車場に車を置き、更に奥地へ入っていく。倒木がそのまま放置され、足元は完全に浸水している。
失敗すれば水中へ、僅かな足場を確かめながら、不安定な足場を一歩一歩湖畔に目指す。
木立が伐採された空間が、一応道になっているが、ご覧の通りの悪路になっている。
水辺際は自然が人の進出を妨げる難路、昼なお暗い鬱蒼とした木立の先の開けた湖畔を目指す。
かっては此処が専用軌道が走って、あのタウシュベツ川橋梁に繋がっていたのである。
◇感動のタウシュベツ橋梁対面
喘ぎながら深い森から糖平湖湖畔に出る。目の前にあのタウシュベツ橋梁が湖に浮かぶ姿に対面し、感動する。
大小の岩場を一歩一歩進めながら、橋元に近づき、既にコンクリートが砕け、陸地近くの橋梁はご覧の通りセメントが崩落、内部の補強用の鉄筋がむき出しに晒されていた。
橋梁を取り巻く四季の変化がこうして基礎部分が削られ、遂に支えるものも無く、徐々に崩落し大地に沈んでゆく。
その先の湖面に姿を現し、目の前にきらきら波打つ湖面に浮ぶ姿は実に感動的であった。足回りは悪い、秘境の世界に、現地に訪れる観光客も見受けられず、静寂の中、糖平湖に浮ぶ橋梁の姿は最高の芸術作品でもあった。
◇ドライブ・旅行記事
JAF会員向けの機関紙であるJAF Mateのドライブ・旅行記事が賑っている。
誌上での紹介記事の関心事は、その姿を背景に語られる記事に心揺さぶられ、是非とも直に見て、おいたいと車旅に駆り立てられる。
一方では、既に行った所もかっての旅先の思い出が改めて蘇る。
そんな場所が近隣では伺い知れない世界が北の大地、北海道に代表され、何度か北海道を周回した。数えればきりがないが、代表例の一つが以下のタウシュベツ川橋梁でもある。
そのJAF Mateとも離別した。こちらで紹介してますので是非ご覧ください
「JAF」の離別