 | 菜の花の沖〈4〉文藝春秋このアイテムの詳細を見る |
【一口紹介】
出版社/著者からの内容紹介
江戸後期、ロシアと日本の間で数奇な運命を辿った北海の快男児・高田屋嘉兵衛を描いた名作が、大きな活字の新装版で一挙大登場!
内容(「BOOK」データベースより)
エトロフ島は好漁場であったが、すさまじい潮流が行く手を妨げ、未開のままだった。しかし幕府は北辺の防備を固めるため、ここに航路を確立する必要を痛感して、この重要で困難な仕事を嘉兵衛に委ねた。彼の成功は、蝦夷人にも幕府にも大きな利益をもたらすであろう。が、すでにロシアがすぐとなりのウルップ島まで来ていた。
【読んだ理由】
「播磨灘物語」に続いての司馬遼太郎作品。
【印象に残った一行】
『女たちの風俗からいえば函館にはすでに独自の文化が存在していたといっていい。
本州の夫人風俗で、中国・朝鮮・安南などと大いに異なるのは、歯を黒く染めることであろう。鉄漿(かね)とか、お歯黒などいった。材料は古鉄屑を焼き、濃い茶の中に投じ、酒や飴を加えてつくる。付着をよくするために、ときに附子(ヌルデのわかめなどにできた、タンニンを含むコブ状のもの)をも加える。
和人が、この奇妙な風習にいつごろからとりつかれたかのはよくわからないが、あまり古い世ではないにちがいない。
公家の男子の風習であったものが、ひろく婦女子一般のものになるのは、江戸期がはじまってからではないかと思える。
屋久島などでは娘が十六になるとつけたという。他の地方では、十七才でつけたりした。しかし嘉兵衛のころになると、嫁入りしてからつけるようになり、既婚者であることがひと目でわかるようになっている。同時に既婚夫人は眉も剃った。
ところが松前・函館の夫人は、娘も既婚夫人も、眉をのこし、鉄漿もつけないのである。』
【コメント】
全六巻は長い。多少中だるみしたが読み切れた。あと二巻。
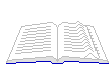
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます