◎それにしても雑誌は買ってもらってなんぼの商売。本来は新聞もそうなんだがほっておいても宅配で買ってもらえた時代が長すぎた。
新聞の販売部数などの推移をグラフ化してみる(2018年前期まで)(最新)
主要メディアの一つである新聞は他国同様日本国内においても、大きな変動の渦中にある。デジタル媒体の躍進に伴う紙媒体としての新聞の相対的重要性の低下に加え、メディア(に携わる人たち、伝えられる情報)そのものの信用性の低下と報道機関としての姿勢などが改めて問われている。日本は紙媒体の新聞の発行部数が多いことで知られているが、やはり世の中の流れに逆らうことはできず、部数は漸減しているのが現状である。今回は【新聞の発行部数などをグラフ化してみる】などで半年ごとに定点観測記事としてお伝えしている、国内主要5紙、具体的には読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞(日経新聞)・産経新聞における、朝刊の販売部数推移の精査を行うことにする。
最初に示すのはデータが取得できる2005年前期以降の5紙における発行部数。産経新聞は一部データが欠けているが、可能な限り補完している。
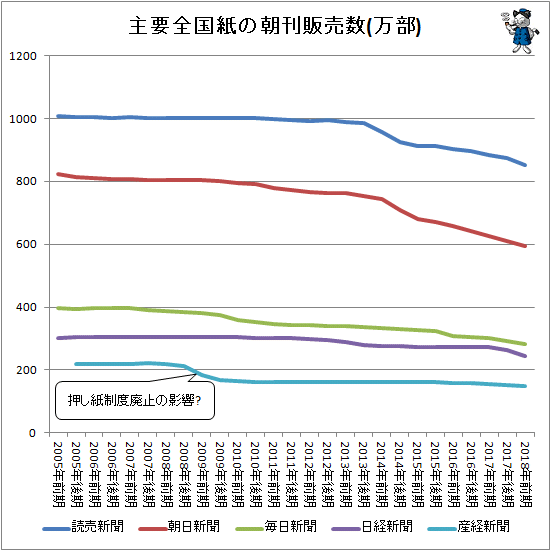
↑ 主要全国紙の朝刊販売数(万部)



























