昭和20年3月10日の東京大空襲では、旧中川沿いも火の海となり、川に飛び込むなどした約3千人が犠牲になったとされる。
遺族や地元の住民ら約5500人の参加が参加し、旧中川に架かるふれあい橋付近で黙祷(もくとう)をささげたあと、約2400個の灯籠を川に流した。(写真を除く記事は産経ニュースから引用)





終戦の日:陛下のおことばに保阪氏 30年変わらぬ信念 - 毎日新聞 https://t.co/ysxxRvKHe2
— achikochitei (@achikochitei1) 2018年8月15日
画面clickで本文が開きます。


|
|
東京における最初の空襲は昭和17(1942)年4月18日であった。その後、しばらく小康状態が続いたが、昭和19(1944)年11月24日からB29による爆撃が始まり江戸川区も被害を受けた。江戸川区は昭和20(1945)年8月1日から2日にかけての最後の爆撃まで軽微なものも含めて二十回以上の空襲にあったが、その中で最も被害の大きかったのは、3月10日の空襲であった。
空襲警報解除までの約2時間半の間に投下された焼夷弾は1,783tといわれ、東京の約4割が一夜にして焼失した。江戸川区内では小松川・平井地区一帯が壊滅的な被害を受け、焦土と化した(右写真)。当時、小松川・平井地区は区内第一の春日町商店街を有する、木造住宅密集地域であったため延焼による被害を大きく受けた。一方、葛西・瑞江・篠崎地区は農村地域であったため、空襲による火災の延焼は比較的拡大せずにすんだ。
この空襲により、区役所も焼失したため、都立第七高等女学校(現在は都立小松川高等学校)で罹災者の救援業務を開始したが、他区の罹災者も扱ったため毎日、行列ができた。そのような中で、町会の果たした役割も大きく、罹災証明の発行、国民貯金の払出し手続き等、区民一丸となって、救援業務に取り組んだ。

<空襲後の小松川2丁目付近>
各戸全員が責任の分担を決め、防火活動への参加が定められた。児童は集団疎開を強いられ、家族と離れて暮らすことになった。
下町のような木造家屋密集地域では、空襲、とりわけ焼夷弾に対しては落下後数秒以内に防火処置を講じなければ、現下の消防力だけでは火災の防止が困難であった。そこで、個々の家庭で防火の徹底を図るとともに、隣組防空群が組織され、バケツリレーや火たたき、あるいは油脂焼夷弾の処置等の訓練を受けた。さらに、もんぺ姿に防空頭巾をかぶり、防火用水に水を張り、火はたき、とび口等をそろえて実戦に臨む体制も整えた。そして、ひとたび空襲を受けた時には、戦火を最小限に食い止めようと必死の活動が続けられた。しかし、3月10日のような大空襲ではとうてい力が及ぶべくもなく、甚大な被害がもたらされた。
戦争が激しさを増すにつれ、児童を戦禍から守り教育を続けるために集団疎開が国策として実施された。江戸川区での疎開先は山形県と決定され、昭和19(1944)年8月から9月下旬まで児童の輸送が行われた。第一次集団疎開児童数は5,118人(『江戸川区の学童疎開』)であり、8地区に分かれて生活することとなった。当時農村地域だった江戸川区は、食糧についてはさして事欠くこともなかったが、疎開先は温泉地が多く、食糧の生産力が乏しかった。児童を引率した元国民学校訓導は「食事は、三食ほとんどおかゆやおじやで、おかずは山菜か、たまに魚が食膳をにぎわす程度であった。篠崎は当時、野菜作りで有名なところだったから、野菜の少ないのには、いささか苦しんだ。」(『江戸川区の学童疎開』)と述べている。また、疎開を体験した児童は「スイカの皮、卵の殻、貝の殻、雑草まで食べさせられた」(『江戸川区史〔第2巻〕』)と当時の食糧難を語っている。
東京新聞:終戦の日を前に 国家は国民を守るのか:社説・コラム(TOKYO Web) https://t.co/VynEpcPAkt
— achikochitei (@achikochitei1) 2018年8月14日
神戸大空襲:重傷の89歳女性「戦争は残酷、罪深い」 - 毎日新聞 https://t.co/WneibKEtEl
— achikochitei (@achikochitei1) 2018年8月15日
青文字か画面clickで本文が開きます。




(CNN) 米ハワイ州でこのほど、スノーケリングを楽しんでいた一家が、体長約6メートルのジンベエザメの頭部に巻き付いていた漁業用のロープを切って救出する出来事があった。ロープは太くて重く、数週間にわたりサメの体に食い込んでいた。
一家がサメを発見したのは先月29日。ラナイ島カウノル沖でスノーケリングをしていた時のことだった。カプア・カウェロさんと夫のジョビー・ローラーさんはどちらも生物学者で、サメの様子がおかしいことに気づいた。
カウェロさんはCNN提携局のKHNLに、「私たちが何をすべきなのか、何が『クレアナ』なのか時間をかけて考えていた」と話す。クレアナはハワイの言葉で、人と人が関わるものとの間との互恵的な関係を指す。
ハワイ土地自然資源局によると、この若いジンベイザメは7月11日に最初に発見され、からまったロープで弱ってきていた。
カウェロさんは「必ずしもこの種の行動が推奨されるわけではないと承知している」と前置きした上で、2人とも生物学者でサメの行動を自分たちのことのように感じ、この場所にいるのは運命なのかもしれないと思ったと振り返った。
そして2人は救助を決断。一家と一緒にいた男性によると、ローラーさんがダイビングナイフを持ってサメのいる水深約9~12メートルの場所まで潜っていった。息を止めたまま一度に30~45秒間、ロープを削っていったという。
およそ45分の間に5回のフリーダイブを行ったといい、完全に切った後にはこの男性と2人でサメの体からロープを引き離した。ロープは太さ約13センチで、重さは少なくとも70キロ近くあったという。
ハワイ州環境当局によると、ジンベエザメは世界各地で絶滅危惧種に指定されており、その生息数は1975年以降に半減した。
ただし、ハワイの野生生物管理当局者は、訓練を受けていない人はロープなどに絡まった動物を自力で助けようとすべきではないと注意を促す。魚がより深く潜ったり、触れた人間に反応して回転したりする恐れがあるほか、人間にロープがからまった場合には悲劇になると警告する。














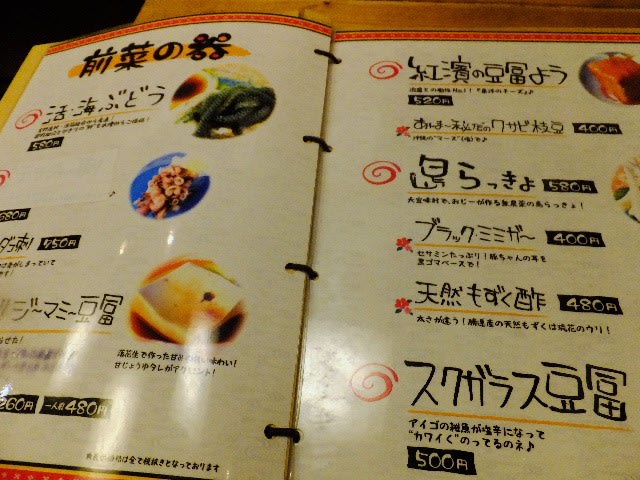


神戸の湊川神社・楠公会館で巽教授の「地震大国・火山大国に暮らすということ」という講演を聞いた記事を2017年の8月11日に掲載した。再掲載します。


八月の昼食会に出ました。先月の例会は肺炎の緊急入院で出られなかったので例会に出るのは2カ月ぶりでした。
今月の講演で一番衝撃を受けたのは「巨大カルデラ噴火は、今後100年間に約1%の確率で発生する。
噴火が起きる確率が1%と言うと、99%大丈夫だと思う人が多い。しかしこれは間違いだ。例えば、1995年1月17日の阪神淡路大震災前日における、
震度6弱以上の揺れが襲う確率は約1%だった。それにもかかわらず、翌日にはあの惨劇が起きた。
つまり、巨大カルデラ噴火は明日起きても何ら不思議ではない。まずこのことをきちっと覚えておいていただきたい。」という箇所でした。
最悪の場合、日本喪失を招く巨大カルデラ噴火 巽 好幸 こちら。必ず目を通してください。




