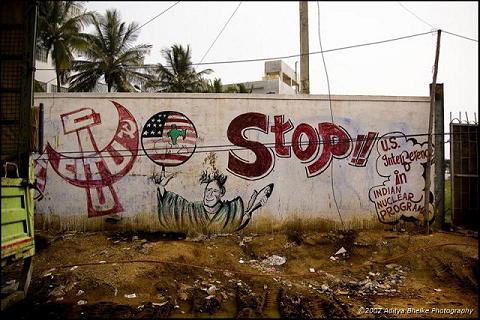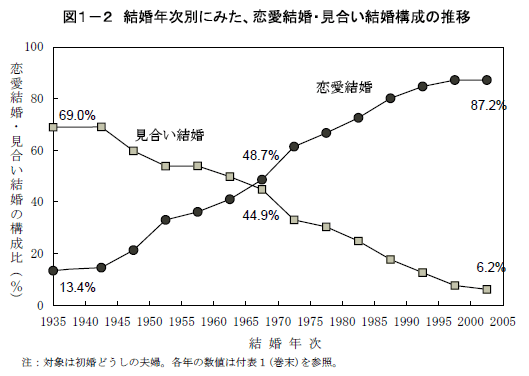(写真はクーデター時のバンコク “flickr”より By Film Colourist )
19日投票されたタイ新憲法案の是非を問う国民投票は、タイ中央選管の暫定集計結果によると、賛成58%、反対42%で、新憲法案は承認されました。
投票率は57.6%で、投票しない場合の罰則がある国政選挙(7割前後の投票率)に比べると低い数値となっています。
今後の政治日程としては12月に総選挙が予定されています。
新憲法案はクーデターで廃止された旧憲法に規定がない首相任期を2期8年と制限し、汚職防止規定を強化、また、下院を小選挙区から中選挙区制に変更するなどタクシン前政権を支えた巨大与党の再現を防ぐ内容となっているそうです。
一方で、クーデターに関与した軍関係者の免責も明記されています。
タイでは昨年9月19日に軍事クーデターが起き、国連総会のため渡米中の前タクシン首相が追放されました。
その後、暫定憲法・暫定政府が続いていましたが、今回の新憲法承認を受けて総選挙が実施され民政に戻る予定です。
昨年のクーデターは、大変な資産家でもあるタクシン前首相のインサイダー取引疑惑等のスキャンダル(6月12日のこのブログを参照 http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20070612 )→総選挙の強行→野党の選挙ボイコット→選挙の無効判決、やり直し・・・という政治的混乱の過程でおきたものです。
私はこのクーデターをバングラデシュ旅行からの帰国便の中で読んだ新聞で知り、タイの“のんびりしたイメージ”と“軍事クーデター”という言葉の緊張感がどうも結びつかず、不思議に感じたのが第一印象でした。
ただ、改めて確認すると「第二次世界大戦後、2006年までに発覚した未遂を含めて16回ものクーデターを計画、実行するほど、軍上層部の政治志向は強い。」(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)とのことです。

(写真はクーデター時のバンコク “flickr”より By lilak )
もっとも、そのように日常茶飯事でクーデーターをやっているせいか、タイ人の国民性か、少なくとも今回のクーデターに出動した軍の様子を伝える写真を見ると、関係ない人間が「こんなにのんびりしていていいのか!」と思うぐらいのどかな雰囲気です。
街の兵士は市民・観光客の格好の被写体になっていたようです。

(写真はクーデター時のバンコク “flickr”より By lilak )
もちろん、タイの人々・社会がいつでも・どこでも、そんなにのどかな訳ではありません。
タクシン前首相は、2003年には麻薬一掃作戦と称して、ブラックリスト掲載者を軍隊・警察により強制逮捕・処刑しましたが、逮捕者は9万人以上、民間人の死者は2500人以上だったそうです。
また前首相は、マレーシア国境近くのイスラム教徒が多く居住する“深南部三県”では厳しい弾圧を行い、それが更にイスラム教徒の激しい反発を招くという悪循環によって、仏教徒の首が切断されるような深刻な対立が生じています。
(6月25日のこのブログを参照 http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20070625 )
今月に入っても、同地域で分離独立を主張するイスラム過激派によって仏教徒9名が殺害されたとの報道がなされています。
タクシン前首相の強硬な政策への反発からこの南部地域においては、今回の国民投票で暫定政府の提起する新憲法への賛成票が圧倒的に多かったそうです。
イスラム教徒と言うと、昨年のクーデターの首謀者と言われているソンティ陸軍総司令官はシーア派のムスリムで、仏教徒が多数をしめるタイにおいて、陸軍総司令官にイスラム教徒が任命されたのは彼が初めてだったそうです。
仏教国タイでムスリムでも最高権力者になれるというのはちょっと意外でした。
恐らく際立って優秀な逸材なのでしょう。
タクシン前首相はイギリスに滞在しており、事実上亡命状態になっています。
汚職に関する国内で進む訴訟に関し、法廷に出席していないため逮捕状が出されています。
今後、イギリスに対する身柄引き渡し請求も検討されています。

(写真はクーデター当時のタクシン前首相と娘(ロンドン)
“flickr”より By koo koo kai)
タクシン支持派は今回国民投票で、新憲法反対の運動を行いましたが、“承認”という結果を受けて、また、タクシン前首相の国内復帰の見通しが立たない状況で、“ポスト・タクシン”の方向に向かうようです。
旧政権与党・タイ愛国党のチャトゥロン元党首代行は「投票結果を受け入れ、新憲法案への反対キャンペーンは終結する。12月の総選挙には参加する」と語っています。