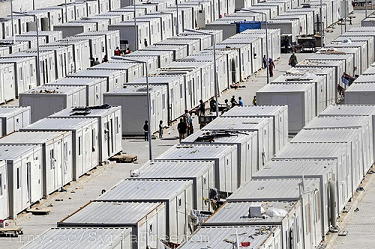(1989年5月19日の早朝、天安門広場でハンストを続ける学生に、涙を流しながら「学生諸君、我々はもっと早く来るべきだった。皆さんに申し訳ない」と拡声器を手にして話す趙紫陽。その隣で正面を向いているのが、当時中央弁公室主任の温家宝。改革派の胡耀邦に師事し、趙紫陽失脚後もしぶとく生き残った温家宝首相ですが、その首相任期最後にあたり政治改革に力を入れているとも・・・。ただ、壁は厚そうにですが。)
【アモイ事件:中央幹部の関与は封印されるのか】
中国建国以来最大の汚職事件とされる「アモイ事件」で、カナダから強制送還された主犯格の頼昌星被告(53)に無期懲役刑が言い渡されました。
アモイ事件(遠華密輸事件)については、11年7月24日ブログ「中国 「アモイ事件」主犯中国送還に見る国内権力闘争の一端」(http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20110724)でも取り上げたように、1996年から1999年にかけて、頼昌星を総裁とする遠華電子有限公司という貿易会社が、約800億元とも言われる関税を脱税したとされている事件です。
主犯の頼昌星氏は、地元政府、税関、公安当局高官、軍人らに高額の賄賂を贈りながら中央政府幹部まで買収し、人民解放軍の艦船に密輸船を保護・先導させて堂々と石油、たばこ、自動車など、巨額の物資を海外から密輸していたとされていますが、その実態は明らかではありません。
江沢民前国家主席側近の関与も噂されていますが、当時の江沢民政権は、政権中枢を揺るがしかねない事態を避けるため、政権中枢の関与は執行猶予付き死刑判決を受けた李紀周・元公安次官以外は公表されないまま封印されたとも言われています。
頼昌星氏が中国へ送還され裁判にかけられることになった背景には、権力中枢におけるで江沢民率いる上海閥の影響力低下があるとも、また、頼昌星氏を中国国内に置くことで、胡錦濤派が頼氏の供述をカードとして使い、党大会人事などで上海閥の動きを牽制することができる・・・といった、党中央における権力闘争絡みの観点が指摘されてもいます。
****収賄10人超に死刑、贈賄側は無期 中国最大の汚職事件****
中国建国以来最大の汚職とされる「アモイ事件」で、福建省アモイ市中級人民法院(地裁)は18日、主犯格の頼昌星被告(53)に無期懲役刑を言い渡した。収賄側の官僚ら10人以上に死刑判決が出ている。中国共産党の最高指導部の親族の関与が取りざたされる事件の全容はなお未解明だ。
頼被告は貿易会社「アモイ遠華集団」の元社長。密輸と贈賄の二つの罪で有罪となった。
国営新華社通信によると被告は、1991年からアモイや香港などにネットワークをつくり、95年から99年の間に自動車や石油製品、たばこなどを密輸入した。判決は密輸額273億元(約3400億円)、脱税額約140億元(約1750億円)と認定した。
頼被告には、地元だけでなく中央政府の幹部らの後ろ盾があったとされる。判決は、国の幹部ら64人に不動産、車などを含めて約3900万元(約5億円)相当の金品を贈ったとした。
収賄側の当時の公安省次官やアモイ市副市長、アモイ税関長ら少なくとも10人には死刑判決が出て一部は執行された。密輸にからむ量刑の見直しもあり、頼被告は無期懲役だった。
■党幹部側と親密関係
アモイ事件の処理のあり方は、中国最高指導部の権力闘争に影響を与える可能性があるとして注目されてきた。
なかでも、共産党の序列4位の賈慶林(チア・チンリン)全国政治協商会議主席の妻は、頼被告と密接な関係があったとされた。妻は当時、福建省の国有貿易企業の首脳で、頼被告自身が、香港誌「亜洲週刊」などに親密だったと明らかにしている。
賈氏は、江沢民前国家主席の引きで最高指導部に入った人物だ。頼被告は、賈氏本人との関係については「贈り物をしたことはある」としつつも、「協力を求めたことはない」としていた。
とはいえ、頼被告が密輸や脱税に手を染めていた時期に賈氏は福建省トップの党委書記を務めていた。習近平(シー・チンピン)国家副主席や賀国強(ホー・クオチアン)中央規律検査委書記も、同じような時期に福建で要職にあった。
頼被告は99年にカナダに渡り、拷問や死刑の危険があるとして保護を求めた。「逃亡生活」は12年に及んだ。
香港紙明報によると、江前国家主席は01年に頼被告の引き渡しを求めた際、死刑にしないとカナダ首相に語ったという。07年には中央規律委幹部も死刑にしないと明言。11年5月には武器などを除く一般物資の密輸での死刑が廃止され、直後に頼被告は中国に強制送還された。【5月19日 朝日】
**************************
事件当時の福建省では、記事にある共産党の序列4位の賈慶林氏が93~96年に省党委書記の地位にありました。
また、次期国家主席の習近平氏も、95~02年に省党委副書記を務めています。
共産党の序列8位の賀国強氏も、96~99年にやはり省党委副書記を務めています。
これだけ大掛かりな事件に、当時の福建省指導部が全く関与していなかったというのは、どうでしょうか・・・。
【権力闘争の“カード”に利用か】
しかし、おそらく共産党支配体制を揺るがしかねない党中央幹部の関与が表に出ることはないのでしょう。
仮に、何らかの関与が取り調べ段階で判明したら、それは権力闘争における“カード”として利用されるのでしょう。コップの中で争いはしても、コップそのものを壊す共産党幹部はいない・・・とも言われています。
今秋の指導部交代を控え、最近、重慶市トップの薄熙来氏失脚を巡る騒動や、詐欺罪などで死刑判決が確定していた中国南東部の浙江省の女性実業家、呉英被告に対し、最高人民法院(最高裁)が刑執行直前に審理を高裁に差し戻すとの決定(事件当時の浙江省トップは習近平氏)など、党中央の権力闘争へ影響しそうな事案が続いています。
総じて、江沢民氏や習近平氏に対し、胡錦濤氏の勢力が有利な“カード”を手にする展開のようにも思えますが、部外者には窺い知れないものがあるのかも。
つい先日も、江沢民氏に近いとされ、薄熙来氏を擁護したとも言われる、共産党序列9位の周永康政治局常務委員(治安担当)の名前が今秋の共産党大会に出席する河北省の代表者名簿に載っていないということで、「落選」か・・・とも報じられましたが、結局“新疆ウイグル自治区の代表に満票で当選したことが分かった”とのことでした。北朝鮮ほどではないですが、中国の党内部の権力闘争はよくわかりません。
【「みんなで分けよう。しょせん国の金だから」】
そうした権力闘争に関する部分はよくわかりませんが、共産党支配体制にあって、地方末端から中央幹部に至るまで、腐敗が横行している状況はよくわかります。
四川、陝西、甘粛の3省で死者6万9千人、行方不明者1万8千人を出し、500万人が家を失った四川大地震(08年5月)からの復興においても、行政による不正、汚職、むだ遣いが指摘されています。
****スピード復興、不正の温床 中国・四川大地震から4年****
中国の四川大地震から4年。中国政府は被災地に巨額の支援を注ぎこみ、公共施設や住宅のスピード再建を成し遂げたと誇る。だが、復興資金を巡る行政のむだ遣いや汚職も徐々に表面化。偽りの災害指定を受け、地方政府が補助金をだまし取った疑惑も浮上している。
■補助金狙い 被害でっち上げ
四川省成都市から車で2時間半、山あいに田畑が連なる射洪県。甚大な被害を受けた地区の一つとして、2009年に「重大被災地区(重災区)」の指定を受けた。震源から約180キロ。地震の揺れは震度4程度だった。
「近所で倒れた建物はない。重災区なんてうそです」。同県明星鎮の農民、陳永高さん(54)たちはそう告発する。
重災区に指定されると、倒壊家屋1戸につき1万6千~2万3千元(約20万~29万円)が国から再建補助金として支給される。これを狙った虚偽の申請だったとの訴えだ。
陳さんたちの調べによると、県政府がまとめた補助金の申請一覧には、ゼロのはずの倒壊家屋が192戸と記されていた。補助金は計400万元(約5千万円)に上るが、住民の多くは受け取っていない。名前が勝手に使われて地震被害が申請されていた。
地元捜査当局が動き、不正は次々に明るみに出た。
「あなたには4千元をあげるから、残りの1万5千元をみんなで分けよう。しょせん国の金だから」。不正申告した補助金1万9千元(約24万円)の山分けを地元幹部から誘われたという住民の証言が、捜査当局の調書に残る。
全国から集まった義援金や、重災区の被災者全員に配られるはずの1日10元(約125円)の生活補助費もどこかに消えていた。申請書には地震前年に死亡した人の名前も使われていた。地元幹部2人が汚職容疑で逮捕された。
ところが、そこで捜査は突然中止された。他の地区で起きた同様の疑惑はうやむやのまま。捜査当局者は「上から命令があった」と住民に伝えたという。
虚偽申請の疑惑は、明星鎮にとどまらず、県ぐるみの疑いに拡大している。
同県の大于鎮。広大な田畑が地震の年、農民の反対をよそに工業団地用の更地になった。被害のない農民の住宅が倒壊家屋として申請されたのだ。
住民には国の補助金平均2万元(約25万円)が渡されたのみ。「開発業者と県政府は、地震を利用して我々を追い出した」と黄遠倫さん(53)は訴える。
同県内で倒壊や重大な被害を受けた住宅は1万7227戸とされ、支払われた補助金は2億4千万元(約30億円)に達する。
県政府の担当者は、各鎮の申請書類に基づいて倒壊家屋を認定したと主張。「すべて見たわけではないが、絶対に倒れている。補助金も確実に住民に渡った」と朝日新聞に話した。(中略)
震災地の地元政府幹部の汚職疑惑も相次いでいる。
四川省政府は昨年3月までに幹部559人を取り調べた。地震で多くの死者が出た綿陽市では昨年5月、廖明副市長が解任された。自宅から1億元(約12億5千万円)を超す現金や骨董(こっとう)品が見つかり、都市計画事業との関連が疑われている。同省広元市や楽山市でも災害復興にあたった副市長がすでに解任されている。【5月15日 朝日】
**************************
この種の、中国における地方行政の腐敗は、常に、いろんな問題で指摘されるところです。
よくわからないのは、そうした地方の腐敗・横暴をどうして党中央がコントロールできないのか、あるいは、中央も何らかの形で関与しているのか・・・というあたりです。
【地元当局などが年間約1千万元かけ、部外者の排除を託す】
「盲目の人権活動家」陳光誠氏と妻、2人の子供はニューヨークに到着しました。
陳光誠氏の出国にあたり、早い幕引きを図りたい中国当局はアメリカとの関係にも配慮して、異例の対応を示していますが、陳氏の母親・親族への圧力は続いているとも報じられています。
****「帰れ」取材車囲み蹴る 中国・陳氏軟禁の村ルポ****
中国の「盲目の人権活動家」陳光誠氏と妻、2人の子供がニューヨークに到着した20日、記者は陳氏が自宅軟禁されていた山東省東師古村へ向かった。
一人っ子政策のもとでの当局の中絶強要を告発した陳氏や妻は、2010年から多数の監視役の男たちに自宅や村を取り囲まれ、暴力もふるわれた。同村には今も陳氏の母親や親族が住んでおり、会って話を聞きたいと思った。
20日朝、記者が同村がある臨沂市の空港に到着すると、3人の男女に指さされ、「安全検査」と書かれた制服を着た職員に呼び止められた。飛行機の搭乗券で名前を確認された。その後、記者の車は黒い車にずっと後をつけられた。
空港から北西へ約70キロ。幹線道路から東師古村に入る細い道の入り口まで来ると、麦わら帽子や野球帽をかぶった男6人が立っているのが見えた。
細い道を入ろうとすると、車が男たちに取り囲まれ、「今すぐ帰れ」と怒鳴られた。用件や身分を尋ねられることもなく、外に出ようとすると、4人がかりで車の左右を蹴られた。
やっと車から外に出ると男たちは一斉に突進してきた。服を両手でつかまれ、「お前は招かざる客だ」。何者かと聞いても、「村人だ」と言うのみだ。胸を何度も突かれ、腕も引っ張られた。そして、頭から車の中に放り込まれ、ドアを閉められた。
車を発進させ、逃げようとする際、窓から体を乗り出し、夢中でシャッターを押した。
こうした監視役の男たちの存在は、陳氏や親族に対する村内での不当な対応が外部に漏れることを防ぐため、部外者が村内に入り込まないようにするものとみられるが、はっきりしたことは分からない。
これまでも多くの外国人記者や支援者が陳氏の自宅を訪ねようとして、監視役たちに阻まれ、時には暴行を受けてきた。陳氏が出国しても、状況は何も変わっていないようだ。
陳氏を山東省から救出した支援者の何培蓉氏によると、監視役は別の村から1日100元(約1250円)で雇われ、約120人がシフト制で勤務。地元当局などが年間約1千万元(約1億2500万円)かけ、部外者の排除を託すなどしているのだという。
米政府系のラジオ局ボイス・オブ・アメリカによると、陳氏の母親は今年78歳。心臓などに疾病があるという。陳氏は「母親は以前、具合の悪いときに病院に行くことも許されなかった」と語っていた。
また、陳氏のおい、陳克貴氏は故意殺人容疑で逮捕されたまま、動静は不明だ。克貴氏の母親も一時連行されたとの情報がある。
朝日新聞は20日、村にいる陳氏の複数の親族に電話をしたが、つながらなかった。【5月21日】
************************
【法律に優先する権力の意向】
日本的感覚からすれば“無法”としか思えない地元当局の対応は、どういう法的根拠があるのか?
おそらく、法律より権力の意向が優先する社会なのでしょう。(中国憲法では共産党が憲法の上位に位置ずけられているそうですから、そもそも法治主義が存在していないとも言えます)
こうした地方の事態を中央が知らない訳はありませんが、中央はどのように判断、あるいは関与しているのか?
政治改革に言及することが多い温家宝首相のもとで、リベラルな知識人や官僚たちが、“共産党が憲法に従う”という一文を党規約・憲法に加えるべきかを検討している・・・とも報じられています。【5月23日号 Newsweek日本版】
日本では当たり前のようなことも、中国共産党の論理に照らすと全く違った判断ともなるのでしょう。
ただ、こうした地方行政の腐敗・横暴の横行が続き、中央もそれに関与しておりコントロールできないというのであれば、やがて共産党支配という“コップ”にも大きなひびが入るのではないでしょうか。