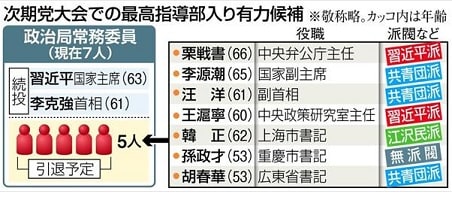(2016年8月3日、大統領の呼びかけによって犠牲となった男性の葬儀で嘆き悲しむ親類の女性 ©NOEL CELIS/AFP/Getty Images 【アムネスティ日本】)
【「軍事的にも経済的にも米国と決別する」のはフィリピンの選択】
中国を訪問し、「軍事的にも経済的にも米国と決別する。米国は敗れた」といった相変わらずの反米発言を連発し、南シナ海問題を事実上棚上げした形で、中国の提供する支援に感謝するフィリピン・ドゥテルテ大統領の言動が話題となっています。
****混乱するフィリピン外交、ドゥテルテ大統領の「決別」発言で****
・・・・ドゥテルテ大統領は20日、中国人実業家ら数百人を前に演説し拍手を受けたが、その際、「私は米国との決別を表明する」と語り、「私は、あなたたちのイデオロギー的な流れに自分の身を置き直した。場合によってはロシアへも行き、ウラジーミル・プーチン(Vladimir Putin)大統領と話し合い、世界に立ち向かっているのはわれわれ三者──中国、フィリピン、ロシア──だと彼(プーチン氏)に伝えるだろう。これしか道はない」と述べた。(後略)【10月21日 AFP】
******************
一昔前のベネズエラのチャベス前大統領やイランのアフマデネジャド前大統領のような、コテコテの反米路線のようにも見えます。
ドゥテルテ大統領の反米感情の背景には、フィリピンがアメリカ植民地として搾取・弾圧されたという歴史認識があるようで、麻薬犯罪者の超法規的処刑に対するアメリカなどの“非人道的”との批判が、そういう認識に火をつけたようにも。
****訪中のドゥテルテ比大統領「中国には侵略の歴史はない」****
2016年10月20日、国際在線によると、中国を訪問しているフィリピンのドゥテルテ大統領は19日夜、北京で北京在住のフィリピン人代表と面会し、「フィリピンと中国の人々は、スペイン人がフィリピンに到達する以前から交流を開始し、それを1000年以上も継続してきた歴史がある。中国には侵略の歴史はなく、フィリピンを侵略したことは一度もない」と述べた。
ドゥテルテ大統領は「中国はフィリピンの良き友人だ。中国には約30万人のフィリピン人が滞在している。中国はフィリピン人に対してとても友好的だ」とも述べた。【10月20日 Record china】
********************
9月にラオスの首都ビエンチャンで開催されたASEAN(東南アジア諸国連合)首脳会議で、オバマ大統領への「売春婦の息子」といった暴言で米比首脳会談がキャンセルされたときも、ドゥテルテ大統領は東アジアサミットの席上で“フィリピンが米国の植民地支配を受けていた約100年前に、米兵に殺害されたフィリピン人の写真も示し、「これは殺害されたわれわれの祖先だ。なぜ今、人権問題を話しているのか。人権はあらゆる観点を含めた上で話し合わなければならない」と強調した。”と、植民地支配を絡めた認識を明らかにしています。
一方の習近平主席は会談で中比両国の交流促進に触れ、15世紀にフィリピン南部のスールー王国の王が明の永楽帝に拝謁し来年で600周年を迎えることから記念行事の開催を提案したとか。
もっとも、“会談で周辺国の「朝貢」に触れたことから、さまざまな憶測も呼んでいる”【10月20日 産経】とも。
アメリカ同盟国日本への訪問の前に習近平主席に謁見し、蜜月を演出し、見返りに大盤振る舞いを受けるというのは現代版「朝貢」かも。
また。中国とフィリピン・ドゥテルテ大統領の急接近の背景には、以前から指摘しているように、両者の体質が似かよっていることもあるでしょう。麻薬犯罪者を超法規的に殺しまくるドゥテルテ大統領にすれば、天安門で政府批判者を戦車でひき殺すことも、チベット・新疆での弾圧も、別に問題視するようなことではないのでしょう。
中国にしても、犯罪が疑われる者の人権などおかまなしに処分するドゥテルテ大統領の“剛腕”は、ごく当たり前ののことでもあるのでしょう。
もちろん、ドゥテルテ大統領の反米感情と国民全体の意識には大きなかい離があることも指摘されています。
****フィリピン「信頼する」1位は米国、日本は3位 中国を信頼しないは55%…市民の親米反中は変らず****
フィリピンの民間調査会社ソーシャル・ウェザー・ステーションは18日、主な外国に対する国民の信頼度調査結果を発表した。1位は米国で、「信頼する」が76%、「信頼しない」が11%、差し引きの純信頼度(小数点以下四捨五入の概数)はプラス66だった。一方、中国は「信頼する」22%、「信頼しない」55%で、純信頼度はマイナス33となった。
ただ、今年6月の前回調査に比べ、米中ともに信頼度が低下した。同月末に就任したドゥテルテ大統領が反米的な発言を繰り返したことや、南シナ海の領有権問題をめぐる仲裁裁定で、主権主張を否定された中国が裁定を無視したことなどが影響したとみられる。
調査は9月下旬、比国内各地の成人約1200人を対象に実施。純信頼度の2位はオーストラリア(プラス47)で、3位は日本(プラス34)だった。【10月18日 産経】
******************
また、政権閣僚の間でも、大統領の過激なアメリカ離れに戸惑いも見られます。
ドゥテルテ大統領の「軍事的にも経済的にも米国と決別する。米国は敗れた」という演説から数時間後、フィリピンの経済閣僚らは「われわれは欧米諸国との関係を維持する。一方でアジア諸国の連携強化も望んでいる」との声明を出しています。【10月21日 Newsweekより】
国民の支持率が8割近くに達する現在の状況では、政権内の異論は、結局は大統領の意向の前で封じ込まれる形になるのでしょう。逆に、支持率が下がってくると、様々な不満が噴出することも。
なお、日本的感覚からすると異様に高いように思われるドゥテルテ大統領の支持率も、フィリピンにあっては、特段に突出したものでもないとの指摘もあります。
****ドゥテルテ人気の真実を疑え****
驚異的な高支持率が取り沙汰されているものの、政策への反応は微妙 賞味期限は意外に短い?
・・・・第1に、ドゥテルテは前任者と比べて圧倒的に支持されているわけではない。最新調査での76%という数字は数十年来の最高記録と喧伝されているが、実はベニグノーアキノ前大統領の就任数力月後の支持率71%と5ポイントしか違わない。
ドゥテルテが大統領に就任した直後の7月、パルスーアジアが実施した調査では支持率が91%に達した。同社の世論調査史上、最高の支持率だと強調する向きもあるが、これもアキノの大統領就任直後の87%という数字とあまり変わらない。・・・・【10月25日号 Newsweek日本版】
******************
フィリピンの中国接近、反米路線は、アメリカとともに東南アジア諸国を巻き込んで、中国の強引な進出に歯止めをかけようとする日本にとっては、梯子を外されるような不都合なものです。
“習近平国家主席は20日、ドゥテルテ大統領との会談を終えると、同じ人民大会堂の客間で、ベトナム共産党中央政治局委員で中央書記処常務書記(丁世兄)と会談した。ラオスもカンボジアもフィリピンも、そしてベトナムさえもとなれば、ASEAN諸国はすでに中国の傘下に降ったようなもので、南シナ海問題だけでなく、東アジア情勢に大きな地殻変動が起きる。”【10月21日 遠藤 誉氏 Newsweek】
ただ、不都合ではありますが、フィリピンがどういう外交路線を選択するかはフィリピンが決めることでもあります。歴史認識にても、中国との関係に期待することも、ひとつの見識ではあります。(賛成するかどうかは別にしても)
【“選択”では済まされない犯罪行為】
一方、こうした暴言や外交姿勢の問題でかすんでしまっている感もありますが、ドゥテルテ大統領が国内で進める超法規的殺人は“選択”では済まされない犯罪行為であり、民主主義の破壊です。
ドゥテルテ大統領の「犯罪」については、9月15日ブログ“フィリピン大統領の「犯罪」 議会で責任が問われるのか、国民支持で不問に付されるのか”http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20160915でも取り上げました。
****比大統領、「麻薬撲滅戦争」手加減せず 死者3700人突破****
フィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ大統領は14日、犯罪者を殺すと脅すことに「非の打ち所はない」と述べて自身の方針を擁護し、既に死者が3700人を突破した「麻薬撲滅戦争」を手加減することなく続けていくと誓った。
国際刑事裁判所(ICC)のファトゥ・ベンソウダ主任検察官は13日、フィリピンの麻薬撲滅戦争について「深く憂慮している」と述べ、ICCがドゥテルテ氏を殺人の扇動で訴追する可能性を示唆した。
しかしドゥテルテ大統領は14日、いつもの調子で反論し、自身の発言と一か月に1000人以上が死亡している麻薬撲滅戦争を擁護。「犯罪者を殺すと脅すことにやましいことは何もない。『犯罪者どもよ。私はお前たちを殺す。ばかなまねをするな』という声明一つとってみても、非の打ち所はない」と述べた。
14日の当局の公式発表によると、ドゥテルテ大統領の就任以降、警察はこれまでに1578人を殺害し、2151人が詳細不明の状況で死亡した。死者の合計は前回発表より368人増えて3729人となった。【10月15日 AFP】
*********************
正規の逮捕・裁判のルートに乗せず、“抵抗した”として警官が安易に射殺してしまうこと(誤った捜査も多いでしょうし、悪徳警官による関係者の“口封じ”もあるでしょう)も問題ですが、“詳細不明の状況で死亡”というのは問題外の殺人行為です。こうした正体不明の「処刑団」には警官も関与していると見られます。
****バイク2人乗りの暗殺者、覆面取ったら警察官 フィリピン****
ロドリゴ・ドゥテルテ大統領の掲げる「麻薬撲滅戦争」で超法規的な殺人が横行しているフィリピンで先週末、女性を射殺した2人乗りバイクの覆面の男たちが、いずれも現役の警察官だったという事件があった。フィリピン警察当局が13日、明らかにした。
容疑者の警官2人は9日、首都マニラから南方に170キロ離れたミンドロ島にある町グロリアで、自宅の外にいた地元女性を射殺したとされる。現場から逃走する途中で地元警察と銃撃戦となり、負傷した末に逮捕されたという。
容疑者の1人はグロリアの2つ隣の町ソコロの交番署長を務める警部補で、もう1人はミンドロ島内の別の警察組織に所属する警部だった。2人は平服で犯行に及び、逮捕された当時は弾丸が装填された複数の拳銃と覆面、かつらを所持していた。
警察当局は2人を殺人容疑で起訴する方針だ。
フィリピンでは今年6月30日にドゥテルテ大統領が就任して以来、警察が強権的な麻薬犯罪の撲滅作戦を遂行する中、既に3300人以上が死亡している。この中には麻薬密売人として警察に射殺された容疑者もいるが、多くはバイクに乗った2人組の暗殺者に撃たれて死亡している。【10月14日 AFP】
*******************
こうしたドゥテルテ大統領の「麻薬撲滅戦争」はフィリピン国民の高い支持を得ているとも報じられていますが、その内容には注意も必要です。また、国民も超法規的処刑を認めている訳ではないようです。
****「超法規的」処刑への懸念***
・・・一方、ドゥテルテが推進する麻薬撲滅をはじめとする犯罪対策は、政策としても高く支持されているように見える。だがここでも、慎重な見極めが必要だ。
SWSの最新調査によれば、違法薬物の密売業者などを徹底的に取り締まるドゥテルテ政権の方針に、「非常に満足している」人の割合は54%、「いくらか満足している」人は30%。メディアは両者を単純に足し合わせて、麻薬戦争の支持者が84‰に上ると報じている。
現実には、対象者の約3分の1は「いくらか満足」と言っているにすぎない。迷いを抱く彼らは、今回のような4択ではなく「賛成」か「反対」かの2択であれば、「反対」と回答した可能性がある。
賛否が相半ばする感情は、別の質問への反応に明らかだ。質問は「麻薬密売業者を殺害せずに逮捕すべきか」。言うまでもなく、密売容疑者が裁判を経ずに現場で「超法規的」に処刑されている現状への懸念を意識した問いだ。
質問に対して、容疑者を殺さないことが「非常に重要」と回答した人の割合は71%、「いくらか重要」と答えた人は23%だった。(メディアのやり方にならって)両者を足し合わせれば、実に94%が「重要」と考えていることになる。
麻薬戦争そのものには、84%が「満足」しているにもかかわらずだ。
言い換えればこういうことだ。麻薬撲滅作戦は全体として高く支持されているものの、その一環として超法規的処刑を行うことへの懸念は支持を上回る。【10月25日号 Newsweek日本版】
*******************
【麻薬犯罪にとどまらない暴力的対応】
また、再三指摘するように、ドゥテルテ大統領の暴力的対応が麻薬犯罪者に限定される保証はありません。政権を批判するような“邪魔者”にも同様の「超法規的」処刑が行われることが十分に予想されます。
9月15日ブログで、議会上院において、フィリピン南部ダバオ市で暗躍したとされる「処刑団」の一員だった男性が証言し、当時市長だったドゥテルテ大統領の指示で過去1000人以上の犯罪者らが違法に殺害されたことや、処刑対象にはドゥテルテ氏に批判的な人物や、ドゥテルテ氏の妹の交際相手も含まれていたこと、国の捜査当局者が殺されたケースではドゥテルテ氏自身が直接殺害したことなどを明らかにした・・・という件を取り上げました。
この上院での公聴会を主導したレイラ・デリマ議員は殺害脅迫を受け、自宅へ帰れない状況が続いています。
****大統領糾弾に身命を賭す反骨の元閣僚****
不倫ビデオで対抗という政権側の手法は行き過ぎとの批判も
フィリピンの首都マニラのホテル内会議室で、レイラ・デリマ(57)は政界仲間と食事中だ。会議室の外には側近の青年2人が警護に立ち、ホテル名は明かさないでくれと告げる。「こんな悪夢のような生活にも慣れてきた」と、人権活動家で上院議員のデリマは本誌に語った
先月下旬、下院公聴会の証言の中でデリマの自宅住所と携帯電話番号が読み上げられてしまった。以来、彼女は友人や親類の家に身を寄せる。殺害の脅迫まで受けたため、怖くて1人暮らしの自宅で夜を過ごすことができない。
アキノ前政権で法相を務めた彼女だが、「愛犬たちの様子を見に時々帰るだけ」。
きっかけは上院の司法・人権委員長だった8月に、ロドリゴ・ドゥテルテ大統領の超法規的な麻薬犯罪容疑者取り締まりに対する批判の急先鋒となったことだ。「ドゥテルテは私を見せしめにして、誰も反対できないようにしたいのだ」と、デリマは憤まんやるかたない様子で話す。「彼は反対意見を受け付けず、周りの人の口を塞ぐ」(後略)【10月25日号 Newsweek日本版】
******************
フィリピンの麻薬犯罪の現状を考えると、ドゥテルテ大統領のような対応も正当化される、やむを得ない・・・といった考えもあるようですが、やはり民主国家においては「一線を越えた」対応と言わざるを得ません。
どうしても処刑したいなら、死刑制度を復活させて、司法の裁きに基づいて行うべきで、正体不明の「処刑団」が暗躍する状況を肯定することはできません。
【憂慮すべき現在の風潮】
こうした麻薬撲滅戦争を国民が支持するなら、外国フィリピンの話ですから、それも仕方ないところではありますが、個人的に一番嫌なのは、日本国内でもこうしたドゥテルテ大統領の姿勢を容認する向きが少なくないことです。
昨日TVでドゥテルテ大統領の中国接近を取り上げていました。視聴者のメールが画面の下に流れるのですが、そのなかに「ドゥテルテ大統領は好きだったのに、中国接近は残念」といった趣旨のものがありました。
ドゥテルテ大統領にしても、アメリカのトランプ候補にしても、あるいは欧州の排外的風潮・極右勢力の台頭にしても、従来は口にすることも憚られたようなことが、いまや公然と語られ、そうした従来の価値観(人権、民主主義、寛容さなど)を“きれいごと”の建前として否定し、むき出しの憎悪をぶつけることが正直・現実的で指導力があると、むしろ好意的に受け取られる・・・・そんな現在の風潮が怖いです。
ドゥテルテ大統領はダバオ市長時代に起きたオーストラリア人修道女の強姦殺害事件について「まず市長の俺にやらせるべきだった」と発言して国際的にひんしゅくを買ったこともありますが(国内的にはスルーされたようです)、冗談にせよこうしたことを言えるのは、大統領の資質以前の問題と思います。
権力の圧政・横暴から個人の権利を守ろうとして長年かけて築き上げてきたものが、音を立てて崩れていくようにも思えます。
まあ、そういう人たちにすれば、私のような言い様は反吐が出る・・・というところでしょうから、お互い様ではありますが。